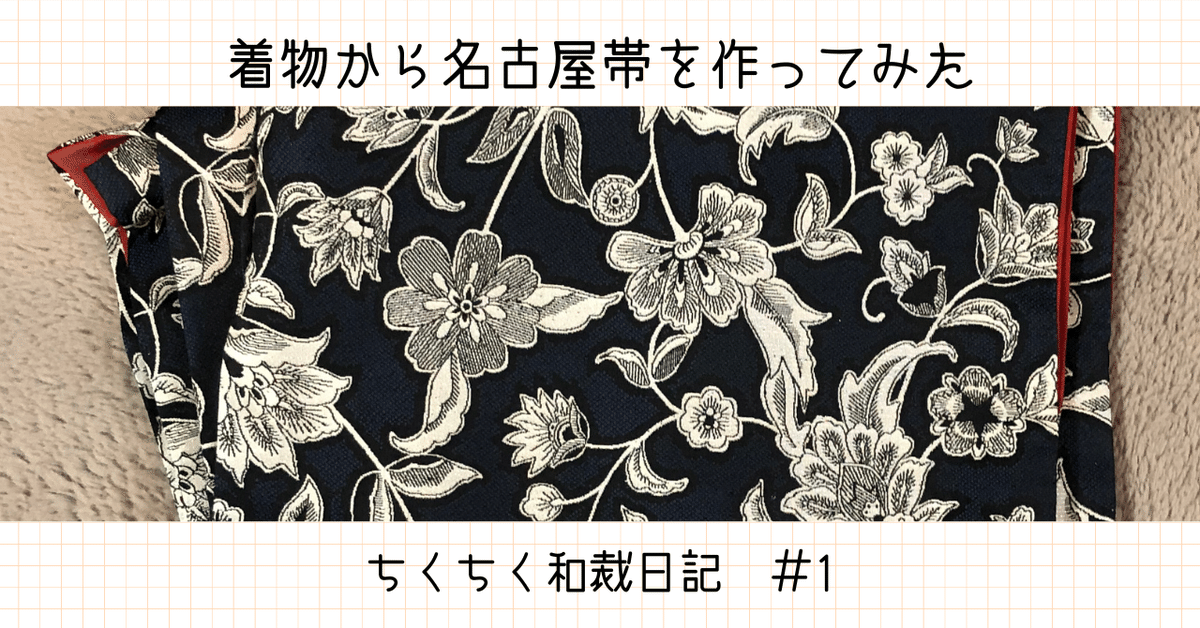
裂けた着物から名古屋帯を作る
出会い
わたしの着物入手先はたいてい催事のリサイクルショップなのですが、先日(といっても昨年ですが)一目惚れして買った着物があります。

黒と緑の地に、シルバーと白でペイズリーのような模様と花が散っている、なんとも素敵な生地です。
しかも「三越」のタグがついていたんですよ。
サイズもぴったり、一体これを仕立てた人は、わたしのために用意していたのかと思うほどド好みです。
お店のおじさんに「また買うの〜?」と言われながら買いました(毎回何かしら買っていくので、わたしのタンスがヤバいことはバレています)。
で、ほくほくしながら家に帰って、順番に着付けていきます。
びり
お?
いまお尻のほうから聞こえてはいけない音がしたぞ?
見てみると、案の定お尻のあたりの表地の背中心の糸が切れています。
よかったー、糸だけならなおせるかな。
そう思いつつ、ぱんぱんと布を引っ張ってみると今度は脇線から
びり
お?
今度は衽を引っ張ってみる。
びり
裏地は全くの無傷。
生地も全くの無傷。
表地の縫い糸だけ弱っていたようで、引っ張ったらびりびりとおもしろいように裂けていきます。
こらあかんわ。
でも生地は好きだしなー。
なんかにしよ。
と思って、しばらく放置していました。
(おじさんに話したら返金していただきましたが、そのお金でまた何か買いました。てへ。)
さてどうする
さてどうする。
一着分の袷の生地。
生地自体はおそらく全く傷んでいない。
裏地も八掛もとてもきれい。
例えば仕立てなおすとして、
ほどき(いくら?)
↓
水通し(表と裏で2万くらい?)
↓
仕立てなおし(3万くらい?)
うん、財布が死ぬな。
わたしは和裁スキルはないので(洋裁スキルはある)、なにか簡単なものに作り直すことにしました。
せっかくきれいな生地、できるだけハサミをいれずにどうにかしたいもの。
着物リメイクを調べていくうちに、どうやら名古屋帯は手縫いで自作できるらしいことがわかりました。
名古屋帯を作ろう
作るものは名古屋帯に決定しました。
その下準備として、
着物をほどく
生地を洗う
という段階があります。
この半年ほどYoutubeで着物系の動画を散々見ていたわたしは、以下の動画を参考に作業を進めていきました。
着物をほどく
参考動画はこちら
道具として、糸切りバサミとニッパー使いました。
あと糸屑がとにかく出るので、ゴミ箱は隣に置いておいた方がいいです。
生地を洗う
薄手で色が落ちそうな胴裏と八掛は今回は畳んだだけでお休み。
比較的しっかりした生地の表地のほうだけ洗いました。
参考にした動画はこちら。
うちは洗剤はエコベールを使っていますが、おしゃれ着洗いならなんでもいいんだと思います。
洗って、しっかり脱水して、裏からアイロンでじゅっと……
アイロンで
じゅっ
の瞬間が一番怖かったですが、たかはさんの女将を信じました。
結果大丈夫でした。

アイロンがかけ終わった生地は、とりあえずくるくると巻いておきます。
ようやく作るよ!
名古屋帯の作り方は、こちらの動画を参考にしました。
まずは材料準備
作り始める前に必要なもの、それは
・芯地
・縫い針
・縫い糸
・ヘラ
・まち針
動画では不織布の接着芯を使っていましたが、たかはしの女将さんは「帯を仕立てるときの芯地の選び方」動画を出していて、そちらは布の(接着じゃない)芯を使うんですね。
どうしたもんかと思い、ユザワヤで聞いてみたところ、
「和裁で使われる方は、こちらを使うことが多いですよ」とメーター売りの不織布接着芯をお薦めされました。
たかはしさんの芯地はアレやな、お店でお仕立てするときの話だろうな。
と納得して、接着芯を購入。
縫い針も種類がいろいろあるので布のタイプを伝えてちょうどいいものを買い(今回は「三の四」でした)、糸も手縫用の絹糸を買い、どこかへ行ってしまっていたヘラを買いました。
追加であって便利だったもの
必要なものは上記ですが、わたしは追加で以下のものを使いました。
・くけ台
・和裁ボード
・広幅のアイロン台(36センチ幅)
くけ台と和裁ボードは、昨年の夏に「半幅帯作ろ!」と思って形から入り、結局使わなかったやつです。
ラッキーなことに、二つ合わせて5000円くらいでメルカリで買えました。
しかも美品。
新品を買うと、それぞれで5000円以上とかしますからね。
そしてこの二つが、今回大活躍でした。
それから意外に便利だったのが、何ということはない広幅の四角いアイロン台。
うちにもともとあったのは洋服用でシャツなどにはよかったのですが、細身なので浴衣のアイロン掛けがとにかく大変だったのです。
たまたまユザワヤで四角いのをみつけて、値段も安かったので買ってみましたが、反物の幅より広いというのはストレスがなくていいですね。
じゃっとアイロンがかけられる。
この辺りが、なくてもいいけどあるととても便利な道具類です。
縫いはじめる
布の準備(洗濯アイロン掛け)と道具の準備をして、ようやく縫い始めです。
結論からいうと、2日でできました。
1日の作業時間は3時間程度です。
こんなに早くできるとは思わなかったので、正直びっくりしました。
参考動画はこちら。
手順はこんな感じ
1.普段よく使っている名古屋帯のサイズを測る。
2.生地の長さ(身頃の部分)の長さを確認。
3.お太鼓部分と胴部分の長さに合わせて裁断。
4.襟部分の切り込みを適当につなげる。
5.お太鼓部分、胴ぶぶんをそれぞれ30センチ幅で印をつける(ヘラと和裁台使用)。
6.接着芯を30センチ幅にそれぞれ切る。
7.印にあわせて接着芯を貼る。
8.まち針で印を合わせて留める。
9.お太鼓部分を縫い、胴部分の布を縫い付ける。
10.胴部分を縫う。このとき、手の先は縫わずに開けておく。
11.お太鼓、胴部分を裏返す。
12.ひっくり返す様に開けておいた部分をまつり縫いする。
13.アイロンをかけて完成。
こう書くと手順が多い気がしますね。
でも実際はそうでもありません。
とにかく「布の裁断」「印つけ」「接着芯はり」「縫い」「アイロンかけ」とそれぞれの工程をまとめておこなってしまえば、道具をあれこれしなくていので簡単です。
そしてくけ台が思った以上にいい仕事をしてくれました。
わたしは床にクッションを敷いてその下にくけ台を挟み込み、目の前にパソコンを置いて動画をだらだら流しながらひたすら直線縫いをしていました。
針仕事がはじめて、という人には大変かもしれませんが、わたしの中学は少々個性的でして、中1の家庭科の夏休みの宿題が運針50本だったんですよね……
全然真剣に取り組まなかったので、がったがたな縫い目でしたが、ともあれ直線縫いくらいなら肩肘張らずにできる範囲内でした。
想定外だったのは、今回使った中厚地の接着芯が思ったよりも硬く、すいすい縫うには程遠かったことです。

どうせ縫い代には接着芯を貼らないので、縫ってから接着芯を貼ればよかったなあと思います。
これは次回への課題ですね。
完成!
そんなこんなで、正月休み2日で完成した名古屋帯がこちら!

ね、すてきでしょう?
柄出しに神経質になる必要のない生地だったのが幸いしました。
とても楽だった上に、これからの着物の楽しみが増えてしまいました。
ダメだ、これ以上ものを増やしちゃダメだ。
仕上がりはというと、もともと少々厚地の絹地だったため、思った以上にバリっと硬い帯になりました。
お太鼓にしたらきっち締まってかっこいいけど、銀座結びにはちと硬めかな、と。
このくらいの生地だったら、芯は薄地でもいいかな、というのが次回への課題です。
そして出来上がってそうそう、つけてみました!

いかがですか?
自画自賛ですけど、すごく素敵にできたと思います。
これからがんがん使っていきたいです。
今回の大成功体験のおかげで、今年はいろんなものを手作りしてみようという意欲が湧いてきました。
名古屋帯、昼夜帯、半幅帯,へこ帯。
夢が広がりますね。
ものを増やさないように、できれば着なくなった着物を使いたいところですが、「着なくなった着物」で手洗いに耐えられそうなものって意外と少ないんですよね……
かといって、洋服地に手を出したら見境がなくなりそうなので、しばらく自重しようと思います。
でもひたすら手縫いでちくちくしている時間は幸せでした。
ちょっと肩は凝るけど、楽しいですね、手作業って。
とりあえず作り方だけ教えてくれ、という方向けのまとめ
<材料>
・帯にしたい着物
・接着芯(不織布、薄地〜中厚地。生地による)5m
・手縫針(サイズはお店の人に相談するとよし)
・まち針(頭にボールなどがついていないやつが使いやすい)
・手縫糸(素材と同じ種類の糸。色は生地の中で一番暗い色に合わせるとよい)
<道具>
・糸切りばさみ
・ニッパー(ハサミで切れない細かい糸をほどく)
・裁ち鋏(布用のハサミ)
・ヘラ(チャコペンは使わない)
・定規(最低でも50センチは欲しい)
・くけ台(なくてもできる。あるととても便利)
・和裁台(なくてもいい。あると絨毯の上でも作業ができて楽。床にヘラの跡がつかない)
・アイロン台
・アイロン
・ゴミ箱(すごく糸屑が出る)
<手順>
1.着物を解く、
2.生地を洗ってアイロンかけ。丸めて保存(畳まない)。
3.使いやすい名古屋帯の寸法を測り、メモしておく。
4.メモに合わせて接着芯を切る。幅は30〜32センチ程度。好みのサイズで。
5.生地を裁断する。
6.生地の切り込みを平らにつなげる。
7.生地の長さが足りない部分は、継ぎ足すようにあわせて裁断する。
8.ヘラで生地に印をつける。
9.接着芯を貼る(厚地の接着芯の場合は後からでも可)。
10.お太鼓部分を縫う。
11.お太鼓部分に胴部分を縫い付ける。
12.胴部分を縫う。
13.縫い目にアイロンをかけ、裏面側に倒して再度アイロンをかける(仕上がりがきれいになる)。
14.接着芯を後からつける場合は、ここで貼る。
15.お太鼓、胴部分をそれぞれひっくり返す。
16.残りの開口部をまつる。
17.全体にアイロンをかけて完成。
<参考動画一覧>
以上!
ものはためし、と思ってまずはやってみるといいですよ!
手縫なので、失敗したなーと思えば解いてやり直せばいいし、多少の歪みはそんなに気になりません。
さてさて、今年は何が縫えるでしょうね。
着物ライフがさらに楽しみになってきました。
放っておいても好きなものを紹介しますが、サポートしていただけるともっと喜んで好きなものを推させていただきます。 ぜひわたしのことも推してください!
