
「一九九五年十二月三十一日、大晦日の午後三時。」
通常、気に入ったシリーズはきちんと揃える派のわたしですが、このシリーズに関しては気に入った巻だけしか買っていないという、少々特殊な例です。
これも一話完結型の作品ならでは、ですけどね。
もちろん作品内時間はつながっているのですが。
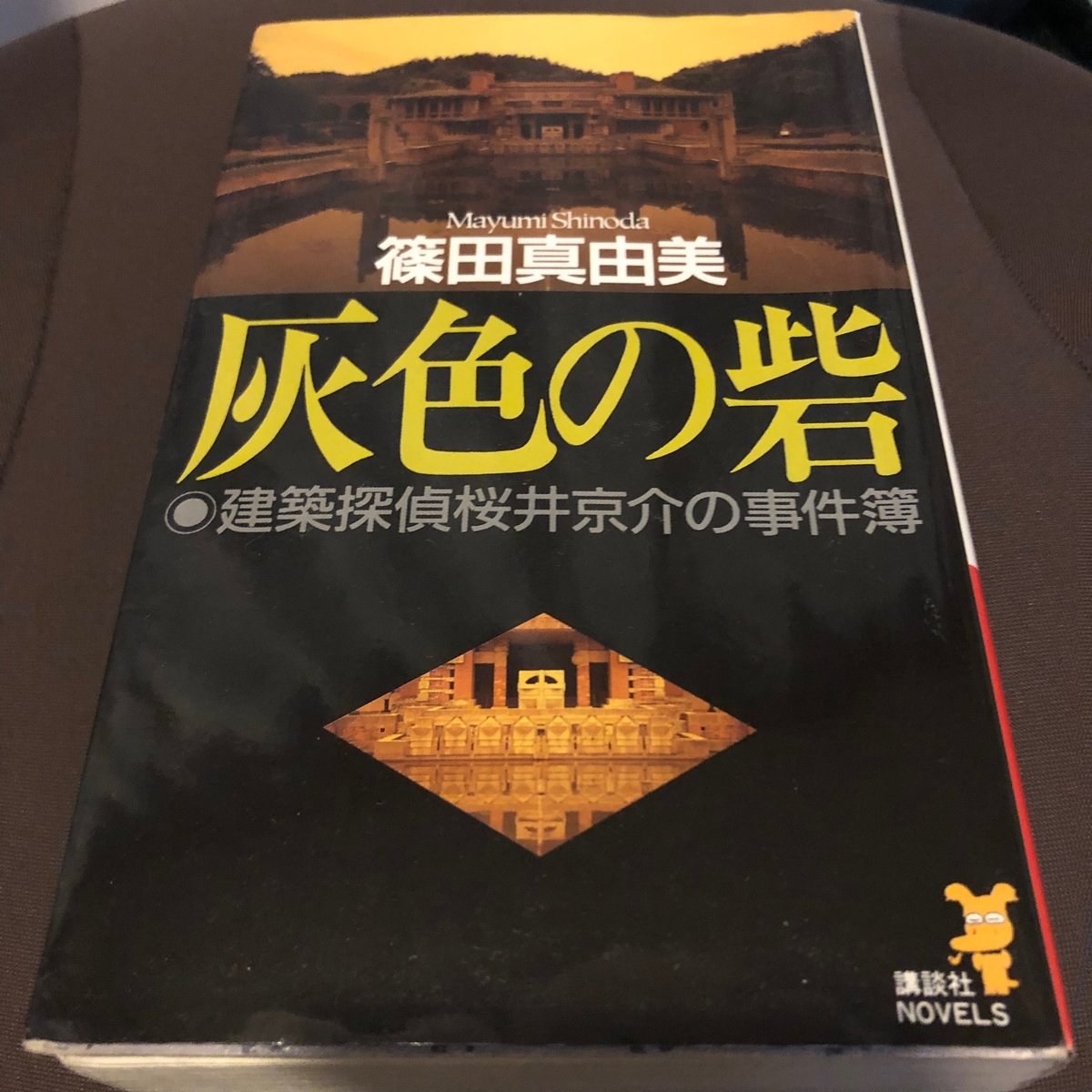
篠田真由美著『灰色の砦』(講談社、1996)
中学2年のころ、わたしの周りでは「講談社ノベルスのミステリ」が流行っていました。
ちょうど、京極夏彦氏が立方体のような本を出したりしていた頃です。
清涼院流水氏のようなやや奇抜な作家も流行っていましたが、篠田真由美氏の作品は硬派というか、いやわたしはキャラ読みしかしないですけども、「建築」をテーマにしたミステリでした。
この『灰色の砦』はシリーズ4作目。
物語の探偵役の桜井京介と、少年ワトソン役の蒼、肉体派ワトソン役の栗山深春のうち、京介と深春の出会いを描いた作品です。
物語の冒頭は、「見たことありそうでないもの」という章題がついています。
さっさと大掃除を終えた深春と蒼が、いつまでも片付けの終わらない京介を待ちながら、手持ち無沙汰に言葉遊びをしている、だらけた年末の風景。
そこから、「見たことありそうでないもの」ゲームがはじまり、蒼が「京介の涙」といいます。
それに対して深春が、「一度だけ京介の涙を見たことがある」といって、物語は二人が大学入学したての、同じ下宿に住んでいた頃に遡ります。
わたしは「学生だらけの下宿」、いわゆる「◯◯荘」的なところに住んだことはありませんが、一種の憧れのようなものがあります。
他人だけど、同じ釜の飯を食う仲間。
過去のことは知らないけれど、今を知っている人たち。
友達ではないけれど、信頼する隣人。
下宿には、そういった絆があるような気がします。
そして、この作品がミステリであるからには、この下宿で、彼らの「砦」の中で、殺人が起こるのです。
他人で、友達でもなく、生い立ちも知らない、けれど信頼する隣人。
その中から犯人を見つけることになった京介は、まだ大学生だった京介は、一体どんな気持ちだったのでしょうか。
そしてそれを横で見ているしかできなかった、まだ京介との関係の浅い深春は、何を思ったのでしょうか。
探偵役を担う人物は、大抵の場合、どこか超越したような、人間味の感じられない、ワトソンの理解の範疇に収まらない人間です。
京介も例に漏れず、生い立ちや過去の出来事など語られず、ただそこに探偵役として、罪を暴く役目として存在しています。
その、涙。
そこには、一体どんな意味があったのでしょうか。
というのがこの巻だけ読んでもわからない!
なんならシリーズをだいぶ読んでもわからない!!
結構あとの方になって、シリーズが完結する頃になってようやく過去が暴かれるのが桜井京介という男!
しかもシリーズ第一部は中学時代に散々読み返しましたが、第二部、第三部(とわたしが勝手に呼び分けているだけですが)のほうは大人になってからでた分もあるので、読み返しがほとんどできていません。
ひたすら重いことだけは覚えている。
いや、殺人を扱う以上、重いのは当然なんだけども。
普段は蒼が語り手となるこのシリーズで、深春が語り手となる珍しい巻でもあります。
この物語を気に入って読み返していたわたしは、やっぱりキャラ読み派なんだなあと、改めて思いました。
だってやっぱり知らない人の事件よりも、知ってる人の事件のほうが読み応えあるもの。
ところでこのシリーズの中で一番好きなのは、次回このシリーズを紹介するときに出るであろう、蒼が主人公となる物語です。
一番好き。
『灰色の砦』はそういう意味では3番目に好きな作品です。
「建築探偵桜井京介の事件簿シリーズ」はいいぞ。
放っておいても好きなものを紹介しますが、サポートしていただけるともっと喜んで好きなものを推させていただきます。 ぜひわたしのことも推してください!
