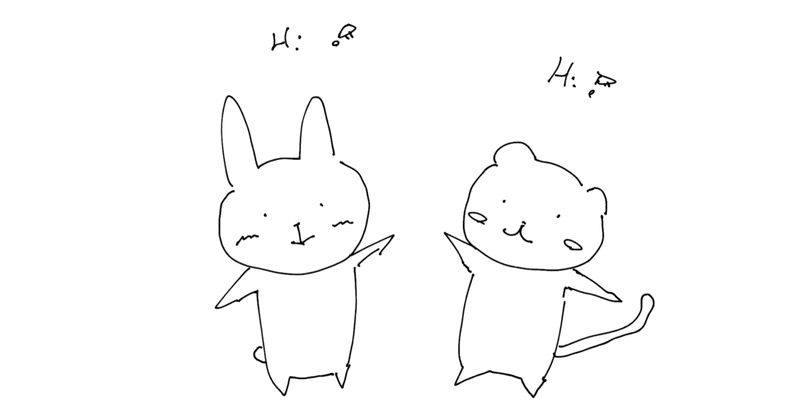
人との距離感は幸福度を分ける
一人の時間が無いとダメな派でして。
こうしてnoteを書いている時間というのは、自分に没頭できるエッセンシャルな時間で、心のバランスを取る上で必要な時間なのかなと感じています。
人との距離感というのは、少なくとも自分にとっては永遠の課題です。近過ぎると疲れてしまう。遠すぎると一人で生きてるのと変わらない。
あまりに近い関係よりも、適度な距離感のある方が心地良かったりするのは、矛盾しているし、贅沢だなぁと自分でも認識はしています。
人は繋がっている
![]()
世界は繋がっています。前に一度使ったお話ですが、世界中のどんな人とでも、6人を仲介すれば、繋がることができると言われています。
スモール・ワールド現象ですね。思ったより世界は広くないのです。
体感的にも転職をすると感じることで、大きな会社に入れば大抵は一人、二人は昔の会社の出身の方がいたりします。
良く言えば、どんなところに行っても繋がることができる人はいる。悪く言えば、人の関係からは逃れられないのが人間ということです。
ちなみに、数学的に同じような考え方で、学校のクラスの中には8割ぐらいの確率で、誕生日が同じペアがいるという話もあります。面白いですよね。
良いフィードバックを貰うには距離感が必要
![]()
これもスモール・ワールド理論を引き合いに何かの講演で聴いたのですが、良いフィードバックをもらうには、適度な距離感が必要と言われています。
自分と密接に繋がっている=一次の繋がりの人は、あまりに近すぎるので、適切なフィードバックをできない状態になっていると言われています。
むしろ、毎日接していないような、1人や2人を挟んだ、 二次や三次のつながりの人の方が、自分を客観的に見てくれているということです。
これは会社が事業を考える時も同じで、会社の中の人は、その環境に浸りすぎて、客観的な判断をできなくなってしまうと言われています。
そこで会社にとっては素人、一方で業界には習熟しているコンサルタントの出番と言うことです。 まあ、半分売り文句ではありますが。
ただ、適度な距離感こそが、客観的で本質を射抜くようなフィードバックを可能しやすいのは、経験からもその通りかなと思います。
頭と心をさらけ出しているnote
![]()
そう考えると、日常的に会っている人よりも、noteぐらいの距離感の人の方が客観的なフィードバックをもらえるのではないかなとも思っています。
発信はその人の頭や心の反映であって、それをしっかりと口頭で語る機会というのは、日常ではなかなか無いのではないでしょうか。
適度な距離感という素地に加え、頭と心をさらけ出しているという事から、よりnoteのフィードバックは適切になりやすいと感じています。
ちなみに私が匿名なのは、会社の中にこんな考えの奴がいるとバレてしまうと、戦略の判断に影響しかねないと思っているからです。考えすぎかもですが。
司馬遼太郎の三国志の最後には、諸葛孔明と司馬懿の頭脳戦が描かれます。その中で、諸葛孔明が何を食べているかを司馬懿がスパイを通じてチェックする描写が出てくるんですね。
それに感づいた諸葛孔明は、司馬懿が自分の命がどれぐらい持つかというのを見極めてると嘆くのです。
これは真理でして、戦略や考えというものは、最終的には属人的なものです。その頭の中を、毎日のように公開している奴が社内にいたら…笑
繋がりと距離感の模索
![]()
それでも、人の役に立ちたいという気持ちもありますし、自分の考えを読んで頂きたい、そして、その反応を知りたいと思っている自分もいるのです。
ということで、結局毎日のように頭の中を公開してしまっています。これは、つまりは繋がりを求めているからなのでしょう。
結局、人は社会的な生き物なので、一人で生きることはできないのです。その中での人との距離感の取り方は、生きる上で必須のスキルのひとつではないでしょうか。
密な関係を求める方もいますし、少し離れた関係を求める方もいる。それぞれの人が、自分にとって心地良い関係を模索すればよいのだと思います。
ということで、積極的に人との距離感を探りましょう。人間関係は人生の幸福感を分ける大きな要因だと思っています。
そして、近すぎる・遠すぎる時には声に出して相手に伝えること。それでしか、上手な距離感は創れないのだと思います。
なーんて言ってますが私、この声に出して伝えるのが苦手なのですが。
皆さまが、心地良い人との距離感を見つけられることを祈っております。
ではでは。
<似たような話題かも>
<関連する本かも>
ブルーバックスの本は、ダイレクトには役に立ちにくいのですが、もの凄く面白い本ばかりです。読んだ後1-2週間は分かった気になって使おうとするのですが、その後はすっかり忘れてしまいます。ただ、分かった気にさせる技術は素晴らしく、次はそこを盗むために、また読もうと思います。
<このnoteを書いたしょこらはこんな人です>
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます!頂いたサポートは、noteを書きながら飲む缶コーヒーになっています。甘くて素敵な時間を頂きまして、とっても幸せです。
