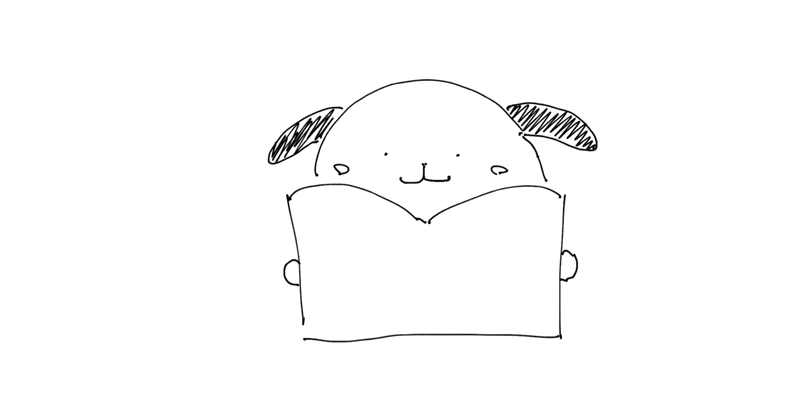
思考の呼び水としての本棚の条件
近年中で、一番ブラッシュアップされている本棚を見てしまった。
先日Web会議があったのですが、その中で本棚を映して下さった方がいらっしゃったんですね。
その本棚が、近年稀に見るブラッシュアップ度合いだったのです。 本当に、素晴らしいの一言でした。
本棚を見ると、その人の頭の中が大体見えると言われています。我々の体は何を食べたかで出来ており、我々の心は何を読んだかで出来ているのです。
良い本棚の3条件
![]()
いわゆる知的生産術系の本を読むと、ほぼ必ず載っているのが本棚の整理術です。本棚とアウトプットは直結しているということですね。
作者の方が、綺麗に整理整頓された壁一面の美しい本棚をドヤっと紹介するお決まりのコーナーです。様式美ですね笑
他方、ジャーナリストの田原さんの仕事部屋が時折テレビに映るのですが、ものすごい資料の量なのです。ただ部屋中に平積みされているので、一見綺麗には見えなかったします。
ただご本人は、おそらく完璧に何がどこにあるのか把握されていらっしゃって、必要な資料を探すのに苦労している感じはありません。
ということからすると、綺麗に本棚が整っている必要もないのだと思います。そんなことから、本棚に求められるのは、以下の3つではないかと考えています。
1. 一覧性
2. アクセスの容易性
3. 叩かれて磨かれた質の高さ
一覧性は言わずもがな一番重要なことです。背表紙を見ることができない本は無いのと同じである、ということですね。
ぱっと見た時に、そこに何があるのかを一覧で見ることができること。これは、本棚の一番大切な要素だと思います。
アクセスの容易性は、カテゴリ分類されているかどうかです。このカテゴリ分類は、当人の考えが一番強く反映されるところです。
例えば、図解の作成術のカテゴリの中に、 哲学の本が入っていてもいいわけです。それは、その人の頭では抽象的に考えるというメタ思考で図解が区分されているということです。
最後に、質の高さです。知的生産術を書くような人のもの凄い本棚は、それはそれで素晴らしいのですが、一般人には難しい。
一方で、そんな大きく美しい本棚でないといけないかと言うと、田原さんの例からしてもそんなこともなく、自分の頭を刺激することができればそれで良いのです。
背表紙を見て何かに気付く。気になった時にふと本を手に取り、付箋を貼っている言葉を見て、頭を刺激する。それができれば十分。
そのために、同じカテゴリーに入る本を、定期的に更新すること。良い本が見つかったら、一番役に立っていない本と入れ替える。
そうすることで、本棚は小さくとも磨かれていきます。
本棚は思考の呼び水
![]()
このような条件を満たす磨かれた本棚は、眺めるだけで思考に刺激をくれるものです。
よく「資料は議論の呼び水」と言われます。これは資料がきっかけで、議論が盛り上がればそれで良いということです。
水面に一滴の雫を垂らした時の波紋のように、何か刺激を与えることで、大きく波紋が広がっていく。 そんな呼び水こそが大切なのです。
そして整理された本棚は、そんな滴のような役割を果たしてくれます。悩んでることに対して、考えのきっかけを作ってくれるのです。
そんな実戦を経て、本棚もまたブラッシュアップされていきます。全然別のカテゴリに入っていた本が、偶然繋がるという経験をするのです。
こうして考えが横断的になり、また新しい考えを見つけることができる。それが、思考の呼び水となる本棚です。
と、ここまで来ると、本棚もその人の外部脳ということになります。自分の頭に加えて、もう一つ頭を持っているような状態なのです。
そんな本棚を持ってる人は強い。素晴らしい思考力を持っているものです。
え、私ですか?数年前の引っ越しで、全部ぐちゃぐちゃになってしまい、心が折れてしまいました。
時間をかけて直していきたいと思います。Kindleだと本当に一覧性が弱いんですよね。やっぱり、ぱっと見パワーは物理が一番。
また、本屋さんに行きたくなっちゃいました。
ではでは。
<似たような話題かも>
<関連する本かも>
『知的生産の技術』に並んで紹介される、知的生産術の定番本です。1986年出版の本が、2008年の東大・京大の生協書籍販売No.1を獲るって凄いことだと思います。発行部数は累計200万部超えで、ここまで来ると教科書ですね。配った方が早いと思います。
<このnoteを書いたしょこらはこんな人です>
<Twitterもぜひフォロー下さいませ>
アイディアが浮かばなくなったら、何でも良いので紙に書く。これはガチですね。何故こんなに効くのだろうと思っていたのですが「自分のものは、ひいきして見てしまう」という言葉で納得。判断のためには、とにかく自分の外に吐き出して、ひいきをやめること。これがリバースエンジニアリングか…(違う
— しょこら (@130KoFF) May 12, 2021
最後まで読んで頂きまして、ありがとうございます!頂いたサポートは、noteを書きながら飲む缶コーヒーになっています。甘くて素敵な時間を頂きまして、とっても幸せです。
