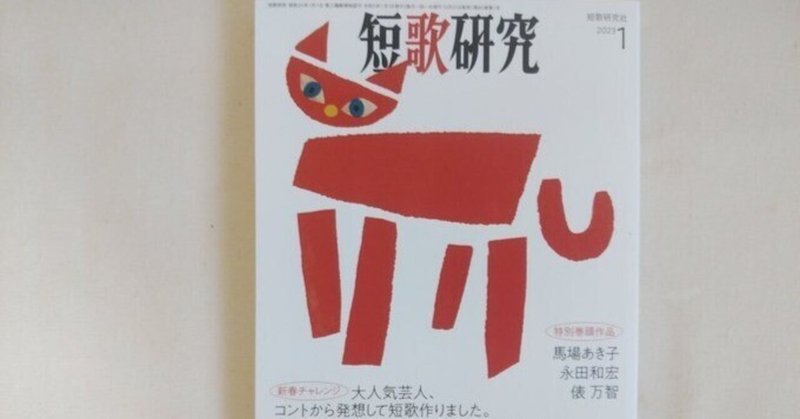
『短歌研究』2023年1月号
①帯広の翌日九州また東京 後期高齢者ほんとかよ、俺 永田和宏 歌集『某月某日』でもその移動量はハンパでは無かった。身体をいたわって欲しいが、忙しいのが好きなのかも知れないと思ってしまう、ここまで来ると。後期高齢者とは言ってもまだまだイケる、俺、という感じか。
②もうすぐ死ぬこれはまちがひないけれどそのもうすぐがわからないから 永田和宏 「もうすぐ」に程度の差こそあれ、誰にとってもそうだろう。また分かったら却って辛い。分からないから生きていられるのかも知れない。この作者の場合は「わからないから」無理してしまうのだ。
③さうかもう還暦だつたか佐野朋子逢ひしことなき人の歳月 永田和宏 小池光と共に佐野朋子も齢を取ったのだ。そこが架空の人物と言えど、短歌作品の特徴だろう。そうでなければリアルさが失われる。小池光の長年の読者にとって佐野朋子の還暦は来たるべきものが来た印象だ。
④吉川宏志「1970年代短歌史 土俗論」〈七〇年代の若手歌人の作品の中にも、ほの暗い風土と死者の歌がしばしば存在していて、深い余韻を齎している。ここには、三十年という時間が経ち、忘れ去られようとする戦死者たちを、戦後に育った人々が思い返そうとする心理が反映していたのではなかったか。八〇年代後半以降になると、戦死者はさらに忘却され、時代は賑やかさを増してゆく。七〇年代は戦死者のなまなましい存在感が漂っていた最後の時節だったのかもしれない。戦後まもない頃は、戦争への厳しい批判が巻き起こり、戦死者を静かに哀悼することができなかった。三十年が過ぎ、ようやく風土の自然の中で穏やかに戦死者は供養されようとしていた。〉
岩田正の土俗論から発して、その功績と弱点を考察するだけでなく、戦死者への視点というところまで論が及んでいる。七〇年代を振り返ることの大切さを痛感した。
⑤楠誓英「短歌時評」10月号「短歌テトラスロン①歌会」について
〈ほとんど批判はなく、少し物足りなく感じた。短歌観や世代が近い人たちで歌会をすることの意味は果たしてあるのだろうか。もちろん、「次世代を担う歌人」という趣旨からすれば、理解できるのであるが、もう少し多様な歌人を集めても良かったのではないだろうか。〉
これには同意する。参加者の多くが同時期に大学短歌会で交流していたメンバーだったのでは。「次世代を担う歌人」というのなら、なおのこと、多様性が重要なのではないだろうか。
⑥楠誓英「短歌時評」〈次に、現代短歌評論賞であるが、興味深い論考が多く、近年の評論賞では最も読み応えがあった。しかし、誌面の都合であろうが、次席(次席は抄録)までしか載っておらず、残念に思った。座談会の内容もなるべく載せて欲しかった。〉
これも同意。楠の文章は褒めるべきところは褒め、指摘すべき点は指摘している。文章もストレートで、読んでいて気持ちがいい。私自身何となくモヤモヤと思っていたことが、この時評を読んではっきりした。あ、そうだよな、という感じ。
2023.1.21.~22.Twitterより編集再掲
