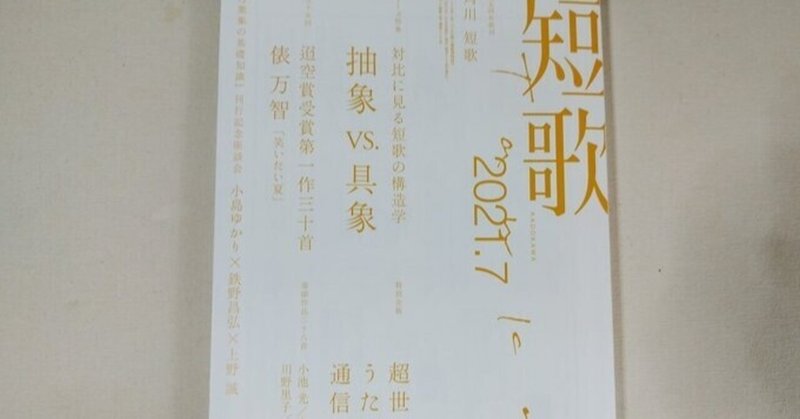
角川『短歌』2021年7月号(2)
⑩みぞおちを絞り上げては新しき涙を呼びて幼子が泣く 浜名理香〈この泣いている幼子は、目の前に居る唯一無二の具象ではない。いつかどこかで、そういう場面を繰り返し見ているうちに普遍化された幼子の像である。〉このように見たものを記憶しておいて再現するのも写実と思う。
⑪高木佳子「まず描く力を」〈対象の把握が明確であることは前提として、読み手が受け取る情報を、作り手がどの程度まで提供するのかが鍵ともいえようか。〉作り手の意識してのコントロールが大切、ということか。伝える情報量に余白があれば思わぬ作用も起こると思う。
⑫島田幸典「具体がまとうもの」〈…短歌の表現に不可欠な単純化、すなわち捨象と抽出がある。抽象は具体に対立するのではなく、それに随伴し、あるいはそこから展開するのである。〉具体があってそこから抽象が始まるというのは今回の書き手にかなり共通する。もちろん私も同感だ。
⑬『万葉集の基礎知識』刊行座談会 上野誠「研究史や、問題点なんかは語り合うんだけれど、好き嫌いという軸が研究者にはない。」実作者の評論との大きな違いだな。私なんか、まず好き嫌いが無かったら、書くエネルギーが湧かないんだけど。常に「好き」を推してます。
⑭『万葉集の基礎知識』刊行座談会
小島ゆかり「どの方も、必ず、文の途中に、細かくカッコして、何年に誰が言ったというようなことを書いていますよね。」
鉄野昌弘「ここまでは人の言ったことだが、ここから先は自分の主張だということをはっきりさせたい。」
研究者の論文を読んで驚くのは、この何年に誰が言ったというカッコの多さ。確かに小島の言うように一般向けの本だと読む時に気が散る。しかし逆に短歌評論には他人の論を踏まえていることがはっきり書いてないと思うものが多い。自分で書く時もどう引用すべきか分からないことがある。ルールが無い。
⑮東郷雄二「時評」〈いまから数年後に、新指導要領に基づく教育を受けた高校生が大学に入学して来たときに、「漱石って誰ですか?」と質問する学生が出て来て、「ついにその日が!」と心の中でつぶやく先生がいないとも限らない。〉すぐそうなると思う。いいとか悪いとかは置いといて。
短歌の実作者ではない、純粋読者である東郷雄二の「時評」が始まった。実作者ではない視点の論が毎月楽しみだ。
2021.8.17.Twitterより編集再掲
