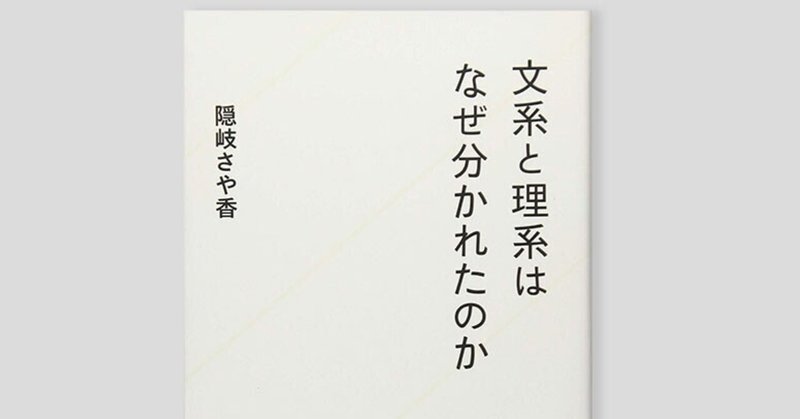
文系と理系はなぜ分かれたのか(感想)_集合知を発揮するために補い合うこと
著者は隠岐さや香で2018年に出版。
「文系と理系はなぜ分かれたのか」は、文系/理系が分かれていく歴史的な経緯だけでなく、ジェンダーギャップ、企業や社会課題への関わり方についても考察されていてとても興味深かった。
ページ数こそ少ないが、情報が広範囲にわたっているため自分なりに整理して咀嚼するために以下、備忘メモと感想などを。
理系の黎明期
日本に西洋の人文社会科学や自然科学が体系的に導入されるのは、19世紀後半ということで、もとを辿り第1章では中世ヨーロッパの歴史的背景から説明される。
中世ヨーロッパの大学では身分制になっており、神学・法学・医学は重視されたが、商業や機械学芸とみなされた数学の扱いは低かった。
それはアリストテレスの考えに従い、自然現象は複雑すぎて数学では記述できないとの理解が主流で、神が創った目という感覚器官を超えたものを技術で補強する必要性を感じていなかったから。
しかし、ルネサンス期に2つの大きな変化によって、自然を数学というフィルターを通して考えはじめるようになったとのこと。
・自然を理解するために、人間の五感よりも望遠鏡などの技術のもたらす情報を信頼するようになった
・数学により、自然をよりよく理解できるとの考えが本格的に広まった
近代的な法学や文学、歴史研究を対象とする文系について
中世までのヨーロッパでは、文系的な知識全体が教会と王権の支配下にあり強い統制がかかったいた。
・歴史は王の求める政治史か、聖書の記す神の歴史しかなかった
・文学的・哲学的な営みについては、教会と王権が問題と見なした文書についての禁書リストが定期的に作られていた
しかし15世紀頃から本格化したルネサンス期に、古代ギリシアの哲学や文芸を模範にした人間中心の視点を強く持つようになった。
そして、大学の中で社会学や経済学といった分野が定着するのは19世紀半ば以降、文学や歴史学、哲学の研究者が人文科学という概念でまとまりを意識するようになるのは19世紀末~20世紀初頭になる。
第1章では以上のように過去の西洋での理系/文系について大まかに書かれており、「自然科学は技術の進歩によって得られる情報をもとに客観的に物事を捉えること」「人文社会科学は神を中心とする世界秩序から離れ、人間中心の世界秩序を追い求めること」と位置づけられている。
文理融合の必要性
第2~4章では、日本に人文社会科学や自然科学が導入された歴史的な経緯、理系が就職に有利な理由、ジェンダー格差や理系が稼げる理由などについて考察されており、第5章では現代の文理融合/連携する意義について書かれている。
読み終えた感想としては、タイトルの「文系と理系なぜ分かれたのか」ということよりも、各分野の研究をどのようにして役立てるべきなのか、と投げかけられている第5章が心に刺さった。
これまで各分野の研究は、主に短いスパンでの利益を出すための技術や、限られた企業・国など狭い範囲での利益を最大化するために利用されてきたということを感じる。それによって各地域や国ごとの格差が拡大を助長することになっていることも。
そもそも社会的課題を扱う/扱わないという選択からして政治的なバイアスから切り離せないという指摘も興味深い。
あらゆる研究にバイアスがかかるのであれば、著者が指摘するように「違う風景を見て、それを継ぎ合わせ」るしかしない。つまり可能な限り多くの情報を集約・検討することで、集合知を発揮させるということだ。
そのためには、マイノリティの意見であっても傾聴できるような文化が必要だが、そうはいっても独特な研究をしている人には自身の研究へのプライドがあり、そのプライドがあるからこそ他者の意見を受け入れ難いというのが本当のところだろう。だからこそ、論争自体を否定しないのも必要ということだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
