
The Trash Can Sinatras(感想)_繊細で瑞々しく、美しいメロディーを奏でるギターポップ
The Trash Can Sinatras(以下TCS)は、スコットランドのアーバインで1986年に結成されたバンド。直帰の予定としては、2021年9月に、当時のシングルB面曲などを追加収録した2ndアルバムの再発が予定されている。

TCSは瑞々しいヴォーカルと美しいメロディーを奏でる良質のポップソングを発表しているが、私の印象では楽曲の品質の高さとチャートやセールスの乖離が大きいのではと考えている。(そのせいで、熱狂的なファンが多いともいえるが)
スタジオ・アルバムでは、1990年~2016年の間にたった6枚を発売したきりなので、活動期間の長さの割にリリース枚数は少ない。
以下、過去作品についての感想などを。

Cake
Go! Discsと契約したTCSはShabbyRoadスタジオを購入し、作成されたデビュー・アルバム。
アレンジや演奏の未成熟さはあるが、むしろネオアコバンドにおいてはそれすらも魅力になるというお手本のようなアルバムで、さわやかなハーモニーや甘酸っぱいメロディーなど、いかにもネオアコ好きのリスナーに好まれる要素が絶妙なバランスで詰まっているアルバム。
その中でもやはり、John Leckieがプロデュース/ミックスを手掛けた「Obscurity Knocks」の爽やかなカッティングギターと青臭いメロディーが心地よく、とてもフックの強い曲のためアルバム入手当時、何度もリピートした曲。今聴き直しても魔法がかかっているのではと思うほどの名曲。
静かでサビのハーモニーが美しい「You Made Me Feel」も何度も聴いた。
当時の日本の音楽雑誌で、本作はThe La'sやAztec Cameraなんかと一緒にネオアコ枠で紹介されており、1998年に6曲のシングルB面曲をプラスした『Cake+6』が再発されている。(Spotifyでボーナス・トラックは聴けないようで残念。。)また、
このアルバムからのシングル・カットは以下3曲で、括弧内の数字は英国シングルチャートの順位。
Obscurity Knocks(86位)
Only Tongue Can Tell(77位)
Circling The Circumference(-)

1990年当時のイギリスはマッドチェスター全盛だったので、アコギと美しいハーモニーというのは、流行りの音楽ではなかったのだろうがそれにしても、「Obscurity Knocks」の最高位が86位で、アルバムも74位と振るわない。よっぽどGO! Discsのプロモーションが悪かったのではないかと勘ぐりたくなるほどだが、USではアルバムが10万枚のセールスがあったというのが少し意外。

I've Seen everything
1993年発表の2ndは、英国アルバムチャートで50位と1stよりはマシだがそれにしても低い。
全体的に控えめな曲調になっており、1stのキラキラした感じの延長を想像していていたため、私としては正直言って期待外れだった記憶がある。
周囲でも同じような評価の人が多く、そのせいでむしろ1stが一番良いという人が多かった。
はっきり言って地味な印象を持っていたのだが、シンプルで深みのある曲調は年を経て何度も聴き直していると、むしろ愛着が湧いてきて、アルバム全体をトータルでは、現時点でのTCSの最高傑作は本作なのではと思うほど良いアルバムだと思う。
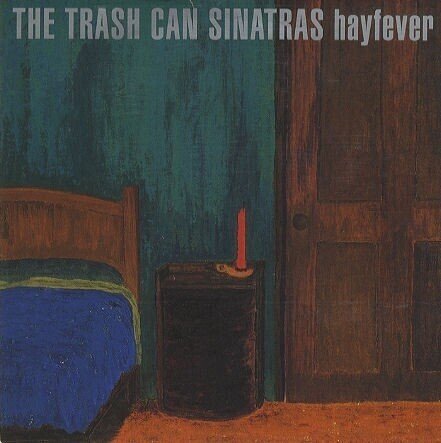
また、1stシングル「Hayfever」のB面に収録されている「Kangaroo Court」も爽やかなポップソングで名曲。
このアルバムからのシングル・カットは以下2曲で、この曲以降シングルはUKチャートにインしていない。
Hayfever(86位)
I've Seen Everything(-)
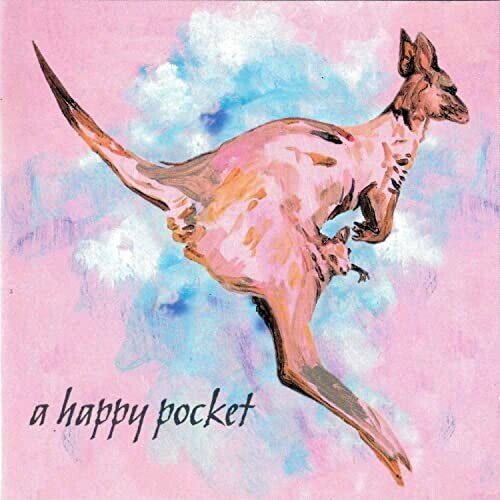
A Happy Pocket
3rdアルバムは1996年に発表。USのディストリビューターは本作を販売しなかったっため、当時の日本とイギリスで発売されている。USではグランジが流行っていた時代とはいえ、こんな素晴らしいアルバムを販売しないなんて。
インストの「Outside」はいつまでも聴いていたいし、シングル・カットされた「Twisted And Bent」「How Can I Apply...?」も良いけど、「I'll Get Them In」の切ない旋律もクセになる。
過去作と比べると、全体的に楽曲のバリエーションが増えて飽きないし、総じてクオリティが高い。トラキャンのアルバムの中では、1stよりも好きな1枚。
1996年当時、UKではブリットポップ全盛と思われるのだが、本作はアルバムチャート125位とセールス的には振るわない。
そうしてこのアルバムの発表後、所属レーベルのGo! Discsが破産してUniversalに買収されるも契約されなかった。また、ShabbyRoadスタジオは売却されているため、金銭面でかなり苦労していると思われる。
1996年はThe Smithsのカバーコンピレーション『The Smiths Is Dead』に、「I Know It's Over」が収録されており、1999年12月にソニージャパンからリリースされたニューシングル「Snow」(Randy Newman作曲のカバー)を発表している。

Weightlifting
ライブは続けていたらしいが、情報が入ってこないためもうとっくに解散しているものと思っていたら、2004年に8年振りに発表された4thアルバム。
発売当時、冒頭「Welcome Back」の賑やかなエレキ・ギターのサウンドからTeenage Fanclubのような印象で、意表をつかれたのだが、アルバム全体を通して美しいハーモニーや瑞々しいボーカルは健在。シングル・カットされた「All The Dark Horses」も佳曲だ。
このアルバムの発表時のインタビューで、同じグラスゴー出身でセールス的に成功しているTravisを引き合いに出して、自分たちだって良い曲をつくっているのにセールスが振るわないことを愚痴っていたと記憶している。
セールスが伴わないのは、音楽の芸術性を大切にするがゆえに、バンドが商業的な成功を嫌悪しているのかもと考えていたのだが、どうやらそういうわけでも無さそうで、バンド活動を継続することにかなり苦労していることが伺える。

In The Music
2009年発表、約4年半ぶりの5thアルバム。
本作のプロデューサー、Andy ChaseはTahiti80も手掛けている人で、その影響のせいか全体的にとても耳馴染みの良い楽曲が揃っていて、キーボードやリズムのアレンジが洗練されているし、バックで邪魔しないように鳴っているパッド系の音が好みでとても聴きやすい。少しTSCらしくないといえば、そうなのかもしれないが、2000年以降の3枚では私の一番好きなアルバム。
Frank Readerのヴォーカルの温かみを感じられる「Oranges and Apples」が佳曲で、Carly Simonがゲスト参加しているやさしいバラードの「Should I Pray ?」も素敵だ。

Wild Pendulum
2016年発表の6thは、前作から7年のブランクがあったことや、私自身もTCSを最初に聴いた頃と比較してかなり歳をとったことで、音楽との向き合い方が大分変化していたが、瑞々しさに溢れる「Let Me Inside (Or Let Me Out)」を聴いた瞬間、やはりこのバンドの良さは変わらないと思った。
本作が日本盤でも発売されたのは、細々とだが日本のファンもまだそこそこ存在しているということだろう。
「Best Days On Earth」での多幸感は、期待を裏切らないいつものTCSだが、ゆったりとした3/4拍子の「I Want To Capture Your Heart」や、は少しだけディスコ調の「All Night」など、かつての素朴なネオアコバンドの音を想像すると意外な印象を受ける。
また、ピアノやオルガン、バイオリンなど音色が増えており、アルバムトータルでの音の厚みやアレンジの幅は広くなっている。
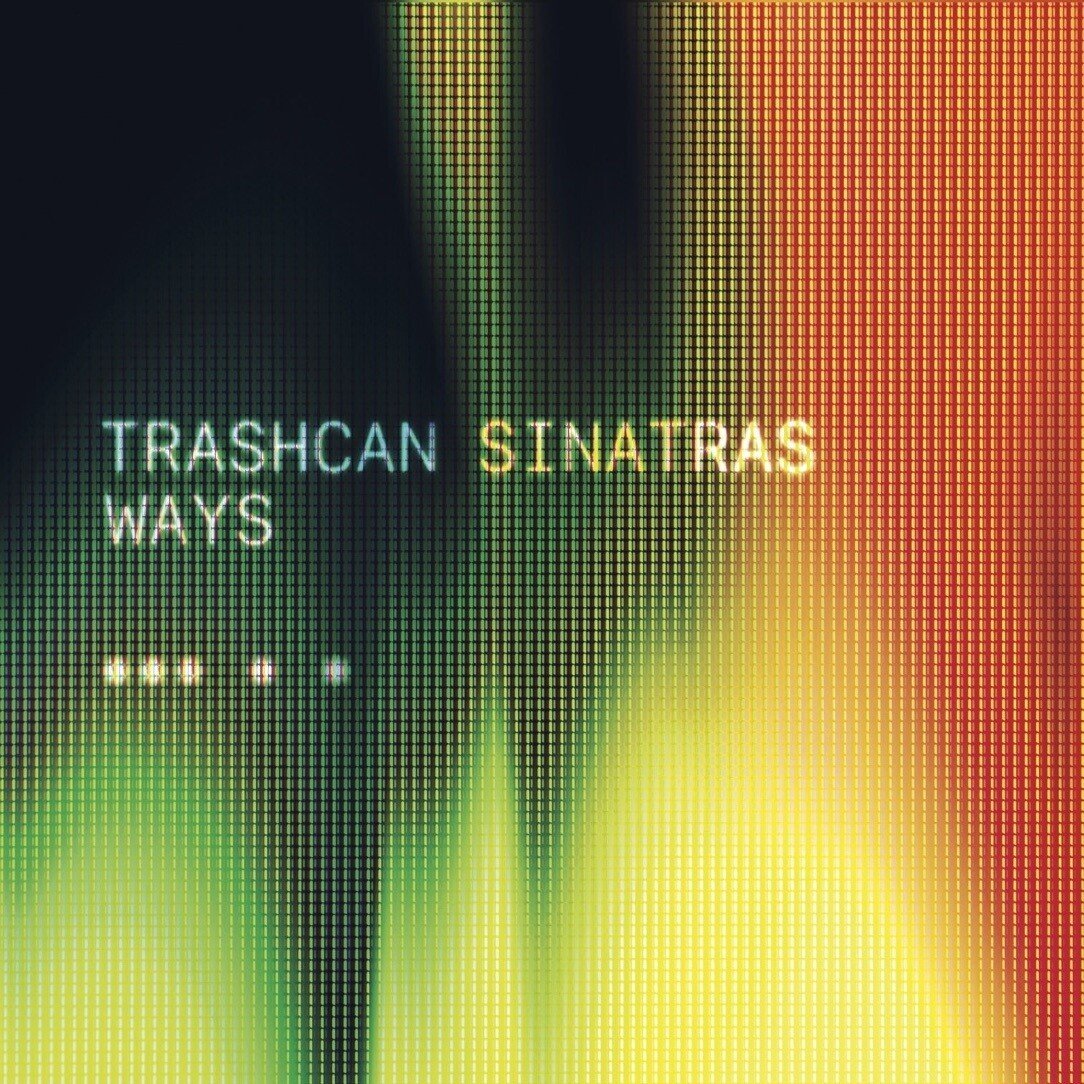
20020年には、久しぶりの新曲となる「The Closer You Move Away From Me」と「Ways」を発表しているのだが、変わらずに美しい旋律を響かせているのが嬉しい。
-----------------------------
また、TCSはライブ盤が多く、オフィシャルなもので9枚発表されている。これは、スタジオ・アルバムが6枚しかないことを考えるとかなり多い。
Chewing A Brick | Live Recordings (1999)
Zebra Of The Family (2003)Fez (2005)
Live Series Radio Sessions Volume 1(2009)
Live Series Radio Sessions Volume 2(2009)
Brel (2010)
On A B Road Acoustic(2018)
All Night In America(2018)
Zebra Of The Family 2(2019)
旧作を含めて改めて聴き直してみると、比較されがちなBell & SebastianやAztec Cameraと比べても、TCSの作品はどれも一定の水準を満たしているのだが、セールスが伴わないのはプロモーションに問題があったのか、それとも私のような日本人の耳に馴染みが良いだけなのか。
いずれにせよ、寡作であることからも器用なバンドではないことが想像され、少し地味な印象であるのは否めないのだが、30年以上も素晴らしい楽曲を奏でてくれていることが嬉しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
