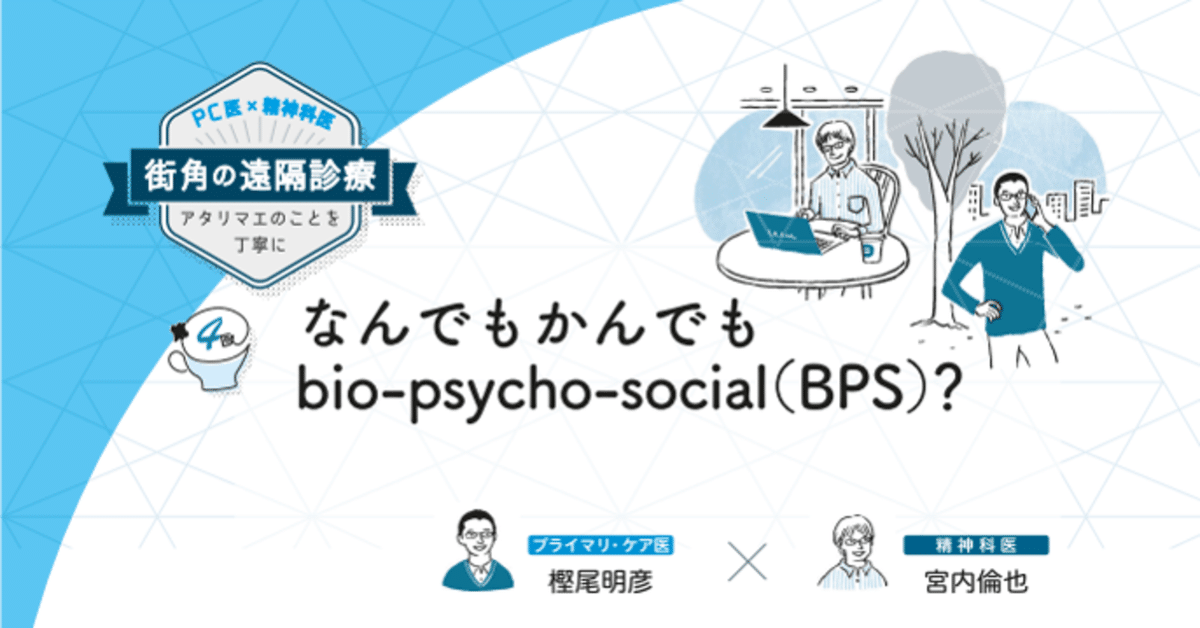
【街角の遠隔診療】第4回 なんでもかんでも bio-psycho-social(BPS)?
樫尾明彦(プライマリ・ケア医),宮内倫也(精神科医)
この連載について
今後広がりをみせそうな遠隔医療.しかし実際にやろうと思うと不安な点がたくさんあります.本連載ではプライマリ・ケア医と精神科医による対話から日常で遠隔診療を行うポイントを探っていきます.
事 例
40代男性,独身.仕事はテレワークになり,家に1人でいる時間が長くなってきたなかで毎日心臓の鼓動を感じるようになって1週間以上経過したため,電話診療希望あり.
樫尾:この患者さんは,いままでとくに既往のない方ですが,テレワークになって1 ヵ月くらいしたら,自分の心拍が気になるようになって,それが続くので電話診療で相談されました.頻脈や徐脈,脈の不整は,問診上なさそうで,労作時はむしろ心拍を感じにくく,じっと仕事をしているときや,寝床について眠れるまでに心拍を感じやすくなったとのことでした.
宮内:精神科では,ほかの科でいろいろ否定されてから患者さんが紹介されてきますが(もちろん精神科で最終的な確認はしますが……),この場合は先生ならどういった点から入っていきますか?
樫尾:やはりまずは身体疾患の有無が気になりますね.COVID-19の影響さえなければ,すぐに来院してもらって,バイタル測定や聴診,心電図を調べたいところですが,心拍数測定と,不整脈かどうかは電話でもある程度判断はできます.もし電話診察中でも脈の不整があるとか,徐脈や頻脈があるなら,やはり来院が必要かと思われます.また,患者さんが電話で相談をしてきた時点で,来院して検査や診察を希望している可能性も高いかとも思われます.
宮内:医療上必要であれば,そして患者さんが診察や検査を希望していれば来院をということですね.混雑が怖い場合は空いている時間に何とか,というところでしょうか.こういう場合は,身体疾患であってもなくても,認知・行動・感情への配慮は必要ですね.DSM-5には“身体症状症“という分類があるのですが,それは DSM-IV-TR の “ 身体表現性障害”とは異なり,身体疾患の除外は必須ではありません.身体疾患であっても症状への“とらわれ”が強ければ精神科的介入は選択肢であるという,非常にリエゾン的な発想でよいなぁと思います.私はこの図1が気に入っているのですが,身体症状にはこのようなスタンスで取り組むことが大事だと考えています 1) .

樫尾:DSMの分類の変化,紹介していただいた図も興味深いですね.疼痛には,その機序だけでなく,いろいろな要因が影響しあっているという理解でよろしいでしょうか.身体疾患が否定できてから精神的な要因を考えるのでなく,当初から両方とも考慮しようというのは画期的ですね.
宮内:この図では「痛み」になっていますが,身体症状全体について同様の考え方をすべきだと思っています.「身体の病気だ」,「精神的なものだ」という二分法ではなく,種々の要素をしっかりと考えて対処していくことが大切です.ただ,これが行き過ぎると「何にでも等しくbio-psycho-socialにかかわろう」となり,思考停止に陥るので注意が必要です.種々の因子は患者さんによって重みが異なるので,どこを重点にするか常に個々の患者さんで考えねばなりません.bio-psycho-socialという言葉は絨毯爆撃的で,ある意味で節操がないのです.
樫尾:bio-psycho-socialといえば,家庭医療でも生物心理社会(bio-psycho-social:BPS)モデルとして,家庭医療の教科書には必ずといっていいほど出てきますが,実はBPSモデルを提唱したEngelは,精神科の雑誌にも発表していましたね 2) .家庭医は,症状の背景にpsycho・social(心理・社会)の課題がないか考えるのはまさに教科書的ですが,患者さんに何か該当するエピソードがあると「きっとそれ(だけ)が根っこの問題だ!」と行き過ぎる傾向には要注意かと思われます.
宮内:精神科ではBとPとSを同じ配分で考えて,何でも BPS で対処するというちょっと悪い習慣ができつつある風潮です.BPSのどこに重きを置いて治療するのかと“熟考”することが,精神科治療においてもっと大事にされるべきですね.
この患者さんに関しても,図1で示した各要素に重みづけをしながら対応するのが妥当かと思っています.
樫尾:精神科と家庭医では,BPSの捉え方がやや違うのでしょうか.家庭医のみが,BだけでなくPとSも考えている……という「わけではない」ことは,改めてわかりました.
この患者さんは,一度来院していただき,バイタル測定,聴診,心電図施行して,とくに異常所見はみつかりませんでした.何も異常所見がなかったことで安心して帰宅しましたが,数日後の電話再診では,まだ心臓の鼓動を感じるのは続いているとのことでした.テレワークを続けていると,昼夜問わず仕事ができる反面,他者とのコミュニケーションはメールや1日1回のweb会議で,食事も出前で頼むと,数日間外に一歩も出ないこともあるとのことでした.家に1人っきりで,コミュニケーションの量がかなり減っているように感じ,1日1回は外出してみるように促してみました.外出に関して,他人と十分な距離をとっていれば,マスクも不要とされています 3) .
宮内:外出の促しとのことで,それでうまくいくとホッと一安心ですが,不安が強いと何度も電話をかけてくる患者さんもいるかと思います.精神科病院であれば病院そのものがそれに慣れているのですが,そうではないプライマリ・ケアの現場では,その点はどうやりくりしているのかをお聞きしたいです.
樫尾:そうですね.頻回の電話の対応は,COVID-19流行前は,在宅患者さんの不安の対応ではあったかもしれませんが,1人暮らしでも訪問介護や訪問看護もすでに始まっていれば手分けして対応していました.この患者さんからは,頻回に電話がかかってくることはなかったものの,外来患者さんの電話対応はなかなか在宅の複数の職種のように手分けをするわけにはいかず,頻回の電話への対応をまさにどうしようかスタッフと相談中です.たとえば,こちらから毎日様子を聞く電話を,一時的にでも,なるべく決まっ
た時間にでもしてみるなどでしょうか.
この患者さんは,外出を促すことと,仕事のピークがその後落ち着いたとのことで,心臓の鼓動を感じることは,だんだん減ってきたとのことでした.
宮内:そうでしたか.プライマリ・ケアで対応するなら,患者さんに「いまは電話が混んでて十分にお話を聞けません.この日の何時から何時までならあなたのために電話を取っておけるから,そのときにお話ししましょう」などとお伝えして,確保した時間に集中させるのがよいかもしれません.もちろん言い方には注意が必要ですし,診療も定期的とし間隔を短くするのがポイントになります.COVID-19にまつわる種々の不安はもっともであり,しっかりとBATHE法に則って対応していれば,じきに改善していくものと思われます.すこし医療者側の辛抱も必要になりますが,電話対応の時間が一定になるだけでもストレスはだいぶ軽くなるはずです.
身体症状症に対しては個々の患者さんに合わせた多面的なアプローチが必要となりますが,プライマリ・ケアでのマネジメント(CARE-MD)を最後にお示ししておきます(表1) 4) .

今回のまとめ
・医療上必要であれば電話だけでなく来院してもらおう.混雑を避ける時
間を提案してもよい.
・BPSモデルを意識しつつも,“何でもBPS”ではなく重みづけを考えるこ
とが大事.
・不安から患者が頻回に連絡してくる場合は,定期的かつ間隔も短めな診
療を提案しよう.その際も突き放さない言い方を.
・不安などで身体症状が強まっている患者にはCARE-MDを念頭に対処しよ う.
参考文献
1) Turk DC,Wilson HD,Cahana A:Treatment of chronic non-cancer pain.Lancet,377(9784):2226-2235,2011.
2) Engel GL:The clinical application of the biopsychosocial model.Am J Psychiatry,137(5):535-544,1980.
3) 厚生労働省:「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました.2020.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
4) Kurlansik SL,Maffei MS:Somatic Symptom Disorder.Am Fam Physician,93(1):49-54,2016.
※本内容は「治療」2020年12月号に掲載されたものをnote用に編集したものです
本連載の著者2人が書き上げた,
「対話で学ぶ精神症状の診かた」が好評発売中です.
プライマリ・ケアにおける精神症状の診かた,向精神薬のさじ加減,精神症状に使える漢方薬,簡単に始められる非薬物療法など内容盛りだくさんとなっております.
・南山堂
・Amazon
・楽天ブックス
電子版
・医書.jp
・M2PLUS

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
