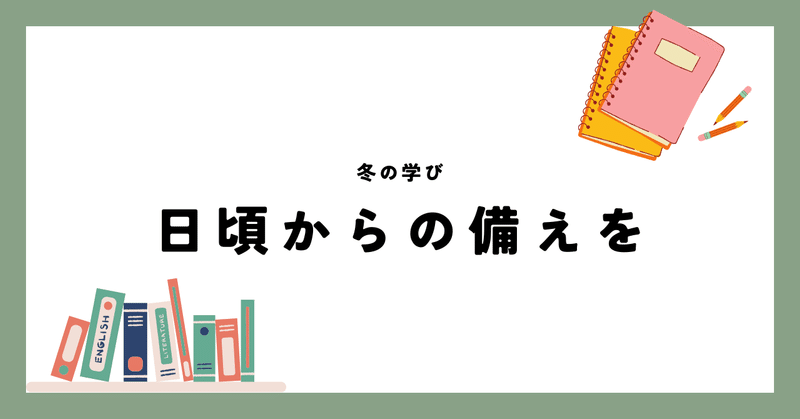
日頃からの備えを 冬の学び#10
被害が大きくならないことを願います。
石川県能登を中心とした、大きな地震が発生しました。
津波の被害もあり、テレビ番組でその被害の様子が放送されています。
被害が最小限に収まるように、多くの方が力を尽くされていることと思います。
自分に今すぐできることは多くありませんが、できることを行なっていきたいと思います。
この記事を読んでいただいている方の周りにも、被害を受けられた方がいらっしゃることと思います。
1日も早く、落ち着いて過ごせる日々が来て欲しいと思います。
日頃からの備えを
4年生の社会科にある、「自然災害からくらしを守る」の単元は、東日本大震災を機に、防災に対する考え方が大きく変化して、学習指導要領に位置付けられました。
それまで、防災は、公的な機関による設備を整えることが中心でした。
防潮堤の建設がその例です。
しかし、東日本大震災の想定外の大きな被害により、これらの設備だけで被害を防げるわけではなく、一人一人の防災に対する意識の向上についても考えていかなければならないことが話題になりました。
これまでの、国や自治体による公助だけでなく、自分のことは自分で守る自助、そして、コミュニティでお互いに助け合う共助の3つをそれぞれ意識して災害からくらしを守る多重防災の考え方になっています。
被害を完全に防ぐ防災ではなく、少しでも被害を減らす減災の考え方にもなります。
いつ起こるかわからない災害に対して、日頃からできる準備をしておくこと、ものの準備だけでなく、人とのつながり、そして、いざという時の動きを確認しておくこと。
このような時だからこそ、改めて確認しておきたいと思いました。
改めて、被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。
お読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
