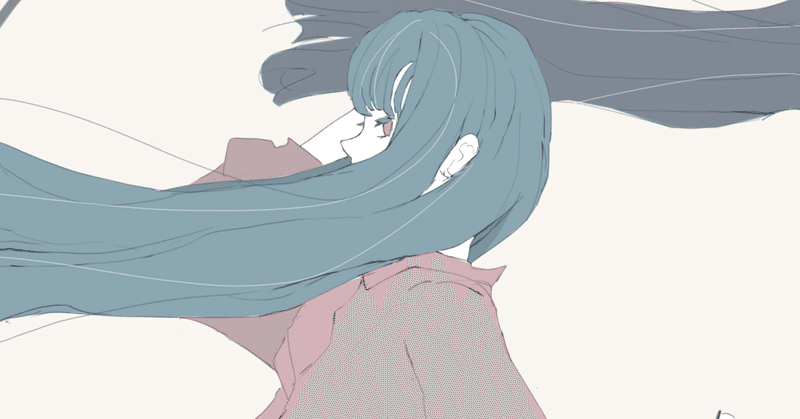
脳を痺れさせる遊び(合法)
なんか、良からぬ遊びと思われたかもしれませんが、違いますよ。
私は、高校生くらいの頃から、難し過ぎる本をよんで脳を痺れさせる遊びが好きです。
難解な文章や、文語体の文章、古典など、私の脳みそでは読んでも理解出来ず、頭に入って来ない様な難し過ぎる文章をあえて読むことで脳内が痺れるような、マヒする様な感覚が楽しいのです。
初めてそれを感じたのは、大江健三郎氏の「芽むしり仔撃ち」と「飼育」という小説でした。
高校生の私には難し過ぎて全く理解できませんでしたが、ただただ物凄くヤバイ気持ちになったのを覚えています。
難解な文章と不穏な内容、作者の脳内をガッツリそのまま押しつけてくる様な圧力を感じ、完全に脳が痺れました。
結局、未だに理解はできていませんし、もう二度と読まない様な気もします。
ちなみに、この2つの小説はメンタルに不安があるときには、あまりおすすめ出来ません。
なんだかわからないけど強くて勢いのある文章を浴びると、脳が喜ぶ感じがします。
文語体の文章もそうです。森鴎外とかロシア文学の翻訳物とか、古い聖書とか、読んでいるとなんだがうっとりとしてきます。言葉の響きでボーっとなってきちゃいます。特に文語体の文章は「かっこいい」って感じです。
内容はじっくり読まなければ入ってきませんので、読みたいと思った物は繰り返し読みます。でも、大体はうっとりとして終わりの事が多いです。
エセ読書ですね。
なので、専門書とかマニアックな趣味の本とかも痺れます。難解な専門用語とかの羅列なんかは、とてもいいです。大変に快楽的です。
本当の読書家の方から叱られそうな、「娯楽的エセ読書」ですが、これにはこれで良い側面もあるのです。
それは、気になる言葉や事柄を調べる事で見識が深まるという事です。
調べる事も含めての「娯楽的エセ読書」ですので、気になる言葉は調べます。
今はスマホで簡単に調べる事ができるので捗りますね。
結果的に、お勉強になったなーって思います。
この「娯楽的エセ読書」。伝わるかな?
でも、結局、私が愛読している本は、難し過ぎるものではなく、わかりやすくて読みやすいものだったりします。私にはそちらの方が合っているのだと思います。
結局、心に沁みる言葉はシンプルだったりしますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
