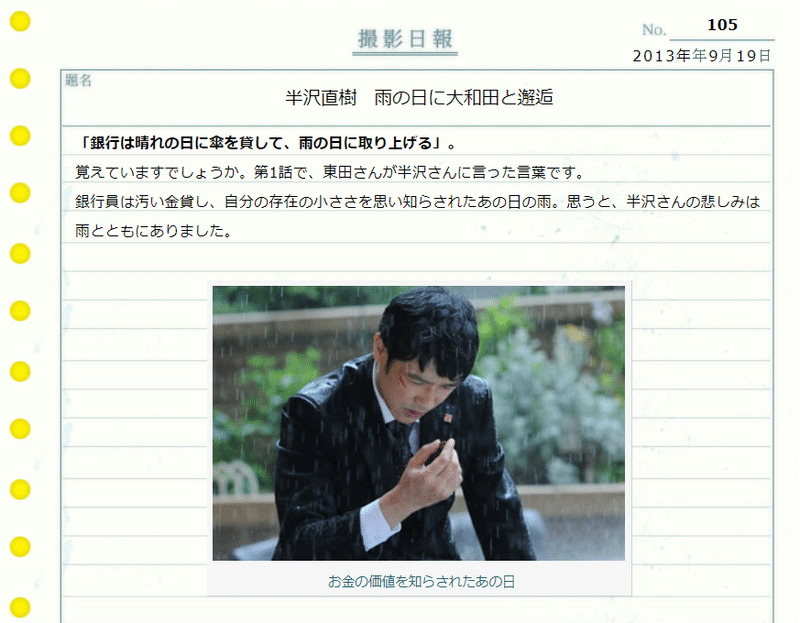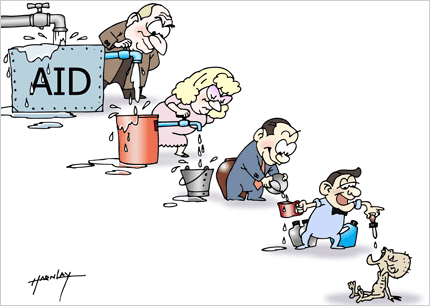経済史:バブルと覇権国で切ってみる
講談を聞いているような面白さ。それでいて、要所をしっかり締めている。さすが、塾講師の筆者(本稿の参考書:下記リンク)。研究者のような独特の視点はないものの、僕の要約(本稿)を読むくらいなら、直接本書に当たってほしいと思います。サブタイトルにもある通り、わずか2時間でざっくり、世界の経済史を見通すことができます。ここでは、本書の内容をわざと逆を追って紹介していきましょう。とりあえず本稿では、現代史の範囲のみ取りあげます。経済史に名を残すであろうと言えば、安倍首相ご自身が命名(吹聴)された「アベノミクス」でしょう。
※冒頭画像は、アベノミクスの理論的背景のひとつにもなったとされるトリクルダウン理論を風刺したイラストです。
日本ではまだ「アベノミクス」の大実験中です。とにかく、ひたすらお金を刷ることで日本経済を救おうとしています。その前の民主的政権が、改革を唱えながら、結局何も変えられなかったこと(日銀の独立性尊重)に比べると、経済景色は一変しました。そもそも、日本の改革ブームは、平成を通して何度もやってきました。痛みをともなう外科手術(小泉政権)、バラマキに戻ったその後(安倍・福田・麻生政権)、そしてモデルチェンジを図ろうとした民主党政権。しかし、今回は気負うことなく、デフレ脱却の道筋を示そうとしてきました。吉と出るか否かは、歴史の答えを待たねばならないようです。
時代区分のひとつとなったバブル崩壊
日本がデフレに苦しみ始めたのは、バブル崩壊でした。バブルとは実体経済と乖離したことから起こる不思議な資産価格の上昇を指します。ひとつのバブルが担保となって、次のバブルを生み出します。あまり理解されていないのですが、見合っただけの(付加価値を有した)生産力上昇があれば、インフレやバブルとは言いません。ただ、生産性とは無関係にカネ余りが続けば、それはやがて「不思議な」資産価格高騰へとつながります。気づけば、誰もが、投機資産をもって売りたくなる一歩手前。そして不安を抱きながら様子を見ていた状態、それがバブル崩壊の前夜です。いよいよその悲劇の手綱は日本銀行の手によって引かれました。五回にわたる公定歩合の引き上げです。その前には不動産融資の総量規制も行われていました。満を辞しての愚行の背景には、膨らみ続けた風船の、今すぐにも弾けようとした状況に対する震えや慄きが行政側にあったとされます。
1989年末、NTT株上場で始まった株ブームが38915円にて最高潮を迎えました。その資金はさらに膨らもうと不動産に向かっていました。津波のようです。このバブル前後の時期を通して僕がつくづく感じたのは、「信用創造」という仕組みは、銀行の都合で勝手に生まれ、縮むことです。バブル期の雰囲気では、相手を見定めず、とにかく貸す。バブルが崩壊した後は、有無を言わさず、回収する(=貸し剥がし)。確か、ドラマ『半沢直樹』の中にも、業界の名言が登場しましたね。「銀行は晴れの日に傘を貸して、雨の日に取り上げる」。そんな雰囲気を醸成した一端は、いわゆるノンバンク(消費者金融、信販会社)事業者であったり、莫大な農協マネーが流れた「住専」だったりでした。金融機関は色々な隠れ蓑を用い、たとえるなら、社会中のマネーを色々なルートで目に見えるダムに集めたわけです。そのダムがついに決壊。1991年のことでした。流れ出た鉄砲水は二年の時を経て下流域の住民を襲います。1993年のことでした。日本国民はなすすべもなく、バブル崩壊の激流の中に放り出されました。漂流するだけの日本経済はその後何年もの間、後遺症に悩むことになります。
追い込まれたアメリカが「キレた」
戦後の世界は、冷戦という鉄のカーテンが東西の間に敷かれました。政治・経済体制の違いから両者は激烈な対立を続けました。それが今や「歴史」になったのは、冷戦に終止符を打ったとされるアメリカの「レーガノミクス」政策があったからです。この正体とは何だったのでしょうか。一般的には小さな政府路線と言われます。ソ連を破滅に追い込んだと言われていますが、その論拠は怪しいものです。まず、巨額の歳出削減を行いつつ、莫大な軍事費を投入するという一貫性のなさ。次に、民間活力を創出すべく、規制緩和を次々行いました。が、しかし、インフレ退治のため政策金利を引き上げた結果、投資マインドは縮小し、ドル高の副作用も生じました。
当時、日本は二度の石油危機を経て、鉄鋼・造船・石油化学の重工業偏重から、家電・自動車・半導体へとモデルチェンジをしたばかりでした。勢いに乗る様々な日本製品が、集中豪雨的に欧米へと輸出されました。逆にその欧米は、自国の病(大企業病や経済のスタグフレーション)に犯され、また円安の要因も手伝って、日本を一気に世界の頂点へと引き上げることになりました。これが、その後の悪名高い、日米貿易摩擦を招くのです。本書の作者風の言葉遣いをすれば、アメリカの親分が出てきて、「オイ、若いの。いつまでも調子こいてんじゃねぇぞ」と日本の胸ぐらを掴んだようなものです。アメリカの高官たちは、日本政府に対して、アメリカ製の車を買えとか、オレンジや牛肉を買えとか、脅しの押し売りを続けます。レーガン大統領と中曽根首相は「ロンヤス」などと仲の良さを内外にアピールしましたが、その裏では円高誘導のためのプラザ合意も締結させられました。まさに、バブル経済(崩壊)への時限爆弾がこの時仕込まれたのです。もっと言えば、輸出の自主規制や現地生産、そして内需拡大もワンセットで決められました。自由主義とは名ばかり。政治主導の子分いびりだったのです。レーガノミクスが終わってみた時、双子(財政と貿易)の赤字はさらに膨らみました。それでも今日、レーガン大統領の人気がいまだに高いのは、インフレと失業率の問題を解決したからです。政府財政と経済関係を傷めつつも、冷戦を終わらせ、国民生活を改善させたという点での評価がなされているようです。ちなみに、レーガン政権が採用したとされる経済理論は「トリクルダウン」と呼ばれます。金持ちを優遇しても、お金は回り回って、下々の人々にまで届くのだそうです。安倍政権も、このロジックを参考にしているみたいです。
戦争に加担しすぎたアメリカの凋落
ではなぜ、世界の覇権国家となったアメリカが、(レーガン政権の寸前まで)瀕死な状態に追い込まれていたのでしょうか。第二次世界大戦を勝利に導き、国土の荒廃したヨーロッパや日本を復興させたのは、間違いなくアメリカでした。なぜなら、国民の一票で成り立っているアメリカにとって、世界経済の復興と広大な市場創出こそ、自国民を喜ばせる方法だったからです。戦後すぐの頃、世界の75%の金はアメリカに転がり込んでいました。これを担保に築いた戦後の経済秩序とは、固定相場(金ドル本位制)と国際基金(たとえば世界銀行)で資金を海外に流し、さらに自由貿易体制(GATT)を強化することによってアメリカの製品を買ってもらう。これが、アメリカの覇権的地位を確固とする仕組みだったはずですが、残念ながらそううまく事は運びませんでした。
最初のつまずきは1950年代の朝鮮戦争、1960年代はベトナム戦争。アメリカの金は次々と失われました。そして1971年、「ニクソン・ショック」と呼ばれる、金とドルの交換停止措置を宣言。1973年、世界はついに変動相場制に移行しました。さらに石油ショックが世界経済を震撼させたこともあり、アメリカ経済の重石になっています。こうして、停滞と混乱を抱え込んでしまったアメリカは、覇権国らしからぬ疲弊ぶりでヘロヘロになっていたまま1980年代に突入。同盟国であるにも関わらず、対日強硬策に踏み切ったのは、こうしたことが背景でした。
覇権は長く続かない、そのコストは割高
戦後、イギリスから世界の覇権を奪ったアメリカですが、そもそも覇権とは何かという話題で本稿を締めたいと思います。まず、イギリスの覇権とは、イギリスの価値観(自由貿易)を世界に広げることでした。お金を貸し、海運サービスにてモノを届け、相手国にイギリス製品を買わせる。その仕組みをヨーロッパ中に広げました。特に金融面での強さは際立ち、いつしか「世界の工場」から「世界の銀行」へと衣替えしていました。そして「世界の工場」としての供給能力は、インドや中国などの植民地に向けられました。同時に、安価な原材料や貴金属の収奪も重要なことでした。このように、世界秩序を自国に都合のよい形に規定し、その優位が続くような外交的取り組みをする。これがイギリスの覇権でした。しかし、ここに挑戦したのが、工業力をつけたアメリカやドイツです。幸い、対立する動機のなかったアメリカとは戦争にならなかったのですが、第一次世界大戦の主戦場となったヨーロッパでは大変な惨事となりました。
それから十数年後、世界は大恐慌に陥ります。アメリカでは株価の大暴落が起こり、購買力が一瞬にして喪失しました。企業活動も萎縮し、失業者が街に溢れかえりました。そうするとさらに消費活動は冷え込んでしまいます。このデフレ循環を止めるために、アメリカは高関税を使って輸入品を排除しようとしました。同時に決済通貨の混乱も招き、他国との貿易が急激に減少していきます。気づけば世界経済は個々に分断されていく、すなわちブロック経済の状態でした。こうなると(植民地を)持てる国と持たざる国との対立が深まり、そして衝突へと傾いていきます。第二次世界大戦です。今から振り返れば、この悪循環だけは絶対に起こしてはいけません。この時のアメリカですが、中立を捨て、明確に連合国側として参戦しました。傍観して、両陣営から儲ける手もあったはずです(第一次世界大戦の時)が実はそれも困難になっていたのです。経済的な困窮と、そこから生じる焦燥感は、日本やドイツの好戦勢力に口実を与え、ちょっとした手違いでも、現場の最前線では軍事衝突が起こってしまいます。どちらが仕掛けたにせよ、いざ喧嘩が始まってしまえば止められないのと同じです。大国が参戦して以降、五年にも満たない戦争の末、決着がつきました。国土が無傷のアメリカは、供給力が万全です。資金の出し手となり、モノの供給が行なえ、取引のルールを定めることもできる。まさに「覇権国」たる条件がここにそろったことになります。
しかし、覇権国の代償は巨大でした。国民レベルで真の繁栄を謳歌できたのは50年代までではないでしょうか。建前を貫くための莫大な軍事コスト、国内では暗澹たる公民権運動が始まり、苦戦するベトナム戦争の反対運動が盛り上がりました。経済では、アメリカ企業が早々に海外移転を進め、国内雇用を顧みることはありません。それなりに豊かな国だとは思いますが、貧困問題をみずから解決できないアメリカ。覇権外交の余波を受け、失業率もその都度跳ね上がりました。今日、トランプ政権が、早々に軍事覇権からの撤退を表明していた様は、おおよそ理解できるものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?