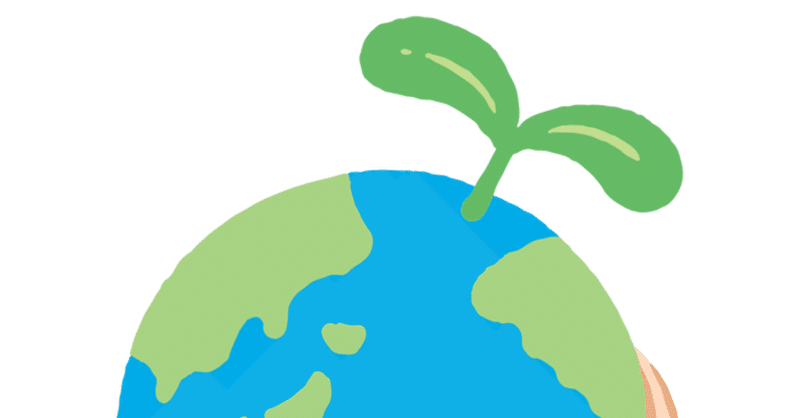
自然に学ぶ持続可能な暮らし方
3月4,5日。お隣の島、沖永良部より石田秀輝先生をお呼びして、
「自然に学ぶ持続可能な暮らし方」講演会を企画致しました😄
<行政・町民向け>
「エシカル循環で目指す サスティナブルアイランド」
<小学生高学年~高校生向け>
「持続可能な暮らしとは」
<海洋共育関係者・教職員向け>
「環境教育の心得」
と、3本立てでお届け致しました。

「環境問題」は本当に難しく、様々な立場や場所によっても変わり、もはや何をしているのかも分かりにくくなってしまうパターンが非常に多いのです。結果、優先順位も非常に迷うところ…。
そんな迷いを一掃する講座でした🙌

※「プラネタリー・バウンダリー」
人類が生存できる安全な活動領域とその限界点を定義する概念。
地球の限界、あるいは惑星限界。
安全域や程度を示す限界値を有する9つのプロセスを定る。人間活動が限界 値を超えた場合、地球環境に不可逆的な変化が急激に起きる可能性がある。
最近夜よく聞くのはごみ問題…
ところが、一番の問題は、「生物多様性の損失」なのです。
「メガソーラーを山を切り崩してつくる」という全く意味の分からない環境対策…
生物多様性の損失時は生き物の住処を奪い、殺傷や神経を狂わせてしまう農薬散布。などなど…便利と安さと効率の良さを重点においた現代社会は、まだまだ環境保全の逆行をし続けています。
生物多様性の豊かさは、土と木💖
ここを守り育むことを優先順位として考えて、社会の仕組みを構築し直していかなくてはなりません。
そして、今の私達の暮らしを世界中の人がした場合、地球が2.8個も必要で、世界を平均しても1.7個…完全なる赤字経営なのです。

祖先や自然が残してくれた貯金を切り崩して生活をしているのが現実です。
次世代に負の遺産を残さないためにも、これまでのテクノロジーを発展させたものと、自然大切にしていく文化の融合が必要なわけです。
では具体的にどうしていけばいいのか…
答えはいつだって自然の中にある…
「ネイチャー・テクノロジー
自然のすごさを賢く活かす、あたらしいものつくりと暮らし方のかたち」
-石田秀輝先生 生物多様性コラムより抜粋-
ライフスタイルからどのようにテクノロジー要素を抽出するのか、それをどのように自然の中から探すのか、どうやって環境に負荷をかけないようにリ・デザインするのか、まだまだ、解決しなければならない問題は多い、ただ、我々は1日でも早く重要な第一歩を踏み出さねばならないのである。地球環境のこと考えながらも、ワクワクドキドキしながら、心豊かに暮らせることを、我々自身、身をもって明らかにし、その素晴らしさを、次の世代に手渡さねばならないのである。

心豊かな暮らしのかたちは、当然のことながら2030年の厳しい環境制約を基盤とする。その、要素の一つは、『利便』であり『自然』である。3つ目の要素が、『育』である。自分や他人や自然を育てることで、楽しみが生まれ、充実感や達成感を感じるという価値観である。そしてAからB、Cに向かうほど心の豊か度は上昇する。例えばエコなエアコン、環境のことは考えられているが、利便性の機能しか持たずAの位置にある。これでは、買ったときにはそれなりに嬉しいがすぐに飽きてしまう。商材としてのライフはきわめて短くなる。今求められているのは、BやCの領域にあるテクノロジーやサービスなのである。

残念ながら、現在のテクノロジーやサービスは、この『制約』を利便性に置き換えるものばかりである。ちょっとした不自由さや不便さ、それがポジティブな制約であっても、知恵や理性を総動員して乗り越えることを許さないのである。制約が利便性にすり変われば、心豊かな暮らしの質は急激に劣化する。「モノを欲しがらない若者」という見出しが新聞を最近賑あわせ、多くの評論家が色々なことを書いては居るが、少なくとも、若者が欲しいものを企業が市場に投入していないということだけは間違いのない事実であろう。
自然を規範とした、ものつくりと暮らし方のイノベーションを起こす
ライフスタイルを基盤にするテクノロジーイノベーションは、地下資源型のテクノロジーからの決別である。自然は倫理観を持つ知能だと思う、自然は地球史46億年、生命史38億年の中で、淘汰を繰り返し、完璧な循環を主に太陽エネルギーだけを駆動力として創り上げている。我々は、そこから、メカニズム、システム、さらには淘汰と言われるような社会性まで学ぶことができるのである。1992年の地球サミット以来、少なくとも先進国は持続可能な社会を構築すべく努力を重ねてきた、しかしながら、現実は理想とはますます乖離を続けている。今こそ、バックキャスト思考で地球環境制約の中に心豊かなライフスタイルを描き、それに必要なテクノロジーを抽出し、それを自然の中に捜しに行き、サステイナブルと言うフィルターを通しリ・デザインし、あたらしいテクノロジーのかたちをつくらねばならない。それこそが、ネイチャー・テクノロジーによるテクノロジー創出システムである。
ネイチャー・テクノロジーを考える上で、我々は、もう1つ、重要な視点を持たなければならない。それは、現在のテクノロジーのほとんどが18Cのイギリスでの産業革命以降の産物であるということである。イギリスの産業革命は自然と決別することで成功し、大量生産大量消費と言う概念を生み出し、結果として、これが現在の地球環境問題を起こしてしまったのである。
では、自然と決別しないテクノロジーであるネイチャー・テクノロジーはサステイナブルな社会構築に真に貢献できるのか? 歴史を振り返ってみよう、自然との決別を原理とした産業革命が世界を席巻する中で自然観を持ち続け、独自の産業革命を進めた民族がある。江戸時代の日本人である。それは、イギリスが資本集約による産業革命を進めたのと正反対に労働集約による産業革命であった。そしてその結果、大量生産大量消費ではなく遊びやエンターテインメントを生み出すテクノロジーを創出したのである。イギリスでの産業革命が物欲を煽るテクノロジーを生み出したとすれば、日本の産業革命は精神欲を煽る産業革命を生み出したのであり、それが江戸時代の『意気』の概念を生み出したのである。その意味では、ネイチャー・テクノロジーは自然を基盤として、この意気の概念を写し取ったテクノロジーと言えるのである。
以上
今やっと世界的にも持続可能な方向へ向かおうとしています。
日本でも
2050年「みどりの食糧システム戦略」を宣言!
2030年国土の30%以上を自然環境エリアとして保全!
(30by30)
が宣言されました。これらの政策を地域に活かし、創り上げていかなくてはなりません。
これからも様々な団体や分野とも協力しあい、持続可能な島づくりを目指していきたいと心新たに決意を固めました。
今後とも石田先生の学びを頂きなら、実践して参ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
