
「明るい部屋 / ロランバルト」喪と悲しみ、苔むす岩の信仰を断ること(読書連想文05)
日々の中に散発する悲しさがあります。愛していた人の記憶をふと思い出す。夢の中、実態のない体を抱きしめる。相手の頬に指をそえた記憶に、目が覚めて。夢遊病の中に戻りたい、そんな空虚なあたたかさと、落差に悲しさを覚えます。ロランバルトの『明るい部屋』を思い出すと、ぼくにとってそれは喪について考えることであります
この本は写真論の古典と言われいます。写真好き、歴史好きにとっては「読まなければならない」そんな脅迫さえ聞こえてくるような、歴史文脈の中に位置させられる本です。しかし読んでみると、期待を裏切られます。写真の歴史や、写真家のスタンスなどは全く書かれていません。いわゆる上手な撮り方も、カメラの使い方も書かれていません。言い回しも難解です。
副題は「写真についての覚書」ということなので、この本を、例えば本屋のどこに置くかと考えると、非常に難解なところがあります。まず、カメラを上達するための技術を読む人は、読んでみて「違うな」と思ってしまう。でも、そういった人にこそが読むべきものであり、写真とは何か。写すとは何か。そういったことの深淵に潜って行くためには重要な羅針盤の、いくつかあ針のひとつには、なり得るでしょう。これから下の文章は、2年前に書いたものと、現在(という名の過去)との混合です。「2018年10月31日 10:38」にぼくは、源となる文章を書きました。

写真は、作家活動として、ぼくが制作しているものです。時々写真について聞かれるのでお答えします。販売もしています。
忘れていたものが、ある時、ふっと。散発的に浮き上がってくる。愛していた人と以前行っていた公園。ここで三年前に桜を見たなぁ。とか、もしくは本来なら関係ないものなのに、ある関連を見出して、そこに悲しみを見いだしたりする。喪について。この悲しみが永続するのか。悲しみが続くのは、心がつらい。けれど、ずっと辛いままでいるのは心がつらい。しかし、愛していた人を、失った。それは、物理的にも、精神的にも、愛する対象が失われたことに、悲しさを持たなくなること、そのことへの悲しみも覚える。喪というのは、愛することの対象の喪失であり、対象との関わりの中にあった自分の現れの喪失である。

その人がいないのに、生きていけている。ことを思うと、その人は自分にとって大事な人ではなかったのではないか、などと考えてしまう。(まず、思い浮かぶ名前がある。その後にも有限ではあるが、限りなく続いていくような心地がある名前がある。他の方々。他、という文字を使いくない。それぞれの、S.K、N.Oなどとの思い出がある)大事な人、というとき、ぼくたちが指し示すのは、その肉体そのものではなく、関わりのあり方である。初対面のときから、時間を重ねて、その人が大切になっていく。肉体を愛することもあれば、彼/彼女との会話、一緒に作った料理、一緒に行った場所、送りあった様々な物理的-概念的ギフト。そういった時間の中に彼/彼女がいて、死というのは、その未来の時間の断絶である。時間を重ねていくことができないという、絶対的な時間による拒絶である。
「私の母を、「母」一般に還元することも欲しない」
この言葉はp90に書いてあったことだ。私はただ単に苦しみたかったのではなく、その苦しみの独自性をあくまでも、大切にしたかった。p92にはこうある。
「私が失ったものは、母なるもの、ではなく、かけがえのないものだったからである」
かけがえのない唯一のものの喪失。取り戻すことのできない絶対的不可能性は、散発的な喪の永続を意味する。時々、霊が見えるという人がいる。イタコという存在も、名前だけは知っている。憑依っていうのはなんだろう。夜の街でタクシーに乗る。1人で乗り込む時に、ぼくは運転手さんに行き先だけ告げて、窓から外を眺める。そしてふと2人分の座席に1人だけで座る自分を思い出す。この空白に、彼/彼女がいてくれたらいいのに、と、ふと涙が出てくる。このわずかな10分だけでもあなたの隣にいたい。生者も死者も、1人の時間には、関係ない。なぜならその肉体には触れられず、頭の中に観念としてしか居ないから。だから、誰にでもあえて、どこにでも行けて、そして、存在しない人、場所、空気に出会える夢は、本当に幸福な場所かもしれない。

今、ふと思い出した名前がある。その人は、いま、生きているのだろうか。ふとしたきっかけで人はいなくなる。今度会おうね、が叶わないときだってある。ぼくがそうだった。次の日には、人はなくなる。ぼくにだってその可能性が、ある。「次会った時に飲んでよ!ばいばい!」と言ったのが、彼に対してのぼくの遺言になると思わなかった。彼の言葉は覚えていない。「またね!」とか「待ってるよ!」だった。手を振る姿は覚えている。だから、今後、人とバイバイする時の最後の言葉だけは覚えておきたい。
喪失体験、と、悲しみの感情とは、同時に現れるものなのか?ずれることもあるんじゃない?マルセルプルースト『失われた時を求めて』という本がある。この本は、3つの出版社からでていて、それほどに重要な書籍である。
「主人公のマルセルは、祖母が亡くなったとき「その死を悲しむ気持ちがほとんど起こら」ず、そのことを不思議に思えば、自分にそれを責めてもいた。」
「しかしある旅先で、ショートブーツの最初のボタンに触れたとたん、嗚咽に震え、涙がこぼれた」
思い出せ、思い出せ。ではなく、ある身体動作によって、昔のことが思い出される。非意思的に記憶や感情が溢れ出す。ふとしたときに「あ、ここは彼/彼女に教えてもらったところだ」とか、しりとりみたいな連想の中で、ふと彼/彼女が色濃く現れた渦に出会う。飲み込まれそうになる。その時に、感情を発露させるのか、グッとこらえるのか。関係が深ければ深いほど、思い出す頻度は高い。しかし、毎回、悲しんでいては、日常生活が送れない。しかし、一切の悲しみを捨て去ることは、彼/彼女を捨て去ることになるのではないか?だから、ぼくはいま、そのバランスを取りながら、文章を組み立てている。文章を書くとき、ぼくはひとりになりながらも、頭の中には幾人もの人々を誕生させ、彼らと会話をしている。そこは盆踊りのようなもので、生者も死者もなく、入り乱れる。そして、新しい子供が生まれる。
「祖母が私の着ているものを脱がせてくれたあの晩」
身をかがめる身体行為が、過去と現在を一致させる。それまでその記憶は、存在しないに等しかった。
「事実のカレンダーと、感情のカレンダーの一致を妨害するあのアナクロニズムのために、祖母の埋葬から一年以上たってはじめて祖母が死んだのを知ったところだった」p339
「つまりはようやく彼女を見出しながら、永遠に祖母を失ったのを悟ったところだった」p342
名前だけの祖母ではなく、そのものを知った。ぼくは2013年、オーストラリア留学中に祖母がなくなった。2人祖母がいるのだが、母に由来する祖母とは仲が良く、父に由来する祖母は、すこし恐れていた。祖母という血縁関係上での呼び名は一緒でも、彼らに想い抱くこと、つまり、祖母のスキーマはこの2人によって重層化された。そう、2013年の死は、突如のことであり、地理的にも離れていた。悲しみや切なさ、思念というのは、徐々に現れる。泣きたいのに、泣けない。
しかし、ぼくは、悲しんでいるということを涙によって再認することで、悲しめるという人間性によってじぶんの存在を強固なものにしようと、他の死を利用してはいないだろうか、とも思う。だから、涙がでてこないこと、もしくは溢れて出てしまうことに、それ以上の意味づけをやめた。なぜなら、意味づけとは理性であるが、涙が流れるとか、喜怒哀楽は、ぼくにはコントロールできない。そこが一切の断絶かと言われると違うが、一対一の対応ではなく、ぼくは、自分の涙を知らない。君が、あの日、ぼくの胸にもたれかかりながら、見せてくれた涙の理由も知らない。涙の理由を尋ねるのは野暮だ。きいたところで、あなたもわからないだろうな、ただ、理解することよりも、涙が流れている、この事実の方が、もっともっと大事だと思った。
言葉をだいじにするが、そこを信仰してはいけない。もっと、転がる岩のように、言葉を流す。川のほとりに岩を留まらせて苔を生やしてはいけない。苔が生えると、あたかも大事なものに見えてきてしまう。あらゆる岩が、石が、砂が等価であり、大きさや、苔の密度で、その大事さを決めては行けない。愛着の度合いなんてものは、ぼくたちの、思いつきに、委ねられている。でかいから、とか、苔が生えているから、とか、他人が納得しそうな理由を、自分自身への説得材料に、しては行けない。
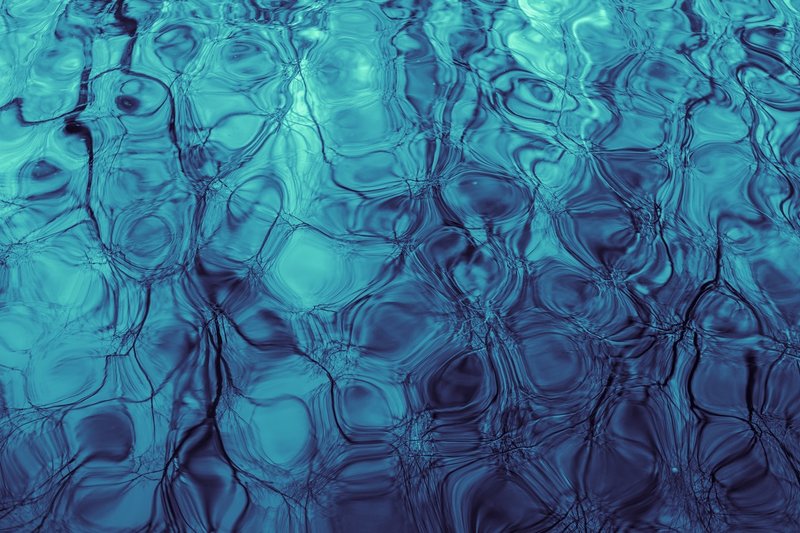
いただいたサポートは、これまでためらっていた写真のプリントなど、制作の補助に使わせていただきます。本当に感謝しています。
