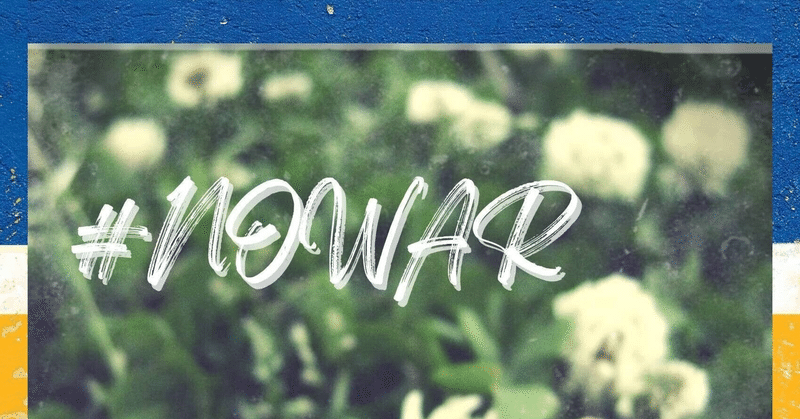
第166号(2022年2月28日) ついに始まってしまったウクライナ侵攻
【インサイト】ついに始まってしまったウクライナ侵攻
あまりにも怪しげな「大義」
すでに広く報じられているとおり、2月24日にロシアのウクライナ侵攻が始まりました。しかも、一部で言われていたようなドンバス地方での限定攻勢ではなく、北部(ロシア及びベラルーシからキーウ・ハルキウへの攻勢)、東部(ドンバス方面への攻勢)、南部(クリミアからヘルソン方面への攻勢)という極めて大規模なものです。
これはもはや「軍事介入」などというものではなく、公然たる「戦争」と呼ぶほかないでしょう。
しかし、現在の国際安全保障の基礎を成す国連憲章は、国家間紛争を解決する手段としての戦争を明確に否定しています。それを国連常任理事国(しかも今月は議長国)であるロシアが公然と始めたわけですから、国際的な非難を浴びるのは当然というほかありません。
一応、ロシア側は、これが戦争ではないという建前を取っています。2月24日、国民向けに公開されたビデオメッセージの中で、プーチン大統領は今回の軍事行動を「特別軍事作戦」であると位置付けました。その意味するところは明確にされていませんが、ひとことで言えば、これは自衛のための行動だというふうに理解できます。
プーチンの言い分はこうです。
曰く、ゼレンシキー大統領率いる現在のウクライナ政府は「ナチス」であり、ロシア系住民の虐殺を行っており、これを止めなければならない。曰く、ウクライナ政府は外国(西側が示唆されている)の支援を得て密かに核兵器を開発しており、国際安全保障全体にとっての脅威である。曰く、ウクライナ政府は西側の手先と化しており、このままではロシアを脅かすミサイルなどがミサイル防衛(MD)システムの名目で配備される可能性がある…
以上に基づいて、プーチンは、「特別軍事作戦」の目標を次の三点であるとしています。
第一はウクライナの「非ナチス化」であり、つまり現在の政権を体制転換するということです。第二は「ある程度の非軍事化」で、これは要するにウクライナ軍の解体を意味するものと考えられるでしょう。そして第三に、ウクライナの「中立化」、すなわちNATO非加盟などを公的に宣言させること(現在の憲法に記載されたNATO加盟方針を撤回させて2013年までの憲法と同様に中立条項を復活させること)が掲げられています。
プーチンの掲げた「大義」は、あまりにもツッコミどころだらけです。
たしかにドンバスではこれまでに1万4000人もの人命が失われていますが、民間人の犠牲は戦闘による巻き添え被害であり、ナチスがやったように絶滅収容所を作って組織的に、かつ選択的にロシア系住民を狙って虐殺をやっているわけではありません。さらにいえば、現在までに出ている死者はロシアが2014年に軍事介入に踏み切った結果なわけですから、全く論理が転倒しています(ついでに述べるとゼレンシキーはユダヤ人であって、同人を「ナチス」と呼ぶのも随分な話です)。
核開発疑惑に至ってはさらに荒唐無稽で、ウクライナが本当に大規模な開発を進めているなら国際原子力機関(IAEA)などから早い段階で疑念が出ているでしょうし、そうだとしてもまずは北朝鮮やイランの場合のように国際的な枠組みで解決の努力が図られるべきではないでしょうか。そうした手続きを一切抜きにしていきなり軍事行動に訴えるのはあまりにも乱暴です。
MDが攻撃ミサイルの配備拠点になるという話もロシアが長年にわたって言い続けてきた話ですが、そもそも固定式のサイトに攻撃兵器を配備するのは軍事的にあまりにも馬鹿馬鹿しいですし、ウクライナのNATO加盟や同国へのMDシステム配備など全く具体化していません。また、仮にロシアがこうした脅威を感じているのだとすれば、まずは軍備管理などの努力を通じて解決すべきであって、やはりいきなり軍事的解決に訴えてよいというものではない筈です。
以上のような杜撰な「大義」を掲げて、これは戦争ではない、自衛なのだと言い募ったところで、まず説得力を持ち得ないのは明らかでしょう。
対話する気はあったのか
開戦前には、もしかすると戦争が回避できるのではないかという期待が持たれた時期もありました。
前号でも書いたように、15日に訪日したショルツ独首相は第二次ミンスク合意をウクライナと話し合う余地があるというメッセージをプーチンに伝えていましたし、同じ日にロシア下院が行ったドネツク・ルガンスクの国家承認を求める決議も、一種の政治的ブラフではないかと私は見ていました。さらに24日にはロシアのラヴロフ外相とブリンケン米国務長官による会談が予定されていたので、ここまでは軍事行動に訴えないだろうとも期待していました。
ところが、21日に全てがひっくり返ります。
同日、「拡大国家安全保障会議会合」を開催したプーチン大統領は、閣僚たちをひとりひとり演壇に立たせて、ドネツク・ルガンスクの国家承認を支持すると発言させ、最終的にこれを認めました。米国は即座にこれに反応し、ドネツク・ルガンスクの国家承認を「侵略」と断定。これでラヴロフ=ブリンケン会談も、フランスのマクロン大統領が仲介した米露首脳会談も完全にお流れとなりました。
ロシアは、この決定が最後の米露対話のチャンスをご破産にすることを理解していた筈です。にもかかわらず、それを実行に移したのは、少なくとも21日の時点で戦争を回避する意図を持っていなかったということであり、それ以前の一週間における「ジェットコースター」的展開もロシアの意図を誤認させる欺瞞(マスキロフカ)だったという疑いを強く持たざるを得ません。
しかも、24日に公開された国民向けビデオメッセージ(前述)に写っていたプーチン大統領の服装は21日時点と全く同じでしたから、これもドネツク・ルガンスクの国家承認が事実上、開戦ののろしであったことを示唆します。
軍事作戦の実際
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
