
【高校入試数学】過去問を使った入試対策の進め方
こちらの記事では、過去問を活用して独学で受験勉強を進めていくためのプラン例と、ポイントや注意点についてお話します。
過去問データベースはこちら
まず考えたいのは「先取り学習をするかどうか」
先取り学習の大きなメリットは、「全範囲の受験対策を早くから始められる」ことです。
特に3年生の後半で習う「二次関数」と「相似・円・三平方の定理」は、入試では超頻出!!難易度的にも高い問題が出題されることが多いです。
学校の進度に合わせていると、この分野の演習ができるようになるのは、早くとも2学期の後半から。実際には2学期の期末テストが終わるまでは難しいと言えるでしょう。
それが、もし3年生の夏休みまでに全範囲を学習し終えられたら、じっくりと問題演習に取り組むことができます。
先取り学習は、入試数学で8割以上を狙いたい人には特におススメです。今、まだ2年生や3年生の春であれば、検討してみてください。
先取り学習をしない場合
先取り学習をしない場合、入試対策の要は「習った部分からどんどん問題演習を始める」です。
3年の冬、「二次関数」「相似・円・三平方の定理」の演習にしっかり時間を割けるよう、1・2年で習った部分や3年の前半に習う内容の演習を進めましょう。
先取り学習をしない場合の問題選びのポイント
問題を選んでいくときのポイントはこちら。
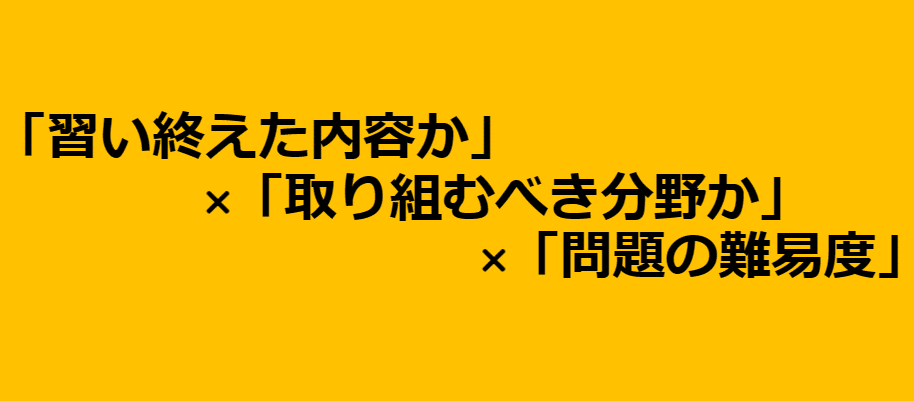
一つずつ解説していきます。
①習い終えた内容か
データベースには、それぞれの問題が、履修時期ごとに「1年」「2年」「3年(夏・冬)」と分類されています。
既に学習した分野のみで構成されている問題を選ぶようにしてください。
また、一つの大問の中に複数の学年が混在している場合もあります。(例:「1年」と「3年冬」など)

この場合、自分の目標点数から考えて「標準」までの学習で足りるのであれば早くから演習に使えますし(2③は解かない)、応用問題も学習するつもりであれば3年冬まで解かずに取っておいた方が良いでしょう。
②取り組むべき分野か
「取り組むべき分野か」について、私がポイントだと考えているのは以下の2つです。更に、自分の習熟度や出題傾向も踏まえ、取り組む問題を選びましょう。
・2年生までで完結する分野を固める
→ 確率、連立方程式、文字式、資料の活用、作図(一部例外あり)
この分野は、受験勉強の序盤からどんどん問題演習を重ね、自分の目指すレベルまで解けるようになっておきましょう。
初めはまんべんなくやりながら得意不得意を見極め、出題傾向も踏まえて徐々に「自分なりの重点分野」に重点を置いて進めていけると良いでしょう。
・3年の内容につながりが深い分野をしっかり理解しておく
→ 関数(比例・反比例、一次関数)、図形(平面、立体、合同)
この分野は先述した「3年後半のヤマ」である「二次関数」「相似・円・三平方の定理」の土台となるものです。
「基本」問題は確実にモノにし、「標準」問題までできるようになっておくと、学習がスムーズに進むでしょう。復習の意味でも、ぜひ3年の夏休みに取り組んでおきたい分野です。
⓷問題の難易度
問題演習でやってしまいがちなのが「難易度の合わない問題に取り組むこと」です。
「受験勉強」を戦略的に考えたとき、入試で6割を取るのが目標の人が、難しい応用発展問題に取り組む必要はありません。(解ける必要のない難しい問題に取り組んで、自信を無くし時間も無駄にするのは本当にやめましょう!!)
自分が解けるようになるべきレベルの問題はどれか、冷静に取捨選択し、効果的な受験勉強を進めてほしいと心から思っています。
データベース上の「難易度」の目安は以下の通りです。

先取り学習をする場合
先取り学習をする場合は、「3年生の夏までに全範囲終わらせる」を目標に、ひとまず先取りにのみ集中しましょう。
教科書を理解する→ワークに取り組む、という形で大丈夫です。いきなり応用問題までバッチリ解けるようになる必要はありません。
先取り学習をする場合の過去問題の選び方
一通り中学校の範囲を学習し終えたら、過去問データベースの「基本」「標準」レベルの問題の演習を始め、徐々に目標点数に合わせて「応用」「難問」を含む問題に取り組むようにしましょう。(難易度については上記③をご覧ください)
まんべんなく演習をしつつ、自分の得意不得意や出題傾向を把握して、徐々に重点的に取り組む分野を考え、進めていけるようになりましょう。
過去問演習を効果的に進める工夫
「よく出る」マークのある問題を優先して取り組む
旺文社の「全国高校入試問題正解」には、問題によって「よく出る」マークが付いています。
データベース上でも備考欄に☆マークを付けて分かるようにしてあります。
実際に、汎用性が高く実力がつきそうな問題が選ばれていますので、問題選びの参考にしてください。
別の紙に解く
「全国高校入試問題正解」は、情報量は圧倒的ですが、解答スペースはありませんので、紙面中に書き込んで問題を解いていくことはほぼ不可能です。
ノートやルーズリーフに「21年○○県 大問3」などと書き込み(復習のため)、1ページ使ってゆったりと式や計算を書きましょう。これにより計算ミスを防いだり、見直しがしやすくなったり、いいこと尽くしです。
また、解答用紙がごちゃごちゃしたり、計算を間違えて消し直すのが嫌な人は、100均のB5判「らくがき帳」を手元に用意しておくとストレスなく勉強を進められます。消しゴムがけしている時間は「勉強」ではありませんからね。
図形やグラフは拡大を
書き込みが難しい「全国高校入試問題正解」。特に気をつけたいのは図形やグラフの問題です。
縮小されて載っていますので、必要な情報を全て書き込み問題を解くのはかなり厳しい。これでは解ける問題も解けません。また直書きしてしまうと解き直しの際にも不都合です。
ぜひここはひと手間かけて、拡大コピーするなり、電子版も購入して画像データを加工するなり、工夫して取り組みの素地を整えることをを強くお勧めします(保護者の皆さんがサポートできる部分です!)
自分で、またはお家の人がやるのが難しければ、私の方でサポートするプランも用意していますので、お問い合わせください。
自己分析、問題分析をしつつ、自分で学ぶ内容を決めて受験勉強を進めていくことができれば、「合格」だけでなく、生涯役に立つ「自ら学ぶ力」を手に入れることができます!
ぜひ充実した受験期を過ごしてください。
過去問の使い方、勉強の進め方、塾に行くべき?といったご相談など、無料でお受けしております!こちらからお気軽にご連絡ください。
LINE公式アカウント
https://lin.ee/mqEBXX3
X(旧Twitter)
https://twitter.com/cc_abiko
また、有料の伴走プランも用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
