三十三間堂
2008年11月3日
前回の「七条通を行く」からの続きです。
日本国第一之大天狗
『玉葉』にある頼朝の言葉である。
大天狗とはもちろん後白河のことで、「このタヌキ親父め」というほどの意味だろう。
『玉葉』自体は関白・太政大臣九条兼実の日記だからリアルタイムで綴られているのだが、頼朝の言葉を直接聞いたとも思えないから、信憑性には?の疑問符がつく。
それでも納得してしまうのは、後世の我々が後白河天皇の動きを知っているからだ。
兄の崇徳上皇との確執から生じた保元・平治の乱を経て、トンデモない事態になだれ込んで行く。
後白河32歳の時に長男の守仁親王へ譲位し、まだ16歳だった傀儡の親王は二条天皇となった。
またぞろ院政の始まりだ。
この院政が時代の混乱に拍車をかける。
院宣の乱発、そして以後、戦国時代まで延々と続く乱世の幕開けである。
ここは駆け足で書くけど、まず、台頭し始めた源氏追討の院宣を平氏に与え、やがて源氏有利と見れば、今度は源氏に平氏追討の院宣を出して、平氏への院宣を反故にする。
ところが、絶好調で進軍する木曽義仲が京に攻め上ると、押し出されるように西へ落ちて行く平氏に、これまた義仲に追討の院宣を出し、ほぼ同時に頼朝にも同じ院宣を連発している。
これだけではまだ不安だったのか、奥州でひっそり息をひそめて静観していた秀衡にも「お前も平氏を追っ払いなさいね」と院宣を出した。
奥州から西日本まで来させようとは無茶な話だが、後白河の命令だから無視はできない。
(結局無視しちゃったんだけどね)
意外と義仲に力がなくて「ダメだこりゃ」と思えば、頼朝に義仲追討の院宣を出しちゃうし、旭将軍が消えて源氏の兄弟喧嘩が始まると、今度は義経にせがまれて頼朝追討の院宣をプレゼントしちゃったり、もう滅茶苦茶!
上皇は、会社でいえば社長の上に君臨する創業者の名誉会長みたいなもので、とにかくワンマンで偉いのだ。
だから社員はもちろん、関連会社や下請け会社までもが服従しなければいけないシステムになっている。
反抗すればカムチャツカ支店へ左遷されるか、馘首となる。
この場合の馘首は、文字の通りの馘首なのである。
もっとも、したたかなのは頼朝とて同じで、やがて、逆に後白河へ、義経追討、奥州藤原氏追討の院宣を出させている。
三十三間堂はどうした! と急いではいけない。
どうせ三十三間堂の由来なんて誰でも知ってるし、書くだけ無駄というもの。
ここはひとまず落ち着いてリプトンのダージリンなんぞ飲みながら一服して欲しい。
要するに、ここでおじさんが言いたいのは、それだけ上皇の院宣というものはオールマイティだったんだよ、ということなのである。
「上皇」と書いたが、43歳で剃髪以後は、称号が「法王」に変わる。
でも面倒だから、以後も「後白河」のままで進めますからね。
紅茶も頂いたことだし、そこんとこを踏まえて続けよう。

一見、日和見に映る後白河。
けれど、院宣によって源氏と平氏を上手くコントロールしていたことがわかる。
結局は頼朝の天下となるのだが、源平それぞれに秋波を送りつつ、皇室による統治を図っていたわけだ。
タヌキ親父の面目躍如である。
それでも藤原信西通憲は後白河を評して「和漢の間、比類少なき暗主なり」と、小バカにしている。
自分に優しく他人に厳しいインテリ特有の身勝手な信西だから納得だが、この信西といい頼朝といい、後白河への批判は注目するところだ。
大日本帝国憲法下では、間違いなく不敬罪で処罰ものだろう。
現在の感覚と違い、それだけ天皇家が軽んじられていた証明ともいえるのではないか。
絶対権力者である創業者の名誉会長も、陰にまわると部下たちは新橋ガード下辺りの赤ちょうちんかなんかで、「ったく、ウチの会長は風見鶏なんだからよぉ」と酒の肴にされていたのだ。
この風潮はすでに、鳴くよウグイス平安京の初期から始まっている。
おじさんが若い頃に強く影響を受けた坂口安吾は、それを「堕落論」の中で的確に指摘している。
日本の政治家達(貴族や武士)は自己の隆盛(それは永遠ではなかったが、彼等は永遠を夢みたであろう)を約束する手段として絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の下位であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって御家騒動の処理をやり、弟は兄をやりこめ、兄は父をやっつける。彼等は本能的な実質主義者であり、自分の一生が愉しければ良かったし、そのくせ朝儀を盛大にして天皇を拝賀する奇妙な形式が大好きで、満足していた。天皇を拝むことが、自分自身の威厳を示し、又、自ら威厳を感じる手段でもあったのである。
以上は「堕落論」の一部だが、「続堕落論」になるともっとわかりやすい。
藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。何が故に彼等自身が最高の主権を握らなかったか、それは彼等が自ら主権を握るよりも、天皇制が都合がよかったからで、彼らは自分自身が天下に号令するよりも、天皇に号令させ、自分が先ずまっさきにその号令に服従してみせることによって号令が更によく行きわたることを心得ていた。その天皇の号令とは天皇自身の意思ではなく、実は彼等は自分の欲するところを天皇の名に於いて行い、自分が先ずまっさきにその号令に服してみせる、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつけるのである。
自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇にぬかずくことによって天皇を神たらしめ、それを人民に押しつけることは可能なのである。そこで彼等は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前にぬかずき、自分がぬかずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。
的確な指摘である。
藤原摂関家や官位上位の貴族から始まり、鎌倉以降の各幕府のまつりごとは、常に天皇制を利用している。
その頼朝から大天狗呼ばわりされた時、上皇は59歳だった。
古ダヌキである。
少しは後白河を持ち上げようとしたが、それは天皇家を取り巻く貴族や武士を貶めることでしか叶わなかった。
おじさんのバランス感覚、筆力はこの程度のものだ。
こうしてみると、現在の天皇が「象徴」と位置づけられている蓋然性の萌芽は、古代にまで遡ることがわかる。
「忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず」
重盛は父清盛をいさめたが、天皇家と対等の立場に昇りつめようとした清盛の野望は、野望のまま終わった。
今でも清盛ご落胤説がまかり通っているが、清盛自身はどう受け止めていたのか気になるところだ。
平家の栄華は、実質、清盛まで。
奥州藤原氏三代の栄華と二重写しになる。
両者を滅ぼしたのは頼朝。
この恐妻家も後白河以上のタヌキ親父だった。

そろそろ三十三間堂に触れよう。
長寛二年(1164年)、後白河のタニマチだった清盛が建立したのがこの大寺、蓮華王院だった。
発願はもちろん後白河院。
藤原摂関家に取って代わった平氏の権力誇示とも言えぬではないが、果たしてこれだけの千手観音は何の意味を持つのだろう。
当時は物量信仰というものがあった。
それにしても、である。
信仰の深さ、信心の篤さが物量に比例すると考えた結果の千体仏なのだろう。
一度の参拝で千体分の法力を得ようとし、千倍の現世利益を求めようとする。
いずれにせよ、欲張りな浄土信仰である。
本尊の十一面千手観音坐像を中央に、両側に五百体ずつの千手観音の脇侍が並ぶ。
本堂の隅から見ると、延々と続くその荘厳の長い列に圧倒され、敬虔な思いに包まれた。
若い頃は一日中、堂内にいた。
そして陶酔した。
南都興福寺の国宝館で阿修羅と対峙する時も一日中動けないが、ここも同じである。
脇侍の前に居並ぶ二十八部衆や、外陣の背面に置かれた風神・雷神なども見事なものだ。
日本が誇る国宝中の国宝であることは、誰にも異論はないだろう。

本堂西側の裏庭である。
堂内の撮影が禁じられているのは残念だが仕方ない。
ここは有名な通し矢が行われる場所。
では三十三間堂のウンチクらしきものを垂れ流すことにしよう。
ガマンして読みましょうね。
今は「弓初め」として成人式の祝いの行事になっているが、昔は武勇を誇る弓の遣い手たちの研鑽の場であり、勝負の場でもあった。
三十三間は柱間のことで、実際は六十六間、120メートルの距離がある。
この120メートルの距離を射るには、剛腕だけでなく、高度の技術が必要だ。
通し矢の記録が最初に文献に現れるのは、慶長十一年の51本。
その後、次々に記録が破られ、寛永年間には3,000本の記録が見える。
寛文二年(1662年)には、尾州藩の星野勘左衛門が6,666本の記録を出した。
ところがその6年後、今度は紀州藩の葛西園右衛門が7,077本で、簡単に記録を更新してしまった。
尾張と紀伊の徳川対決である。
尾州の勘ちゃんは面白くない。
そこで奮起し、翌年には再挑戦で8,000本を通した。
それを見て、さらに奮起したのはもちろん紀州藩。
18年後になるが、和左大八郎なる若者が8,133本を通して面目を立てた。
記録とは、常に破られるために存在する数値なのである。
この通し矢が行われる裏庭で、西村公朝仏師を思い出した。
初めて師を見たのはもう20年くらい前の教育テレビだったろうか。
確か「祈りの造形」のタイトルで、仏像の魅力を語っておられた。
話は興味深く、仏像好きのおじさんは面白く拝聴したし、毎回ビデオにも収めた。
でも申し訳ないが、師のご尊顔は決して好もしく映らなかった。
ドラえもんのスネ夫が年を取ると、たぶんこんな顔になるんだろうな、という印象だった。
ところが、師はとてもスゴイ人だったのである。
戦前戦後を通して、堂内約六百体もの仏像修復を手掛けた、超一流の仏師なのだ。
修復の場所が、この通し矢が行われる裏庭の矢場だった。
その矢場にゴザを敷き、一体ずつ担架で仏像を運ぶ。
最初の作業は仏像の埃を払うことから始まった。
長年の塵や埃は、まるで厚い雑巾が乗っているようだったという。
そして本格的な修復の開始となる。
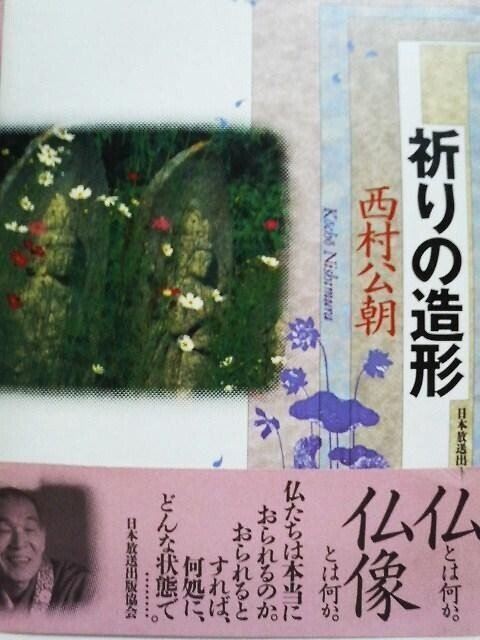
師の著作である「祈りの造形」から、無断だが少し転載してみよう。
三十三間堂参拝の折には、きっと役立つはずだ。
昭和のはじめに大修理のための調査を行ったとき、千体仏に番号をつけていきました。入り口からいちばん奥の最上段、つまり、最南端の最後列を一号とし、入り口側の最前列を千号としたのです。ですから最前列は、奥の最南部から北に一〇号、二〇号、三〇号と進んでいくことになります。最前列で見ることのできる長寛仏は、一六〇、二八〇、三〇〇、四四〇、四五〇、五七〇、六七〇、八〇〇、八九〇の九体あります。鎌倉期の仏像では、湛慶の銘のある一〇、二〇、三〇、四〇、五二〇、五三〇、五四〇、五五〇、五六〇の九体が、顔がピリッとして、内面から力がにじみ出てくる感じです。
(中略)
私どもが、二十年かけて千体仏を修理していて偶然発見した見分け方があります。それは次の二点です。
まず第一の点は、耳に巻毛があるのが鎌倉時代のもので、ないものが平安時代のものだという点です。一般には、巻毛があるのが平安時代、ないのが鎌倉期以後の特徴なのですが、三十三間堂では反対になっています。しかし、ここで注意しなければならないのは、院派の仏像には巻毛がないという点です。
第二の点は、石帯(ベルト)の一部があらわれているのが平安期、ないのが鎌倉期のものです。これには例外はありません。しかし、鉄鉢手といわれる手が、ちょうど石帯の位置に組まれているので、慣れない人には、ちょっとわかりにくいかと思います。それで、まず、遠くから耳の巻毛の有無を確認し、次に石帯の有無を確かめるとわりあいに簡単です。
< 日本放送出版協会発行 西村公朝著 「祈りの造形」より抜粋 >
※ 湛慶を始めとする南都の仏師集団を慶派といい、京仏師たちを院派という。
公朝師の訃報を聞いた時はショックだった。
お元気なうちに、ぜひ愛宕念仏寺を訪ねたかった。
次回「ノープランで行こう」へ続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
