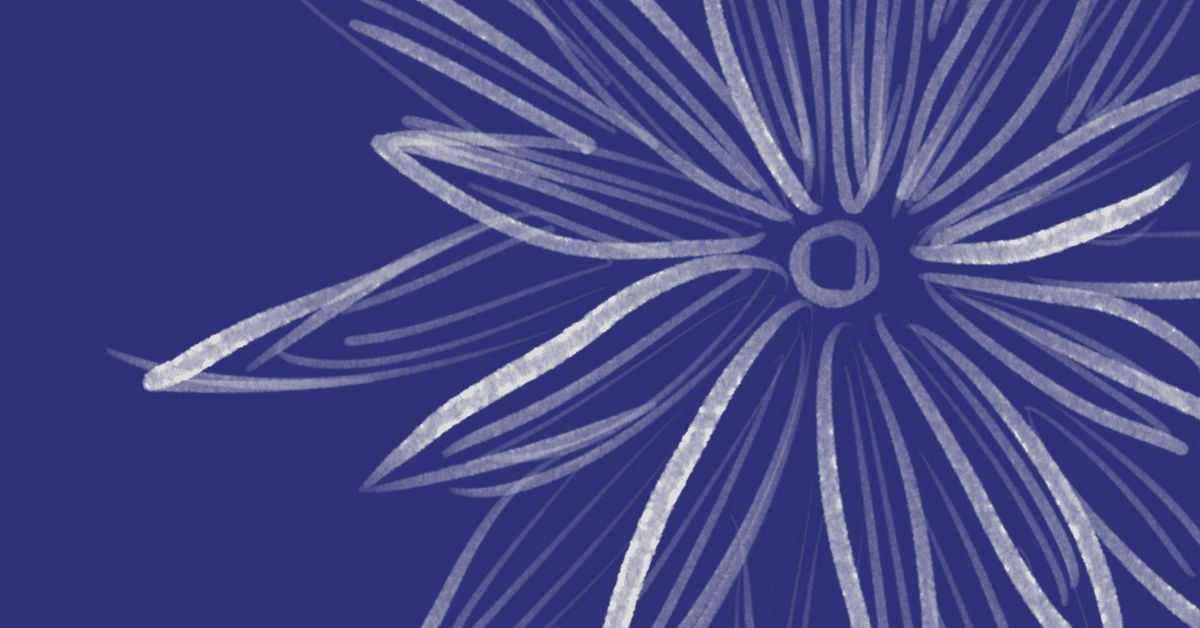
『サンダカン八番娼館』 山崎朋子
〈からゆきさん〉とは、「唐人行」または「唐ん国行」ということばのつづまったもので、幕末から明治期を経て第一次大戦の終わる大正中期までのあいだ、祖国をあとに、北はシベリアや中国大陸から南は東南アジア諸国をはじめ、インド・アフリカ方面にまで出かけて行って、外国人に肉体を鬻いだ海外売春婦を意味している。その出身地は、日本全国に及んだが、特に九州の天草島や島原半島が多かったといわれている。
1972年初版の本書は、70代80代の老女となった元からゆきさん達の生の声を取材したドキュメンタリー作品である。
貧困ゆえに苦しく耐えがたい人生を送った女性達の声なき声を聞くことが、女性史研究者としての仕事であるという著者の強い想いが、プロローグで語られる。
貧困地から南洋に送られて行った彼女達に、階級と性という二重の虐げが集中して表されている、つまり、日本における女性の苦しみの原点がある、と著者は論じる。
(天草が貧困地となった自然的また歴史的要因、そして、貧困と性との繋がりが、なぜ日本の女性問題の根本となるのかについては、最終章に詳しく述べられている。)
海外での売春生活は当事者にとっては忘れ去りたい過去であり、また家や一族の恥になるという強い心の抵抗もある。そんな彼女達からその経験を聞き出すために、著者は、彼女達の住む地に自ら住み込み、同じ生活をして、閉ざされた心の解きほぐれるのを待つという方法を採った。
また、その取材相手も、過去に同様の取材を受けている女性達や、現在豊かな生活をしている、からゆきさんの中では成功者に属する女性達ではなく、まだ誰一人訪ねたことがない、「文字どおり地を這うように生きて来た」からゆきさん達にしたいという考えだった。
そして実際に著者は、おサキさんという一人の元からゆきさんの家に泊まり込んで、三週間、共に生活をする。
おサキさんの住居は、炊事場も風呂もトイレもないばかりか、畳は腐ってムカデの温床となっているという貧困の極みであり、そこでの生活は想像を超える過酷さだったという。
しかし、ポケットマネーで快適さを導入したくなる気持ちを、著者は心で叱りつけて抑え込む。
おまえは、おサキさんとまったく同じ生活を送るつもりで、この天草を再訪したのではなかったか。おまえがおサキさんの麦飯を三度三度食べ、腐って百足の巣になった畳へ坐り、かつては何千人かの異国の男たちが横になったボルネオ綿の蒲団に眠り、さらに裏の崖ぶちへ穴を掘って用を足すという生活に耐えなければ、彼女はおまえを、自分と同じ立場の人間とは見てくれないだろう。そしてからゆきさん生活の本当の話など語ってくれないだろう。
おサキさんは、からゆきさんの取材をさせてほしいと正式に申し込んだ相手ではない。
著者は天草で偶然出会ったおサキさんに、身分と目的を隠して近寄り、おサキさんは著者を、事情のある不憫な女性であると理解して、家に招じ入れてくれたのである。
そのような状況なのでテープレコーダーも取材メモもなしで、切れ切れに断片的に聞き取った内容を、一人になった時を見計らっては便箋に書きつけて東京の自宅に送るという方法で著者は取材を行ったという。
研究者の執念のみならず、社会に何物かを伝えなければならないという強い想いがなければできない、困難な取材だったことだろう。
おサキさんが昼に夜にぽつぽつと語ったのであろうその人生の物語は、著者によって構成し直され、おサキさんの話し言葉で綴られている。
おサキさんが生まれたのは貧しい集落であり、その村だけでも、「あすこの家からもここの家からも」少女達がからゆきさんとして南洋に売られて行ったという。
父を亡くし、母は再婚したものの、その母に反発して子供達だけで生活していたというおサキさんと兄と姉。
その生活はもちろん困窮を極めたもので、おサキさんの南洋行きも、兄が畑を持ち嫁を貰えるだけのお金を得られるようにと、自分から願い出たものだった。
おサキさんはまた、友達も南洋行きに誘い、3人の少女達で連れ立って出発したという。10歳11歳の少女達である、「毎日きれいな着物を着て白いお米がいくらでも食べられる」と聞いて、不安の中にも晴れがましいような気持ちで出かけたのだろう。そのあどけない笑顔も想像されるだけになおさら残酷な話だ。
売られたとはいえ、内実は少女に多額の借金を背負わせ、体で稼いで返させる、という仕組みである。
ボルネオのサンダカンに送られた少女達は、同じ女郎屋に置かれ、数年後から客を取らされるようになったという。
その生活は本書に詳しいが、肉体的にも精神的にも過酷な、人権など無いに等しいものである。が、驚愕なのはその彼女達の、社会的な扱われ方だ。
おサキさんと同じく彼女の姉もからゆきさんとなっており、二人が借金を返しながらこつこつと仕送りをし続けたために、おサキさんの兄は嫁も家も手に入れることができた。
しかしおサキさんの一時帰国時に、誰一人出迎えにも来なかったのだ。おサキさん自身も、外聞が悪いのだろうと恨みにもしない。
貧困地の女性が、体を売って命を削ってお金を得る。それに対し、悔恨の涙を流して頭を下げるどころか、土地の恥として蔑み黙殺しようとする。女性本人も身を小さくせざるを得ない。その社会意識の構造に怖気が立つ。
サンダカンの話に戻ると、ここに、おクニさんという女性が登場する。
サンダカンの女郎屋は一番館、二番館、、、と呼ばれていて、おサキさんは初めは三番館に入っていたのだが、その後の紆余曲折の末に八番館に身を置くことになった。
その八番館の親方が、おクニさんという有名な女性だったという。
木下おクニさんはな、〈サンダカンのおクニ〉と言われて、南洋では知らん者はおらぬお人じゃった。・・・普通、女郎屋の親方はみんな男で、うちらお女郎をしぼることしか考えんが、おクニさんは女じゃけん、女郎のめんどうばよう見てくれるもんで、サンダカンじゅうの女郎が、「おクニさん、おクニさん」と頼っておったお人やった。
寛永二年生まれのおクニさんは、義侠心に富んだ女親分で、サンダカンで命を終えた日本人のために、海の見える丘の上に日本人墓地を開くなど、人徳を語る逸話も多い。
還暦を迎えた時に「これからは男になるとじゃ」と宣言して、髪をばっさり切って男物の羽織袴で写真に収まったという。大胆でカリスマ性のある人物だったのだろう。
そのおクニさんが親分をしていた八番館の名を本書のタイトルに据えたところに、著者の想いがうかがえる。
おサキさんは、辛い過去にも極貧の現在の生活にも、恨みの言葉は一切吐かない。それは、彼女が持つ人格的な資質が一番の理由だが、その娘時代の生活に多少なりとも救いがあったのには、おクニさんの存在も大きかったに違いない。
このドキュメンタリーにあるのは、女性達の運命の悲痛だけではなく、おサキさんとおクニさんに体現されるような、どんなに底辺にあっても穢れない美しい心や人間の尊さがもたらす感動でもあるのだ。
著者のからゆきさん取材は、強い信念あってのものだったと先に書いたが、その想いは、最終章に熱く語られている。
本書は貴重な証言と事実を集めた女性史研究書であると共に、社会政治に変革を求める思想の書でもあるが、それは著者の、喫茶店のウェイトレスや写真モデルといった、女性が搾取の対象にされかねない職業に就いた経験や、理不尽な暴力を受けた経験と、信念に基づく真摯な取材、そして思想家達の書に学んだ聡明な頭脳の結実ではないだろうか。
