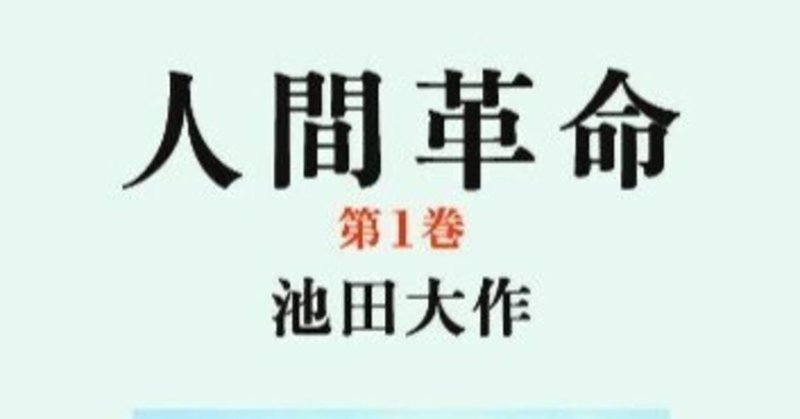
小説「人間革命1巻」⑤~千里の道~
人間革命1巻の「黎明」では、戸田先生が出獄され自分が獄中で悟った悟りを確認され、「再建」では戸田先生の現実世界での現状認識をされる。「終戦前後」では日本における終戦手前から戦後において主とし、「占領」では終戦後の対応で人々の現実にどのように影響を与えたかを記している。「一人立つ」では戸田先生自身が今まで思索し決意されてきたことを牧口先生の前で言葉にし宣言され、そして、本章の「千里の道」では、実際の創価学会の活動へと進んでいくのである。
思想研究の原点
戦前、初代会長の牧口は、常々、神についての正しい認識を与えようとして、神を三つの視点から分類して教えていた。
第一は、天地を創造したと考えられている神。第二は、祖先を神として崇めるもの。第三は、仏法で説く神である。
本章の最初では、当時の日本の食糧状況に触れながら、諸天善神について戸田自身が考察しつつ、牧口の神の考察に触れる。そして、日本における国家神道について記載が進んでいく。
創価学会の思想探求は、自分たちの宗教のみならず広範囲にわたる。それは、近年の取り組みではなく、牧口の時代から行われていたことが伺える。そもそも、日蓮仏法には、思想の浅深を明らかにし、民衆に正しい思想の種を植えていこうという魂が、信仰の中に含まれている。それは、日蓮大聖人も日本国中にある宗派の探求を行い、法華経こそが末法の人々を救う方法であると見つけ、時の執権に「立正安国論」を提出することで思想を正そうとした。御書を見ると、他宗への批判も多くあり、国内の思想を正邪を正していこうとの想いを見ることが出来る。一方で、信心を求めている民衆や門下に対しては、様々なたとえを通し分かりやすく教え説いている。その例えは、自身の宗派の域を超えて、歴史や自然科学など万波にわたる。日蓮仏法における思想探求や研鑽、すなわち「学」は、正邪を正す破邪顕正の「剣」となりながらも、その心には民衆を守るという「盾」という役割があると見える。
神は、人間の心がつくりだしたものであり、生命のもつ働きを具象化したものといえる。その働きが、人間生活に価値をもたらす場合には、梵天・帝釈という諸天善神としてとらえられ、悪をもたらす場合には、魔王と位置づけられるのであり、善悪両方の働きを、生命はもっているのだ。
「生まれながらにして善か悪か」と捉えるのが西洋の哲学観であるが、仏法の生命観では「生命は常に善悪を共に兼ね備えている」と捉える。
GHQは、この神道の問題、すなわち国家神道が、明治以来、日本の政治体制の根本原理となっていた事実を突き止めていたからである。これが、今後の日本の民主化にとって、最大の障害になると見ていたのだ。物事は、常にその本質を論じ、見極めることが大事である。GHQは、よく本質を見極めていたといえる。
敵国であったアメリカは、日本の探求をし続けてきていた。それは、日本の本質、内在的論理を的確に見極めていた。あくまで筆者の主観だが、日本人は、他に対する内在的論理を見極めることの重要性の欠如が比較的強いのではないかと思われる。それは教育の中においても「自分の嫌なことは人にするな」というのにも表れているのではないかと思う。あくまで主観的であり、本当に相手が嫌なことなのかは実際は分からない。すなわち、善的な感覚が強く、自分の考えていることは皆も同じように考えているという傾向性が強い民族なのではないかと思う。
そして、本章はp.248から国家神道について記載され始める。
一八八九年に発布された明治憲法では(中略)天皇を絶対化し、国家統治の権力の一切を天皇に帰することによって、国家の統一、安泰を図ろうとしたのである。
こうして、天皇という一人の人格において、政治と宗教は完全に一致してしまった。この天皇崇拝は、やがて、天皇そのものを現人神とする「宗教」になっていくのである。
現代では、ご法度である「政教一致」がなんなく行われてしまっていた。具体的には以下のように記載されている。
政府は、天皇の権威と一体の関係にあった神道に対してだけは、特別な政策を一貫して取り続けた。神社の格に応じて、国家予算をつけ、公費を支出、あるいは神官・神職に、官位を与えて官吏とするなど、他の宗教と明らかに異なる扱いをしていた。また、皇室や国の式典は、天皇の威信を示すものとして、神道式の儀式が次々と定められ、これに参列することは、一般官吏の義務とした。
日本は法治国家である。それは当時も同様であったはずだ。しかし、神道だけは特別扱いであった。そして、それは習慣であるとし始めることで、人の信じるという本然的に持っている性質を使い、大衆を先導するのであった。
特定の宗教への礼拝を強要することは、憲法に照らし、矛盾をきたすことは明らかであった。
「神道の国教的地位」と「信教の自由」をめぐって、仏教やキリスト教関係者などから、しばしば疑問が呈された。政府は問題が起きるたびに、「神社は宗教にあらず」を建前にして、苦しい答弁を繰り返していた。
政府の対応に、異をとなえ始める団体はあったが、政府は明確な回答を出せなかった。しかし、それでも進んでいくのである。また迎合するもの多かったという。日本基督教団もまた日本にあるキリスト教を政府要請によってまとめあげられた団体となってしまった。ここに、当時の日本の未熟な民主主義があったのではないかと思う。
宗教各界もまた、弾圧を恐れて、国家神道に同調し、迎合するしかなった。(中略)明治、大正、昭和と天皇が絶対化されていく時流に乗ろうとした宗教家も少なくなかった。
前々章のp.180「占領」の中にある「力のない宗教は権力と結託しようとする」とは、まさにこの部分である。
日蓮主義を標榜する田中智学ら国柱会は、進んで国家神道を宣揚する役回りを演じた。田中智学は、法華経、日蓮大聖人の法義を、皇室神話に結び付けて解釈し、唯一絶対の天皇が統治する神国日本こそ、世界統一の根本国であると喧伝していた。
日蓮大聖人の精神を捻じ曲げていく団体も現れる。先ほど、「日蓮仏法のには思想の浅深を見出そうとする魂がある」と書いた。しかし、ここでは真反対のことが起き、大聖人の認識を歪曲させている。認識の歪曲は、経典などの文章をかいつまんで、エイヤ!っとやってしまえば意図も簡単なことである。要するに、問題は「誰の解釈を信じるか」ーなのではないかと改めて感じることができる。新人間革命6巻「宝土」の章には、その点について山本伸一が以下のように語っている。
これからは学会も、世界の宗教に対する、しっかりとした研究と勉強が必要だよ。そして、たとえ一つの言葉でも、誰が言ったものなのか、どこから出たものなのか、本当のことなのかを、見極めていかなくてはならない。
今後、創価学会が未来永劫に続いていくとすれば、三代の会長の意思とは反した曲解を示す人たちも出るだろう。実際、現代においてもTwitter上を見ればそのようなことは散見する。しかし、明確なエビデンスがない。また仮にエビデンスがあったとしても、当時の時代背景等の検討が足りず、その場や時代においてを見極めようとはせず、結果認識のままで発信を行う。だからこそ、我々の世代において、最も根幹とすべき日蓮大聖人の御書、創価学会の精神の正史である人間革命、新人間革命を虚心坦懐に読んでいくことが何よりも重要であり、それを体現し明言できるだけの行動と言論が重要なのだ。
一九三九年、政府は、宗教団体法を制定し、すべての宗教を国家統制のもとに置き、強制的に各宗派を合同させるという暴挙に出た。宗教界はこぞって、天照大神を祭り、天皇を絶対とする挙国一致の報国運動に同調していった。もはや、そこには、宗教者としての信念の片鱗すらもうかがわれなかった。
この部分について、近年の研究の中では、創価教育学会も実質的には政府に反対をしていなかったのではないか、との議論がなされている。これに関して、創学研究所所長の松岡幹夫氏は「創価学会の思想的研究<上巻>」ではこのような論文を出している。
創価教育学会の戦時対応が根本において日蓮仏法の論理に基づくものであり、そこには「見えない」反戦の行動があったと指摘した。はっきりと戦争反対の声をあげることは政治的な「見える」反戦であるが、反戦の仕方には他にもある。教育を通じて人々の心を平和に向けさせる、宗教の力で戦争の原因そのものをなくす、これらも教育的あるいは宗教的な「見えない」反戦といえるだろう。
当時また現代においても、創価学会は大きなデモ行動などは起こさない。それは、真の日蓮仏法に基づき、「調和的非暴力」を貫く。そもそも非暴力には、大きく二つある。それは「対立的」か「調和的」である。「対立的」とは、反対を大きな声で叫びながら相手と戦う。時には暴力的な行動も辞さない構えである。一方、「調和的」とは、対話が含まれ相手の意をつかみながら、自身の主張を貫いていく方法である。これは厚い壁を壊すのではなく、壁の向こう側に見方をつくる戦いといえよう。牧口先生、戸田先生の戦時中、そして獄中ではまさに、調和的非暴力での反戦であったといえる。
世界大戦に突入すると、国家神道を中心とした政治形態は、祭政一致の古代社会そのままに、神がかり的な全体主義の権力を、容赦なく国民のうえに振るい始めた。(中略) 戦争遂行のための思想統一を進め、無謀な侵略戦争に一国を駆り立てていったのだ。
神がかり的な全体主義、すなわち、神を利用したファシズムであったということだ。ヒトラー率いるナチスは、労働者階級のホワイトカラーを先導していった。「このまま資本主義が進めば、あなたたちの生活が脅かされる。そしてそれはユダヤ人のせいでもある」と。ホワイトカラーの彼らは、ある程度の生活はできるが、一つ踏み間違えれば自身の生活を脅かされるかもしれないという階級の人たちである。すなわち、中間層を巻き込んだ全体主義を起こしていった。日本にはおいては、国家神道という宗教を使っての全体主義としていったという点で大きく異なる。この点において、日本における思想、またそれに伴う信念の脆さが見える。
権力が、宗教を手段として国民を支配する時、どのような悲劇を招いていくのかー戦前の歴史は、それを何よりも物語るものであろう。
「何のための宗教なのか」これに誰も気づかなかったのだろうか、とふと思うが、それにも気づかないほどに民衆は扇動されていたのだろう。
真実の民主主義は、単なる政治機構や社会体制の変革だけで、出来上がるものではない。何よりも、個人の生命の内側からの確立が出発点であり、土台となる。それが次の時代の幸福生活への第一歩でなければならんことも、戸田は鋭く見抜いていた。彼はまた、宗教に対する無知が、人類最大の敵であることを、胸中に深く確信していた。この無知の壁は厚く、高く、牢固として抜きがたく立ちふさがっていた。
「悲惨の二字を無くしたい」これは、創価学会における永遠のテーマである。この悲惨を無くすために、何と戦っていたのか。それは「無知」であった。広宣流布とは、この「無知」から民衆を目覚めさせることにほかならないだろう。その精神は、当然のことながら私たちにも含まれ、我々の政治活動においても同様である。
大きな一歩
広宣流布達成まで、それが千里の道のように見えようとも、一歩一歩の前進を、決して忘れてはならない。この一歩の前進なくして、千里の道が達せられることはないはずだ(中略)
その力強い第一歩として、彼は、法華経講義を始めることを決意した。
創価学会の再建に向けて、実質的に行動し始める。だがそれは「法華経講義」という一見、小さな一歩であった。広宣流布を進めるという観点からすれば会員を増大させることの方を優先すべきではなかったのかと思う。実際、牧口門下の人たちをかき集めるなどの行動もとれたはずである。また、宣伝し呼びかけることもできたのではないか。しかし、戸田はそうは考えない。今いる目の前の現実からスタートしようとしたのである。まずは着実な一歩を踏むことにしたのだ。
”すごい・・・いったい、いつ、彼(戸田)は、こんなに勉強してしまったのか!”
この夜の三人には、解けぬ謎であった。彼らは、ちょうど、鹿野苑で釈尊の説法に感激した阿若憍陳如等の五人のようであった。北川直作らの三人も、講義を通して、戸田の偉大な境涯に触れ、言うべき言葉を知らなかったのである。
法華経の研鑽を終え、ここで初めて、経済グループの4人は戸田の凄さを知る。当然のことではあるが、これを獄中闘争があったからこそ体得しえたのである。
岩森君、心配するなよ。大聖人様のおっしゃることが、心から信じられないから、われわれを 凡夫というんだ。しかし、凡夫といえども、信心を一生懸命して、それがわかれば、一人残らず仏になれるわけだ。これは間違いいない。
御本尊様を受持し、強盛に信行学に励めば、いつまでも、悩める凡夫でいるわけがない。それが大聖人様の御力なんだ。
ここにおいても、目の前の人を励ますのである。そして、共に広宣流布を進める同志となるように諭しているのである。
”永遠とは、瞬間、瞬間の連続である。瞬間の連続が、永劫である。その瞬間の本源、本体こそ、南無妙法蓮華経である・・・”
この瞬間、瞬間という連続の中にあると、戸田自身が悟っていたからこそ、法華経講義という小さくとも大きな一歩を進めたのである。
戸田は、彼らを見て思った。
”彼らが、少しでも理解してくれれば、実にありがたいことだ。彼らに理解できなくても、かまわない。彼らがどうであろうとも、この講義は、最後まで続けよう。彼らのうち、落後する者が出てもいい。また、新たに参加する者もでてくるだろう。最も大事なことは、ともかく今の講義を、続け切っていくことだ”
大事なことは続けていくことである。常に勝ち続けることである。一時代の栄華を誇っていても、その次の世代で廃れていってしまっては無意味
になってしまう。まさに「建設は死闘、破壊は一瞬」なのである。この一歩一歩歩みを進めていくことを絶対に忘れてはならない。
近年の創価学会の活動は、時に選挙、選挙、選挙のようにみえる。その一つ一つを立てた目標に対して勝ち超えていかなければならない。しかし、その一つ一つで勝ったとしても、組織を含め自分自身の信心が強固になり、そして組織が発展していかなければ、選挙家と同じなのではないかと思う。
この点について改め見つめなおしながらも、常に上昇しつづけていける自分自身でありたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
