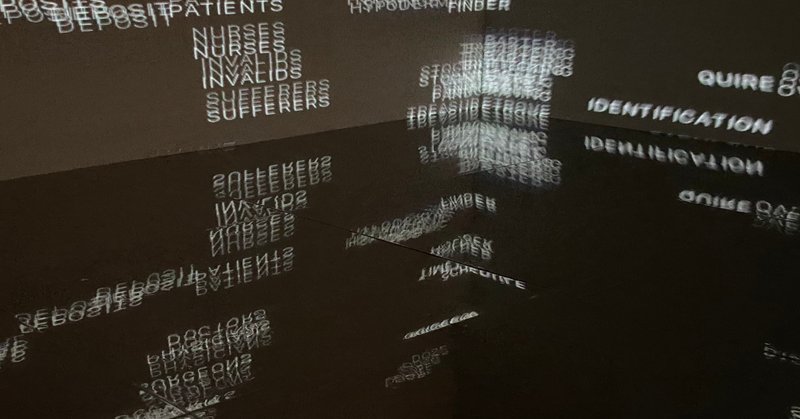
「購入」はマーケティングにとってゴールなのか?スタートなのか?
よく自分が話すセミナーなどで、現在の多様性を認める社会以前での価値観を表現する優れた広告コピーとしてTOYOTA クラウンの「いつかはクラウン」を上げることが多い。
「男性」は「家族」や「車」を持ち「出世」していくべきだという考え方が主流の中で、このコミュニケーションは、クラウンに「車」と「出世」の価値観を掛け合わせたポジティブな意味を付加すること(記号化)に成功しているからだ。
もちろん、この価値観は当時の社会性を反映しすぎるがゆえに、現状では反面教師的な位置づけになってしまうのは仕方ないが、広告が記号を生み出す。という面においては学ぶべき点が多い。
クラウンを買うということは、私が「出世」したという記号を手にすることであり、わざわざアピールしなくても他人にわかるように仕向けてくれるのはいろいろ便利である。
もしも車に全く乗らなくても「出世」の記号は、自宅の駐車場に置いておくだけで、通りがかる人々に対して勝手に「起動」してくれる点も興味深い。当時、広告はこのような記号のお膳立てをしていたからこそ、今以上に必要とされていたという穿った読み方もできるかもしれない。
コミュニケーションによってブランドを何かしらの記号に変えたいという目標は、ビジネスを効率的にするためのマーケティング上のゴールの1つだ。
しかし、価値観が多様化した今、クラウンのようなメッセージでのブランドの記号化は困難になっていると思われる。
そのため、今回はデジタルネイティブ環境において「ブランドと記号化」について考えてみたい。
ところで最近、マーケティングは「購入」をゴールではなく、もっとスタートとして考えるべきだと強く思っている。
企業目線では「購入」はお金を伴う行為であり、ビジネス的には重要なゴールである。
しかし、カスタマーにとってはどうだろうか?
クラウンのように「購入」するだけである程度、記号性を発揮する場合には、カスタマーにとってもゴールとしても問題ないかもしれない。
しかし、多様性を認める価値観の元で、この考え方は人々の共通項にはなりにくい。そのため、購入してもらうためには別のモチベーションを用意しなくてはならないと考えている。
そのモチベーションとは、カスタマーが購入によって「新しく何かがスタートできる」という期待感を持たせることだ。
「何か」とは新しい体験に他ならない。その製品を所有することによって可能になる体験のことだ。
例えば、コーヒー好きなあるカスタマーは、時間に余裕がある土日の朝しかできなかった「自宅で自分好みの美味しいコーヒーを飲む」という体験を、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる全自動コーヒーメーカーを購入することで忙しい平日の朝でも手に入れられる。
機能的な視点だけで見れば、この体験は製品スペックによる限定的なものに見えるかもしれなく、新しさはないだろう。
しかし、デジタルネイティブ環境下でのポイントは、その体験は容易に人にシェアできるということだ。リアルな会話に加えて、ネットへのシェアの機会が莫大に多いことが、体験のプライオリティを格段に上げている。
また体験のシェアがハブとなり、同じ体験を持つ人々がつながりあうことでゆるいコミュニティとなり、再び規模の大きい多様性=クラスターを形成していく再帰性があることも重要だ。
全自動コーヒーメーカーの例で言えば、平日の朝に飲んだ美味しいコーヒー体験は何かしらのリアルな会話やネットでのシェアを生み、価値を生み出しているといえる。そしてその時、どんなブランドによってその体験が実現できたのか?はシェアの価値をさらに上げる可能性がある。
つまり「コーヒーの歴史の長いイタリアのブランド」もしくは「日本ならではの丁寧なモノづくりのブランド」など、ブランドのコンセプトが明確だとその人の価値観も明確になるといえばわかりやすいだろう。
ここに新しい時代の「ブランドと記号化」に関するポテンシャルがある。
購入は何か体験のスタートだとし、さらに体験の期待感やシェアすることの価値が高まっていると考えた場合、体験の後ろ盾になることがブランドの役割ではないかと思う。
後ろ盾になるためにはいくつかのポイントがある。
まず1つは「体験の記号化」だ。
ある体験がまだはっきりと記号化されていない場合、つまり固定した名称や、面白さや社会的価値、クラスターの存在が明確ではない場合において、ブランドは体験に「名称を固定する」「面白さや価値を伝える」「クラスターの存在を明確にする」ような投資(広告)を行うことで体験が記号化される可能性が高い。
もう1つは「優位性」に関する点だ。
体「○○という体験はうちのブランドじゃなくても実現できるから優位性がない」という言い方をよく耳にする。
しかし、それはデジタルネイティブ環境ではカスタマー不在の考え方だ。
情報が膨大にある時代において、ほとんどの体験はどこかにあり、そのブランドじゃなくても実現可能だ。また可能性のあるクラスターが存在している場合はリーチ的なスピードの観点で有利だが、そこには当然、他社ユーザーもいる。そんなことを気にしていてはこの時代のブランド優位性を得ることはできない。
その体験の"一番"の後ろ盾になろうという意気込みこそが優位性になりうるのではないかと思う。
その中でも大塚製薬「イオンウォーター」の取り組みは秀逸だ。
イオンウォーターは「サウナ」という体験を記号化することに数年取り組んでいる。なお、サウナには従来の記号が存在(中年男性イメージなど)があるため、ミレニアルズ層にとっての記号の再構築と言ったほうが最適かもしれない。
「サウナ」の記号の再構築は大塚製薬以外にもYAMAHAも取り組んでいるが、いわゆるスポーツドリンクとサウナを結び付けることはどこの会社でもできることだ。
しかし、イオンウォーターはサウナへの注目を元に、「ととのう」という価値(自社発案ではないのが素晴らしい)の固定化を促し、サウナ施設紹介サイトを作ることでクラスターを明確化する、つまり記号化するための投資を通じて、サウナという体験の後ろ盾になることをやり切っていることが素晴らしい。
なお、その意気込みはイオンウォーターはブランドページのトップに「サウナといえばイオンウォーター」と書いてあることからもうかがえる。
最後にまとめると、今まではブランドはそれ自身が社会に対してポジティブな記号となることを目指すべきだったが、これからは、ブランドにとってポジティブに作用な体験を記号化することが、「ブランディング」になりうるのではないかと考えた次第である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
