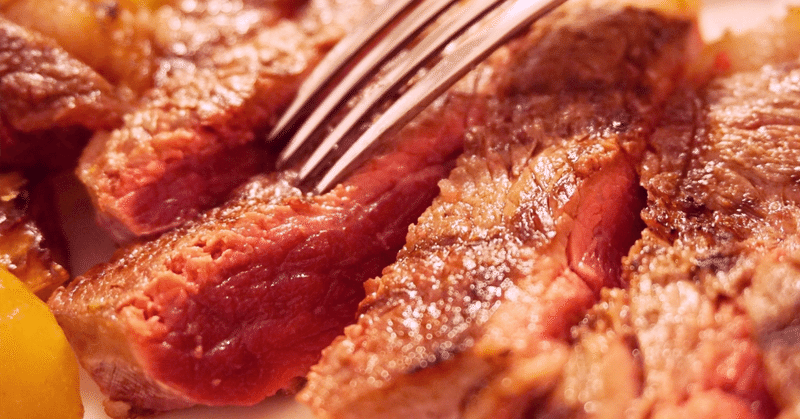
肉の加熱:主にタンパク質について
こんにちは。
以前見た城ニ郎さんというYouTuberの方の動画の中で、お肉の調理温度とタンパク質の関係性について言及されていたので、少し調べてみました。今後機会があったとき参照する用に、以下に書いておきたいと思います。訂正や補足の必要性があった場合は、その都度加筆・修正します。また本記事で対象にしたのは主に豚や牛などの陸上生物のお肉です。温度などは動物やお肉の部位によって少しずつ変わってくるので、あくまで目安です。
以下がその動画です。少し話は逸れますが、本動画でフランス料理の国際コンクール、ボキューズ・ドールの紹介と応援のためのクラウドファンディングのお知らせがあったのですが、既にクラファンの期間は終了してしまいました。それまでに記事を出したかったのですが… ただコンクール自体は来年なので、是非日本を応援しましょう。
肉中のタンパク質:構造、主な働き
タンパク質の種類と筋肉の構造
動物の筋肉を構成するタンパク質は3種類。
1. 筋原繊維タンパク質:ミオチン、アクチン、アクトミオシン
2. 筋形質(筋漿)タンパク質:ミオグロビン、酵素
3. 結合組織タンパク質:コラーゲンなど
筋肉は、筋繊維が筋内膜で包まれ、更にその束が筋周膜に包まれ、更にその束が筋外膜に包まれた構造を取る(いずれの膜もコラーゲンにより形成)。筋繊維を構成するのは、長い繊維状の筋原繊維タンパク質と筋形質タンパク質(後者が前者の間に挟まれる)。それぞれの比率は動物によって異なるが、食肉の場合1が50%前後、2が約20〜30%、3が約20%〜30%。

筋原繊維タンパク質
筋原繊維タンパク質は細くて長いアクチンフィラメントと太くて短いミオシンフィラメントより成り、筋肉の収縮に関与する。加熱により収縮・硬化する。水には不溶。またミオシンとアクチンは共に塩溶性(ミオシンはわずかに水に溶けるとも)であり、塩を揉み込むことで両タンパク質が溶解し、結合してアクトミオシンとなる。ハンバーグやかまぼこなどの食品はこのアクトミオシン等が生み出す粘性を利用する。死後硬直も同じくアクチン・ミオシンが互いに結びつくこの反応により起こる。(ただ時間が経つと肉中に存在する酵素が結合を分解し、軟化を促す)。
筋形質タンパク質
筋形質タンパク質は水・塩溶性で球状。ミオグロビンや酵素などで構成される(アルブミン、グロブリン等も?)。お肉の色はこのミオグロビンに由来する。酸素を貯蔵し、運動時など必要に応じて筋肉に酸素を供給する。詳しい構造については私の化学的知識の不足もありここで記述はしないが、大まかに言えば酸素と結合したり加熱したりすることでその色を変化させる。
酵素は主に糖質分解とタンパク質分解を行う。前述のように、両者は死後硬直中にそれぞれグリコーゲン(→ATP/アデノシン三リン酸及び乳酸?)、アクトミオシンを分解する。また熟成中にもこれらが働くことにより、タンパク質からイノシン酸を中心とした旨味成分が多く作られ、調理後のお肉の食感・風味・味に大きな影響を与える。
重要なのでここで生成される乳酸で、これにより微生物の繁殖が抑制され、酵素の働きが調整される。元になるグリコーゲンの量は屠殺前のストレスを含む様々な要因により変化する。従って動物の扱いによって肉の質が低くなったり腐りやすくなったりする。
結合組織タンパク質
肉基質タンパクとも。水・塩水等に不溶。結合組織タンパク質は主にコラーゲンで構成され、前述の通り筋内膜・筋膜として筋繊維を束ねると共に、腱のように筋肉を骨に固定する結合組織繊維構造としても機能する。従って人間と同じように、肩や足の部分に多く含まれている。ちなみに重力に逆らい体を支える必要のある陸上動物と違い、魚はこのような構造を必要としない。また魚は瞬発力を必要とするため、筋肉の繊維は陸上動物のそれより短くて細い。
加熱:タンパク質の変性と色の変化
加熱する際に目指すのは、病原体を死滅させつつ、タンパク質の過度な硬化を防ぐ、つまりお肉が硬くなりすぎないようにすること。以下では主に後者に焦点を当て、加熱の際の適切な中心温度を検討する。
お肉の赤色とその変化
まずお肉の色とその変化について。先ほども書いたように、お肉の赤色はミオグロビンのものである。本来ミオグロビンの色は紫がかった赤色だが、保存中に酸素と結合することでオキシミオグロビン(鮮紅色)に変化し、そのまま放置すると酸化してメトミオグロビン(茶褐色)に変化する。更に加熱することによりタンパク質が熱変性し、メトミオクロモーゲン(灰褐色)になる。 その他にも亜硝酸塩によるニトロソ化などもあるが、よく分からないので割愛。ところで、所謂香ばしい焼き色はメイラード反応によるもの。味噌や醤油の製造でも利用されるが、通常の調理中は更に高い温度帯(150℃〜200℃)で起きる。
それぞれタンパク質の変性温度
3種類のタンパク質の変性温度はそれぞれ異なる。
筋原繊維タンパク質:45℃〜50℃で変性開始。
筋形質タンパク質:56℃〜62℃で変性開始。
結合組織タンパク質(コラーゲン):65℃付近で収縮するが、75℃以上で分解・ゼラチン化。変性自体はもっと低い温度から始まるか。
ミオグロビン(筋形質タンパク質)は約60℃で変性開始。食肉科学技術研究所のコラムによれば、タンパク質であるグロビンには鉄の酸化防止作用(つまり鉄が酸化することによって起こる上記のような色の変化を防ぐ効果)があるらしい。ただこの効果は、グロビンが熱により変性すると失われる。よく焼いたはずの肉の内部にピンク色の部分が残っていることがあるが、それはこの酸化防止作用によるものと考えられる。従ってピンク色が見えるからといって焼けていないとは必ずしも言えない。
50℃以上で筋原繊維タンパク質が凝固するが、この時点ではまだその間にある筋形質タンパク質が凝固していないので、柔らかいままである。しかし筋形質タンパク質が変性するとそれを挟む筋原繊維タンパク質とくっついて凝固するため、硬くなる。
コラーゲンが多い部位に関してはその分解が起こるまで加熱する必要がある。煮込んだ肉の柔らかさはコラーゲンのゼラチン化によるものなので、コラーゲンがあまり含まれない部位を長時間加熱しても望む食感は得られない。
何度が最適か
以上のことから導き出せる理論的な結論としては、中心のピンク色を保ちつつお肉の食感を柔らかく仕上げるためには、中心温度が60℃未満になるように加熱する必要がある、ということ。始めに紹介した動画では、お肉を57℃で真空調理していたので、60℃未満に当てはまっている。65℃を超えるとコラーゲンが収縮して水分が大量に流出するため、少なくともこの温度帯までに止める。
ちなみに以上の結論は「『熱』の科学」を参考にしたが、「Cooking for Geeks」の記述ではそもそもタンパク質の分類が異なり、従って理想とする温度帯も異なる。これによると重要なのはミオシン・アクチンの2つで、前者が50°〜60°で、後者が66°〜73°で変性する。本書は理想的な温度帯をミオシンを変性させつつアクチンが変性しない範囲、即ち60°〜67°としている。
どちらの説がより科学的に正しいか?
14/9/22 『NEW 調理と理論 第二版』を参照
その内容を含めると、お肉を加熱した際その硬さに影響する要因は筋形質タンパク質、結合組織タンパク質(コラーゲン)、アクチンの3つ。ミオシン、アクチンはそれぞれ変性を開始する温度が異なるが、アクチンの変性がお肉の弾性率及び水分流出量の増加を引き起こす。食感を柔らかく保つことに焦点を当てれば、これら3つのタンパク質の変性が起こらない温度帯、即ちそれが最も低い筋形質タンパク質に注意すれば良いことになる。
殺菌
厚生労働省によれば、食中毒防止のための加熱条件として「75°C、1 分」、「70°C、3 分」、「69°C、4 分」、「68°C、5 分」、「67°C、8 分」、「66°C、11 分」、「65°C、15 分」という数字が紹介されている。ただここに書かれている温度帯・時間で加熱した場合、食感が悪くなることが予想される。
あくまで消費者向けの安全の基準であるため、60℃未満でも問題はなさそうだが、当然その分加熱時間を長く設定しなければならない。またお肉自体が新鮮であることが必須条件であって、それに不安がある場合は完全に火を通す方が安全。
食中毒を引き起こす細菌・ウイルス等については厚生労働省のサイトを参照。
豚肉と牛肉:赤いままで食べられるか
これは単純に前から疑問だった問題。何故牛肉は中が赤いまま食べられるのに、豚肉はダメなのか。内閣府の食品安全委員会が製作した資料には「豚肉は中心までよく焼いて食べましょう」の文言も。この問題について考えてみる。
有鉤条虫と無鉤条虫
可能性の1つとして挙げられるのが、寄生虫の有鉤条虫と無鉤条虫。前者は主に豚や猪に、後者は牛を中間宿主とする。中間宿主とは寄生虫が幼少期を過ごす場所のこと。従っておそらく問題になるのが虫卵・嚢虫の方だが、無鉤条虫の場合、虫卵による感染はない。嚢中感染の場合も無症状か、あったとしても腹痛や食欲不振等の軽いものだという。対して有鉤嚢中は重い症状を引き起こし、最悪の場合死に至る。ちなみに、いずれも成虫の危険度は高くない。
内閣府の食品安全委員会によると、60℃を超える温度帯で加熱することによりこれらの寄生虫は死滅するが、同時にミオグロビンの酸化反応が起こることにより褐色に変化する。言い換えれば、有鉤嚢中が死滅したことを示す指標としてお肉の色に注目していると考えられる。また低い温度で一定期間冷凍することでも死滅させられる。
E型肝炎ウイルスや他の細菌類の存在も懸念すべき要因だが、特に豚に注意が求められる理由は不明。何故牛は表面の細菌のみ死滅させれば安全なのか。
脂肪の融解について
それぞれの動物の筋肉に含まれる脂肪は融点が異なる。融点とは脂が油になる温度のことで、牛40℃〜50℃、豚33℃〜46℃、羊44℃〜55℃、鶏30℃〜32℃、馬30℃〜43℃が目安。この違いは主に脂肪を構成する脂肪酸の種類・量の差異によって生まれるものだと推定できる。例えば羊の場合、融点の高い飽和脂肪酸及び一価不飽和脂肪酸の割合が牛や豚のそれより多い。脂肪を美味しく味わうためには油として溶けた状態である必要があり、調理後口に運ばれ、咀嚼されるまでに上記の温度を下回らないよう配慮する必要がある。
参考文献
Cooking for Geeks Second Edition Jeff Potter
おいしさをつくる「熱」の科学 佐藤秀美著
料理の科学① ロバート・ウォルク著
紀文 練り物教室:塩と加熱が不可欠な練りもの
熊本県畜産広場 食肉の知識
東京都福祉保健局 食品衛生の窓
内閣府 食品安全委員会 寄生虫による食中毒にご注意ください
厚生労働省 食品
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
