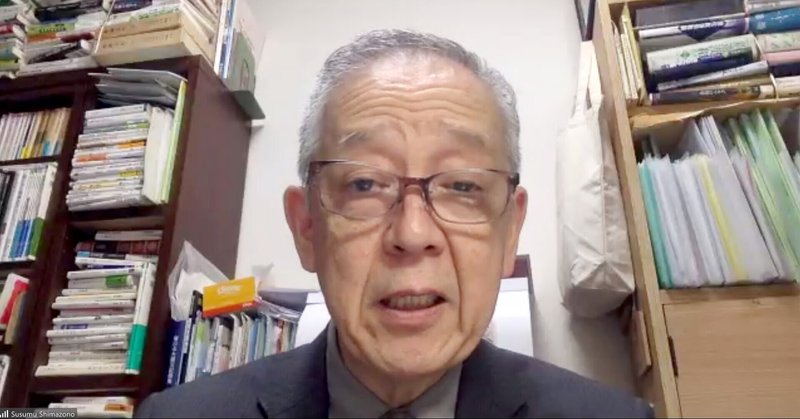
顔の見える支援を 宗援連が設立10周年
※文化時報2021年4月12日号の掲載記事を再構成しました。写真は島薗進宗援連代表。
東日本大震災の被災者支援に取り組む宗教者と研究者らでつくる「宗教者災害支援連絡会」(宗援連、代表・島薗進上智大学教授)が1日、設立10周年を迎え、記念シンポジウム「東日本大震災と宗教者の支援活動の新たな地平」をオンラインで開催した。約70人が参加し、被災者との信頼関係を構築するため「顔の見える支援」を継続することが必要との認識を共有した。
宗援連は震災直後の2011年4月1日に設立され、これまでに情報交換会を34回開催。16年に「『防災と宗教』クレド(行動指針)」を策定し、宗教者が防災を自らの使命とすることを社会に発信した。宗教者による学びと実践、行政や市民団体との協働の場になっている。
シンポジウムでは、全日本仏教会の戸松義晴理事長ら4人が登壇。島薗代表は開会あいさつで「宗教界の横の連携を通じて、さまざまな立場の人が被災者とより良いつながりを持てるよう、この会を続けたい」と述べた。
登壇者4人の主な発言は次の通り。
資金も持続可能に
全日本仏教会理事長 戸松義晴氏
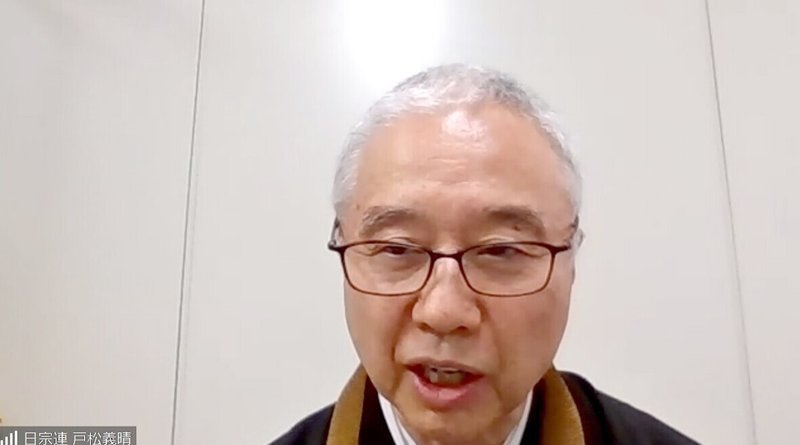
東日本大震災では、亡くなった方々を弔い、苦しむ人々に手を差し伸べたいと思って活動してきた。私たちに何ができるかではなく、何を感じ、被災者と共に何ができるかを学んだ。
発生直後は火葬が間に合わず、棺ひつぎの数が足りないという事態が生じた。東京都内の斎場では、被災自治体の要請で犠牲者の火葬を行い、宗教者は宗教・宗派を超えて回向した。ある場所では当初、宗教者が入れてもらえず、町内会が頼んでやっと弔いができた。一方で普段から地元仏教会が行政と連携していた所は、スムーズに入れた。
文化庁宗務課は今年1月、事務連絡「宗教法人が行う社会貢献活動について(情報提供)」を通じ、防災などの社会貢献活動を宗教活動と見なせるとの見解を示した。これには宗援連の存在が大きかったと思われる。宗教法人は社会に対していっそうの説明責任を果たす必要があるだろう。
今後は、寄り添いと復興に向けた中長期の支援が求められる。募金が減る中、資金面でも持続可能な支援の在り方を考えなければならない。
個人同士で心開く
世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会事務局長 篠原祥哲氏

WCRP日本委員会は「失われたいのち」への追悼と鎮魂、「今を生きるいのち」への連帯、「これからのいのち」への責任を復興方針に掲げて活動してきた。
その中でも、2014~19年に行った「フクシマコミュニティづくり支援プロジェクト」では、182団体の262プロジェクトを支援した。広域避難者のネットワークづくりや高校生のまちづくり会議など、活動はさまざまで、団体の種類を問わず、1団体20万円以下の財政支援で復興を後押しした。
支援金はスタッフが訪問し、直接手渡した。これについては、支援対象団体へのアンケートで、90%が「良かった」と回答した。顔を合わせることで直接、お礼ができたと評価してもらえた。被災者と支援者が、社会的役割でなく、個人と個人で互いに心を開くことが重要だと分かった。
キリスト教にはインマヌエル、仏教には同行二人という言葉がある。神仏と共にいるという意味だ。問題解決型の支援に比べて、寄り添い型の支援はこれまで弱かったが、宗教者にはできる可能性がある。
心のケアで役割を
ノンフィクションライター 千葉望氏

実家は岩手県陸前高田市の真宗大谷派正徳寺。高台にあり、地震発生当日に近隣住民ら約150人が避難してきた。弟の住職一家は約5カ月、避難者らと寝食を共にした。
2013年に本山から「親鸞教室」の会場に選ばれ、12回にわたり教室が開かれた。当初は難しいと言っていた参加者も、熱心に通ううちに理解が深まり、住職は「こういう時期だからこそ、インスタントの法話や派手なイベントではなく、本気の法話が求められている」と感じていた。
震災後、葬儀や法事の在り方は、再建後の住宅事情もあって変化せざるを得なかったが、最近は新型コロナウイルスの感染拡大が拍車を掛けている。人が集まれなくなったことで、伝承すべきことが伝承されないことを危惧している。
震災から10年たったが、長い年月が過ぎたからこそあぶり出されるグリーフ(悲嘆)がある。お寺は、場を用意していつでも話を聞き、口出しせず一歩下がって見守ることが大切だ。檀家・門徒数が減っても、心のケアでお寺が果たせる役割は、まだ大きい。
教会同士の助け合いも
クラッシュジャパン副代表理事・事務局長 山尾研一氏

プロテスタント系の日本福音同盟に所属する教会で牧師を務めており、2005年に米国人宣教師が立ち上げた東京の被災者支援団体「クラッシュジャパン」に所属して活動している。
クラッシュジャパンは、キリスト教徒のボランティアを動員し、被災地域の教会に仕えて、必要な人々に助けと希望をもたらすことを目標にしている。平時は教会の防災ネットワークづくりを促進している。
東日本大震災では、教会同士の壁、教会と地域社会の壁、日本と世界の壁が崩れた。多くの教会が、言葉による伝道だけでなく、行いをもって普段から地域と関わる大切さを認識した。被災地の教会が窓口となり、全世界から支援を受け、人々の思いをつなげる役割を果たした。
そうした中で、がれきになった陶器のかけらでアクセサリーを制作するプロジェクトや、フードバンクなどの支援事業が行われた。
これからは被災者中心、地元主体、協働の3原則を基に、心のケアに当たる聖職者・チャプレンの養成や、教会同士で助け合う「教助」を進めたい。
【サポートのお願い✨】
いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。
私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。
新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。
しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。
無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
サポートをいただければ、より充実した新聞記事をお届けできます。よろしくお願いいたします<m(__)m>
