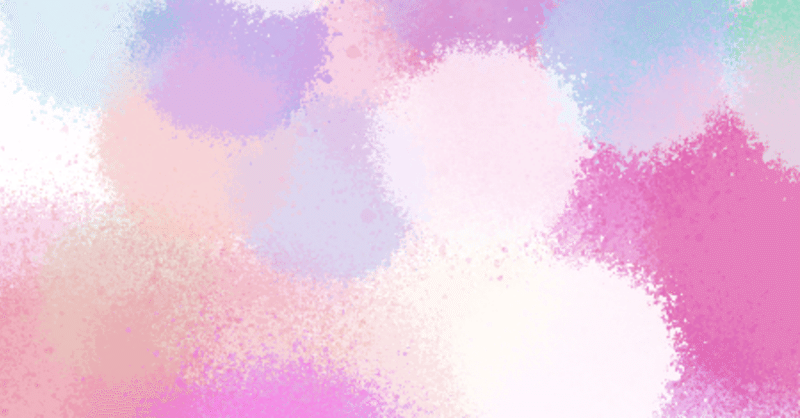
千鶴子さんと。
いつからか音信不通になってしまった千鶴子さんのこと。
作文を書く先輩で、ずいぶんお世話になった。とても、ユニークで興味深いかただった。
*****
年上の友人千鶴子さんに横浜桜木町であったおりのこと。
赤羽駅で人身事故があったとかで、電車のダイヤが乱れていた。また、違う線でも何件か同様のことがあったらしい。
昨日あんなに暖かくて、今日はこんなに寒くて雨模様だから、その気温や気圧の変化に対応できず、そのひとたちの気持ちがうつむいてしまったのかもしれないなあ、なんてずいぶん遅れた電車のなかで勝手な解釈をしていた。
憂鬱な時期よりも憂鬱から脱したときの方が危険なのだと聞いたことがある。いったい今まで何をしていたのかと失われた時間に対する悔恨の思いが湧いたときがあぶないらしい。
死にたいと思ってプラットホームに立つのだろうか。あるいはふっとそんな気持ちになってしまうのだろうか。
答えの出ない自問を投げ出して持参の本を読み始めた。電車内専用の本。「徒然草」。そんなときはなんとなくシンクロする。
「あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからむ。世は定めなきこそいみじけれ」
(口語訳)
「人間がこの世に永住して死ぬことがないならば、人生の深い感動は生まれてくるはずもない。やはり、ひとのいのちははかないほうが断然いい」
つまり、限られた時間であるからより濃密に生きられるということか。
いつだったか、エホバの証人の友人は「永遠の命」という概念を教えてくれた。そのときに感じた違和感のもとはこういうことだったのかもしれない。
「あかず惜しと思わば、千年を過ぐとも、一夜の夢の心地こそせめ」
(訳)「もしもいのちに執着すると、たとえ千年のながい年月を過ごしても、それはたった一夜の夢のようにはかなく感じるだろう」
ああ、そういうものだね。執着とはそういう悲劇だね。
40歳そこそこで死ぬのが無難だと兼好さんは言う。
その歳を過ぎると容貌の衰えを恥じる気持ちがなくなるそうで、子孫を溺愛して長命を望んで世俗の欲望ばっかりが強くなって深い感動の味わいがなくなるんだって。
「ひたすら世をむさぼるこころのみ深く、もののあはれも知らずなりゆくなむ、あさましき」
ああ、これいいたくなる場面、多いなあと思ってしまう。
世を騒がせたあのニュースにもこのニュースにも、あのおやじにもあの若造にも、言ってやりたい気分になる。
この時代の平均寿命がおよそ三十歳らしい。四十になると長寿のお祝いをしたという。
だから平安の貴族の仕事は恋だったのだなあと思う。早く子孫を残さないと死んでしまうものなあ。
でも、その先を考えられないのは幸せか不幸せかわからないなあとも思う。
どうせ三十歳でしんでしまう命なら、わざわざ電車に飛び込むこともないかもしれない。これからさきの時間をどう生きればいいのかわからない、なんて言ってる時間もないんだから。
でも、
「命長ければ辱多し。長くとも、四十に足らぬほどにて死なむこそめやすかるべけれ」
といった兼好おじさまも70歳まで生きていたらしいではありませんか。
ことほどさように思い通りにいかぬのが人の世ではありませぬか。
90歳になるうちのばさまが呪文のようにくり返し言う。
「はよ死んでしもたらええのに、自殺もようせんし」
健康自慢できたひとが自分の長寿を呪うことばを口にする。しあわせな不幸だな。
そんなふうに思いがいのちという言葉のまわりを思いが経巡っているとき、テーブルの向こうで、80歳の千鶴子さんは憧れのドクターの話をしはじめる。
今は恋する千鶴子さんなのだ。食事の前に雑誌に載った爽やかなドクターの顔写真を見せてもらった。なるほど、千鶴子さんが恋するわけだ。
「この雑誌、先生からもらったのよ。もらった日から三日間枕の下にこの雑誌を忍ばせて寝たの」
「まあ、かわいいこと」
「わたし、こんな気持ちはじめて」
ちょっと不思議そうな顔になって千鶴子さんはいう。自分自身にとまどっているのかもしれない。
戦前の教育を背骨にまっすぐ叩きこまれた師範学校卒の千鶴子さんの人生を思う。清く正しく、たゆまぬ努力、勤勉な誰かのための日々。
命に関わる病気をしてから、新しい自分に出会っているのかもしれない。
以前、このドクターの診察してもらう直前、待合室で千鶴子さんは息苦しくなって倒れた。肺に血栓が出来ていたのだった。もしもよそで倒れていたら、今こうして笑うこともできなかっただろう。ドクターは命の恩人でもあったのだ。
そうして、千鶴子さんは恋する老女になった。そのときめきを聴いた。
たくさんのご親切のお礼にとこちらが贈った手作りのキルトをうれしそうに見入って、ちょっと第一関節の曲がった指でいとおしそうに撫で、「ありがとう。うれしいわ」と言った。
久しぶりに会う千鶴子さんの背中はその憧れを抱え込むようにますます丸くなっていた。会うたびに小さく小さくなっていく千鶴子さんがどうにも切なかった。
なにげなくその小さな肩を抱いた。
千鶴子さんはアラッという顔になったが、そのままでいた。
手のひらに感じる体温が命だと思った。恋する生命体だ、と。
読んでくださってありがとうございます😊 また読んでいただければ、幸いです❣️
