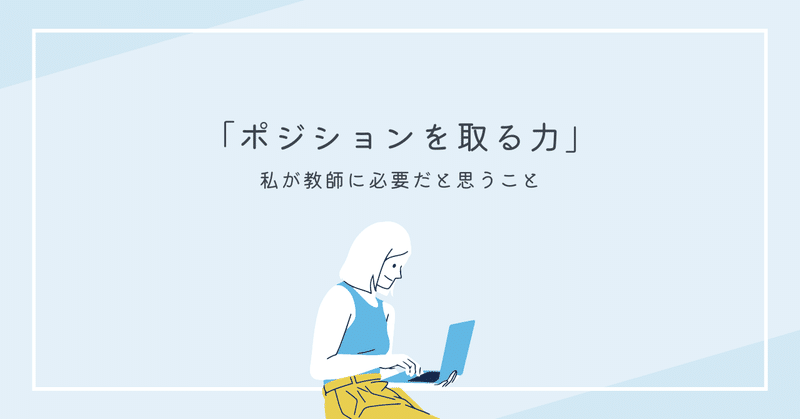
教師にはポジションを取る力も必要
こんにちは。新米教員の咲希です。
私は受容力には自信があります。
相手のありのままを受け入れる力です。
相手がルールを破っていても、誰かを傷つけていても、たとえ死にたいと言っていても、その気持ちを受け入れることができると思います。
大抵のことは「そういう人もいるよね」「きっとこの人も傷ついてきたんだよね」と思って受け入れてきました。
これは自分を守るのに役立ってきたように思います。
相手を拒絶し続けるのは辛いです。
特に仕事仲間や家族の中に嫌いな人がいると毎日がストレスになります。
それならば無理矢理にでも受け入れてしまったほうが良い。
「この人にも事情があるんだ」と思ってしまったほうが楽なのかもしれません。
教員になればこの受容力が活きてくると思っていました。
学校は多様な価値観を持った生徒がいます。
そして、子どもはありのままの自分を他者に受け入れてほしいと思っています。
本当はその役割は親だと思うのですが、親にありのままの自分をすべて受け入れてもらえている子どもはそんなに多くありません。
それなら身近な大人である教員がその役割を持つこともできるんじゃないだろうか。
そう思っていました。
しかし実際はそれ以上にきちんとポジションを取ることの方が教師にとっては大事なのかもしれないと思うようになってきました。
ポジションを取るというのは、「私はこれが良いと思う」「これは正しくないと思う」というのをはっきり相手に伝えることです。
悪く言えば、自分の中にある「正しさ」を相手に押し付けること。
でも、それがきちんとできることが教師にとっては大切だと感じています。
今の私は授業中にスマホを見ている生徒も「それで損をするのはその子自身だから、そのうち分かるよね」と見て見ぬフリをしてしまうことも多いのですが、
本当はきちんと「授業中にスマホを見るのは良くない」または「私はそれが気に入らない」とはっきり伝えるべきなのかもしれないと思います。
生徒にも事情があるかもしれません。
昨日いやなことがあって、気持ちが授業に向かわないのかもしれません。
悪いことをしてしまう人でも必ず何か事情があるのに、それも聞かずに価値観の押し付けをするのは相手を傷つけてしまう。
そう思って注意するのをためらってしまいます。
しかし教師は授業ではクラス全体を見ていないといけないのです。
ひとりひとりの行動をなんでも許してしまうのは、全体が進むべき方向性を見失わせてしまいます。
全体を動かすためには、教師は自分の中にある理想的な状態を生徒に分かりやすく提示しないといけません。
それに合わない行動ははっきりダメだと言わないと、正しくやろうとしている生徒は混乱します。
スマホを注意するかというのは一例で、どんなポジションを取っていくのかは教員ひとりひとりの価値観だと思います。
ただ、なんでも許容して許してしまうのは団体を仕切るのには物足りない。
相手を傷つけたり自分が嫌われたりするのは厭わずに、自分の価値観の軸をブレずに伝え続けていかないといけないと思います。
相手を許容していくのは心理カウンセリングなど、主に相手に発信させる場面には有効です。
生徒と面談する時には自分の受容力は活きてくるでしょう。
場面で使い分けることが必要です。
私は相手や自分を傷つけるのを恐れて相手を受け入れてばかりいました。
そのため自分の教育の軸を見失いかけています。
夏休み期間で少し授業から離れている間に、自分の価値観をしっかり固めていこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
