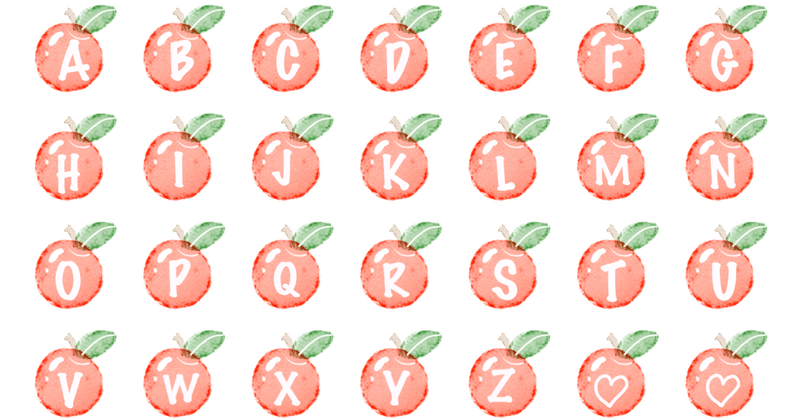
多読多聴を再開したら気持ちがすっと楽になった
こんにちは。またご無沙汰していました。
私立高校で英語を教えている新米講師です。
1学期の中間試験が終わってから、6月は本来休めるはずの週末には毎週のように行事や部活があり、息つく暇もないという感じでした。
ベテランの先生ならいつもの状況なのかもしれませんが、
毎日の授業をこなすだけで精一杯な私は帰ってから自分のために英語を勉強する時間はほとんど取れていませんでした。
そして久しぶりに二連休が取れた今週、私の英語学習の原点とも言える「多読多聴」に立ち返ってみることができました。
というのも私の学校には夏休みに無料の夏期講習があり、講師が自由な内容で講義を開くことができます。
私はそこで「多読多聴実践講座」というのを高校一年生向けに開くことにしました。
多読多聴信者を自称しているものの正直最近は多読に距離を置いてしまっていた自分は、講座を開くために酒井邦秀さんの著書「すべての悩みは量が解決する!英語多読」を改めて読み直してみました。
読み直してみて、多読から離れている間にだいぶ自分は英語に肩肘を張って向き合っていたことに気付かされました。
多読三原則は
・辞書は捨てる
・分からないところは捨てる
・自分に合わないと思ったら投げる
そしてとにかく読書を「楽しむ」ことが何よりも大切なのです。
そして多読では英語を必死に理解しようとしなくて良い。
分からないところは予想すらせずに、見なかったことにして飛ばして良いのです。
しかも酒井さんは「多読多聴は辞書を捨てろ!」とまで言っています。
私はそれをすっかり忘れていました。
私は英語講師だから正確でない英語は許されない、と思い最近は英語の動画を見るときもいちいち動画を止めて辞書を引いていました。
実際そうして「正確な英語」「100%理解している英語」を目指した結果、英語学習は私にとって苦痛なものになり、仕事と両立することができなくなっていました。
基本に立ち返って改めて多読多聴をしてみると、英語学習においては圧倒的に「質より量」だと思います。
そしてリラックスした状態で臨むことが質をも上げてくれるような気がします。
分からない単語が出てきても全く気にする必要はなくて、いつか分かるようになると思っていればよい。
そう思うと英語学習に対する気持ちだけでなく、張り詰め続けていた仕事への気持ちもすっと楽になりました。
学校で生徒に文法を細かく教えている自分ですが、
文型や過去分詞など難しい文法用語は言語学者だけが知っていれば良くて、ただ英語を話せるようになりたいだけの人たちは楽しく多読多聴をしていれば良いのではないかと思います。
夏期講習の多読多聴講座が高校生たちに取ってより良いものになるように、私自身がリラックスして臨めたら良いなと思います。
追伸
やはり本から知識や情報を得るのは良いなと思います。
SNSや動画で要点だけを拾うのは一見効率が良いように思いますが、
根底にある著者の価値観を深く知ってこそ自分のものにできますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
