
切れたメビウス〜神々が降りる島|#短篇小説
このお話は、以下の短篇小説のスピンオフになります。
↓ ↓ ↓
「太田さん・・・」
呼ばれて、太田が透羽子に向けた眼差しは、“慈しみ”に近いものかもしれなかった。
「今年も、この島のことを色々教えてもらって、嬉しいです・・。
また来ます」
(私を)待っていて下さい、とは続けて言えなかった。
自分の心が、島を愛しているのか、それとも太田を愛し始めたのか、まだ判然と輪郭が見えないのだった。

切れたメビウス〜神々の降りる島
これまで幾度も、数ヶ月前にも訪れたその島は、「隠れキリシタンの里」としてよく知られており、村ごと(今は町ごと)にそれぞれ特長ある教会が建っていた。
透羽子は学生時代、長崎に友人と観光して、大浦天主堂で潜伏したキリスト教徒の歴史を学んだ。踏み絵も見た。また微《かす》かに、遠藤周作の本の印象も残っていた。
後で島へ渡って、本物の隠れキリシタンの遺物とも言える多くの教会群に触れた。ルルドを初めて見て、外国みたいだと感慨が一入だった。




この島の教会群は、今は世界遺産に選ばれているけれども、それだけでなく兎に角海が本当に美しい。
山に囲まれた遠浅の渚では、マリンスポーツのレジャースポットがあって、島の唯一の若者の溜まり場になっていた。
透羽子と友人はそこでバナナボートなど、数種類の海のレクリエーションを楽しんだ。中でも、ウインドサーフィンは、ほとんど波の立たない凪の渚でするので、初心者には持って来いだった。
透羽子も友人も、夕方になるまで存分に教えてもらった。
―――何処までも続くエメラルドの海。
青く突き抜けた空。
潮風に吹かれ、帆を動かして一体となってボードに立っているのは、都会にはない至福の時間だった。
それを、優しく穏やかに教えてくれたのが太田だった。透羽子は訊いたことはないが、おそらく30歳前後だろう。
親切な「若い先生」という印象だが、島の若者たちの間にいると、班長みたいな立ち位置で、やはり慕われているように見えた。
年齢的なこともあるのだろう。


透羽子はその島の居心地の良さがすっかり気に入り、ウインドサーフィンをマスターしたいのもあって、毎年夏になるとフェリーでひとり、島へ渡った。
夜、地元からバスに乗って、早朝フェリーに乗り換えると、翌日昼には島に着くのだ。
何年も何年も島を訪れたので、顔見知りが増えた。
「―――透羽子ちゃん、また来たの?」と島の若者に声を掛けられたり、偶々行くのを連絡しなかった年は、マリンスポーツの施設の社長から新鮮な烏賊が自宅に届いて
「―――今年は来ないのか?」
と電話で尋ねてくれたりしたものだ。

「自由な島」を満喫出来るのは勿論だけれど、毎年訪れていくうち、目的が徐々に変化してきたのは否めない。
正直に言うと、目的は美しい島と海から、ウインドサーフィンを教えてくれる太田に会うため、に心が移行してきた。
透羽子はシーズンになって久しぶりにボードに乗る度に、扱い方を忘れて
ほぼ1からのスタートになってしまう。そんな様子を見て、毎年根気よく思い出すまで教えてくれる太田の誠実さに、心が惹かれてきたのだった。
太田はまた、来る度にその島の「良い場所」を透羽子に案内してくれた。
草原の美しい高台や、趣きのある古民家のジブリの資料館、絶景の灯台、また教会巡りに付き合ってくれたり、地元ならではの美味しい店に連れて行ってくれたり・・・。
(・・・これは、ただ「親切」なだけなんだろうか・・)
自分の「想い」に気付いてからというもの、何処か期待する部分が生じていたのだが、自分から太田に問うてみることまではとても勇気が出なかった。

太田への想いが高まってきたある夏の日。
島の若者たちと男女含め10人ぐらいで、バーベキューパーティーのようなことをした。
数人が車で肉や魚、野菜やお酒など買い出しをして、マリンスポーツの施設の前で賑やかに準備をした。
この島の娯楽はほとんど無いので、みんな楽しそうだった。
「―――クーラーボックスに氷入れた?」
「―――お前炭に火、熾すの上手だろ?やれよ」
「あー腹減った」
「肉足りるかな?女性陣、野菜とか準備出来た?」
・・・等々。
「バーベキューのあと花火大会ねー」
手をメガホンのように囲みながら、知らせる男性もいた。
太田は煙草を吸いながら皆が立ち働くのを眺めて、設営しにくそうなときや、重いものを動かすときにすっと入って手伝っていた。年長者の風格があった。
―――
お酒も、バーベキューの肉や野菜なども、大いに身体に入れたあと。
浜辺で民家から離れているのを良いことに、声を大きくしたまま花火をした。
小さめの打ち上げ花火、鉄の細い棒に火薬が巻かれた手持ち花火。男性陣は手持ち花火の火をかざし合ってふざけていた。白やオレンジ、青の炎が綺麗だった。
(楽しそうに酔ってる・・・)
もう目を開けるのもしづらくなっていた透羽子も、やはり楽しく酔っていた・・・

すべての宴が終わり、南の島人らしくざっくりと片付けて、ぞろぞろとマリンスポーツの施設に入ったまでは透羽子もぼんやりと覚えていた。たしか、「雑魚寝しよう」と誰かが言ったのも。
ごたごたと寝る場所を決めるのが始まって、何処でもいい、と投げやりになって、記憶が薄れながら眠った。
―――翌朝。
まだ誰も起きていない様子で、早朝みたいだった。気付いたら、ごく間近で、太田が寝ていた。息遣いや体温まで感じるくらいに。
透羽子は心底驚いた。そして、太田に、自分が起きたことを察して欲しいと思った。何となく、今なら自分の想いを伝えられる気がしたのだ。
覚醒した・・・ような気配がした。
太田は小さく咳払いをした。
然し・・・そのあと、ぎこちない感じで、仰向けになってまた眠ってしまった。
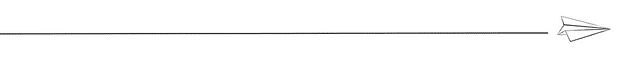
それから間もなくして、透羽子は地元へ戻ることにした。
社長より先に、太田に最初に帰ることを告げた。
「そうか・・・」
いつもの穏やかな調子のまま、太田は答えた。
「帰る前に、島の行きたい場所へ連れて行ってあげるよ。
・・・何処が良い?」
透羽子は太田を見たまま、
「前に連れて行ってもらった、灯台が良いです・・・」と言った。

ロープを張った階段を上って、丘の上に聳え立つ灯台の下に辿り着いた。風が、強かった。
夕陽が沈む大海原の景色は相変わらず神々しくて、透羽子は何か、特別な瞬間に立ち会っている心持ちになった。
(こんな景色が日常的にあるなんて、この島の人はどんな生活だろう・・・)
透羽子は、太田と並んで、黙って夕陽が海に溶けてゆくのを見ていた。海が金色に輝く時間は過ぎていたが、また違う趣き―――幽玄と言っていい、奥深く計り知れない広さと時間を感じた。
「―――太田さん」
暮れゆく海を眺めながら声をかけた透羽子に、太田は目を遣った。
「あのね。この景色を見て思い出したんですけど・・・
こんな言葉、知ってます?」
「・・・・」太田は次を待った。
「―――長き夜の 遠の睡りの みなめざめ
波のりぶねの 音のよきかな―――
何となく、永遠のような景色だと思って。
これね、後ろから読んでも前から読んでも、同じ歌なんですよ?」
(ふたりの仲が永遠であって欲しい)
そんな想いを込めて、透羽子は言った。
見上げるようにして見つめ続ける透羽子の長い話が、どれだけ伝わったか分からないが、太田に心だけは通じたようだった。
「君は・・・」
と言って、太田は俯向いたまま、黙ってしまった。


透羽子は思う。
今なら、彼の気持ちが少し分かる。
雑魚寝のとき隣に寝ていたのは、他の人から離すために、ふたりで端に寝るようにしてくれたのだ。
あちこち島の良いところを案内してくれたのも、やはり意味があったのだろうか。
「君は・・・」
その先は、聞くことが出来なかった。
曖昧なまま、ふたりのメビウスの輪は途切れてしまった。それからもう島へ行かなかったから・・・。
もし、メビウスの輪が繋がっていたら。
今頃透羽子は、ヒールの靴を履くこともなく、夕陽が落ちる海を毎日眺めていたかもしれない―――。
▶Que Song
Missing/野田愛実(COVER)

🌟Iam a little noter.🌟
🤍
🌹おまけ🌹
長崎 五島列島の観光案内。
今年は久し振りに娘と行く予定です!(聞いてない)
↓ ↓ ↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
