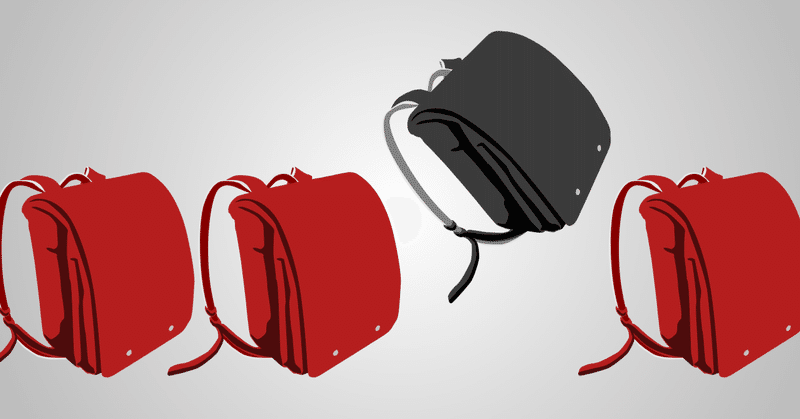
黒いランドセルと“僕”のこと
黒いランドセルで小学校に通った。入学前に買ってもらった新品だった。青みのある色合いも、艶消しの質感も、他のランドセルとは一味違っていて大人びた雰囲気があった。自分のランドセルが大好きだった。
1. 僕のランドセルです
6年生に進級した初日。クラスメイトがみんな席に着いたあと、教壇に立った先生が教室の後方にあるロッカーを見て言った。
「間違えて女子のロッカーにランドセルを仕舞った男子は誰ですか?」
皮肉めいた言い回しが好きな先生だった。このとき、私はたぶん先生と同じ勘違いをしていた。新しい教室とロッカーに不慣れな男子児童が指摘されて間違いに気付き、慌ててロッカーに駆け寄るものだと思い込んでいた。あるべき場所にあるべきものを戻す。そう複雑なことでもない。
それなのに誰も名乗り出なかった。周囲のクラスメイトと同様、私も不思議に思って教室の後方に視線をやった。
壁に沿って大きなロッカーがふたつ。上下左右に仕切り板が渡されているだけで蓋も名札もない、簡単なロッカーだ。左側のロッカーには黒いランドセルが並んでいて、右側のロッカーには赤いランドセルが並んでいる。右側のロッカーにポツンとひとつだけある黒いランドセルは確かに異質で、目を引いた。
私はそこで初めて自分と先生の間違いに気付いて言った。
「あれは僕のランドセルです」
教壇に立っていたのはその年に転任してきた新しい先生だった。黒いランドセルを背負う女子児童がクラスに居ることを、教室で先生だけが知らなかった。
そして当事者の私は自分のランドセルの色が異質だと思わないばかりかすっかり慣れきっていて、自分が「間違えて」いるとは露ほども思わなかった。おまけに当時の私は自分のことを”僕”と呼んでいたので、新しい先生を混乱させる要素に事欠かない存在だった。
このやりとりで思い出されたのは、私にランドセルを買ってくれた日の母の忠告だ。
「これから6年間、ずっと『なんで黒いランドセルなの』って言われ続けるんだよ」
実際、黒いランドセルを背負って6年目になっても新しいクラスメイトからは『なんで黒いランドセルなの』と言われた。言われない年はなかった。母の予言は当たっていた。
2. おとこのこの箱
ランドセルをレジに持って行った時のことを今でも覚えている。私のランドセルは両腕で抱えるほどの大きさの箱に入っていた。売り場には「おとこのこ」と書かれた箱と「おんなのこ」と書かれた箱があり、私が「おんなのこ」の箱を持とうとすると、母は「おとこのこ」と書いてある箱を渡してきた。これであってるよ、と母が言った通り「おとこのこ」の箱には私の黒いランドセルが入っていた。
でもこれは20年も前の話だ。多様性が叫ばれる今のランドセルの流行はどうなっているんだろう。
ランドセルの老舗メーカーが行った人気色アンケートのレポートでは、女の子と男の子で結果が大きく割れている。黒が60%を超える人気の男の子とは違い、女の子は紫・ピンク・水色・茶色がそれぞれ30%〜10%と「人気の色が分散している」のだそう。
肝心の黒いランドセルについては、女の子からの人気は2%ほど。色味が近い紺・青も同じく2%とのことだ。黒いランドセルが一強の男の子の市場よりもカラフルな色味が定番化しているとはいえ、女の子で黒を選ぶことはまだ一般的じゃないのかもしれない。性別よりも年齢の影響が大きいんだろう。
レポートとは別に、女の子が黒いランドセルを選ぶことについてのページ(よくある質問丨女の子でも黒色のランドセルを選んでも大丈夫でしょうか?)があった。親の心配と色についての先入観というものは、子供が好きな色を選んだらいいという新しい時流や販売者の意図とは一定の距離を保ったところに根深く存在しているらしい。
今の流行のランドセルの外箱はどんなのだろう。「おとこのこ」「おんなのこ」はまだ書いてあるんだろうか。20年前にこういった心配を胸の内に秘めた上で忠告とともに「おとこのこ」の箱を持たせてくれた両親を思うとありがたいばかりだ。
3. 成長する一人称
省略しにくい名前だからか、あだなで呼ばれることはない。呼び捨てで呼ばれることが多い。女性なので「ちゃん」付けのこともある。私が希望を伝えたときは「さん」付けで呼ばれる。でも「〇〇ちゃん」と呼ばれても何も思わないので「さん」付けを希望する場面は少ない。
一人称について言うと、きょうだいがいるから自分のことは名前で呼んでいた。自分の呼び方を意識し始めたのは小学生になるあたりだった。女の子の間で自分のことを“ウチ”と呼ぶのが流行り始めたからだ。そこで初めて考えた。一人称にはどんなものがあって、どれが自分にふさわしいのか。
当時の自分の選択肢にあった一人称とその印象を一覧にする。
一人称と印象
わたし 公的
ぼく 私的(公的な場合もある)
あたし 私的
おれ 私的
うち 私的
名前 私的(幼稚)
ところで私は友達と遊ぶときにも襟のあるシャツを着て、たまにはジャケットも羽織る類いの人間だ。シャツのボタンは一番上まで閉めることもある。要するに、普段からフォーマル寄りの振る舞いを好んでいて、カジュアルな振る舞いを避ける傾向がある。
そんな人間が自分なりに子供っぽさからの脱却を図る。“私”は大人っぽすぎて使いにくい。幼稚でなく公的にな印象に近いものがいい。“僕”は当時の私の要望にピッタリだった。そして周囲の友達も半分くらいはちょうど“僕”への切り替えの時期だった。あんまり迷わなかったと思う。
結局、小学生を卒業するまでずっと一人称は“僕”だった。中学生になって周囲の男子と同様に“僕”が恥ずかしくなると、一人称がない期間と自分の名前の期間を反復横とびし始めた。シミュレーションゲームで設定を求められたときは、困り果てた末に性別のない一人称として“先生”を選んだこともある。高校生になって“私”が定着するまではずっと揺らいでいた。
今はフォーマルながら物腰柔らかな雰囲気も出る便利な一人称として“私”を使っている。自分に似合っていると思うし、それが嬉しくもある。私の一人称に成長の過程があるのと同様に、私自身も“私”という一人称に見合うまで成長していた。
4. 無頓着という立場
黒いランドセルで小学校に通った。自分のことを“僕”と呼んでいた。男子の友達とばかり遊んでいた。同期が伸ばした髪を結い上げて袴で着飾る中、襟足を刈り上げてパンツスーツで写真に入った。女性とお付き合いしていた。
ここまで書いてきたのは私が「昔から男の子だった」エピソードじゃない。実際、ここまで書いてこなかった人生の中にはとびきり“女の子っぽい”エピソードも含まれている。私は昔から自分が女性であることを知っていた。ただ私自身がそれと不便なく折り合いをつけることができて、特に気にならなかっただけだ。自分が女性の体を持っていることに対する疑問はなかった。
だからこういう言い方もできる。これまで書いてきたのは、私が「昔から性別に無頓着だった」エピソードだ。だからこそ与えられた選択肢に従うだけでなく、吟味した上で好きな選択肢を採ることができると知った。同時に、従わないことを選ぶなら反発が起きることを覚悟するように教えられた。
これを書きながら「性別に無頓着だというなら大人しく体の性別に収まっていればよいのでは?」「わざわざ性別の話をするのはとりわけ気にしている証左なのに」と思う自分もいる。
そこで、前に読んだ本にあった性別の話を引用する。
出生時に決められた性は私たちの生物学的特徴に基づいているのに対して、ジェンダーは生物学的特徴を超えて「自分が何者なのか」という感覚に基づいている
私も基本的にはこれに似た考えで性別を捉えていると思う。そして私は自分の性別に無頓着なので、生物学的特徴に基づかない前提で「何者か」と問われたとして「女性です」と答えるほど自分の性別に思い入れがない。それどころか「女性です」と答えると、何者かという私個人の在り方を体の形に囚われ過ぎているように感じる。
近頃は選択肢があれば性別の欄に「その他」と記入することがある。ジェンダーを問われる場面ではノンバイナリー(どちらでもない)と答えたり、答えなかったりする。自分が特に気にしていない属性をもとに個人を判断されることに対して戸惑いとためらいがあるからだ。
受け手が性別に対して先入観を持っていた場合に備えて偏見を回避することに抵抗はない。実際、黒いランドセルを背負っている女の子であるというだけで無邪気に質問され続けることは身をもって知っている。私が嫌うとすれば、対象は自分の性別や体の形じゃなく、他人の先入観や偏見に晒されて勝手に個人を判断されることだと言える。
あとがき
つい先日、ずっと記憶に残っていたマンガを読み直した。一条ゆかりの『星降る夜にきかせてよ』に同時収録されている『ハスキーボイスでささやいて』だ。
同作には、いつも”男っぽい”振る舞いをするせいで誰にも女性だと気付かれない設定のキャラクターが登場する。彼女に対して「どうして初めから女だって言わなかったんだよ」と告げた主人公のボーイフレンド(ローリエ)に対して彼女がした返事がこれだった。
そんなことわざわざ言うことじゃないだろ
ローリエだって男だって断らなかったじゃないか
40年以上前の作品というだけあって、主人公が顔を歪めて「ゲイだなんて気持ち悪い!!」と吐き捨てる描写があるので特におすすめはしない。ただ、自分が何者だろうと誰かに何かを説明する義務なんてないんだ、ということを知った作品なので引用した。このセリフに子供のうちに出会えてよかったと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
