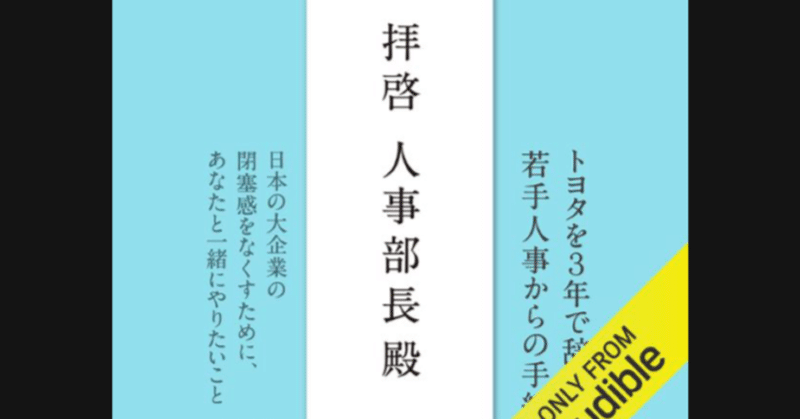
「拝啓 人事部長殿」働きやすい会社とは。
すべての会社員に読んでほしい!と言える、働き方改革の本。この本を出してくれた著者へ感謝の言葉を伝えたい。そして「ありがとう。あなたはとにかく偉いよ」と伝えたい。
期待と情熱に燃え、採用された企業へ入社。しかし、いざ入社してみると想像していたのとは違う、独特の組織風土やヒエラルキー、発言しづらい空気、硬直した思考体系、理解のない上司、配置換え…。「理想と現実は、かけ離れていた」と働きづらさを感じ、モチベーションを削られ、「まぁ、サラリーマンなんてこんなものか」と思考停止に陥りがち。
この本は、トヨタ自動車に入社した著者が働きづらさを感じ、3年で退職した後、当時の上司である人事部長からの問いかけに対して自分なりの答えを出した本です。著者が退職するとき、上司や先輩から投げかけられた問いが3つありました。①「なぜ、会社の平等は重んじられてきたと思うか」②「なぜ、会社の成長は続いてきたか」③「なぜ、会社の変革は難しいか」。この問いへの答えが、この「拝啓 人事部長殿」という本の内容になっています。
著者がトヨタ自動車を退職し、転職した会社はサイボウズというIT企業でした。サイボウズは社員の幸福のため、働きやすい環境のため、多様な働き方、情報共有の仕組み、配置、育成、評価制度など、斬新な取り組みを様々に実践しており、本の途中では、「サイボウズはこんなにも良い会社です」という自慢?とも思えてしまうのですが、ここで著者が偉いと思えるポイントの一つ目がありました。
それは、著者がそもそも人事制度の成り立ちについて、一から調べようと思い、日本の雇用や労働法、労働組合の歴史、欧米のジョブ型雇用と日本のメンバーシップ型雇用(終身雇用)の違いについて調べたことです。
そこから、日本の終身雇用制度や自動昇給というシステムが故のフルコミットが求められる雰囲気や、「上司の命令は絶対」的なヒエラルキーなどが何故生まれてしまうのか、なぜ会社に対して「私、頑張ってまっせー!」という姿勢をせっせと見せ続けないといけないのか?なぜ、会社から常に成長を求められるのか?という背景が見えてきます。私としては、このことについて言語化してもらえただけでも、この本に感謝したいと思いました。スッと腑に落ちた感がありました。
今まで納得いかずイライラしたり、疑問に思ったことがあっても、自分で雇用の歴史や終身雇用制度について調べるには至らなかった。だから、私はこの著者の情熱、探求心に感謝したい。「代わりに調べてくれて、そしてこうして本にまでしてくれて有難うございます」と。
そして、ここから著者がさらに偉いと思えるポイントがあります。社員が幸せに働けるために、大手企業がどんな働き方改革の取り組みをしているのか、それぞれの企業の人事担当者へヒアリングに行くことです。
ヒアリングしに行った企業は、富士通、タニタ、ANA、ユニリーバ、ヤフー、みずほ銀行、ソニー、NTT、味の素、コンカー、ソフトバンク、良品計画の11社。
これは、本当に偉いし、ここで書かれているヒアリングの内容は本当に貴重だと思いました。やはり、それぞれの企業が昨今の世相に合わせて、社員の働き方の多様性について考え、様々な取り組みを行っていることが分かります。
大まかに例を出すと。
・富士通の「職種約束コース」新卒でも自分で職種、配属先を選べる。
・タニタの「日本活性化プロジェクト」従業員が個人事業主として契約し、働き方や副業などを自由に決められる。
・ANAの「グループ外出向」
・ユニリーバ・ジャパンの「WAA(Work from Anywhere and Anytime)」
・ヤフーの「時間と場所に捉われない働き方」
・みずほ銀行の「週休3日・4日制」
・ソニーグループの「社内募集」「キャリアプラス」「FA制度」「キャリア登録制度」可能な限り本人自らの意思でキャリアを形成しやすい仕組み。
・NTTデータの「Advanced Professional制度」「Technical Grade制度」自動昇給ではなく、職務、ポストをもとに市場価値で評価する。専門性の高いスペシャリストに適切な処遇を与える。
・味の素の「味の素流健康経営」
・コンカーの「オールハンズミーティング」と「フィードバックする文化」社内コミュニケーション。
・ソフトバンクの「ソフトバンクユニバーシティ」自ら手を挙げた人同士が学びあう。
・良品計画の「バックパス制度」「カムバック採用」退職しても、また戻ってこられる。退職時に再雇用を約束。
最終的に著者が人事部長や先輩たちに対して出した答えとしては、「一人では何も変えられないではなく、一人だから何も変えられない」「様々な雇用の歴史や企業の歴史があって、人事は社員が幸せに働けるように少しずつ改善を試みている。だから、みんなで話し合い、協力し合って少しずつ改善していこう」という話しだったように思います。
(これは私の意見ですが)昨今、話し合われている働き方改革とは、欧米のジョブ型雇用と日本のメンバーシップ雇用の比率、バランスをどのように取っていくか?という問題のように感じました。働く時間や週何日働くのか、どこで働くのか等、ジョブ型の個人事業主的な面と、メンバーシップ型の組織に従属する面のバランスを、社員それぞれが働きやすいように決めるということなのではないかと思います。
また、なんだかんだ職場にはややこしい問題(人間関係とか)があるとは思いますが、「働き方」というキーワードで、上司や会社がここまで耳を傾けてくれる現在の世相・風潮は、どちらかというと、これまでの歴史からみると恵まれている方なのかもしれないと思いました。
「サラリーマンなんて、そんなものだよ」と腐ったり、会社を辞める前に一度読んでみる価値のある本だと思います。辞めた会社の上司や先輩に、こんな厚い本を書けるくらい調べて、内容をまとめて、出版してしまう著者の情熱に感謝したいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
