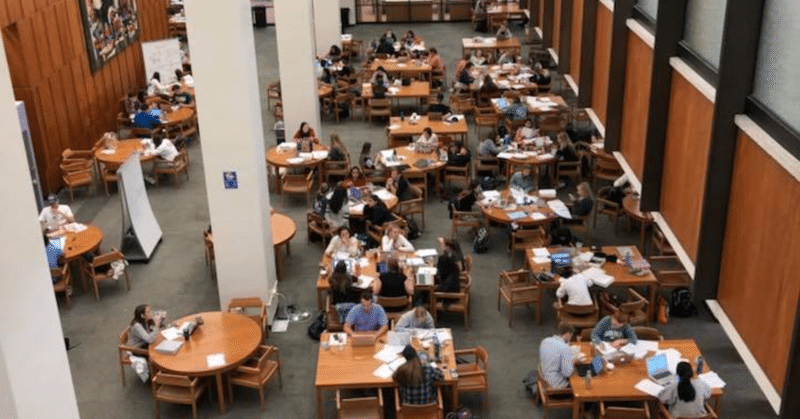
自分史(2001~2003)音楽専門学校時代の話し②
音楽学校は2年制で、それぞれの楽器の授業(ドラムⅠ、ドラムⅡ)や音楽理論のカリキュラムがあり、個別に選択する仕組みをとっていた。そのため、朝から夕方まで学校にいるというよりは、選択している授業がある時間だけ学校に行けばよかった。
そのうえ、私は愚かにも「俺はドラムだけで生きていく。つまらない音楽理論のクラスなど必要ない!」と考え、ドラム以外の授業にはほとんど出なかった。
今考えれば音楽理論や作曲の方が大事なくらいです。
その頃の私は、ドラムのテクニックを磨くことしか頭になかったのでしょう。もったいない。新聞配達をしていれば学校のお金を心配する必要はなかったので、授業料のことなどまるで考えていませんでした。
その代わり、学校のなかのスタジオは、授業がなければ練習に使って良いことになっていたため、ほとんど毎日学校に行ってドラムの練習をしていました。これは本当に良かった。スタジオ代が浮きました。
なので、当時の生活としては
3:00 起床。新聞の朝刊を配る。
6:30 配達から戻り、一度仮眠をとる。
9:30 再び起きて学校へ行く。
10:00 学校で練習するか授業に出る。
14:30 夕刊の配達。
17:00 配達から戻り、授業orバンド練習。
22:00 寝る。
3:00 起床。
という生活のループでした。
「ドラムⅠ」のクラスは、ドラムの基礎的な技術を身につけるクラスで、ベテランのスタジオミュージシャンが講師をしていました。
「ドラムⅡ」は、世間的に有名なドラマーが講師をしていて、授業の内容はそれぞれの講師に任せられていました。
生徒としては「憧れのドラマーがドラムを教えてくれる!」ということで、
学校側としては「ドラムⅡ」の講師が一番の宣伝材料、生徒を呼び込むための広告塔的な存在でした。
私が受講したドラムⅡのクラスは、日本の「フュージョン」というジャンルで有名なドラマーでした。当時の私はとにかくテクニック志向だったので、フュージョンもよく聴いていましたし、当時のドラムマガジンの内容もフュージョン寄りのものが多かったと記憶しています。そういう時代だったのかもしれません。
そして、その先生の授業内容といえば。
「今日なにやりたい~?」でした(笑)
これは、、、
まぁ、先生が悪いというよりは、オープンな授業スタイルというか、
今思えば、教えられる側にもテクニックや才能があれば、先生と生徒の化学反応が起こり、レベルの高い授業が展開されていたのかもしれません。
しかし、現実ではそんなことは巻き起こらず、とくに才能もなく、いろいろ教えてほしいという18歳からすれば、自分より10歳くらい年上の社会人生徒が
「先生こんなこと教えてください!」とゴマをすり(偏見)。
先生が
「あぁ、それはねぇ、こうやるんだよ(ニヤリ)」と答えて、演奏する。
生徒が
「うわぁ、先生、やっぱ凄いですね!」
と言ってるだけの授業のように感じた(-_-;)
今思えば、ついていけていなかった私が悪いのか。
こっちが悪いのか。教え方が悪いのか。分かりませんが、そういう型にはまらない授業形態でした。
ということで、「私にはこの先生の授業は合わない」と思い、その授業は半年も経たずに卒業し、別のスタジオミュージシャンの先生につくことになりました。
そして、入学から半年後。
「アンサンブル」という授業が始まるのですが、
その話しはまた次回③へ続く。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
