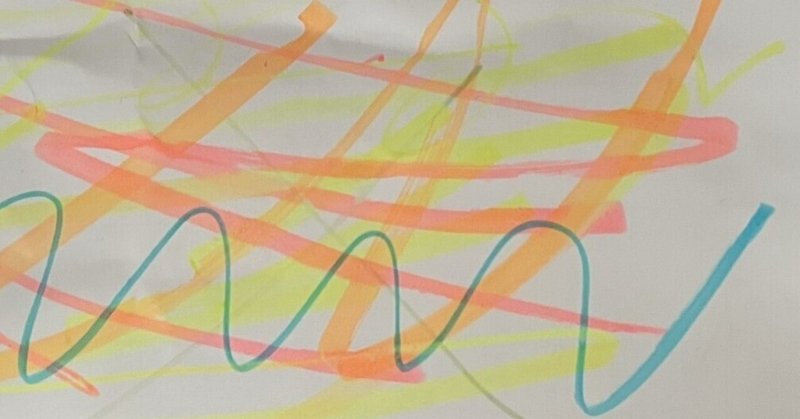
美山さんのまずいコーヒー
桐山みつ子は七時五十分に職場についた。いつもより十分以上早い。照明は始業時間になるまでつけることはできないから、職場は薄暗かった。気を付けて歩かないと、誰かが足元に置きっぱなしにした商品サンプルやごみ箱を蹴飛ばしそうになる。慎重に歩いて窓際に近い自席に辿り着くと、カバンを置いてほっと一息ついた。通りを挟んだ向かいのビルの窓にも、人影が見えた。あちらはしっかり、明かりがついていた。
四日ぶりの出勤だった。鼠色のスチール机には休みのあいだ自分あてに残された薄黄色のメモ付箋がいくつも貼ってあった。みつ子はそれよりも先に、袖机のうえの白い箱を確認した。親が送ってきた羊羹が入っていた、細長い箱だ。
箱のなかには、蛍光ペンが行儀よく積み重なっている。イエロー、ピンク、グリーン、ブルー、オレンジ。十本と少しあって、イエローがやや多めで半分ぐらい、オレンジとピンクが二本、それからブルーとグリーンが一本ずつ。悪くないバランスだ、とみつ子は満足した。
備品の蛍光ペンは使い捨てではなく、インクを補充して再利用するタイプのものが使われていた。時間外の消灯と同じく、備品に関しても経費節減と環境への配慮が会社の方針となっていたのだ。
インクが足りなくなったら、ペンの先を取り外して、スポイトに入ったインクをスポンジの軸に染み込ませる。しかしこの作業には少しコツが必要で、だいたいの社員はペンからインクをこぼし、指や机に鮮明な染みを残してしまう。
みつ子はインクの補充が得意だった。誰彼に頼まれているうちに、いつのまにか、インクの補充がみつ子の仕事に加わった。鮮やかなはずのラインががかすれ始めると、職員はみつ子の袖机に置いてある白い箱に蛍光ペンを入れ、別の棚から補充済みの蛍光ペンを持ち出す。みつ子はペンの先を外してインクを満タンにし、棚に戻す。課の庶務担当が定期的に購入する補充用インクはすべて、みつ子の袖机の引出しにしまわれていた。
みつ子は、自分が休んでいた四日間のあいだにインク補充を待つ蛍光ペンがほどよい量溜まっていたことに満足した。まだ薄暗いのでいつもの賑やかな色彩はないけれど、小さな箱に収まっている蛍光ペンを見ていると、お腹をすかせ眠ってしまった雛鳥が待つ巣に帰ってきたみたいな気がした。久しぶりの出勤で少し重かった気持ちもだいぶ、軽くなった。
一人、二人と出勤する者が現れ、呟きのような挨拶を、誰に向けるともなく口にし、静かに自席についた。みつ子のいる営業支援課第二係には五人の職員がいる。右隣は清田係長、左隣は加藤、正面は佐伯、左斜め前は美山さん。第二係の「島」は、十分もするといつもの顔ぶれで埋まった。始業のチャイムが鳴ると同時に、課長の藤島が柱の陰にあるスイッチをぱちぱちと押した。起き抜けの蛍光灯がためらうように点滅し、ネズミ色のスチール机や書類棚を照らした。
連休中に溜まった仕事を片付けるまえに一本だけ、蛍光ペンの腹を満たしてやることにした。
やり方は簡単だ。ペンの先をゆっくりあけ、そっとインクを染み込ませる。スポイトを摘む指先には、ほとんど力を入れない。そっと押し当てるだけで、鮮やかな色のインクは軸のなかのスポンジに吸い込まれていく。大切なのは待つことだ。そして蛍光ペンの声を聴いてやることだ。ムリヤリ押し込んだら、雛鳥がエサを吐き出してしまうのは当たり前だ。決して焦ってはいけない。静かに待っていれば、蛍光色の液体は勝手にスポンジに吸い込まれていくのだ。どうしてこんな簡単なことが、誰もできないのだろう。何人かにコツを教えたこともあるが、だいたいみんな、手や机をインクで汚してしまう。しかしみんながうまくできないことは、みつ子にとっては好都合だった。いじらしい、お腹を空かせた可愛い雛鳥たちを独占できるのは、このうえない特権的な贅沢だった。
イエローの蛍光ペンを一本、満腹にしてやった。気持ちがすっと落ち着く感じがした。もう一本だけ、インクを補充してやろうと思った。ほかの雛たちがいっせいに、ぴいぴいと可愛らしい声で賑やかに鳴き始めた。みつ子は微笑んだ。実家には大きな庭があって、母親が趣味のガーデニングをしている。庭木の小さな実を狙って、小鳥が集まっていた。シジュウカラやツグミの鳴き声を、懐かしく思い出していた。するとそのときとつぜん、黒い丸が割り込んできた。
美山さんのコーヒーだった。白い紙コップに入ったコーヒーは、鼠色の袖机にぽっかり空いた穴のようにも見えた。
美山さんは毎朝、同じ係の職員たちに自分で淹れたコーヒーを振る舞う。きっちり五人分。しかしみつ子は美山さんのコーヒーが苦手だった。苦みと酸っぱさがアンバランスで、えぐみが強く、口のなかでケンカをする感じがするのだ。
美山さんは自宅から注ぎ口の細くなった専用のポットとドリッパーを持ってきている。コーヒーも、自宅近くの自家焙煎の店で仕入れているらしい。季節ごとにブレンドした限定のコーヒー豆だそうだ。しかしいちども、美山さんのコーヒーを美味しいと思ったことはない。心が浮きたつ穏やかな春の日でも、うだるような暑さの夏の日でも、空が澄み切った爽やかな秋の日でも、頬を切るような寒風が吹く冬の日でも、忙しい日でも、暇な日でも、美山さんのコーヒーは常に不味い。
コーヒーは嫌いではない。むしろ好きだ。家でもたまにドリップコーヒーを淹れているし、休みの日、深い緑色の観葉植物が飾ってある、薄暗い静かな喫茶店でサイフォンで淹れた苦みの強いコーヒーを飲みながら好きな小説を読んでいると、けっして大袈裟ではなく、生きているという感じが込み上げてきてたまらなく幸せな気分になる。しかし美山さんのコーヒーはひとくち口に含んだだけで心がざわつき、苛立ちさえする。理由はわからない。コーヒー豆が古く、保存状態が悪いのかもしれないし、給湯室の水のカルキ、あるいはドリッパーやポットを洗っていないのかもしれない。しかし美山さんのコーヒーが不味い原因を突き止めるために、じっくり味わう気には到底なれない。
みつ子はいつも、砂糖とミルクをたっぷり入れてなんとかまずいコーヒーを飲み干す。コーヒーが不味いからいらないとは、もちろん言えない。そんなことをすれば美山さんを深く傷つけることになる。定年退職後再雇用されみつ子の職場に来た美山さんは、ちょっとだけ思い出話に夢中になってしまうこと、勤務時間中もふらふらと職場を離れてしばらく帰ってこなくなること、パソコンの操作が苦手なことを除けば、あの年代の男性に特有の偉ぶった態度や、嫌味な口調はぜんぜんなく、ほとんど雑用みたいな仕事を与えられても不満など言わずにこにこしながらこなすし、おおむね、好人物と言えるのだ。
同僚たちはというと、別に文句も言わず、ブラックのままでコーヒーを飲んでいる。係長の清田にいたっては、いつもお代わりをもらったりしている。みつ子はそれが不思議でならない。自分の味覚がおかしいのかもしれない、と思う。
みつ子は、鮮やかな色彩の横に置かれた黒い液体を、ぼんやりと見ていた。そして慌てて、ごちそうさまです、と美山さんに言った。もう何百回も、ごちそうさまです、と言っている。美山さんは血色のいい、つやつやした頬を膨らませて笑う。その笑顔を見ると、いつも申し訳なくなる。タバコの臭いがした。
美山さんの不味いコーヒーについて、同僚の誰かと話をしたことはない。そもそもみつ子は、同僚とは仕事以外の話をほとんどしない。
隣の席の加藤は四十代半ばの男性だ。子どもが一人いると聞いたことがある。総務部や資材調達部を経て、営業部営業支援課に異動してきたのは一昨年だ。小柄で体も細く、いつもファイルや書類のなかに埋れている感じがする。仕事は問題なくこなすが、不愛想だし、残業を嫌がるので、営業課の職員からの評判はあまりよくない。急な仕事はたいていみつ子に回ってくる。
加藤は社会人オーケストラに所属している。みつ子が就活をしているとき、学生向けのパンフレットに、ワーク・ライフ・バランスを実現している社員として紹介されていた。なんという名前か思い出せないが、丸っこい金色の楽器を抱えてすました顔をしている姿が、なぜか印象に残っていた。同じ職場になったときは驚いた。いちどだけ演奏会に誘われたことがあるが、会場が遠かったこともあったし、ほかに用事があると言って断った。それっきり、誘われたことはない。
正面の佐伯は去年入社してきた女性の新入社員だ。広報部か国際営業部を希望していたが営業支援課に配属され、初日から不満を言っていた。ちょうど一年前、梅雨に入る少し前に鬱病を発症して一か月休んだ。それからずっと、仕事の割り当ては少な目で、急な休みも多い。
愛嬌もあって華やかな印象のある佐伯は配属当初から目立つ存在で、毎晩のように、若い男性職員を引き連れて食事に行っていた。みつ子は、どこか危うさもあるような気がした。いつも寂しさを感じていて、誰かの気をひいていなければ気が済まないタイプだ。休みに入ったときは、やっぱりな、と思った。
佐伯は女性職員たちとはあまり折り合いがよくない。ロッカールームでは佐伯の悪口をたまに聞く。佐伯が上司や男性職員と話すときの、媚びたような表情や口調を器用に真似する先輩職員がいて、ロッカールームは笑いに包まれる。みつ子は自分が悪口を言われているようで、嫌な気分になる。佐伯のようなタイプが一部の女性からあまり好かれないことは経験上知ってる。みつ子自身はというと、もちろん佐伯のことを嫌ってはいない。そもそも、人を嫌いになることがあまりない。人を嫌うことは、とても体力を使うのだ。人の悪口を言うのも、聞くのも、とても疲れる。
そして美山さんだ。美山さんは営業部営業課に長くいて、定年退職後に営業支援部で再雇用された。三年前だ。三年間ずっと、毎朝、不味いコーヒーを同僚に振る舞っている。
美山さんの仕事は、書類整理や簡単な端末の入力作業など、みつ子たちの補助的な作業だ。再雇用は長年勤めあげたご褒美のようなもので、中学生でもできるような、簡単な仕事ばかりだった。それでも美山さんは皺のないスーツをきちんと着て、薄くなった白い頭髪を丁寧に撫ぜつけ、毎朝八時十五分きっかりに職場に来る。つやつやした丸い顔の真ん中に小さな眼鏡をかけて、少し猫背になって、ディスプレイを覗き込んだり、書類をファイリングしたりしている。役員の一人が美山さんの同期入社で仲が良いらしく、たまに美山さんの席に来て雑談をしている。雑談はときどき、一時間以上になる。二人でどこかに出て行き、数時間帰ってこないこともある。美山さんがいないところでそれほど業務に支障が出るわけではないから、誰も文句を言わない。
美山さんは佐伯の話相手でもあった。佐伯は美山さんがわかるかわからないかなどお構いなしに、韓国ドラマやコスメの話をしている。美山さんはにこにこ、笑みを絶やさずにいちいち頷きながら佐伯の話を聞いている。まるで孫と祖父のような関係だ、とみつ子は思う。しかし佐伯が去年急に休暇に入ったあと、わりあい早く職場に戻って来られたのも、美山さんのお陰なのはまちがいない。加藤はもともと不愛想だし、みつ子自身は佐伯とうまく話す方法がよくわからなかった。
佐伯が仕事でわからないことがあると、美山さん経由でみつ子に質問がくる。佐伯は自分のことを苦手に思っているのかもしれない。それか、昨年配属されるなり長期の病気休暇を取ったことを後ろめたく思っているのかもしれない。どっちでもかまわない。みつ子は端的に、仕事のポイントを美山さんに伝える。自分が代わりにやることもある。
みつ子が勤めているのは中堅の印刷会社だった。本の印刷はもちろんやっているが、どちらかというと食料品のパッケージや家電製品、雑貨の装飾印刷が主力商品だった。職場には、カップ麺の袋とか清涼飲料水のパッケージ、家電製品のプラスティック部品などがあちこちに散らばっていた。
美山さんが現役だったころは紙の印刷がメインで、本、雑誌、カタログ、美術書から折込チラシまで、手広く手掛けていた。美山さんは当時のことをなんども、懐かしそうに話す。あるアイドルがヌード写真集を発売することになったとき、ワイドショーや週刊誌の記者たちが印刷工場の入り口に待ち構えていた。写真集の発売は直前まで秘密にされていたが噂は広まっていて、マスコミはその真偽を確かめようと色々なところに網を張り巡らせていたのだ。アイドルの自宅、事務所、出版社、それから、印刷工場もそのひとつだった。美山さん自身、その写真集の印刷を担当するチームの一人だった。会社のまえで記者にしつこく付きまとわれたことが何度もある。まるで僕がアイドルみたいだったよ、と美山さんは笑う。これは美山さんの定番ネタで、もう何度聞かされたかわからない。しかしそんな話も、みつ子たち若い社員にとっては分厚い社史に載ったいちエピソードに過ぎなかった。紙の印刷を扱っている営業一課は、いまではたった四人の小所帯だった。
みつ子がいる営業支援課の主な仕事は、同じ営業部の営業課が受注した商品に関する細々した書類、製造部への指示や顧客への輸送便の手配などだった。営業課に頼まれて他社の調査をすることもある。要するに、営業課の職員たちが煩雑な事務に煩わされることなく営業活動に専念するための、雑用係だった。
みつ子は入社してから七年、ずっと営業支援課にいる。今年で八年目だ。仕事は地味だが、嫌いではない。みつ子は大学を卒業するまで、四国の片田舎にある実家でのんびり過ごしていた。ロクにアルバイトもしたことがなかったから、どんな仕事が自分に向いているか、よくわからなかった。入社時は佐伯と同じように、華やかな営業部や広報部、企画マーケティング部に憧れもした。しかし、営業支援の仕事はどうやら自分に向いているようだった。ふつうにやっていても、ほとんどミスなく、平均的な職員の三割増し程度のスピードで、正確にこなすことができている。そう気付いたときは自分でも驚きだった。営業部や製造部の人たちからも、頼りにされているのは自覚している。ある営業職員が営業成績トップになって表彰されたとき、どんな仕事でも素早く正確に処理してくれた支援課の桐山さんのおかげだ、と言ってくれたことがあって、そのときは嬉しくて涙が止まらなかった。
佐伯は休みがちだし、加藤はオーケストラの練習が忙しいので残業はしない。みつ子の仕事は少なく見積もっても加藤の三割増し、佐伯の七割増しだった。清田係長も小さな子どものお迎えがあるから、ほとんど定時で帰宅する。暗い職場に一人で残っていることがよくある。三係は桐山さんでもっているな、と課長に言われた。それは嬉しかった。しかし、仲のいい同期に、いいように使われてるだけじゃない、もっとわがまま言っていいよ、と言われたこともある。思い切って四日間の休みを取ったのも、友人の言葉が心に引っかかっていたからだった。
しかしべつに、自分の負担が他の社員より多いことについて、不満はなかった。自分がやった方が速く、正確にできるのだから。二人が中途半端に手をつけた仕事の後始末をさせられる方がよほど大変だった。それに、山積みになった仕事を目のまえに並べ、どうすれば最も効率的かつ正確に処理することができるか考え、戦略を練るのは楽しかった。スマホのパズルゲームをやる感覚に近かった。似たような色のブロックを繋げて消していくゲームだ。営業部の職員から、悪いけど急ぎで、と言われると、ぱっと心に火がついて、闘争心が芽生えるのがわかる。そして、計画通りに書類を処理済みの棚に投げ込んだときは爽快な気分だった。
美山さんは午前と午後にそれぞれ一、二回外に出て、二十分ぐらい帰ってこない。帰ってきたときはタバコの臭いをぷんぷんさせている。営業支援課には美山さん以外に喫煙者がいないので、帰ってくると職場の周辺にタバコの臭いがこもる気がする。露骨に顔を顰める職員もいる。会社が入っているオフィスビルにはもちろん、周囲にも喫煙所はない。歩いて二、三分のところにある古い喫茶店が、美山さんの喫煙場所だった。みつ子もいちどだけ、先輩に連れられて入ったことがある。喫茶店とはいえ、昼どきにはナポリタンやトンカツ定食を出しているからか、油っぽく、それから、タバコ臭かった。
ひょっとしてあの不味いコーヒーは、喫煙者の味覚に合うように調整されているのではないか、と思った。しかし加藤も佐伯も、清田係長もタバコは吸わない。しかし三人とも、なんともない顔をして美山さんのまずいコーヒーを飲んでいる。おかしいのは自分の味覚なのかもしれない。ときどきみつ子は、美山さんがタバコ休憩に出かけているあいだに、こっそりコーヒーを給湯室の流しに捨てる。
昼休みになると、執務室の照明が八割消される。経費削減、それから資源を節約して持続可能な世界を目指すことがみつ子の会社に与えられた重要なミッションなのだ。持続可能な世界、と言われると、さいきんのみつ子は暗い気持ちになる。自分には将来を託す子どもがいないし、これからもずっと一人かもしれない。
白い箱のなかの蛍光ペンは溜まったままだった。先ほどまで公園で遊ぶ子どもたちのように賑やかだった蛍光ペンたちもすっかり元気をなくして、眠っているようだった。
みつ子は薄暗い自席で、家から持ってきた弁当を食べる。ずっとそうだった。入社したての頃は同僚に誘われて外食していたのだが、一人暮らしだったし、積み重なるとバカにならない出費になるので、弁当を持ってくることにした。だんだん、弁当を作るのが楽しくなってきた。最初はご飯と冷凍食品で済ませていたが、まえの夜のうちに、タマゴ焼きやら、ミニハンバーグ、ポテトサラダ、唐揚げなどを作るようになっていた。弁当箱の蓋を開けたとき、賑やかな色彩がぱっと目に飛び込んでくるのが楽しかった。
今日は旅行中に港の市場で買ったマグロの角煮がメインで、副菜はニンジンと里芋の煮物、ホウレン草のお浸しだった。色彩的には地味だったが、角煮の味を引き立てるためには多少の妥協も必要だった。晩酌のおつまみみたいだな、と思って、一人で笑った。
旨いおつまみのことを、酒泥棒というらしい。旅行先で入った居酒屋の主人が言っていた。旨すぎて酒が進みすぎるということだ。
「シマノは給料泥棒だな」
カウンターで飲んでいた常連の男が口を挟んできた。シマノというのはみつ子の二つ隣で一人で飲んでいた、保険会社の社員だった。東京出身で、地方支店で単身赴任しているという妻子持ちの男と、みつ子は少し、話をした。
旅行は楽しかった。一人で気楽だった。旅行に行くのは久しぶりだった。いままで長期休みは必ず、飛行機や新幹線で実家に帰っていた。それが旅行と言えば旅行だった。しかし最近は、地元に残った友人たちが結婚して子どもができ、あまり会う時間が取れなくなったのと、口にこそ出さないものの、両親がみつ子の結婚のことを気にしていることが伝わってきて、なんとなく、実家から足が遠のいていた。
どこかに一人で出かけたいとは思っていた。でもそういう気分が高まるのはたいてい仕事が忙しいときで、山場が過ぎれば、なんだか面倒くさくなってしまう。登山やソロキャンプがしたいと思って、色々調べたこともある。それも真冬だった。春が来れば山に登ろう、と思っていた。でもけっきょく、春が来ると面倒くさくなってしまうのだった。
仕事はかなり念入りに計画を立ててやるが、プライベートはなんの予定も立てないほうが好きだった。朝起きたときの気分と相談して、散歩ついでに美味しいパンを買って公園で食べたり、喫茶店で本を読んだり、あるいは、一日家にこもって映画やドラマを見たり、行き当たりばったりでその日の行動を決める。そういう方が、自分に合っている。
今回は半年前に宿の予約と休暇を入れた。面倒くさくなっても行かざるをえないところまで、自分を追い込んでみたのだ。結果、行って良かったと思う。五月の連休のあとで人も少なかったし、少し肌寒いくらいの気候も、レンタカーで走り回ったり、美味しい店を探してあちこち歩き回ったりするにはちょうどよかった。これからは旅行を趣味にしよう、と思った。六月になればボーナスも出るから、新しい服を買って、ちょっとした登山をしてみるのもいいかもしれない。昼休み中はスマートフォンで、次の旅行先を探していた。
昼休みの終わりごろ、総務課の山崎さやかのところに行った。山崎は同期入社で、たまに食事に行ったりする。会社にいいように使われているんじゃない、とみつ子に言ったのも山崎だった。山崎にお土産を渡し、旅行の思い出話をした。一人でレンタカーを乗り回していたことを、山崎は、凄い、と言った。山崎は免許を一応持っているが、一人で運転なんてとてもできない、と言った。そういえばシマノも、車好きな女性は珍しい、と言っていたのを思い出した。べつに車そのものが好きなわけではなかった。レンタルした車の名前すら、ぱっと思い出せなかったぐらいなのだ。ただ、運転は好きだった。好きな音楽を流しながら、景色がどんどん目の前を流れていくのを見ているのは、世界が自分のためだけに作ってくれた空間を切り裂いていくような気分だった。
みつ子の実家には車が三台あった。そのうちの一台、白い軽自動車は姉の名義だったが、姉はほとんど恋人の家にいたから、みつ子が自由に使っていた。それで大学にも通っていたし、買い物や、ちょっとした旅行にも行っていた。車を運転するのは、ほとんど自転車に乗るような感覚だった。もちろんいままで、無事故無違反だ。
しかし今回の旅行では一度だけ、危ない場面があった。交差点を右折しようとしたとき、凄いスピードで飛び出してきた高校生の自転車とぶつかりそうになったのだ。自転車には全然気づいていなかったが、勝手に足がブレーキを踏んでいた。車は急停車し、頭ががくんと前に折れ、シートベルトが胸に食い込んだ。最初はなにかにぶつかったのかと思った。血の気が引いた。自転車はなにもなかったように、みつ子の車を避けて走り去っていった。
道をひとつ間違え戻ろうとしているときで、そちらに気を取られていた。しかしたぶん、視界の端で猛スピードの自転車が近付いていることを、無意識が認識していた。それで勝手に筋肉に指令を出し、ブレーキを踏んだのだった。目のまえに飛んできた虫を手で払うのと同じだ。しかし今でも、思い出すと冷や汗がでる。ときどき夢に出てくることさえあるのだ。そのことは山崎には話さなかった。
旅行のあいだに溜まった仕事は思ったよりも多くて、蛍光ペンの相手をする暇はなかなかなかった。
仕事が多いのはたしかだったし、いままでも、これぐらいの仕事に追われたことは何度もあった。しかしなにか、以前とは違う気がした。やり方は変えていない。まず優先順位を決め、とにかく緊急性の高そうなものを先に処理する。それから、一日、二日なら余裕のありそうなものを仕分けする。同じような内容の案件なら、まとめて処理した方が速い。パズルゲームの要領だ。いつもどおりに仕事を整理し、なんとか、明日中には終わらせることができそうだと目安をつけた。しかしなにかが違う気がした。パズルのピースをぴたりと埋めるような、しっくりする感じがない。そのあいだにも、新しい仕事が飛び込んでくる。野田というお調子者の営業職員が、これ大至急でお願い、といつもの軽い調子で目の前に書類を置いたときは、思わず睨みつけてしまった。
美山さんに朝貰ったコーヒーのことをすっかり忘れていた。コーヒーはすっかり冷めていた。製造部に急ぎの仕事の電話を入れたあと、なんだかどっと疲れがきて、美山さんのコーヒーをブラックのまま、口にした。舌の端のほうにまとわりつくようなえぐみに一瞬顔を顰めたが、それほどまずいとは思わなかった。家で淹れるコーヒーとか、お気に入りの喫茶店で出てくるコーヒーと、それほどの違いはないような気がした。パソコンのディスプレイから目をそらせたのと、美山さんが書類から顔を上げるタイミングが重なって、少し目が合った。
気分転換が必要だ。みつ子は蛍光ペンの山に手を伸ばした。そしてゆっくり、キャップを外した。
翌日、始業前の薄暗い職場に電話のベルが響いた。みつ子が受話器を取り、××印刷です、と言うと、数秒の間があった。かすかに溜息のようなものが聞こえた。それでだいたい、用件がわかった。去年は何度も、この小さな溜息を聞いた。予想通り、電話の相手は、佐伯優佳の母です、と言った。
佐伯さんは体調不良でお休みだそうです、と、清田係長に告げた。最近元気だったのになあ、悪いけど、緊急の案件だけ、加藤さんと二人で分担してもらえるかな。清田が言った。加藤はあからさまに、渋い顔をしていた。公演が近いのかもしれない。みつ子は、わかりました、と言い、加藤には何も言わず、佐伯の書類ケースから仕掛中の書類の束を取った。
佐伯の休みは続いた。三日目に、佐伯の母から清田係長あてに連絡があって、外に出るのも難しいような状況なので、ひと月休むようにという医師の診断が出た、ということだった。加藤はみつ子の頭越しに、なにやらぶつぶつと要領の得ない話を始めた。面倒な件をいくつか抱えているから、いまは佐伯の仕事をこれ以上持つことはできない、と言いたいようだった。清田がなにか言いかけたところで、みつ子は、あとは私がやるからいいです、と言った。
美山さんがいつものように、コーヒーを持ってきた。今日は小さなチョコレートがついていた。最寄り駅のデパートで売っている。仕事終わりに行っても、たいてい売り切れている人気店のチョコレートだった。美山さんは、みんなで佐伯さんのぶんをカバーしましょう、と言った。僕も、やれることはなんでもやりますから。美山さんの言葉に嘘はない。しかし美山さんにはほとんど期待できない。美山さんが退職する五年ぐらいまえにようやく、社内の受注システムが完成した。それまでは紙の書類が大量に行き来していた。だから美山さんはシステムの扱いに慣れていない。だいたい美山さんはパソコンが苦手だ。いまでもキーボードは、ひとさし指しか使えない。パソコンを使わない仕事も、いまいち覚束ない。いちど、配送便の手配のような簡単な仕事をやらせたことがあるが、美山さんはミスを連発し、パニックを起こしてしまった。美山さんは六十半ばで、みつ子の両親とそう年齢が変わらない。両親のことを考えると、新しいことを覚えるのが難しいことはなんとなくわかる。だからせいぜい、美味しいお菓子を買ってきてくれることぐらいしか、美山さんに期待できることはない。じっさい、チョコレートはとても美味しかった。
チョコレートとあわせれば、ひょっとして美山さんのコーヒーも美味しく感じるかもしれない、とみつ子は思った。しかしいつもどおり、不味いコーヒーだった。美山さんのコーヒーを不味いと思わなかったのはけっきょくあの日だけだった。みつ子は一口口をつけただけで、美山さんのタバコ休憩のあいだに給湯室に捨てた。
佐伯の仕事のほとんどをカバーすることになり、十時を回ってから職場を出る日が続いた。さすがに家に帰ると疲れきって、メイクを落としてシャワーを浴びたらすぐに眠った。弁当を作る余裕はなく、近くのコンビニエンスストアでサンドイッチを買った。昼休みも、薄暗い職場で、サンドイッチを食べながら仕事をしていた。スーツは皺がついたままだったし、メイクは最小限、伸びた髪もざっくりひとつに縛っただけだった。週末に美容院の予約を入れていたが、寝過ごしてキャンセルしてしまった。
思うように仕事が進まない日が何日かあった。いつもやっている仕事をいつもと同じ手順で進めているだけなのに、なかなか書類の山がなくならなかった。夕方近くになって、急に捗り始めることもあった。たぶん、集中力に波があるのだ、と思った。疲れているせいか、波がいつもより大きい。アップダウンが続く道なのにそれと気づかず、いつも同じ力でアクセルを踏んでいる。だから余計に、頭や体に負担がかかっている。いつもなら些細な変化にもすぐに気づいて微修正をしていたのだ。
ある日、佐伯がやった仕事のなかにミスが見つかった。取引先や、ほかの部署との調整が必要そうだった。佐伯が製造部に書類を回したタイミングでは、納期遅れになるのが確実だった。そういうときは先に、製造部に話をつけておくべきなのに、佐伯はなにもしていなかった。担当の野田と清田係長が激しく口論しているのを聞いた。どちらが悪いというわけでもなかった。佐伯の仕事のやり方は社内の規定上特に問題はなかった。営業支援課が急ぐ案件であることを察知して製造部に手を回すというのは暗黙の了解みたいなもので、みつ子から見れば、佐伯に任せっぱなしにしていた野田に隙があった。製造部も、本来のルールを盾にしてなかなか、首を縦に振らない。スケジュールを大幅に組み直さなければならないし、工場の人たちの残業や休出も増えるだろう。野田が取引先に頭を下げて済むならそうしてほしいのだ。「むかしは、そういうときは製造部も固いこと言わずに、いっちょ営業部のためにやってやろう、ってなったんだけどね。その代わりあとで女の子がいる店に行って酒を奢ったりしてね。やっぱりこういうときのために、ふだんから製造部と気持ちが通じ合うようにしておかないとね。僕なんかは毎週一度は工場に行って、製造部の連中と飲みにいったもんだけどね。やっぱりそういうのも必要だよね」
みつ子は美山さんの話が自分に向けられていたものだと気付いて、微笑んで頷いた。
みつ子はただ、清田係長の指示を待って書類を作るだけだった。やることさえ明確にしてもらえれば、すぐにでも、完璧な書類を用意することはできた。
野田と野田の上司の古田、それから清田が製造部に出向くことになった。製造部は埼玉にあって、電車とタクシーで一時間以上かかる。三人は慌ただしく出発した。
みつ子は久しぶりに、工場に行きたいと思った。新卒の研修以来、足を伸ばしたことはない。有機溶剤とプラスチックが溶ける匂いと、ごうごうという機械音が充満して、しばらく立っていると、ぼんやりと意識が遠くなる気がする。同期入社の社員のなかには気分が悪くなる者もいたが、みつ子は気にならなかった。
とくにみつ子が好きだったのは、巨大な印刷機が置いてある工場の床や壁に散乱した、鮮やかな色のインクの飛沫だった。赤、黄、白、緑、様々な色の破片が、お互い譲らず、しかし不思議な調和を保って、一つの抽象画となっていた。理屈ではなく、脳に直接飛び込んでくるような色彩だった。それをじっと見ていると、うまく説明できないが、強く心を動かされる気がした。ひょっとして、人の感情と言われるものの正体は、ああいうものなのかもしれない、と思った。
みつ子は、袖机の蛍光ペンがずいぶん溜まっているのに気付いた。工場に行った清田から連絡がくる前に、一本、インクの補充をしておこうと思った。いつものようにキャップを外し、補充タンクの口を切った。鮮やかなイエローの玉が、机のうえにポトリと落ちた。
帰りに立ち寄ったコンビニエンスストアで、若いサラリーマンが缶チューハイを買っているのを見て、自分も手に取った。原色を配したパッケージデザインは悪くなく、なんだかうきうきした気分になる。店を出るとすぐに飲みたくなって、近くの公園の、人目につかないベンチに座ってプルトップを開けた。すぐに顔が熱くなった。梅雨前の、少しだけ湿り気を帯びた風が心地よかった。風が吹くと鬱蒼と茂った木の葉が囁き合うように揺れた。木と話をしているような気持だった。その日から毎晩、帰り道は公園で缶チューハイを一本空けてから、アパートに戻った。
八割照明を落とされた職場で、みつ子は一人だった。営業課のデスクにもちらちら、明かりが点いていたはずだし、どこかからカップラーメンをすする音が聞こえ、スープの脂っこい匂いが漂ってきていたのだが、気付くと誰もいなかった。
白い箱のなかの蛍光ペンは溜まる一方だった。みつ子は机に顔を伏せた。ここのところずっと、職場を出るのは十一時半を回ってからで、それも終電を逃さないためだから、仕事が終わったわけではなかった。そのまま眠ってしまいそうだった。
このままではいけない、と顔を上げた。しかしどうしても、目のまえの仕事に手を付ける気にはならなかった。明らかに仕事のスピードが落ちている。自分のイメージの半分も、進んでいない。でも期限は容赦なく迫ってくる。
みつ子は袖机のうえの白い箱をひっくり返した。机のうえに、色とりどりの蛍光ペンが広がった。くすんでいた。みつ子は勢いよく立ち上がって柱のところまで行き、照明をつけた。ぱっと、職場が明るくなった。
蛍光ペンたちは、賑やかな色彩を取り戻していた。みつ子は少し、元気になった。この子たちをお腹いっぱいにしてやってから、もういちど戦略を練り直そう、と思った。みつ子は、乱雑に積み重なったファイルを脇によけた。
「あ」
机のうえに、真っ黒な液体が広がった。美山さんのコーヒーが、朝からずっと、手つかずのままだった。黒い液体はどろどろ、ねばねばしていて、蛍光ペンたちを真っ黒に覆いつくす。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
