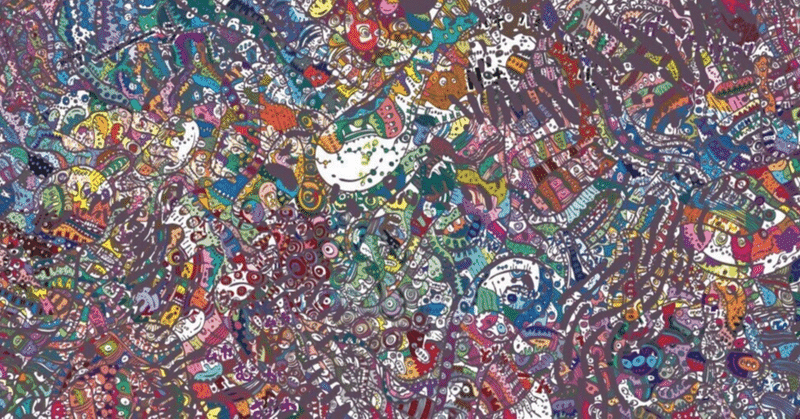
たましいの救済を求めて第十一章第三話
第三話 羽藤の怪我
遅刻はするなと言ったけれど、そもそもホーストコピーに時間の概念があるのだろうか。ホーストコピーは虚空を漂う魂の分身だ。
十一時からの面談開始時刻が迫り、麻子は白衣を身に纏う。
腕時計にも視線を落とした麻子を駒井が「行ってらっしゃい」と、送り出す。
麻子は口角を上げ、「行ってきます」と、返事をした。
駒井と目と目が合うだけで、面談室へと赴く勇気が湧いてくる。
ついさっき、クソ意地の悪いチョビ髭野郎と思っていたのに、ゲンキンなものだと自分を笑う。
駒井は事務室の続き部屋になっている院長室へ足を運び、麻子は薄暗い廊下に出た。直後に感じた血の匂い。
ハッとして周囲を見渡した。
「先生」
と、どこからともなく呼ばれた麻子は「ぎゃっ」と言う。飛び上がらんばかりに驚いた。麻子は廊下の電気を明るくした。
「先生。中に入ってもいい?」
第一面談室の前に柚季がいた。右膝のあたりのデニムの生地が大きく裂けて、脛に血の筋が出来ている。
「どうしたの? それ」
「転んだんだよ。羽藤の奴が」
「転んだの?」
立っているのも辛そうだ。
麻子は面談室のドアを開け、足を引きずる柚季を定位置のパイプ椅子に座らせた。その前で膝立ちにあり、傷の具合を確かめる。
裂傷がひどく、出血が止まらない。
「まさか、ケンカじゃないわよね?」
「ちげーよ。だから、羽藤の奴が足滑らせて、コンクリの上で転んだんだよ」
くり返される説明の意味が、わからない。ともかく今は手当が先だ。
「ちょっと待ってて。事務室に救急箱があるから持ってくる」
「いいって、こんなの。ほっとけば、そのうち止まるし」
「良くない!」
柚季を叱りつけた時、強張っていた柚季の顔が、小鹿のように円らな瞳が、不思議なものでも見るかのように、あどけなくなる。
不思議なものでも見るように。
「そこにいるのよ? いいわね? 逃げたらホントに怒るわよ?」
さんざんに念を押してから、麻子は面談室を飛び出して、事務室の棚から救急箱を取り出した。それを下げて駆け戻る。
面談室に入ると、柚季が大人しく座っている。良かったと、安堵の息が思わず漏れた。
「……かわいそうに。痛いでしょう?」
再び柚季の前に跪く。擦れて破れたデニムの生地をハサミで切り取り、円にする。コットンに消毒薬を含ませて、いちばん深い裂傷を消毒した。
途端に柚季の足に力が入る。「……痛っ」という、小さな声が頭上で聞こえた。
「あと少し、我慢して。傷口に小石とか付いちゃってるから、拭き取るわ」
できるだけ痛くないよう、そっと汚れを落とした麻子は、消毒薬を含ませたガーゼを、裂傷に押し当てる。
「このまま持ってて。包帯巻くから」
顔を上げた麻子を柚季はしおらしく眺めている。言われた通りにガーゼを押さえる。麻子は救急箱から包帯を出し、止血をかねて、少し強めに巻きつけた。
「院長室に先生がいらっしゃるから、痛み止めの薬を出してもらうわね。私がやり取りするだけだから。柚季君は院長に直接会わないようにするからね?」
ぼんやりしている柚季に告げる。そういえば、彼はホーストコピーだったことに気がついたのは、処置が終わってからだった。
「……えっ……と、あの。ごめんなさい。痛み止めの処方箋は院長から書いて頂くことは出来るけど。薬局が開いてないから薬をもらうことは出来なかったわ。ごめんなさい。私……、慌ててしまって」
「先生でも、慌てるんだ」
柚季は、クスっという失笑した。麻子は柚季と同じ目線になる、パイプ椅子に腰かける。救急箱を腿に乗せ、痛み止めの薬が入っていないか、中身を探る。
「でも、って、どういう意味ですか?」
「図太いくせに、って意味だけど」
ああ言えば、こう言う、減らず口を叩かれる。それでもなぜか、それを不快に感じない。むしろ親和性が高まった。麻子はわざと眉間に皺を寄せてやる。それが抗議だ。
「……あっ、あった。ロキソニン。良かった。入ってた」
ほっとした声を出し、市販薬の痛み止めの小箱を出した。
「少し待っていてちょうだい。水を持って来るからね」
ホーストコピーに鎮痛剤がいるのかどうかは、わからない。けれども柚季は痛いと言った。もし痛感があるのなら、薬で軽減してやりたい。
「すぐに戻って来るからね。絶対そこにいてちょうだい。絶対にだから」
「逃げたら本気で怒るんだっけ」
「そうよ! 本気で怒るから!」
「マジ恐そう」
と、肩越しに笑う。
笑われたのだが、侮辱ではない。挑発でもない。
救急箱を持って出ると、事務室に入り、給湯室で水を汲む。救急箱は自分のデスクに、ひとまず置いた。点けっぱなしにしていた電気を消してから、面談室に帰って来た。
そこにいた柚季の後ろ姿。パイプ椅子に片腕を掛け、腰をずり落とす格好で両足を伸ばしている。だらしがないと思ったが、それが柚季だ。ほっとした。
「これ。痛み止めのロキソニン。少し多めに渡すけど。一回につき一錠よ」
テーブルに三日間分置いてから、まずは一錠飲めと言い、水を注いだグラスも添えた。柚季はそれを大人しく飲む。残りの錠薬はブルゾンのポケットに無言で収める。視線は床に落ちている。
ようやく一息つけた麻子は、残りの面談時間が十五分足らずだと考える。
治療に要した時間は面談の規定外にすべきかどうかで、思案する。
「先生。これは俺が転んで作った傷じゃないから」
と、ぼそりと告げられ、麻子は顔を振り向ける。柚季は変わらず視線を伏せたままだった。
「羽藤の体が傷つくと、俺の身体に傷がつく。俺は痛みを感じるけれど、羽藤は痛みを感じない。俺が身代わりだからだよ」
打ち明けられた実情に、麻子は理解が追いつかない。
確かに羽藤に、無痛症だと言われていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
