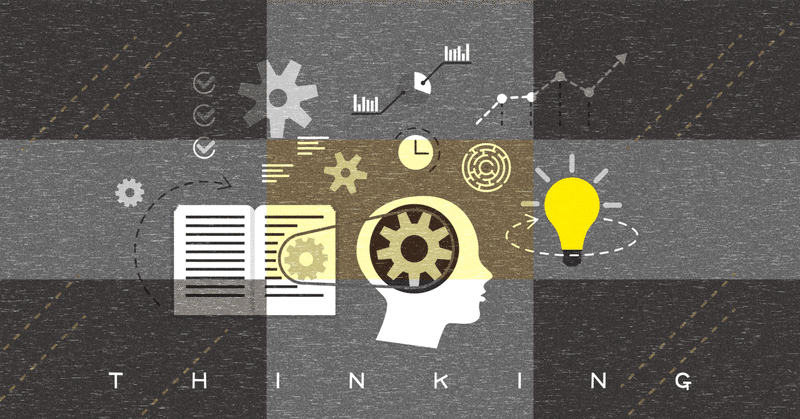
【読書記録】樺沢紫苑『言語化の魔力 言葉にすれば「悩み」は消える』【みんな毎日悩んでいる】
悩みがあると本に頼る私ですが、このところ、YouTubeにも頼っています。
精神的に悩んでいて、出会ったのが精神科の樺沢紫苑先生の動画でした。
そんな樺沢紫苑先生の著書です。
先生のYouTubeチャンネルでは、本書に引けをとらない内容の動画を無料で見ることができます。
しかもショート動画で端的に話されていたりして、さくっと腑に落ちることができます。
(動画よりも詳しく説明はされていると思います。動画には動画の、本には本の良さがあります。)
でも悩んでいる人というのは、何度も同じことを尋ね、何度も同じことの答えを求めてしまいます。
私もそろそろその段階から抜け出し、自分の手綱を自分で握っていかなくては…と思います。
以下、心に残った部分を引用します。
悩みを乗り越えることができた時、必ず「自己成長」が怒ります。それによって、問題解決能力はアップし、その後に抱えた「悩み」は、もっと楽に乗り越えられます。
「悩み」を抱える人は、どうしていいかわからないから不安になり、パニックに陥ります。「対処法」「TO DO」が明確であれば、それを行動にうつすだけでいいのです。
多くの人は、悩みに直面した場合、根本的な解決を求めて原因を取り除こうとします。一気に悩みをなくしてしまおうと考えるのです。まずこれが問題です。目標が高すぎるのです。
解決が難しいために悩んでいるわけですから、いきなりの原因除去は、そもそも不可能なのです。その不可能を無理にやろうとすれば、「つらい」「苦しい」が、さらに増大するのは当たり前。(中略)
悩みの原因を解決する必要はありません。原因は保留にしたまま、やれることを、やれる範囲で、1つずつ片付けることが重要です。
悩みは「解決」するな。心のなかのストレス、モヤモヤ、不安を取り除いて「解消」するのです。
悩んでいる人は、常に近視眼的になりがちです。目前の「悩み」しか見えなくなってしまう。
情報不足は不安を引き起こし、不安はさらに「視野狭窄」を招きます。
自分で意識して、視座を変えることが重要です。
ニュートラルとは、
▼感情に振り回されて一喜一憂しない
▼1つの情報に踊らされず、データを集め、先入観や偏見を取り除く
▼部分ではなく、全体を見て判断していく
▼中立的に判断、行動する
▼すぐにあきらめずに、冷静に観察しながら、粘り強く続けていく
ということです。こういう考え方ができる人は、苦境に陥っても一喜一憂しないので、ストレスを受けづらい。
ほとんどの人は、1段も上らない状態で「上る」「上らない」を決めます。
とりあえず、10段目まで上ってから、「上る」「上らない」を決めても手遅れにはなりません。むしろ「より正しい」判断ができるというものです。
1段も上らずに、遠いゴールを見上げて「あーどうしよう、どうしよう」と悩んでいるのは時間の無駄。とりあえず1段、とりあえず10段上ってみましょう。
つまりは、上りながら考える。実際に、行動、アクションしながら悩めばいい。
認知バイアスの1つとして「ネガティブ・バイアス」というのがあります。
人間は、ポジティブよりも、ネガティブに引っ張られやすいという傾向です。
▼自分の長所よりも、欠点に注目してしまう
▼仕事の「うまくいっている部分」よりも「うまくいっていない部分」に注目してしまう
▼「ほめられた言葉」よりも「批判された言葉」が記憶に残る
▼ポジティブなニュースよりも、ネガティブなニュースを見てしまう
これらは全て「ネガティブ・バイアス」です。
つまり、自己肯定感が「高いか低いか」の二択で「低い」と判断してしまうのは、認知バイアスであり、脳の基本的なプログラムなのです。
「職場の人間関係で悩んでいる」人は、どのくらいいるでしょうか。
調査の結果、「人間関係で悩んでいる」と答えた人は67.2%。3人に2人が人間関係で悩んでいます。
自分の職場の人間関係が良くないと「どうしてこんな会社に就職してしまったのだろう」「なんて自分はついてないんだ」と思うでしょうが、世の中の3分の2の職場で、人間関係が良いとは言えないのです。つまり、人間関係がギスギスしている職場が普通。多数派なのです。
言語化のメリット
1 悩みの可視化
見える化、取り扱い可能、自己客観視できる
2 整理される
分析、自己解決能力、「どうしていいかわからない」からの脱却
3 外化
棚卸し、脳が軽くなる、ワーキングメモリの解放
4 ガス抜き
心が軽くなる、ストレス解消
5 共有可能、伝わる
コミュニケーション、共感による癒やし
6 行動化
行動が促される、言葉を変えると行動が変わる
人は、なぜ相談できないのか。「相談できない症候群」の原因は何でしょう?
人に相談するのに、心理的障壁が高くなってしまう理由は、「相談することが自己開示」だからです。
「自己開示」とは心理学の用語ですが、「ありのままの自分」をさらけ出すこと。(中略)
ありのままの自分をさらけ出すことに「恐怖」を感じるのは、人の自然な心理です。
「人は、目標が完了していないタスクの方を、完了したタスクよりもよく覚えている傾向がある」
つまり、「一件落着した出来事は忘れやすい。継続案件は忘れない」。
歩きながら考えれば、考えごとはすぐに解決します。
歩きながら悩めば、悩み事は解消に向かいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
