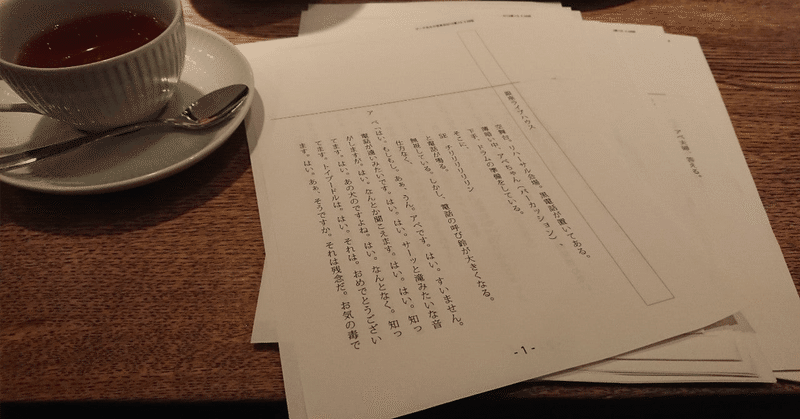
【読書記録】鈴木敏昭『人生の99%は思い込み』【人生の脚本を書き換える】
「人生を変えたい」
誰もが一度は考えることではないでしょうか?
私もたくさん本を読み、昨年から少しずつ意識をしてきました。
ただ、多くの人がなかなか人生を変えられず悩んでいると思います。
なぜ、変えることができないのでしょうか?
それは、無意識に自分の人生の「脚本」を書き、その通りに生きているからだと本書で語られています。
では、その「脚本」を書き直すにはどうすればよいのか。
そのヒントがこの本にあります。
人の意識が現実を創造するのであって、客観的な事物など存在しない
――ニールス・ボーア
以下、本書の内容の中で、私が重要だと思った部分を要約します。
第1章 人生は「自分で書いた脚本」どおりに進む
人生を決定する「人生脚本」は、無意識に深層心理の中で書いている。
人は、自分について思いや信念を抱くと、無意識にそれに合うように行動し、結果として現実化する。
「人生脚本」は、7歳くらいまでにつくられる(親からのしつけ、周囲からの評価、学校教育等)。
第2章 人生脚本は多くの「思い込み」でできている
自分が思っている性格は、その性格に合うように行動を自分が選択しているだけである(勝手にそんな性格だと自分が思い込んでいるだけ)。
なぜ人は、思い込みの心理を持つようになるのか?
それは「思い込み」は脳の負担を減らして、楽に生きられるからである。
すべてのことをいちいち考えていると効率が悪いため、無駄な思考をしないように「思い込み」がある。
人は情報を集めて秩序をつくりあげ、不完全なデータから完全な意味を読み取る習性を持っている。それは、自分の心のフィルターを通じてなされる。自分に都合のよい秩序をつくりあげ、自分が納得するような完全な「意味」をつくりあげているのだ。
しかし「本当の自分」というものはない。
というよりも、もっと深い話をすれば、「自分」というのも思い込みなのだ。人は生まれてきて自分というものがあるのだと思い込んで生きているが「自分」という存在すら思い込みがなせるわざなのである。(中略)自分というアイデンティティをよりどころとすることで安心しているのが、私たち人間なのである。
一方で、あなたは「人に悪く思われている」「嫌われているんじゃないか」と感じたことはないだろうか。
人の立場に立ち、相手の気持ちを考えるのはひじょうに難しいのに、人のネガティブな気持ちはすぐに分かったつもりになってしまう。(中略)
心理学の世界で、「読心」という言葉がある。ただし、超能力のテレパシーのように、相手の心を読み取る読心術ではない。これは「認知のゆがみ」という症状の一つである。
第3章 人生を支配する「思い込み」の正体
思い込みを形成する外的な要素は4つある。
①家族(幼少期は親とのやりとりだけが「世界」である)
②教育(教育は思い込みの上に成立している)
③会社・職業(「経済的・物質的豊かさこそが幸せをもたらす」という思い込み)
④社会常識
思い込みは気づくのが難しい。何が根源的な思い込みなのか、「諸悪の根源」を突き止めないと退治することもできない。
思い込みを突き止めるステップ4つ。
ステップ① 問題リストをつくる
ステップ② 思い込みチャート分析図をつくる(起点となる悩み・問題をあげ、なぜ?なぜ?を繰り返し細分化していく)
ステップ③ 「思考のゆがみ」の種類を突き止める(ステップ②のチャートの末端になると思い込みが出現する。そこから自分の思考のクセを見つける)
ステップ④ 思い込みの出発点を突き止める(チャート図をながめると、現在の悩みの背景に隠れた重要な問題がある。そこまで突き止めてみる)
第4章 「思考のゆがみ」はこうしてなおす
自動思考から抜け出すために、意識的に自分の普段の考え方、物の見方を疑う必要がある。
思考の自動操縦を、パイロットである自分の手に取り戻す。
その手法は「認知」である(認知療法とは、認知の仕方を変える心理療法)。
思考のゆがみのそれぞれに対する対処法がある。
(本書の中に具体的な手法がたくさん紹介されている。)
(例)ネガティブフィルター・マイナス化思考の克服
①メリットとデメリットを考える(書き出してみると、マイナス面だけではないことに気づく)
②適応的思考(悲観でも楽観でもなく、偏りのない思考。自動思考に対して「根拠」と「反証」でもって、思い込みを解除していく)
私たちは完全な「白紙」の中で考えることはできない。いつもある枠組みの中で、あるいは何かとの比較で、物事をとらえる。よって、ここから抜け出るのはとても難しい。
第5章 「思い込み体質」の根本的な治療法
人生に対して、誰もが「構え」があり、それを修正しなければ真の思い込みからの脱却は難しい。
構えを修正する上で効果的なのが「ポジティブなストローク」(相手からの愛情のこもった言葉、声かけ、態度や動作のこと)。
(具体的な手法が本書では紹介されている)
そもそもの話だが、悩むというのは「悩んではいけない」という思い込みに囚われているだけだ。(中略)
自分に勝手なルールを設けて苦しめているのは、まぎれもない自分自身である。自分の思考をブロックしているものに気づくことで、現実は変えられるのだ。
第6章 「思い込み」を利用して「人生脚本」を書き換える
思い込みのすべてがマイナスではない。思い込みを味方につけることで、問題を解決し、性格を変えることもできる。
(例)ポジティブな自己暗示、プラシーボ効果
性格を変える4つのメソッド。
①行動を変える(人間には「一貫性を持たせたい」という性質があり、ある行動に対し、自分の中でつじつまが合うように「自分はこういう人間だ」という思い込みが生まれる)
②「振り」をしてみる(誰かの「振り」をしてみると、理想像に少しずつ近づき、いつの間にか「それが自分だ」と脳が思い込む)
③環境を変える、環境を増やす(ストレスの溜まる環境を「多くの環境の中の1つにすぎないようにする」)
④服装を変える
「できない」という思いには、常に「したい」という気持ちが隠れている。(中略)
「できない」と思っているところには、いつも自分がつくり出した基準がある。それは世の中の基準だと思っているかもしれないが、結局のところ、受け入れているのなら自分の基準である。
自分でつくり出した基準なら、いくらでも変えられる。変化を止めているのは、自分自身なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
