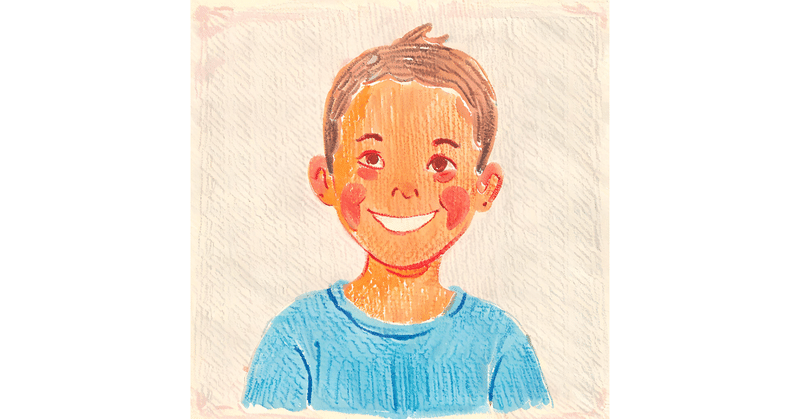
栄養素を見直したら、体調とニキビが改善してきたお話[2]
では、それぞれのコルチゾールの出ていく側面と入ってくる側面をそれぞれ生理学的に調べてみよう。
まずは、出ていく側面。コルチゾールの生理学的な機能として出ていく側面としては、以下の通りである。
抗炎症、抗感染症
血糖値上昇
アミノ酸、脂肪を元に肝臓内から糖新生
上記に上がった機能に肝臓内での糖新生といった機能加えて、コルチゾールは賄っている。
一方で、コルチゾールのコルチゾールの生理学的な機能として作られる側面としては、以下の通りである。
鉄
亜鉛
ビタミンB
ビタミンC
などである。これらがコルチゾールの生成に必要なのである。コルチゾールは、このようにして出入りするわけである。今回はこの中でも、出ていく側面に着目してみたい。
まず、コルチゾールは大まかの使われ方がある。
血糖値の維持
抗炎症
この二つに付随する機能が枝分かれしているというわけである。つまり、この二つの使われ方日中で防ぐことができたら、ある程度の出ていく側面は防ぐことができるということになってくる。では、血糖値に維持と抗炎症をさせないためにはどうしたらいいのであろうか?
血糖値を食事から摂取してカバーする
副交感神経が優位の状態をなるべく作る
ずいぶんとシンプルな方向性であることがわかる。
まず、血糖値を食事から摂取してカバーするとはどういうことだろうか。まず、血糖値はエネルギーに関係してくる。エネルギーは人間が動くに必要であるということは自明だ。そのエネルギーは体の外から摂取しないことには、作り出すことができない。確かに、エネルギーが足りない時に補う機構というものもあるのだが、ずっとエネルギーをとっていなかったら当然死んでしまう。いわゆる餓死に陥ることになる。
では、そのエネルギーというものは、何を介してやり取りされているのだろうか。食事を取ったらなんでも、エネルギーになるのではなく、体内で反応を得てからエネルギーになる。それは、ATPという通貨のような物質を持ってやり取りされる。この通貨を持って生み出すエネルギーを担っている物質として、三大栄養素(糖質、タンパク質、脂質)がある。他の栄養素は、直接的にエネルギーになることはない。そして、この栄養素の中で特にエネルギー効率の良い物質がある。それが、糖質である。糖質には、細胞質で解糖系を通過し、ミトコンドリアの中でクエン酸回路を通って、電子伝達系を経由してエネルギーを産生する。それ以外の、タンパク質と脂質は解糖系という回路を通って、再度グリコーゲンになり、一から上記のような回路を通ってエネルギーを産生する。つまり、効率が悪いということになる。このようにしてエネルギーが産生されるというわけであるが、エネルギーを体が利用していくには階層がある。つまり、使われる順番が元から決まっているということである。その順番を列挙していく。
血液中のグルコースを利用する
肝臓内のグリコーゲンを利用し、グルコースに分解して利用する
筋肉や脂肪を分解して、糖新生を起こしてグルコースを生み出す(コルチゾールを使う)
このようにして、体内のエネルギーを生み出す階層は決まっているということである。今回の目的は一貫して、コルチゾールを無駄遣いしないことである。では、コルチゾールを生み出さないためには、1,2をクリアしておく必要性がある。そのための方針を立てていこう。
その方針は、簡単に言えば、エネルギーの産生を全て食事由来のグルコースで担うということである。すなわち、体脂肪や筋肉を使うことなく、食事の糖質で必要なエネルギーを生み出していくことである。では、食事由来のエネルギー産生によって必要なエネルギーを生み出す食事とはどうやったらいいのだろうか。まずは、必要なエネルギーを推定エネルギー量をもとにして計算する。私は、21歳の男性で運動量がそこまで多くないので、2300kcalほどである。そして、PFCバランスはPFC=15:25:60(%)=345:575:1380(kcal)=86:63:344(g)となっている。
このように、糖質を1日で344gも摂取する必要がある。さらに、コルチゾールを低血糖時に分泌しないために、低血糖なることを防ぐ必要もまたあるため、1日のうちに3回食事をするとした場合は、一回の食事で40gの糖質を摂取するとする。その場合は、残りの200gを他の食事で補うことになる。つまり、残りの糖質を補食によって補う必要があるということだ。これは、よく考えると現実的でない。というのは、現実的に考えて一回10gの糖質の捕食を20回も行うことはあまりに回数をして多いからだ。これではかなり達成することが難しいと思うので、考え直す必要がある。つまり、食事の回数を4回もしくは5回にすることで定期的にまとまった糖質を入れる必要があるということである。しかし、仮に5回だとしても140gで、1日のうちに14回も入れる必要がある。このように、補食を取ること自体はいいのだが、それが本当に自分にとって適切な量と質の糖質かどうかは判断することが難しい。つまり、低血糖にならないような一回の糖質の量を食事で確保しながら、1日の摂取カロリーを2300kcalほどに持っていかないといけないからである。
このような状況に陥っているために、血糖値を上げない糖質の量を知るために、リブレを使って測定することが必要になってくると考える。次回は、リブレを使用すること等による解決を見出していこうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
