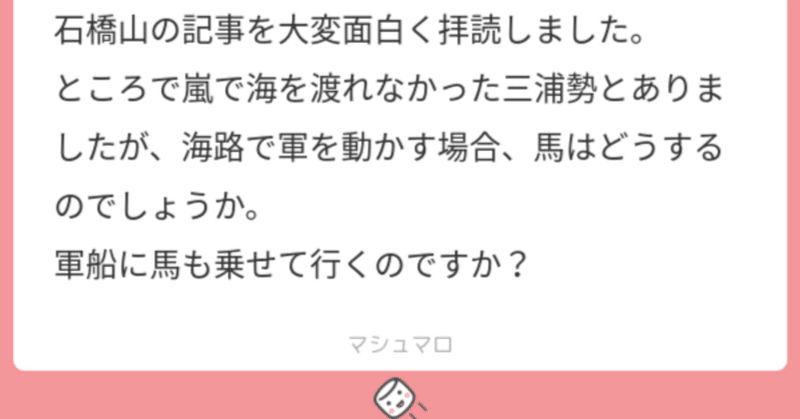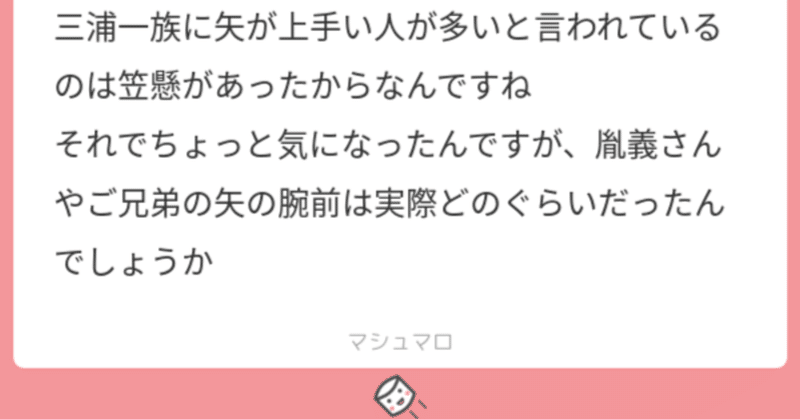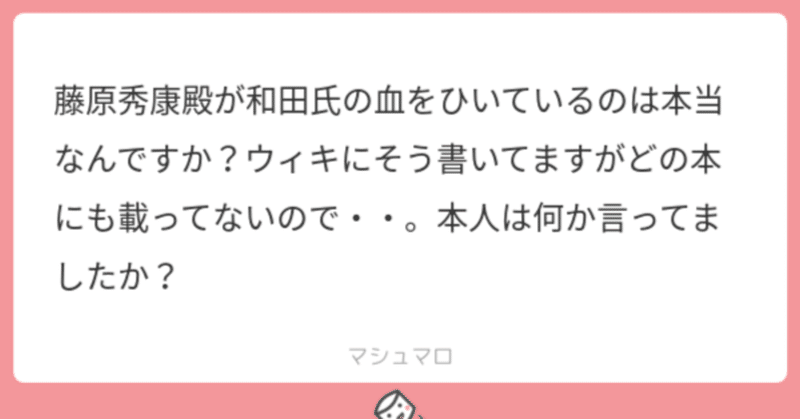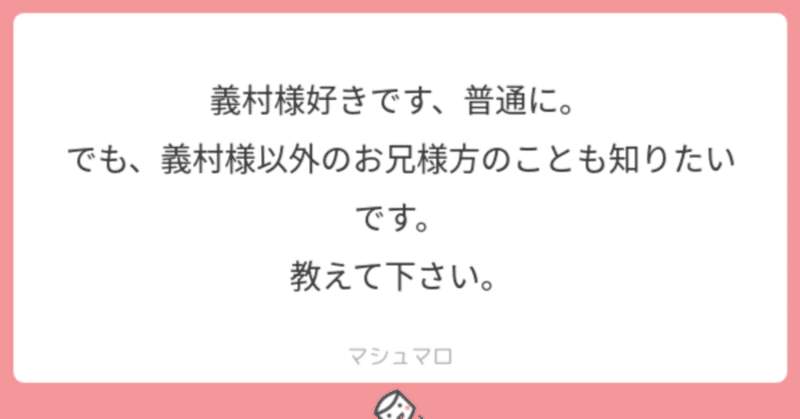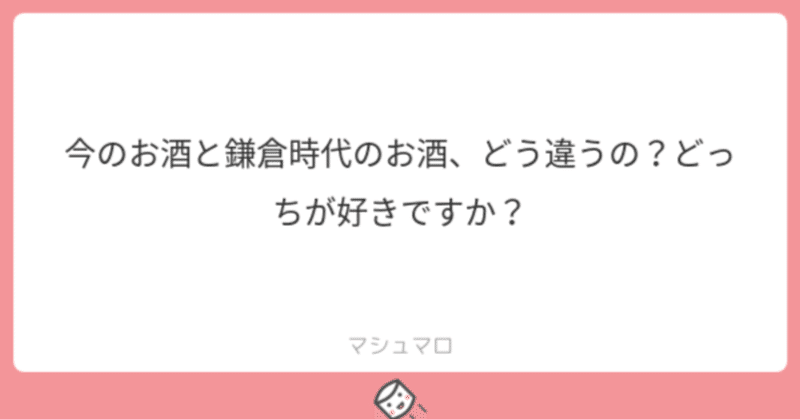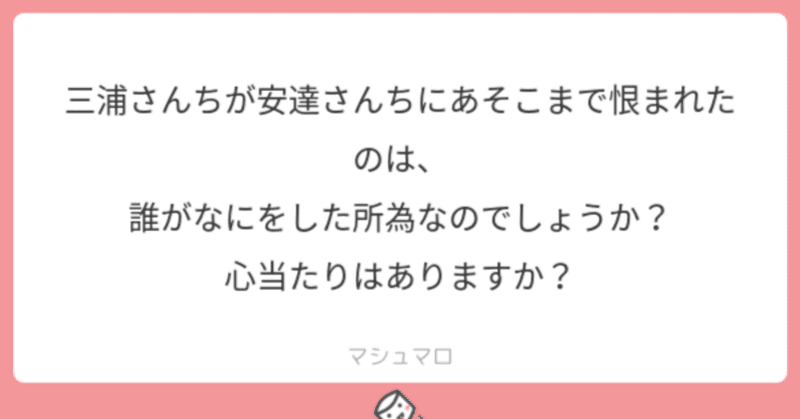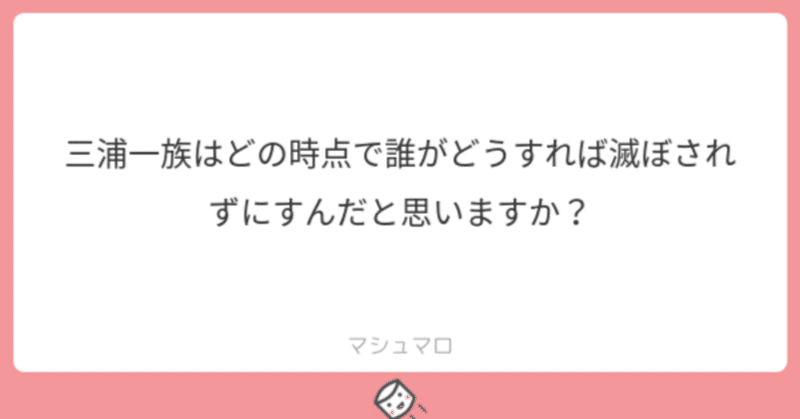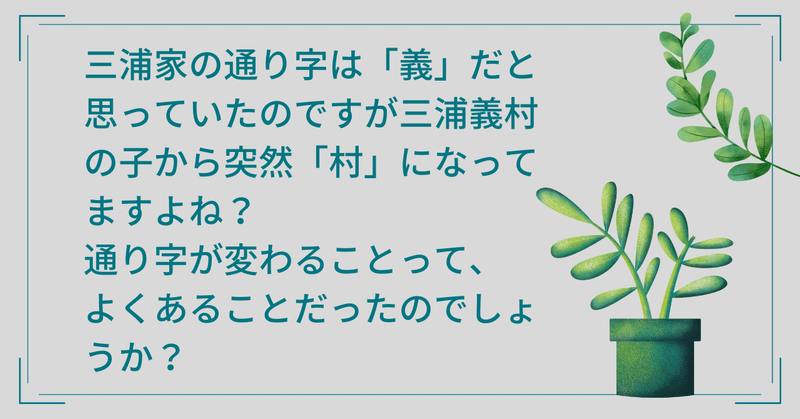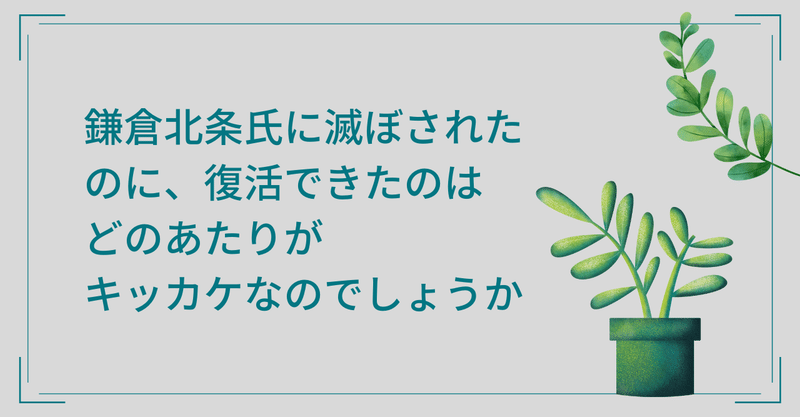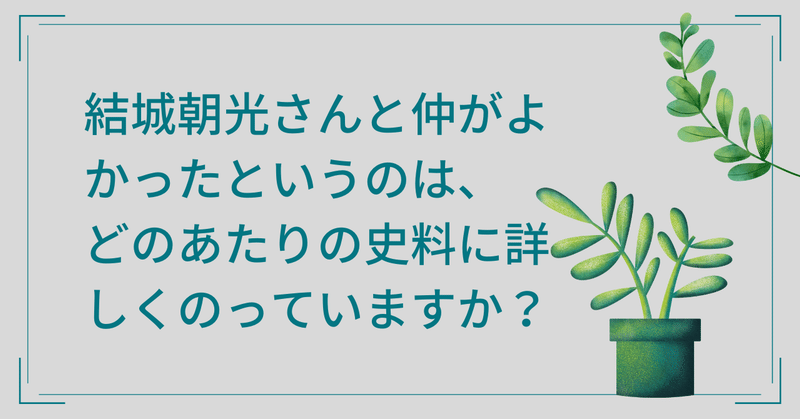#日本史がすき
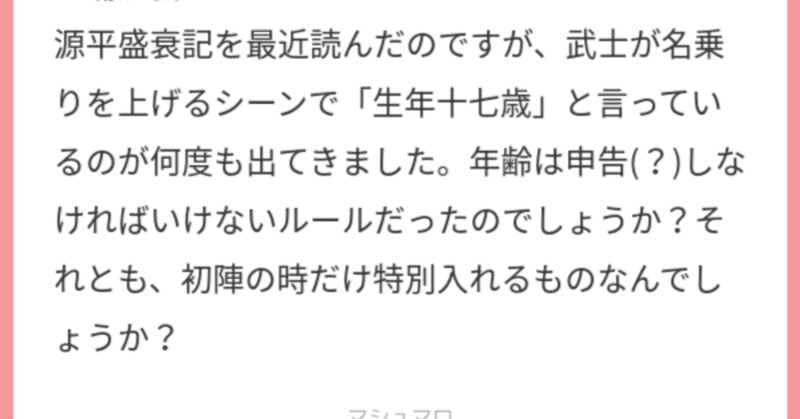
武士が名乗りを上げるシーンで「生年十七歳」と言っているのが何度も出てきました。年齢は申告(?)しなければいけないルールだったのでしょうか?
武士の名乗り、年齢を名乗る場合と名乗らない場合はぶっちゃけノリかのう……。初陣じゃなくても年齢入れる場合もある。 ちなみにな、義茂の「生年17」、実は「おいおい」なんだ。 義盛・義茂の父である杉本義宗が亡くなったのは1164年の1月。 当時の年齢は数え年なだから、衣笠城合戦の時(1180年)生年17だとちょうど満年齢は16歳で、1164年生まれになってしまう。 ん? ならギリギリ生まれてる可能性があるって? 実はな、義茂の下に弟だけでも5人ぐらいいるんだ。 だから義