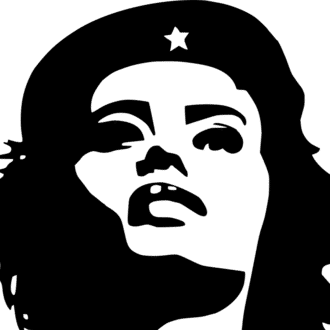『21世紀の貨幣論』メモ
数年前に邦訳されてその面白さから一部で大受けしたフェリックス・マーティン『21世紀の貨幣論』の覚書。貨幣の歴史を学ぶならこの一冊という感じである。
まず財のやり取りは、物々交換ではなくなんらかの経済的概念をもとにした信用取引であることをヤップ島のフェイの事例などで例示する。次いで貨幣の要件についての説明となるのだが、一つは普遍的な経済的価値という概念、二つ目は文字、数字を基盤とする会計技術である。最後は譲渡性(受領性)だ。これらが揃うと貨幣は決済システムを形成することになる。
実態のない貨幣が流通するためには、それが最終的にはなんらかの実物と交換されうるという信用がなければならない。古来より主権者は経済規模が大きく(流動性が大きい)、また具体的でわかりやすく、そして徴税権ははじめとする大きな政治的権限を有しているために、主権者の借用書は貨幣として流通しやすいといえる。そして主権者は貨幣の価値を増減させることで再分配したり、貨幣鋳造益を得ることができる。このようなマネーをソブリンマネーという。
だがソブリンマネーに反抗して私的な借用書を貨幣として流通させるマネー権力者やマネーマキと呼ばれるものが出現する。彼らは悪鋳などで搾取する主権者に反旗を翻すのだ。このような貨幣をプライベートマネーと呼び、アルゼンチンやアイルランドの例を用いてこのような貨幣も十分に流通しうることを示している。
プライベートマネーは君主の支配を逃れて私的な決済ネットワークを形成することで流通範囲を広げていくことになる。そこでは流通性と相互信用の構築が重要でその過程で銀行業が誕生することになる。しかしプライベートマネーは、君主のような強制権がないために銀行業の信用の範囲内でしか通用しないし、デフォルトのリスクがあった。
この対立を止揚するために、ソブリンマネーとプライベートマネーを結合したのが、イングランド銀行を嚆矢とする中央銀行システムである(マネーの大和解)。中央銀行は君主の名のもとに銀行券を発行し、政府や民間銀行に融資できる。やがて国債市場が発達するにつれ、中央銀行の政府の資金調達手段としての役割は縮小し、政府の支払いの代行、債権の発行を管理する組織となっていく。
という現代のマクロ経済環境とほぼ変わらないところまで説明したところで、本書は古典派および新古典派マクロ経済学、ネオリベラリズム批判へと急に舵を切っていく。手始めにジョン・ロックをやり玉にあげる。彼の貨幣感は、貨幣の標準は固定されていて、君主のほしいままにできるものではないということだ。まあ立憲主義が成立しつつある17,8世紀にこういう考え方がでてきたのはわからなくもないが、あまりにも実態とかけ離れている。君主の恣意とも関係ないが、民間の経済活動にしたがって自律的に、内生的に供給されるのが貨幣であって、その標準は変動しうるものだ。
しかし当時のロックの権威によって間違った貨幣観は広まってしまう。また神聖にして侵すべからざる私的財産権という観念は古典的自由主義と相性がよかったこともあるだろう、そして新自由主義とも。。。
貨幣がモノであり物理的実在であるかのような観念は、貨幣の標準がなんであるかという議論をどこかへやってしまう。貨幣による利潤を追求することは見えざる手に導かれて万人の利益になるという観念ともあいまって間違った経済学を発展させてしまう。筆者はこのことを、ミダス王まで持ち出して執拗に批判する。
あるいはジョン・ロー、ジョン・メイナード・ケインズのような経済学史の常連から、ウォルター・バジョットやハイマン・ミンスキーのようなマイナーキャラまで登場させて延々と新古典派を批判し続けるのである。最終的には貨幣システムが本質的に孕む不安定性を封じ込めるには、銀行から資産市場を切り離して決済業務に特化させるナローバンキングを支持するに至る。
本書は貨幣論、貨幣システムの歴史の本であると同時に、最終的には新古典派マクロ経済学や新自由主義批判へとつながっていく。それはある意味、当然のことで正しい貨幣観を紹介したら、返す刀で間違った貨幣観を自明のものとしている学派を痛罵するほかないのである。そして新自由主義のご都合主義な貨幣観はジョン・ロック以来の根強いものだと知ることができる好著である。自由と平等は歴史的に相性が悪いのだ。
いいなと思ったら応援しよう!