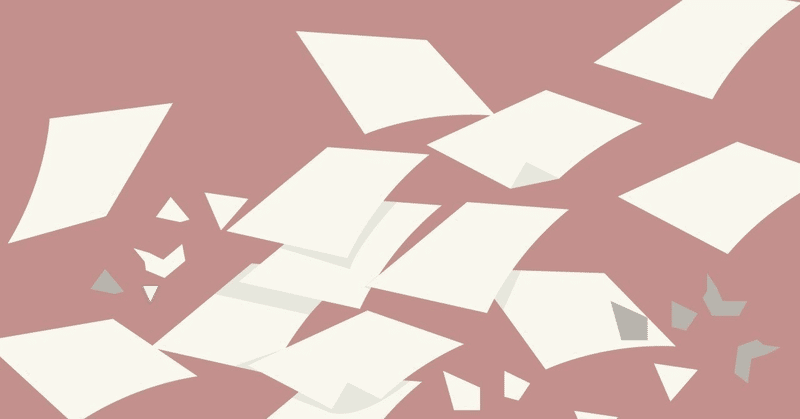
【抜書き】『読書からはじまる』~「8 失いたくない言葉」「あとがき」
こんにちは。5月9日(月)04:10です。
8回に及んだ『読書からはじまる』の読書会も、本日9日(月)開催予定分が最終回となります。おつきあいくださいまして、ありがとうございました。このnoteでは、その最終回で取り扱う最終章からの抜書きをお届けします。従来どおり、◯囲いの数字は本文中の「小見出し」に便宜的に割り振っているものです。では。
①もう読書の時代ではない?
・「これから」を語るために語られ、論じられてきたのが、情報です。反対に、読書をめぐる言葉は、どうかすると過去形によって語られ、「これまで」を語る言葉にとどまっています(略)けれども、そんなふうに、読書と情報を「これまで」から「これから」へという文脈で語ろうとすれば、誤ります。
②「育てる」文化と「分ける」文化
・読書というのは生産・製造に似ています。そして、情報というのは物流・流通に似ています。
・必要なものは、努力です。育てるということに十分に努力しなければ、穫り入れは期待できない。
・読書の核をなすのは、努力です。情報の核をなすのは、享受です。読書は、個別的な時間をつくりだし、情報は、平等な時間を分け合える平等の機会をつくりだします。
・読書は情報の道具ではないし、情報によって読書に代えるというわけにはゆかないからです。
・読書というのは「育てる」文化なのです。対して、情報というのは本質的に「分ける」文化です。
③情報としての読書がつくりだすもの
・根底から変わったのは、「分ける」文化のあり方です。
・社会が「育てる」文化を育てられなくなっているのです。
④どこもおなじ風景
・「育てる」文化と「分ける」文化というのは、拠って立つものが違います。「育てる」文化の基本は、個性です。「分ける」文化の基本にあるのは、平等です。今日の世界にひろくゆきわたったのは、平等の文化の景色です。
⑤音楽に象徴される文化のあり方
・音楽というのは、もともとは典型的な「育てる」文化です。しかし二〇世紀という時代のレコードが生んだのは、「分ける」文化としての音楽です。
⑥「分ける」文化のもつべきゆたかさ
・辞書という「育てる」文化をよく熟成させてきたものは、時間です(略)生きた時間の蓄積と遺産あってのことなのです。
・「育てる」文化のゆたかさがあってはじめて、新しい技術革新が先導する「分ける」文化のゆたかさがあるのだ、ということです。
・本を読む人をつくりだすのは、習慣としての読書です。情報としての読書がつくりだすのは、本を読まない人です。
⑦「蓄える」文化の必要
・享受が求められて、努力が求められなくなって、わたしたちが目の当たりにすることになったのは、「分ける」文化につよくなり、「育てる」文化に脆くなった、わたしたちの社会の光景です。
・そうであれはこそ考えたいのは、「育てる」文化と「分ける」文化を繋ぐものについてです。繋ぐものというより、繋ぐちから、というほうがいいかもしれません。
・どんな時代にも、社会の力量というものを左右するのが、じつは、その見えない文化のちからです。「蓄える」文化がゆたかな社会は、底力がつよい。「蓄える」文化の貧しい社会は、底力がない。
⑧アレキサンドリア図書館の教訓
・図書館はまさに「蓄える」文化そのものであり、アレキサンドリア文明の生気となったのは「蓄える」文化です。
・「蓄える」文化を失わせるものは、「消費する」文化です。もっとはっきり言えば、「消費する」だけの文化です。
・社会を深いところで変えるのは、人びとの文化に対する考え方なのです。社会のあり方を律するのは、いつのときでも結局のところ人びとが日々に分けあう考え方です。
・しばしば人びとの活字離れや読書経験の欠落が語られますが、「蓄える」文化としての本のありようが問われることはなく、語られるものはもっぱら、市場を賑わす「消費する」文化としての本のありようについてです。
・本という文化についての考え方の転換が、一人一人に求められていると言うべきです。
・「蓄える」文化としての本のありようの可能性が、社会に問われなければならないのです。
⑨読書からはじまる
・問われなければならないのは、「育てる」文化と「分ける」文化とを繋ぐ場所としての、ありうべき「図書館」という思想です。
・「図書館」がわたしたちにとってなくてはならない場所であるのは、人びとの記憶の庫(くら)としての「図書館」という場所が、わたしたちの社会にとって、遠くを見はるかす展望台のひろびろとして空気のように必要だからです。
・犀星のそのような詩の言葉は、蓄えられる言葉、蓄えられてきた言葉だからです。すべて読書からはじまる。本を読むことが、読書なのではありません。自分の心のなかに失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です。
あとがき
解説 池澤春菜
・今ではない、ここではないどこかに連れて行ってくれる本がなければ、人生のどこかで生きることを諦めていたかもしれません。
* * *
抜書きは以上となります。お読みくださいまして、ありがとうございました。なお、後日今までに作成した分のリンクを一つにまとめたものを作成して公開いたしましたので、ご参照ください。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
