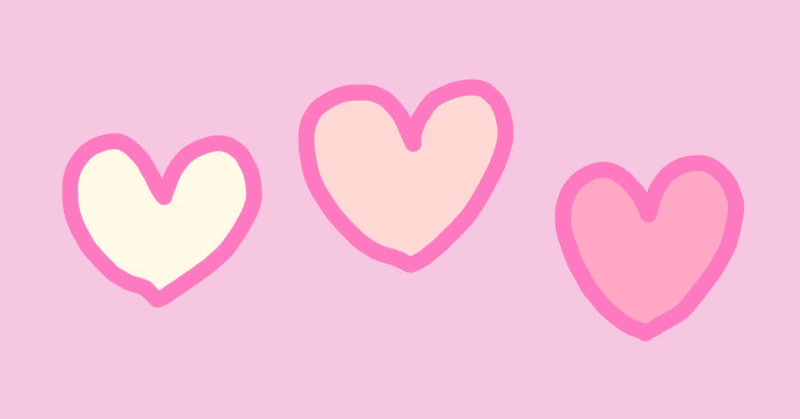
【読書会】オンライン読書会の進め方について。
こんにちは。
私がclubhouseに参加したのは2021年2月初旬でした。比較的すぐに、オンライン読書会と「100分de名著を語ろう」のルームを開設しているので、もう半年以上やっていることになります。
今回は、そのうちの「オンライン読書会」の進め方についてのお話しをさせていただきます。
1)読書会のスタンス
新型コロナウィルスの影響下にあって、「読書会」もその運営のあり方の変更を迫られてきました。もっとも、私はコロナ禍の影響が出る以前から「オンライン」での開催に執着してきました。
理由はいくつかあります。私が精神疾患を抱えている当事者であること、それに付随して、なかなか外出する機会を得られないこと、そして「仲間」を募る方法がわからなかったことなどがそれです。オンラインという方法が、その全てを解決したわけではなかったと思いますが、ともあれ半年以上継続してこられたのは、ご参加くださっているお一人お一人のおかげと、心から感謝しております。
「読書会」は、敢えて分類しようとすると、
①対面で行うか、オンラインで行うか、
②テーマやテキストを決めた上で行うか、「推し本」の自由紹介で行うか、
などの対立軸が求められるように思われます。つまり私は、「指定テキストの講読」を、「オンライン」で行うタイプの読書会を主催していることになります。
それ故、指定テキストの指定範囲を、予め読んできていただくことが理想ではありますが、それができなくてもご参加を歓迎しています。お気軽にご参加ください。
2)ご参加の方法
日程や内容については、私のTwitterやclubhouseアカウントを通じて配信しております。また、最近では、ご希望いただいている方をDiscordにご招待しておりますので、そちらを通じてのご案内もしております。これらのご利用については、どうぞお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
各回の参加については、事前の登録や申し込み等の必要はありません。当日ふらりと、手ぶらででもご参加ください。
お問い合わせは、このnoteへのコメントでも、私のTwitterアカウントでもけっこうですので、いつでもなさってください。
また、ごく最近ではありますが、Googleから提供されている「問い合わせフォーム」作成アプリを利用して、以下からもお問い合わせいただけるようにいたしました。ご利用くださいますと幸いです。
3)実績と予定
今までのところ、基本的には批評・論説的な著作と、小説などの創作的な著作とを交互に読んできました。1点の著作を、3~10回程度で読了してきています。著作と著作の間には、小休止的に「推し本」や「上半期ベスト本」等のご紹介をいただいたこともありました。先に4冊目のテキストを読み終えて、10月11日(月)21時より、5冊目のテキストの講読を「第5期」として始める予定でいます。
以下、10期までの実績と予定について記述します。
①宮本輝『錦繍』
②若松英輔『本を読めなくなった人のための読書論』
③アリソン・アトリー『時の旅人』
④竹田青嗣『中学生からの哲学「超」入門』
⑤須賀しのぶ『革命前夜』
===以下は「予定」です。一部修正しました。===
⑥斎藤幸平『人新世の「資本論」』
⑦岩城けい『さようなら、オレンジ』
⑧河合隼雄『こころの最終講義』
⑨ハインライン『夏への扉』
⑩橋爪大三郎『人間にとって教養とはなにか』
※基本的に、文庫ないし新書で提供されているものを選んでいます。
4)結びにかえて
機会を捉えてご案内さしあげておりますが、9月下旬に、noteとDiscord、clubhouseを相互乗り入れさせたサークル「読書の杜」としてリニューアルさせました。年内は「試験運転」期間と考えております。読書を通じ、読書を介したコミュニケーションを図ることで、私は私自身の可能性を引き出せるようでありたいと考えています。しかしながら、最優先させたいのは、「楽しい」という感覚の追求です。その都度その都度に、ご参加くださる方々のご意見をうかがいながら、より充実した運営に向けて注力してまいりたく存じます。どうぞご指導賜りますよう、お願い申し上げます。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
