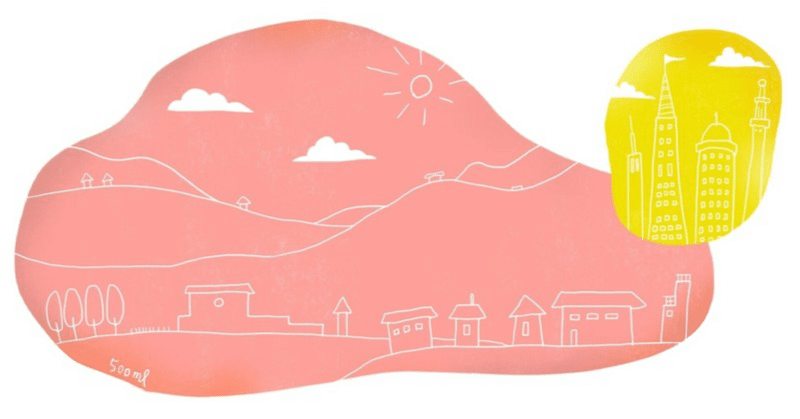
Photo by
lisa500ml
『コミュニティデザインの時代』山崎亮
この前読んだ『来るべき民主主義』の中で紹介されていた本。最近読む本はだいたい数珠つなぎのように、関連する本が多くなっています。少し前の本ですが(2912年9月初版)、でも書いてあることは十分いまに通用しそうです。
まず面白いなと思ったのが「適疎」という考え。
いまの日本の人口減を嘆く声が多いけど、長い歴史で見ると1900から2000年手前の人口が急増していた時期のほうが特殊で、むしろ適正な人口に戻りつつあるのでは、という見方。なるほどと思います。多いほうがいいという固定観念ってことですね。
人口が減少していることを嘆くだけでなく、それぞれのまちや流域で生活できる適正な人口規模を見据え、その人口に落ち着くまでのプロセスを美しくデザインすることが肝要である。1920年以降の人口減少を踏まえて「昔はよかった」というばかりでなく、「昔は少し無理をしていた」と考えてみると、さらに長い歴史の中で適正だった人口規模に戻ろうとする地元の将来像がどうあるべきかをポジティブに考えることができるかもしれない。
「昔は少し無理をしていた」と考えられる人かどうか?がとても大事な気がします。
増えることは良いこと、という考えを、違うかも?って切り捨てられる柔軟さ、軌道修正できる素直さが必要なんじゃないかと。
歳を取ると切り替えが苦手になる人、多い気がしますね。
今日はこの辺で。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
