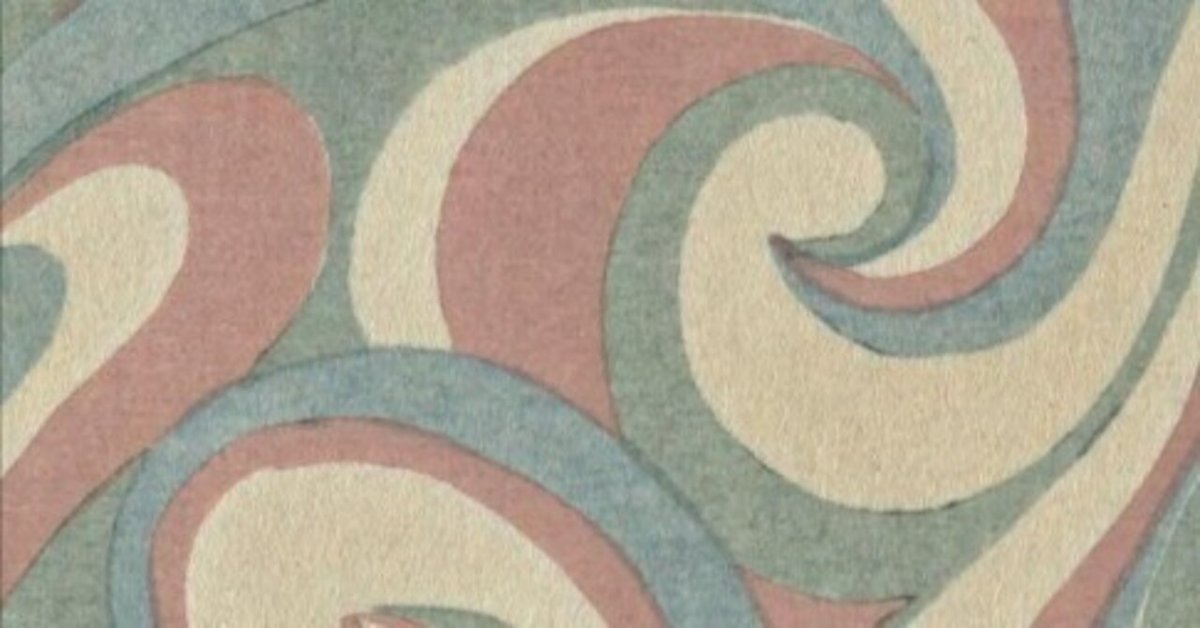
読書感想文:エレガントパズル エンジニアのマネジメントという難問にあなたはどう立ち向かうのか
エレガントパズル エンジニアのマネジメントという難問にあなたはどう立ち向かうのかを読んだ。
原書は、An Elegant Puzzle: Systems of Engineering Managementという本で、どうしても読まなければと使命感にかられて今年の3月に買ったが、日本語訳本が出ると聞いて、待っていたら読めたので本日一気に読み上げた。
目次を読んで想像した期待感
まず、目次を読んで以下のタイトルに惹かれた。
2.4.1エンジニアが増えるほど問題も増える
3.1.1ストックとフロー
4.3.2強い関係性はどんな問題にも勝る
4.3.4困難なことからすぐに取り組む
5.6.2プログラマーのヒーローをやっつける
この5つの目次から想像するに、人が増えた時のことを考える必要性と、著者がシステム思考を意識していることに気づいた。また、関係性構築を重視する身としてはそのバランスも気になるところだ。
優先度が高い箇所こそ一番忙しいと想像しがちなので、困難なことからすぐに取り組む必要性に想像が向いた。また、「ヒーロー」とあるのはハードワークとバーンアウトのことかと気にしながら読んでみた。
全体の感想
まず、日本語訳がとにかく読みやすい。
スルスルとつまることなく頭に入りやすい文章だった。注釈も丁寧で、なるほどそういう意味なのだと感じることができたし、QRコードをこれでもかと参考リンクを載せていたので、リンクに飛びつつ読むことができた。
3章まではサクサク読めて、4章の「アプローチ:問題解決につなげる」は、実践の難しさから読み進めるペースが一気に落ちてしまった。この章は、私にとっては視座が高く、実体験と丁寧に内省する必要があった。
速度に関する議論の最高のアウトカムは、重要な制約に取り組むための現実的なアプローチを特定することだ。
たとえば、上記もその手前の制約の話や冒頭のポリシーと例外の説明を踏まえると、一貫性を保つ難しさが想像できる。また、優先順位と文書化の重要性は理解しているものの、実施となると難しい。
6章は採用の話が多く、身近で採用ファネルの話は実践しているとうなずくしかなかった。また、新しい職種を作る時の考え方は参考になった。参考文献も日本語で読めるものが多く、読んできたものもあって身近に感じた。
身近といえば、技術的負債とマイグレーションの話(3.6.1 なぜマイグレーションが重要なのか?)は、インフラエンジニアを経験した身としては、確かに重要な手段だったなとこの本の視点で改めて実感した。
4.3.2強い関係性はどんな問題にも勝る
目次で期待した項目よりこの段落のページは全てにハイライトをつけた。
チーム内部の問題のほぼすべては、関係性の欠如や悪化に帰着し、すばらしい関係性があれば何でも一緒に解決できるだろう。
関係性を重視する行動を心がけていた身としてはうれしくなる言葉だ。ただ、後半で.関係構築に時間を使いすぎることに警告もしており、さまざまなことを担当するEMならではの優先度づけに思った。
他にも採用の時間配分も重要だとしつつも、かける時間は短時間に収めるような配慮や面接も負担の見直しを図るなどスケジュールと優先度のバランスが本書のところどころで顔をだす。
さいごに
一番心に響いた文章を引用する。
より経験豊富なマネジャーは次のようにして行き詰まることが多い。1.前の会社でうまくいったことをする。新しい仕事を始めたり新しい役割に就いたりしたとき、すべてを「修正」し始める前にいったん立ち止まり、耳を傾けて理解を深めよう。
必ず現場の声を聞く。信頼性構築に努める。でも、会社規模に応じてきちんと成果を残す。この本にあることを参考にしたいが、そのままの輸入には注意をしたい。きちんと自分の中に落とし込んだ上での選択肢だ。
本書は、チームの人数の最適化にも細かいレベルで経験からくる実践知が盛り込まれている。そこが魅力であり、だから6〜8人のチームをとなるが、盲目的にならず人数についても現状を把握して捉えたい文章と感じた。
あと、「悪いゴールは、単なる数字と区別がつかない。」という文章も響いた。用語だと、スキップレベル1on1という言葉は知らなかったので覚えて本書にある使用タイミングを意識していきたい。
このように読書感想文を書いてみて本書の良さに再度気づくことができた。
参考画像:https://dl.ndl.go.jp/api/iiif/1182502/R0000013/2288,768,1068,1760/,800/0/default.jpg
