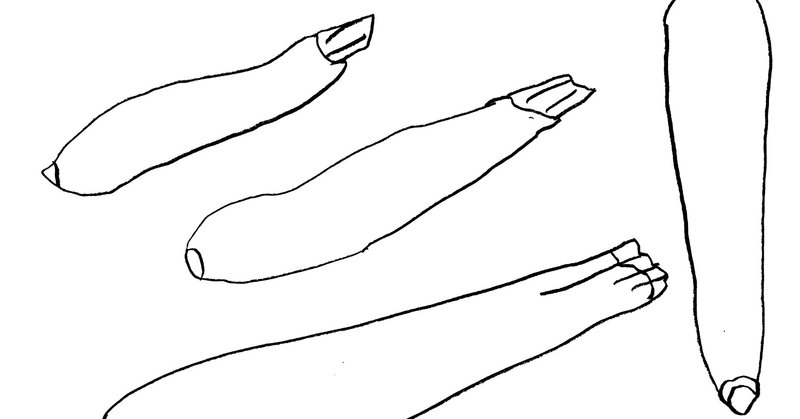
『働くことの人類学【活字版】』 第5話|逃げろ、自由であるために 中川理
コクヨ野外学習センターの人気ポッドキャスト〈働くことの人類学〉の単行本『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』から、【第1部】働くことの人類学の全6話を特別有料公開。

『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』
松村圭一郎 + コクヨ野外学習センター 編
出演:柴崎友香/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理/久保明教
コクヨ野外学習センターが贈る人気ポッドキャスト〈働くことの人類学〉待望の【活字版】登場。
もっと自由で人間らしい「働く」を、貝殻の貨幣を使う人びと、狩猟採集民、牧畜民、アフリカの零細商人、アジアの流浪の民、そしてロボット(!)に学ぶ。文化人類学者による目からウロコの8つの対話。仕事に悩めるすべてのワーカー必読!絶賛発売中です!
◉書籍の購入はこちら
*
第5話 逃げろ、自由であるために 中川理
国境を越えて移動し、世界中で暮らすモン。
フランスや南米の仏領ギアナなどで暮らすモンとともに
フィールドワークされてきた中川理さんに
その「トランスボーダーな生き方」を学びます。
Illustration by Tomo Ando
中川理︱なかがわ・おさむ
国立民族学博物館准教授。フランスや仏領ギアナをフィールドとして、人びとと国家とグローバリゼーションの関係について研究。最近の仕事として、『移動する人々』(共編著)、『文化人類学の思考法』(共編著)、『不確実性の人類学』(アルジュン・アパドゥライ著・翻訳)など。
松村 中川理さんは、若林さんに推薦文を寄せていただいた『文化人類学の思考法』(世界思想社)を一緒に編集した方で、私より少し先輩にあたるんですが、ずっと刺激を受けてきた尊敬する人類学者のおひとりです。 中川さんは長年フランス南部でフィールドワークをされてきて、いまはフランス南部にいる東南アジア出身のモンの人たちを研究されています。この対話シリーズは、第1話の深田さんがオセアニア、そのあと3話続けてアフリカの人たちの話が続きましたが、ここで取り上げるモンの人びとは、まだ取り上げていない東南アジア、ヨーロッパ、南北アメリカに暮らしています。
もともとラオスなどに暮らしていた人たちが、なぜ世界中で暮らす状況になったのかというところから聞いてみたいと思います。まずは、中川さんのモンの人たちとの出会いなのですが、最初南フランスに行かれたのは、モンの研究をするためではなかったんですよね? そのあたりの経緯からお話しいただけますか。
モンの数奇な運命
中川 これまで登場した人類学者の方々と違って、私が研究対象であるモンの人たちと知り合ったのは比較的近年のことです。松村さんから紹介していただいたように、私は長年フランスで調査をしてきたのですが、博士論文はフランスの相互扶助アソシエーションについての研究でして、モンについての調査は最近始めた感じです。
これまでの4人の方々は、研究者として自己形成をしている学生時代にそれぞれ対象としているフィールドの人たちと出会っているので、対象とする人たちの世界が骨の髄まで染みついている感じがあったと思います。私の場合は40歳になろうかという頃に、いまの調査対象であるモンの人びとと出会いましたので、なんというか中年になってからの新しい発見のようなところがあります。
これまでのみなさんも、偶然に自分の研究対象と知り合ったという話をされていたと思いますが、私の場合も同様で、モンの人たちとの出会いはまったくの偶然でした。モンの人びとを集中的に調査するようになる前は、南フランスで農民の調査をしていました。フランスの農民というと伝統的な土着のフランス人というイメージがあるかもしれませんが、南フランスの農民社会は、実はさまざまな移民が次々に入ってきて形成されてきました。フランス人の農民がいて、その後イタリア人、スペイン人、ポルトガル人が入ってきて、マグレブ人、主にモロッコからの人びとが入ってきて、結果として多民族的になっています。そんな彼らが、いったいどんな社会を形成しているのかということにすごく関心があったわけです。
松村 なるほど。
中川 その研究をする上で一番注目したのが市場でした。南フランスのアヴィニヨンの近くに、生産者が仲介業者に農業生産物を直接販売するとても大きな市場があります。私はそこに通ってさまざまな人にインタビュー調査をするようになりました。そして、その市場で、以前からなんとなくその存在について聞いていた、私と同じような顔をした人びとに偶然出会ったんです。特に、市場のなかでズッキーニを売っているあたりに、その人たちがたくさんいた。
最初は警戒感から、あまりうかつに近寄らないほうがいいかな、と思っていたのですが、向こうから知らないことばで話しかけられて、「いやいや、私はあなたたちと同じ民族じゃないよ」と。でも市場に通ううちに次第に「お前は、なんのためにここに来ているのか」と聞かれるようになって、徐々にやりとりが生まれたんです。
最初の頃は、多民族からなるフランス農民の一部としてモンの人びとについて研究を始めたのですが、研究を進めるうちにどんどん興味が出てきて、2015年あたりから、しばらくのあいだ集中して研究してみようと決意して調査を始めたという流れになります。
松村 モンの人たちは、歴史的にはどの辺りに暮らしていて、そもそもなぜフランスの農村で生活するようになったのでしょう。
中川 モンの人たちは数奇な運命を辿っていまして、ノマドのように色々な土地を渡り歩いて暮らしてきました。もともと、といっても歴史に残っている限りにおいてということで、それ以前を遡ると実態がよくわからないところもありますが、中国山間部の貴州省や雲南省に居住していたとされています。
その後の経緯については諸説あります。一般的には18世紀から19世紀にかけて東南アジアに向けて移動し始め、ベトナム、ラオス、タイにまで移動して住むようになっていったと考えられています。そして山地の高いところに住んで焼畑農耕をするようになった。彼らが中国から出ていったのは、戦争に巻き込まれて逃げたり、焼畑の土地を求めて移動したりとさまざまな理由がありますが、徐々に中国から南下して山間部のあちこちに点在して住むようになっていったわけです。
では、なぜ東南アジアからフランスにまで来るようになったのかというと、そこにはラオスの内戦が大きく関わっています。1953年に始まった内戦は、最終的には1975年に社会主義国のラオス人民民主共和国が樹立されるまで続きました。モンの人びとの多くはアメリカ側につき、反社会主義勢力としてゲリラ戦争を戦いました。そのため、最終的に社会主義側が勝利した際、多くのモンの人たちは難民化しました。直接的に戦争に関わった人もそうですし、関わらなかった多くの人も難民となって、メコン川を渡ってタイ側に逃れました。
タイ側に逃れ、1975年から80年代までの数年間をタイの難民キャンプで過ごした後、モンは難民として色々な国に渡ったんですね。多くはアメリカに移住しました。10万人単位の規模でアメリカに移住したのですが、ラオスの旧宗主国ということもあって、1万人ほどがフランスに難民として移住していったというのが大まかな流れです。
松村 一番多いのがアメリカで、その次がフランスと考えていいですか。
中川 そうですね。
松村 中川さんはいま、フランスだけではなくて仏領ギアナなど他の地域にいるモンの人たちの調査もされていますよね。その地域に住んでいるモンの人たちも、同時期に一斉に国境を越えていったんですか? それとも別の時期になるんでしょうか。
中川 移住については色々なパターンがあります。仏領ギアナに関して言うと、初期の難民はフランスに滞在せずに直接仏領ギアナに行きました。この人たちは飛行機で難民としてフランスに運ばれて、いったんパリに着陸はしたものの上陸せずにそのままギアナに渡っています。
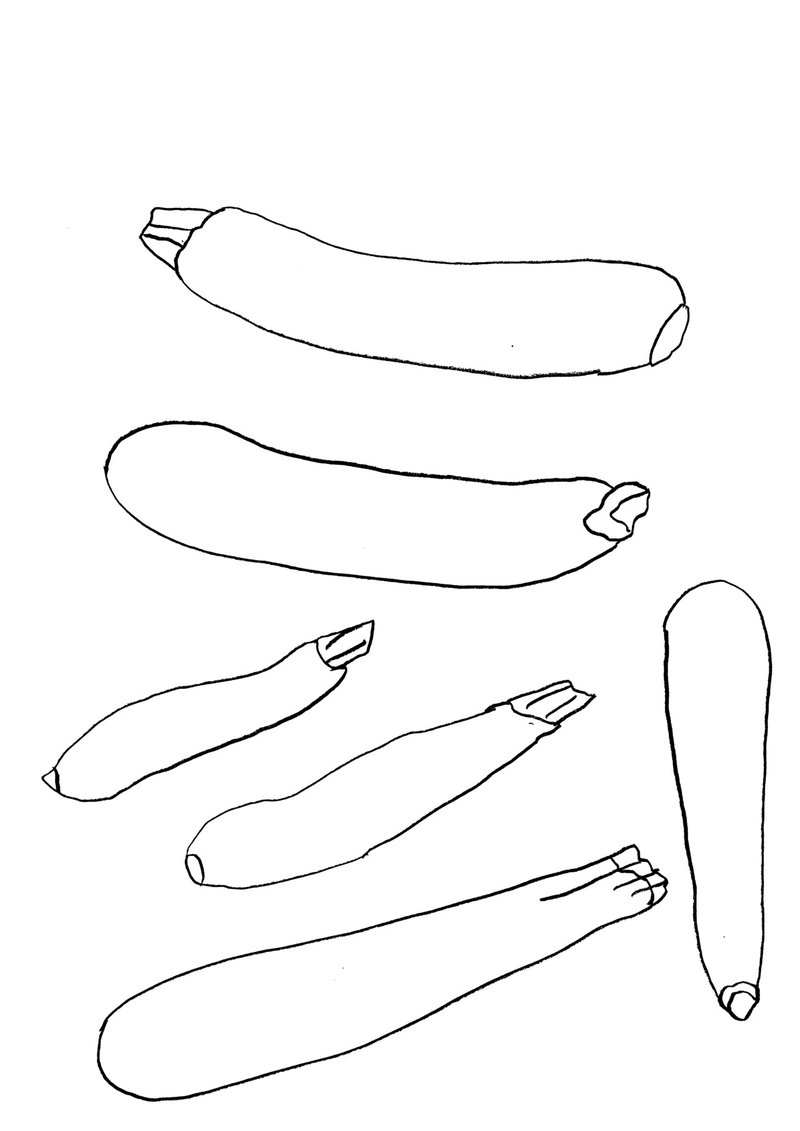
松村 仏領ギアナって、ブラジルの北にあるんでしたっけ。
中川 仏領ギアナは、ブラジルのすぐ北側、赤道に非常に近い、熱帯にあるフランスの海外県です。一部のモンは一夜のうちに何もないジャングルのただなかに連れていかれて、一から開拓してそこで住むようになりました。
面白いのは、そうやって仏領ギアナや、フランス、アメリカに定住した人たちも、いったん定住したらずっとそのままそこで暮らすのではないということです。そこから二次的、三次的移住をする傾向があります。この話はまた後で出てくるかもしれませんが、彼らはいったんある国に落ち着いたとしても、その後も色々と移動しながら生きていくことが多いんです。
松村 2020年にアメリカで起きた「Black Lives Matter」運動の契機となったジョージ・フロイド殺害事件に関連して、「モン」ということばを耳にした方も多かったと思うのですが、そもそもモンの人たちは歴史的にあまり表舞台には出てこなかったイメージがありますね。フランスにたどり着いたモンの人たちの暮らしはどうだったのか、そこから教えていただきたいのですが、モンの人たちは移住先のフランスでは、当初どんな仕事をしていたんですか?
中川 彼らがとにかく早く自立して生活していけるようにするのが当初のフランス政府の方針でしたから、職業訓練や言語訓練は本当に短い期間しかやってもらえなかったそうです。ですから多くの人は、非常に短い適応期間を経て、全国の中小都市に送り込まれました。
そこでどういう仕事をするようになったかというと、単純な工場労働者です。タイヤや車をつくっているフランスの有名企業と言えばすぐに、みなさんいくつかの名前が頭に浮かぶと思いますが、そういった企業の工場で流れ作業の一部をやる仕事に就いていったわけです。もちろん、それはやむを得ないことでもありました。
戦争中、ちゃんとした教育を受けられなかった人たちが難民としてやってきた。一部には師範学校を出てフランス語ができる人もいましたが、それはごくわずかでした。ほとんどの人はフランス語もできない、なんの技能ももっていない人たちだったわけです。そういった人たちを手っ取り早く生活できるようにするためには工場労働がいいだろうということで、政府の方針で全国の工場に就職先を見つけて送り込んだわけです。
松村 フランス南部でズッキーニをつくっている農業地帯に暮らすモンの人たちは、最初から農業に関わってきたわけではないんですね。
中川 そこがひとつ面白いところだと思います。当初は工場労働をさせられたわけですけれども、一部のモンの人にとって、それはすごく耐え難いことだったんです。その理由は「モンらしさ」と関わっていると考えることができます。
ジェームズ・C・スコットの『ゾミア:脱国家の世界史』(みすず書房)という有名な本のなかでは、東南アジアの山岳地帯に住んでいる人たちは、ヒエラルキー関係を極端に嫌う存在として描かれていますよね。モンをはじめとする山地民は、支配される、あるいは命令されるという関係を非常に嫌って、平等主義的な社会を望んできた。だから、彼らが高地に暮らしているのは、平地を追われたからではなく、むしろ、より自由な生き方を求めて、自ら望んで山に入っていった結果なのだとスコットは考えました。この議論には学問的により精緻に論じなければならないところはあるのですが、非常に面白い考え方だと思います。
というのも、この見方は、実際にフランスにやって来て工場で働くようになったモンの人たちにうまく当てはまるところがあるからです。つまり、工場での単純作業労働は、どうしたって命令に従わなければならないものですし、決まったリズムで働かなければならないものです。それが多くのモンにとっては、耐え難い経験だった。その経験を彼ら自身は「奴隷をする」ことだったと語ります。
親族をツテに新しい場所へ
中川 私自身は工場で働くモンの調査はしていませんが、調査をした人の論文を読むと面白いエピソードが色々と出てきます。例えばモンの単純労働者が「給料を上げてくれ」と言うのですが、その理由は「私たちは命令を聞くという苦行をしているのだから、その分、給料を上げてもらうのは当然である」という、私たちには思いつきそうにないものだったそうです。つまり、命令を聞いた分だけ補償をしてくれ、と彼らは要求をしたわけです。私たちなら「命令を聞く立場なのだから給料が安いのは仕方がない」と思うところです。
もちろん工場で働き続けた人たちもいるわけですけれども、一部の人たちは我慢ができず、そのうちのひとりが南フランスで土地を得て、農業を始めました。すると、農業によって、これまでの工場労働よりもずっとモンらしい生活というか、人に命令されない自由で独立した暮らしに近いものを実現できることがわかった。ひとりが成功して「農業がいいらしい」と噂が広まって、工場で働いていた人たちの一部が「じゃあ俺も行こう」「俺も行こう」と、次々と農業をするために南フランスに移住していきました。
ちなみに、こうやってすぐに噂が伝わることをフランス語の表現で「アラブの電話(téléphone arabe)」と言いますが、それになぞらえてフランスのモン自身が「モンの電話」と言ったりします。まさに「モンの電話」ですぐに噂が広がったわけですね。
当時モンの人たちが入っていった南フランスの地域は、もともとはブドウや桃などの果樹の生産地だったのですが、栽培がうまくいかず生産をやめてしまった耕作放棄地がたくさんあり、そうした土地に、モンの人たちがどんどん入っていったわけです。
松村 それはいつ頃ですか。
ここから先は
¥ 300
