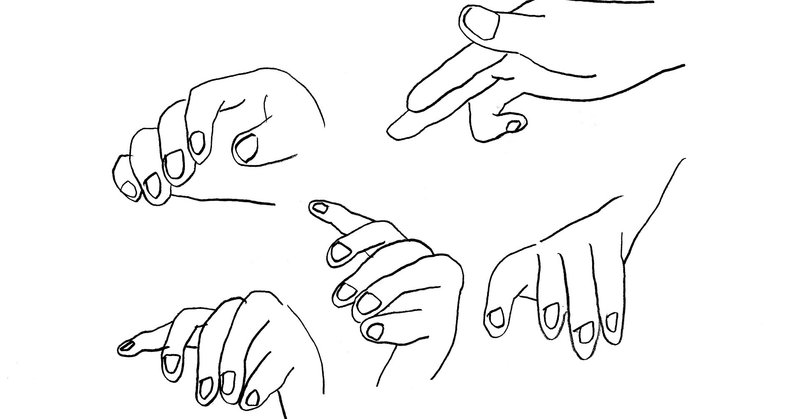
『働くことの人類学【活字版】』 第6話|小アジのムニエルとの遭遇 久保明教
コクヨ野外学習センターの人気ポッドキャスト〈働くことの人類学〉の単行本『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』から、【第1部】働くことの人類学の全6話を特別有料公開。

『働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話』
松村圭一郎 + コクヨ野外学習センター 編
出演:柴崎友香/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理/久保明教
コクヨ野外学習センターが贈る人気ポッドキャスト〈働くことの人類学〉待望の【活字版】登場。
もっと自由で人間らしい「働く」を、貝殻の貨幣を使う人びと、狩猟採集民、牧畜民、アフリカの零細商人、アジアの流浪の民、そしてロボット(!)に学ぶ。文化人類学者による目からウロコの8つの対話。仕事に悩めるすべてのワーカー必読!絶賛発売中です!
◉書籍の購入はこちら
*
第6話 小アジのムニエルとの遭遇 久保明教
ロボットやAIを人類学の立場から研究されてきた
一橋大学の久保明教さんをゲストに
「テクノロジーと共に働くこと」について考えます。
Illustration by Tomo Ando
久保明教︱くぼ・あきのり
一橋大学社会学研究科准教授。主な著書に『「家庭料理」という戦場:暮らしはデザインできるか?』(コトニ社)、『ブルーノ・ラトゥールの取説:アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社)、『機械カニバリズム:人間なきあとの人類学へ』(講談社選書メチエ)など。
松村 久保明教さんは私が編集した『文化人類学の思考法』(世界思想社)のなかで「コラーゲン、プルプル」の章を書かれた方です。非常に切れのいい鋭い文章を書かれる方で、『ロボットの人類学:二〇世紀日本の機械と人間』(世界思想社)、『機械カニバリズム:人間なきあとの人類学へ』(講談社)、『「家庭料理」という戦場:暮らしはデザインできるか?』(コトニ社)など、本もたくさん出されていて、テクノロジーに囲まれた私たちの現代的な状況をテーマに人類学の観点から研究されています。シリーズの締めくくりとなる今回はこれまでの回を振り返りつつ、私たちに身近な状況に引き寄せながら「働くこと」を考えていけたらと思っています。 人類学では近年、「科学技術の人類学」という分野が注目されています。これまでの対話は、どこか遠いところに住む人を対象にする研究者が多かったですよね。人類学というと、一般的に現代化された私たちの暮らしとは異なる人びとを研究する学問というイメージがあったと思うんです。でも久保さんはあえて日本の文脈において、なかでも人間ではないロボットや人工知能や機械を人類学の研究対象にされてきました。なぜそうしたものを研究対象とされたのか、まずは、そこからお伺いしたいと思います。
久保 はい。よろしくお願いします。僕は、大学院に入って人類学の勉強を始める少し前ぐらいから、クロード・レヴィ=ストロースの神話論(『神話論理』)に触れていました。南アメリカで古くから語られてきた神話では、技術や制度、慣習といった、この世界に存在するものの起源が語られる場面において、動物と人間が話し合ったり、騙し合ったり、結婚して子どもが生まれる、といったモチーフが繰り返し現れます。神話だけでなく、人類学の文献には、例えば「ジャガー人間」や「ハイエナ人間」のように、動物と人間が交ざり合った存在が両者の間をつないでいるという事例が豊富にありますよね。それらを横目で見ながら身近なところを考えてみたときに、現代社会におけるロボットやAIも似たような存在なんじゃないか、つまり 動物と人間の間を「動物人間」がつないでいるように、機械と人間の間を「機械人間」がつないでいるのではないか、と考えるようになったわけです。
そもそも、ロボットにしてもAIにしても、単なるハードウェア、プログラムだと考えれば、別にわざわざ「ロボット」とか「AI」と言う必要はないですよね。それらが「ロボット」や「AI」と呼ばれるときには、常に私たち人間と何らかの意味で類似した存在と見なされていますし、そうした存在を媒介にして機械と人間が関わる未来が想像されています。それは南米の人びとが、人間と動物が交じり合った存在を神話において語るあり方と、ある意味で近いのではないか。つまり、非近代的な社会では、人間と動物の関係がしばしば重要な社会的・文化的争点になっていて、そこで良いことも悪いことも起きるわけですが、私たちが暮らす近代的な社会における機械と人間の関係についても同じようなことが言えるんじゃないか、と。そう考えて研究対象にすることにしたわけです。まあ、いまはこのように整理して言えますけど、当時はそんなに体系的に考えていたわけではないです。
松村 人類学というと人間社会を対象に研究する学問というイメージがありますが、もともと神話などでは、人間と動物がコミュニケーションをとったり、人間と人間でないものが交じり合ったりする状況が書かれていて、人類学はそういう対象を研究にしてきた。それがもしかしたら現代の私たちのなかでは、機械やロボットやAIと呼ばれるものなのかもしれない。そう考えると、ちゃんと古典的な人類学の研究の延長線上にロボットや機械の研究もあるということですよね。
久保 うーん、どうですかね。人類学者側はあくまで人間を対象としてきたけれど、研究対象の人びとにおいて人間が人間だけで閉じてなかった、ということじゃないでしょうか。彼らにとっての「人間」というのは、私たちが「人間」だと見なすものに限定されていなくて、ジャガーや精霊のような存在とも交じり合っている。そう考えると、現代のテクノロジーや機械の存在も、たいして違わないじゃないかと思ったわけです。でも、先輩の人類学者から見れば意味不明だったと思いますよ。「ロボットについて研究しています」と言ったら「人類学も終わったな」とか言われるような感じでしたから(笑)。
松村 へぇー、そうなんですね。ロボットやAIを人類学の研究対象にすると言われると、誰もが投げかけてくる質問だと思うんですが、「人間の仕事がやがてAIに奪われるのか」とか「人間の能力をAIが超える時期がやってくるのかどうか」といった問題、久保さんはどう答えていますか。
久保 そうした質問は、授業についての学生からのコメントでも多いですし、よく話題になりますよね。それに対しては、「あぁ、またそれか」という(笑)。
「シンギュラリティ」という仮説は、本来は文明の発展がそこから先は予想できなくなる技術的な特異点が現れるだろうという話なので、一般的に広まっている「機械が知的能力において人間を完全に超える時がいずれ来る」という言い方とはそもそもズレがあると思うんですが、「いずれ機械が人間を代替するのでは?」というのは、おそらく17〜18世紀あたりからあるイメージで、技術が進展するたびに少しずつ異なる仕方であれ、繰り返し喚起されてきたものだと思います。
例えば1920年代、大正時代の日本で「第一次ロボットブーム」が起きていますが、話題の中心になったのは「テレボックス」という、アメリカで開発された遠隔操縦機でした。この機械は周波数の変化によって指令を出せるもので、科学雑誌の特集では、外出中でも電話口で笛を吹くと「テレボックスの女中さん」が煮炊きとか色々な仕事をしてくれる、といったぐあいで未来の生活が描写されています。だから「ロボットが人間の仕事を代替する、奪う」という未来予想は何もいまに始まったことではなくて、これまでも繰り返しなされてきたわけです。
そもそも「ロボット」ということばが広まったのは、人間の仕事を代替するように見える機械が登場してきた時代です。例えば、1920年代のアメリカでは、新たに登場した自動販売機が「ロボット」と呼ばれました。それまでは街中に飲み物を売る人がいたので、自動販売機が登場すると人間の労働を代替する機械であるように見える、だから「ロボット」と呼ばれる。ところが、飲み物を人間が手売りしている記憶が薄れると、つまり、ロボットに代替される人間の労働者のイメージがなくなると、自動販売機はもはやロボットとは呼ばれなくなるわけです。実際、いま私たちは、自動販売機を見てもロボットだとは思わないですよね。
あるいは1960〜70年代には「産業ロボット」と呼ばれるものが普及しましたけれども、現代的なロボットのイメージだと、産業ロボットは主流ではないですよね。つまり、ロボットが人間の仕事を代替するという見方が出てくるのは常に過渡期の状況で、実際に人間の仕事が機械に代替されて、それがもはや人間の主要な仕事ではないということになってしまえば、「ロボットが人間の仕事を代替している」ようには見えなくなる。この流れが、毎回忘れられ、繰り返されているように見えます。
「AIが人間の仕事を奪う」と言われる現象は、「新たな技術の登場によって仕事の環境が変わる」とも表現できるわけです。「ロボット」や「AI」といってもソフトウェアやハードウェアなんだから、技術的な環境が変わるだけで、それに沿って労働の仕方も変わっていくだけだ、と。
ただ、これはやはり、そうした変化のなかでうまいことやっていける人の側の言い分でしかない。うまいこと新しい環境に合わせてやっている人はそう言えるけれども、実際その状況についていけない人からすれば「機械に仕事を奪われた」という言い方も妥当ですよね。
とはいえ僕自身は、「人間と機械が競い合って機械が人間の仕事を奪う」という考え方、あるいは「機械やロボットやAIは道具にすぎないから仕事の環境が変化しているだけだ」という考え方のどちらでもない見方をとっています。このふたつの言い方は、いずれも、「人間の側も機械によって変化する」という視点を欠いているからです。何を人間らしいものとするか、何が働き方として有効なのかということ自体が、人間が機械と相互作用するなかで変わってくる。「人間なるもの」のあり方自体がテクノロジーとの関わりを通じて変化していく。だから、人間と機械のどちらが主でどちらが従でもない、一方がもう一方を支配するのでもない、そうした互いに影響を与え合うような相互作用においてお互いがどう変化してきたのかという観点から、調査や分析を行ってきました。

AIはプロ棋士になれるか?
松村 久保さんが研究されているなかで、人間と機械のどちらが主か従かわからないような形で展開しているものというと、例えば、将棋界におけるAI、つまり将棋ソフトがプロ棋士に勝ってしまうみたいな状況がありますよね。まさにいま、将棋をする能力において人間よりもAIが強く見えるような状況が起きていると思うんですが、これは「AIが棋士よりも強くなっている」と言えるんでしょうか。
久保 それはすごく言い方が難しいですねぇ。将棋ソフトは単体で動いているわけではないので。すごく昔のパソコンを使えば棋士が勝ちますよね。
松村 たしかに(笑)。
久保 あるいは、大量の熱いコーヒーをパソコンにかけてしまえばいい。
松村 (笑)。
久保 でも、じゃあ、なんでそれをしてはいけないのかということですよね。
例えば第2回将棋電王戦では、数百台のコンピュータをつないで並列処理で動かす将棋ソフトが出てきて、実際にめちゃくちゃ強かった。第3回電王戦からは、人間ひとりに対してパソコンも1台であるべきだという意見が出て、複数のコンピュータが用いられるのは禁止されましたが、単一の整合性をもったプログラムを動かすという観点からは、コンピュータが1台でなければならない理由はありません。なぜ1台のパソコンがひとりの人間と同等だと言えるのか、なぜ1人対1台がフェアなのか。考えるとよくわからないですよね。
というのも「ひとりの人間」に相当する明確な単位がコンピュータにはないからです。人間のプロ棋士と将棋ソフトが戦う場面において何がフェアな勝負の条件なのかはあらかじめ確定できない、ということですね。
実際問題として、最新のハードウェアとプログラムによって、トップ棋士を圧倒的に蹂躙するようなソフトはつくれるでしょうし、そんなソフトはすでにあるとも言えるでしょう。でも、「将棋の強さ」をいったいどうやって測るのか、人間と人間以外のもののあいだに、共通する強さの基準があると言えるのかという問題は、簡単には答えが出ません。
たしかに勝負における勝ち負けはわかりやすい強さの基準のように見えますが、人間を測る基準と機械を測る基準がそもそも違うので、プロ棋士と将棋ソフトを対決させることは、「異種格闘技」のようなものにならざるを得ない。「猪木対アリ戦」のような、全然違う基準で測られる強さがぶつかる場合、単に勝敗によってどちらが強いのかを判定することはできない、ということですね。
例えば、第3回電王戦で将棋ソフトに負けた棋士がリベンジを試みるエキシビションマッチが行われて、棋士が将棋ソフトに勝ったケースがありました。そのとき、実際に指している将棋盤とは別に、もうひとつ「継盤」と呼ばれる将棋盤を用意して、棋士は継盤で駒を動かして検討しながら指しました。そうすることでミスが少なくなりますし、戦っている棋士自身が候補手の検討を言語化してくれるので見ているほうも面白かったのですが、電王戦本戦では導入されませんでした。なぜ導入されなかったのかというと、棋士同士の公式戦では継盤など使わず頭のなかで考えているので継盤を使うと正々堂々と勝負しているように見えない、という理由くらいしか思いつかないですね。でも、将棋ソフトは、実際の指し手も候補手の検討も同じ種類のデータとして処理しているわけですから、棋士も継盤を使ってその両方を同じ媒体(将棋盤)で把握するのがフェアだとも言えます。結局のところ、棋士とソフトのフェアな勝負の条件というのは、「1人対1台」とか「継盤は卑怯」といった曖昧な理由で設定するしかなかった、ということかと思います。
あるいは将棋ソフトのほうも、棋士と同じようには戦っていないわけです。将棋ソフトは休憩せずにずっと計算し続けています。でも人間には体力的な限界がある。すると将棋は純粋に知性の勝負のように見えても、実際には「一局の将棋」の区切りをどこでつけるか、という問題が出てきます。
例えば、先ほど話したエキシビションマッチは、大晦日の朝10時に始まって元旦の明け方4時ぐらいに「指し掛け」(対局を中断して後日続ける)という裁定がされました。序盤は一進一退で、日付が変わる頃には棋士側が優勢になっていましたが、ソフトがあきらめの悪い手を指し続けてなかなか終わらせてくれない。プロ棋士だったら、これはもう負けだと思って、お正月だしここら辺で投了か、となるわけですが、ソフトはそういう判断をしませんので、延々と指し続けるわけです。
そうすると、そこで比べられている強さとはいったい何なのか、同じ基準で比べられるものとして考えていいのかという問いが出てくるわけです。ですから、「ロボットやAIが人間の仕事を奪う」というときにも、人間と機械の知性を同じ基準で測って比べられることが前提になっていますけど、そもそも同じようには測れない、ということが問われるようになると考えています。
松村 どんなにAIソフトが出てきても、プロ棋士という仕事が単純に奪われるみたいな話にならないわけですよね。
久保 それも結構、難しいところですよねぇ。例えば、藤井聡太さんがプロデビューしたときに、ある将棋ソフトの開発者の方が、「おいおい、14才でよりによって『AIに奪われる職業ナンバー1』に決め打ちしちゃだめだろ。たぶん10年後、遅くとも20年後には棋士は『食べていける職業』ではなくなる。20年後、34才。どうすんの」といったコメントをして話題になったことがあります。
棋士の方々は、「将棋を指して大半の人間より強いことを結果で証明する」ことによって、具体的には奨励会三段リーグを勝ち抜くことによって、棋士という職業についているわけです。それが棋士の仕事だと言うのであれば、それはたしかにソフトによって代替可能であるように見えますよね。でも、現時点では公式戦にソフトは登場しませんから、対局という最も主要な仕事がソフトに代替されるといったことは起きていませんし、その兆候もいまのところ見えません。そもそもプロ棋士の仕事は何かというと、将棋を指すだけではなく、生中継で対局を解説したり、将棋ファンが集まるイベントで多面指しをしたり、企業の将棋部に招かれて指導対局をしたりもします。そのほとんどの場面で、自らの心身をもって将棋を知り尽くしていて、それについて語れる人物であることが大きな意味をもっています。いまの将棋ソフトは、候補手と評価値しか出してくれないですから、その意味がわからない将棋ファンにとっては、やはり棋士が解説してくれないと楽しめないわけです。

松村 そりゃそうですね。
久保 あるいは、棋士の方は「揮毫」といって、扇子や色紙にかっこいいことばを書きますね。「天衣無縫」とか「百折不撓」とか、普段あまり使わないような漢語を記すわけですが、若いときから書道の指導も受けていて、みなさん書もうまい。タイトル戦ともなれば全国の老舗旅館に赴いて、その地方のお偉いさんたちと歓談し、高価な和服を着こなして対局に臨みます。和服を着こなすことが将棋の強さと関係するとは思えないけど、和服もスーツもうまく着こなせないから、いつも公式戦はジャージです、という棋士はいないですよね。でも、これを機械で代替しようとすると、ちょっとわけのわからない機能の寄せ集めになってしまいます。正座して、たまに胡坐になって、時々立ちあがることができて、和服の着こなしも書もうまい機械というのは現在のロボット工学の水準からいっても難しいでしょうし、さまざまな将棋ファンやお偉いさんたちと歓談できる高度な会話能力を備えたプログラムというのは現在の人工知能研究の水準からいっても簡単ではないでしょう。たしかに「遅くとも20年後には」こうした機能も実現可能になっているかもしれませんが、そんな奇妙な機械を誰が望むのかというとよくわからないですよね。むしろ、将棋棋士という仕事がこれから「将棋を指して強い」という機能にどんどん還元されていけば、ソフトによる代替は可能だと思います。でも、そういう仕事をする人って「将棋はすこぶる強いが、服はいつも同じ、解説に呼ばれても候補手と評価値しか喋れず、勝っても負けても何の感情も示さない」人なんですよね。
人間が行う仕事が、ある入力に対して特定の出力が返ってくるという機械的な機能として捉えられる限り、機械との優劣の比較はできますし、ある職業がそのようにしか捉えられなくなれば、それはたしかに機械によって代替され得ます。でも、私たちが漠然と「仕事」と呼んでいるものは、そういった機能では捉えられない特徴をたくさんもっているのではないでしょうか。
棋士という仕事は、将棋を指して強いだけじゃなくて、和服の着こなしとか、話の上手さとか、将棋とは直接関係ない色々なことが結びついて形になっている。そして棋士だけじゃなくて、仕事というものは結構そういうものじゃないかと思うわけです。
特定の機能で捉えれば、より効率的な機械に置き換わり得るように見えるけれども、実際私たちが仕事と呼んでいるものには、休憩時間の雑談とか、出張から帰ってきたらお土産を配るとか、愚痴や陰口を聞くとか、顧客に笑顔で接するとか、仕事なんだかどうなのかよくわからないものが付随してあって、さまざまな関係性のなかで成り立っている。そのうちの一部のものが、仕事として浮き上がって見えているけれど、仕事というものは、そうしたさまざまな関係性の効果として、特定の機能、入出力が仕事として見えるようになっているということなのではないか、と思っています。
松村 どんなにAIソフトが強くなっても、AIソフト同士が対戦するのを見ても、たぶん全然面白くないわけですよね。
久保 まあ、現時点ではそうですよね。ソフト同士の対局は、いまのところ主に「この手は人間には指せない!」という驚きとか「この手は人間の将棋にも導入できるだろうか?」といった興味のもとで観戦されていると思います。でも、その「つまらなさ」というのは別に本質的に機械が面白さをもっていないということでもなければ、人間は本質的に面白くなる性質をもっているとか、将棋を見ている人は人間の生の感情を見たいんだ、ということでもないんじゃないかとは思います。むしろ面白さというものは関係のなかで生じるわけだから、機械であってもその関係性をうまいことつくれば、面白い対局をつくることはできるんじゃないか、という気もしますけどね。
松村 でも、いま人間がやっているプロ棋士の仕事の大半は、ただ盤上で将棋を指してゲームをする以外のことが占めているわけですよね。例えば、対局のお昼休憩で何を注文したかとか、デザートは何を食べたかとか、みんなそういうことに関心があって、それもまた棋士の仕事の一部になっている。
「仕事」というと、私たちは久保さんが言ったように、すぐに仕事の機能の部分だけを取り上げて、それが機械に置き換わるかどうかみたいな話をしてしまいがちだけれども、そもそも仕事を機能で捉えてしまうことがおかしいんじゃないか、という見方は面白いですね。プロ棋士の「能力」も、単に将棋の強さだけではない。解説がうまいとかしゃべりがうまいプロ棋士もいるように、その「能力」も、盤上での将棋を指すこと以外に広がっているんですよね。
久保 もちろん、将棋が強くなければ棋士にはなれません。でも、棋士を仕事として成り立たせているものは、将棋の強さだけではない。しかも、その「だけではない」ところに何が含まれるのかは、あらかじめ決まっていないんじゃないか、ということですね。
「人間=機械」の意味
松村 プロ棋士も引退まで常に勝ち続けていくわけじゃないですよね。どこかで衰えていくわけで。じゃあ負け始めたらすぐ引退になるかというとそうでもなく、あるキャラクターをもった存在としてみんなに親しまれるプロ棋士もいるわけです。そう考えると、私たちもいま色々なテクノロジーに囲まれて、例えばメールを打ちながら仕事をしていると思っていますが、その部分が本当に仕事なのか?仕事の能力ってなんなの?という問いが生まれそうですよね。
ここから先は
¥ 300
