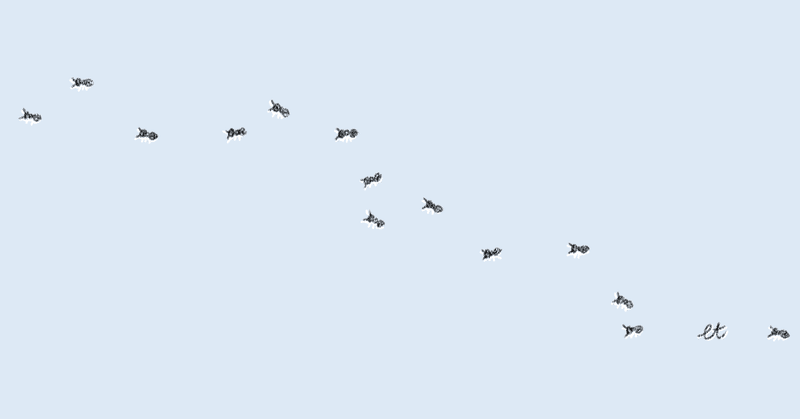
働かないアリに意義がある (メディアファクトリー新書) 新書 – 2010/12/31
人事の人たちと会話していてときどき話題に出る「2:6:2の法則」。組織や集団は「優秀な2割」と「平均的な6割」と「貢献度の低い2割」で構成されるという説(経験則?)で、どこまで検証されているかについては不勉強ですが、組織マネジメントを経験してきた人なら直感的にうなずけるところがあるかと思います。
本書は、この「2:6:2」が、人間社会だけでなく、働き者というイメージのあるアリ社会にも当てはまるという話から始まります。あちこち忙しく動き回っているように見えて、実は2割くらいはたいした働きをしていないという話。そして興味深いのは、働かない2割を取り除いても、残りのアリたちが再び2:6:2の構成比になっていくというところ。あれ? そこも何となく私たちに身に覚えが…。
われわれ人間社会における企業という組織内では、しばしば「組織の筋肉質化だ」といった掛け声が飛び交います。生産性向上の名のもとに、無駄をなくそうと経費削減プランを実施したりします。そして最後の矛先は人件費。採用の凍結はもちろん、場合によってはローパフォーマーを解雇したり、子会社に押し付けたり…。でも、上記が真実なら、苦労して下の2割を切り落としても意味ないじゃん…。どうやら結論から言えばその通りらしく、私たちは、もっと知恵を使っていかねばならないことに気づかされます。
ではどうするのか? 話は少し逸れ気味ですが、解法としては「多様性」とも結びつく話題のような気がしています。要は、漠然と優秀かそうでないかといった単軸しか測れないモノサシでは、もはや実態を把握しきれない事態が起きているということ。言い換えると、一見すると下の2に属する社員たちも、新たに据えた別軸に沿ったモノサシを当ててみたら突出している者たちが混ざっていることを発見できるかもしれない…ということです。
たとえば、製品企画部署でなかなかパフォーマンスを発揮できなかった社員が、実は官公庁からの転職者だとわかり、行政とのパイプ役を探していた他部門にとっては貴重な人材になったとか。あるいは、前職が流通業界で渉外業務を担当していたので、同業界とネットワークづくりを進めようとしていた営業部署には喉から手が出る人材だったとか。
こうした話なら特に目新しくないですが、たまたま上司同士が仲が良かったなど、ほとんど偶然に頼ってきたところが大きいのではないでしょうか。タテ社会傾向の強い日本企業では、こうした偶然を待つ仕組みだけなので、ほとんどの才能と情熱は埋もれたままになります。つまり、多くの社員が持つ能力や意欲は、発見されることなく闇に葬りさられているのです。
確かに、昭和時代なら、そんなことはやりたくてもできませんでした。でも今なら技術的には可能でしょう。「わが社にはどんな社員がいるの?」について精緻に認知して管理する方法はすでに存在していて発展していくばかりです。この流れは決して後戻りすることがなく、あとはどういうスピード感で取り組んでいくかだけが各社の論点になるのだろうと思います。
社員のタレント情報を蓄積することと並行して、上述のようないわば評価軸をどんどん追加していく。すると複数の2:6:2が浮かび上がってくるはずです。どこまでいっても2:6:2であることは自然の摂理ですが、これまでの極めて雑な人単位の2:6:2から、一人の社員の中に内包されている細かい業務熟練度の2:6:2へと移行していきます。そうすれば、社員個々の「上の2」に注目した業務アサインが可能になり、組織全体としてのパフォーマンスは上がっていくという理屈です。
企業としては、せっかく縁があって仲間になってくれた社員ですから、シンプル過ぎる評価軸の中で優劣を語るよりも、複数視点で人材を語れるようになりたいものです。植物に例えれば、実だけでなく、葉も茎も根っこも食べられるというまさに無駄のない人材のエコロジーシステムが作れるのではないかと妄想します。繰り返しですが、そういう技術はすでに存在していて、それをうまく活用できた企業・組織だけが、向こう5年10年30年を生き残るのではないかと想像しています。さらに、そういう企業が日本の産業をリードしてくれるのではないかと思っています。
働き手の立場に向けた言い方に変えると、誰かの空き時間を有効活用したUberEatsが生まれたように、また、誰かの家の空き部屋を有効活用してAirbnbなどが成り立っているように、今いる場所であなたが発揮し切れていない”才能と情熱”を、地球のウラの誰かが求めているかもしれない…。そんな表現するのは果たして大げさでしょうか?
(おわり)
※絶版になってしまったようですが、文庫で復刻版が出ているみたいです。
bizlogueではYouTubeでも情報発信を行なっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
