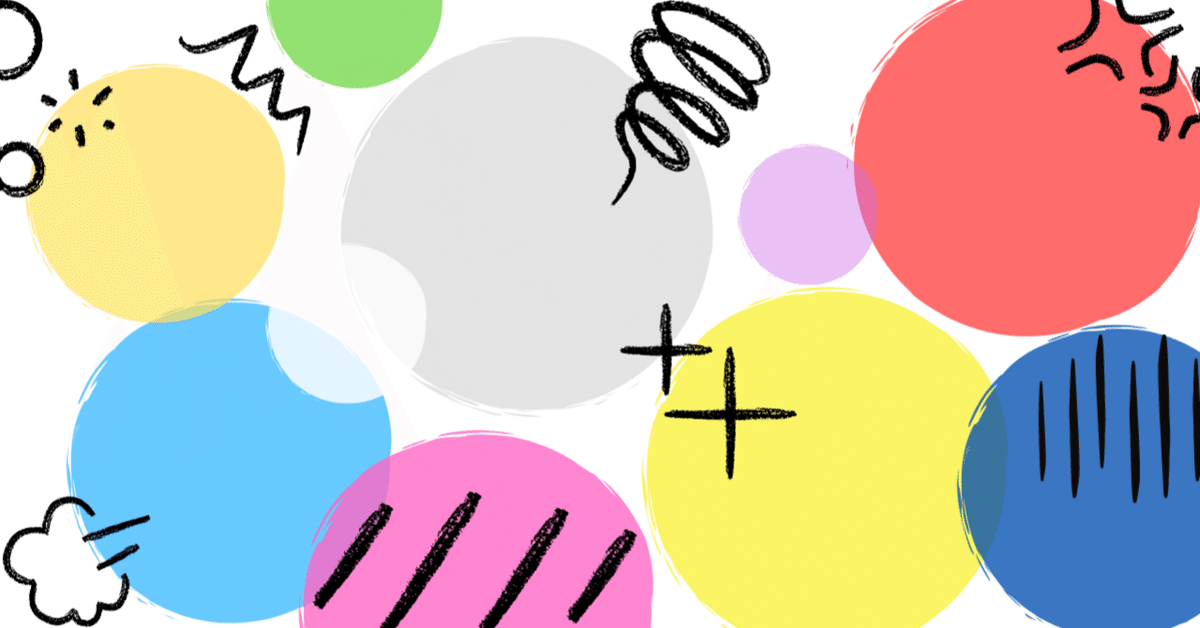
数年越しのモヤモヤが、やっと解決したけれど、今は気力がソレどころではない話。
この度、やっと霧が晴れました!
だけど、この件は もうおしまいで良いかなぁ…今は疲れ果てています。
すっかり気力が萎えています。
いつか気持ちが上昇したら、その時のために、ここに書き記したいと思います。
改めまして、結構しつこい性分の、焼菓子店のBitteで焼いている人です。
焼菓子店ということは、ベーカリーではありません。
初めて行動を起こしたのは、何年前のことだったか…もう、それすら忘れてしまっています。
それから疑問が生じるたび、幾度となく問い合わせをしていました。
が、返って来る返答は変わりません。
確かに法律が変わらなければ、その返答もまた変わることなどあり得ません。
解っていても、あぁまたか…その返答、文言はしっかり記憶に刻まれましたょ。
初めての税務署。
4~5年くらい前のことだった…かも知れない。
当時の知人から「そもそも菓子屋が酵母を起こす行為自体も、そのうえ商品にして販売するなんてこと、禁じられているはずだよ。調べてごらん」
そう言われたことから、この話は始まります。
それに係る管轄、それは税務署でした。
何だか敷居が高い…でも謎の究明だからと、税務署の門をくぐりました。
私が聞きたい内容は…一般的な税務相談とは違います。
受付で相談内容を話すと、別室へ案内されました。
最初に対応して下さった署員の方と、その署員に呼ばれた上司と思しき方が、私の相談に耳を傾けてくれました。
「あの…私、菓子店をやっているんですが、その…菓子の種類の中でも酵母を使うものもあるんですね。その際、既成の市販されているイーストではなくて、酵母を自分で起こして、あのぉ…世間では天然酵母とか言われているんですが、それを使って菓子を焼いて販売することは法律に触れるんですか?違法行為になるんですか?
実は知り合いから「酵母を起こす行為自体が違法だ」と言われまして、それを知りたくて来ました」
このような言い方をしたかも知れないし、もっと意味が不明の表現だったかも知れない。
すると…法規法令が書かれている分厚い書物のページをめくり、
「ココ、ここに書いてある通りなんですよ」と、指を指しながら言った。
(酒税法 第三条24号)
はぁ。
何だか解り難いけれど、ここに記されている業種は酵母を起こして製品化を認められているが、以外は、つまり菓子店は許されていないことは理解しました。
そうなんですね…。
良い人に出会った。
それから、その税務署の方、特に上司の方は1時間以上も腕を組んだまま、宙を仰いでフリーズしていました。
そして「ハッ!」っと閃いた、その瞬間、ムックと体勢を変え、私に「パン、焼けますか?」と聞きました。
私、「はい」。
「だったら、パンを店頭に置いて下さい。こちらが自家製の酵母で焼いたパンです。そしてこれはパンと同じ酵母で焼いた焼菓子です。
このように税務署員がいつでも理解と納得ができるようにしておいて下さい」と言ったのです。
業種はベーカリーではありません。
菓子店です。
しかしパンを並行販売することで、一部ベーカリー部門と言う体裁を保持し、同時に自家製酵母の使用を菓子に於いても可能にすると言う、限りなく黒に近いグレーな提案をしてくれた。
こう言うかたちで、私の希望が叶う方法を導いてくれたのです。
市民に寄り添い、疑問解決と希望へ向けて共に考えてくれる、
良い方々に巡り会えて嬉しかったことを覚えています。
もちろん、感謝の思いは今でも続いています。
知恵を携え、人の気持ちに沿える人。
私も、そういう人になりたいと今でも思います。
再び、ナゾ解明にアクション!
あれから数年が経ち、今は再び、パンを焼かない菓子屋のBitteになりました。
また最近、再び謎が噴出したのです。
な!な!なんと!自家製酵母で菓子を焼く専門店の存在を知ったからでした。
何故だ~??
私は「パンを焼く」と言う〝裏の手法〟で許可されたと認識していました。
同じ国内で、同じ法律下にいるはずなのに、
一方では正々堂々と自家製酵母菓子専門店と謳っているではないか?
一瞬、もうこの問題に触れることはやめておこうか…と思ったけれど、
何故?の謎が、気になって気になって…。
気が付いたら、再び税務署へ電話を掛けていました。
4~5年前の最初の疑問から始まって、今回の質問に至るまで、長い長い経緯を話す…延々と話す…もうそれだけで疲労なのですが、謎の解明のため。
終盤になって、やっと、「同じ国内の同じ法律の下にいて、同じ業種でありながら、片一方ではパンを焼き、もう片一方では発酵菓子専門店と堂々名乗れているのは、どうしてですか? 菓子店が自家製酵母を起こして商品製造販売の可否を、知ってしまった者は不可能になり、知らなかった場合は許されるのですか?」
怒涛の如く言葉が溢れた。
今回もまた何人かの人に、同じ話を繰り返し、繰り返し…。
そしてやっと明快な回答が、しかも私に都合の良い返答が得られたのです。
自分に都合の良い言葉、信じて良いのかしら~?
この質問に、返って来た答えは…
「酒母(しゅぼ)というものがありましてね、その酵母が酒造のための酵母作りか?または酒造を目的としない、あくまでもパンを焼くため、または菓子を焼くため、酒造以外を目的とした酵母作りか?そのあたりの見解ですね…。」
私は「酒造を目的としていないなら、菓子店であってもパンを焼かなくても、自家製酵母の菓子です!と、名乗って良いのですね?」
幾度も幾度も念を押していました。
勿論、最後は感謝と御礼の思いは尽きなかった。
電話を終えて…
あら~!この数年、何だったのかしら?
それより、こんなにあっけなく自分に都合の良い言葉が返って来るなんて…
法律、変わったの?
この返答を鵜呑みにして、信じて良いのかしら?
え?私、疑り深いイやな人かしらぁ??
結局のところ皆モヤモヤしてる。
それから、ほかの人はどうしているか?を、ネットでクルクルと検索してみました。
すると、何ということでしょう!
多くの人が、同じように悩んでいることを知ったのです。
偶然にも私が税務署の方から聞いた返答と、ほぼ同じ内容が書かれていたので拝借、下記に貼付させて頂きました。
もし、仮に、例えば、これから私が酵母を起こすようなことがあるとしたら、
ほぼお酒になり得ない、酒造に向かない酵母を選ぶことだなぁ!
そう言うものが有ればだけど。
そして国税庁が言うには、起こした酵母は毎回使い切りにして、必要の都度、新たに起こすようにしましょうね!って訳ですね!!
それよりも、今の私は酵母を起こす行為を語る以前に、酵母を起こす〝気力を起こす〟方が、難しい感じですが…。
今のこの店は、発酵器がありませんから…。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
