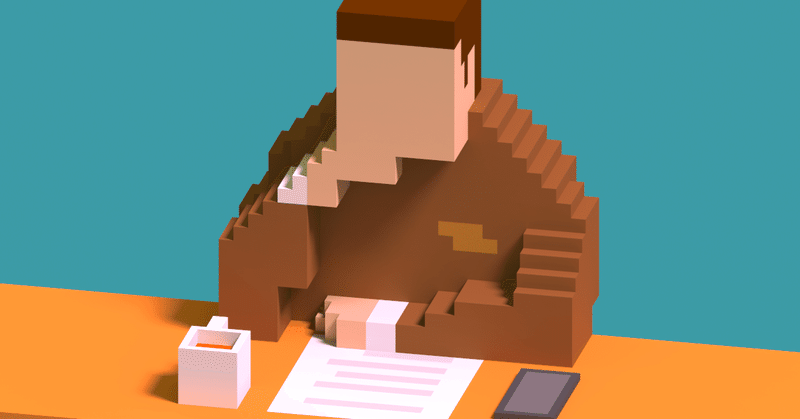
ルソー『エミール』の冒頭に学ぶ、文章を書く姿勢。
ジャン=ジャック・ルソーの『エミール、または教育について(Émile, ou De l’éducation)』は、1762年に発行された教育学の古典である。岩波文庫から3冊の分冊で発行されている。
学校に勤める先生ではないし、教育学や哲学の研究者でもないから、ルソーとは遠い世界で生きてきた。けれども、なんとなくルソーの人物と思想に興味があり、図書館でワイド版岩波文庫を手に取って読んだ。文章がすっと入ってきて、これは借りて読む本ではなさそうだ、所有すべき本だ、と直感した。そこで岩波文庫の古本を手に入れて、あらためて上巻から読んでいる。
まだ全体を読んでいないので、ルソーの教育論については何ともいえない。けれども、冒頭に記された彼の宣言に感銘を受けた。
序文においてルソーは、この著作における書く姿勢を示している。彼が言おうとしていることは、すべての文章を書くひとたちに参考になるのではないかと感じた。そのことについて書きたい。
まず訳者の今野一雄さんが冒頭に掲げている解説、インターネットで調べたことから、ルソーの生涯について人物像の背景を押さえておく。
ルソーは音楽好きだった。正規の教育を受けていないにも関わらず、音楽教師になろうとしたという。作曲したり音楽辞典の原稿を執筆したり、多彩な活動を行っている。一方で思想家としては、教会への批判を扱った挑戦的な書物により、出版禁止や弾圧を受けた。かなり過激なマルチアーティストのようだ。彼のアグレッシブな経歴に共感する。
『エミール』の著作は「二十年間の省察と三年間の仕事」を要した。20代の頃から取り組んだ壮大なライフワークである。
若い頃のルソーはイケメンだったので、女性たちにモテモテだったらしい。パリで暮らしていたアラサーの頃には「決して捨てないし結婚もしない」という条件のもとに、23歳のテレーズ・ルヴァスールという文字の読み書きができない女性と恋に落ちた。彼女との間に5人の子供が生まれたが、ルソーには経済力がなかったから、すべての子どもは孤児院に収容された。ひどい気がするが、その当時ではよくあったことのようだ。
そして1756年、はなやかなパリを去って孤独な生活にひきこもりつつ、腰を据えてルソーは『エミール』の著作に着手する。
『エミール』の序は、次のように始まる。
順序なく、ほとんど脈絡もなく、反省したこと、観察したことをまとめたこの書物は、ひとりの、ものを考えることができる、よき母を喜ばせるために着手された。
教育や社会全体を読者に想定していたわけでなない。「ひとりの」読者に自分の思いを伝えるためにルソーは書き始めている。自省をこめて。
当然のことながら彼が思い浮かべたのはテレーズ・ルヴァスールかもしれないし、生まれた子どもの誰かかもしれない。あるいは出会った女性たちのひとりかもしれない。しかしそれは、抽象化した「ひとり」だろう。
もしテレーズ・ルヴァスールに宛てるのなら、手紙や私信でよい。けれども彼は「ひとり」の「よき母」に向けて書き始めている。だからこそ、あらゆる人のこころに伝わる。
文章表現では、個人という突端を通して、その向こうに拡がるすべての人々に向けて書くことが大切だ。だからこそ文章は届く。もし、たったひとりだけの人に向けたプライベートのメッセージを綴るなら、意味の拡がりはない。閉ざされたコミュニケーションになる。しかし、抽象化することで多くの人に伝わる。
このプライベート(個人)/パブリック(全体)の2つのPのバランスが文章表現には大切ではないか。まだ理論化が十分ではないので検討が必要だが、考え方を図解してみた。

個人に向けた恨み言や説教のような、あまりにもべたな私信ではいけない。一方で、全人類に向けた抽象的な提言では薄味になってしまい、誰にも伝わらない。具体的な経験や体験を内包しつつ、抽象化する必要がある。
この一文のあとにルソーは「数ページの覚え書きを書くつもり」だったのがいつの間にか膨大になり、出版をすべきかどうか「長いあいだ迷っていた」という内情を記している。
文章を書くものとして、ルソーの気持ちがとてもよく分かる。真剣に文章に向き合おうとすると、どれだけ書いても書き足りない。どんどん長文化するのだ。簡潔に書く技術も必要だが、テーマによっては複雑なものを簡単に、膨大なものを短くまとめられないものがある。だから途方に暮れる。
ルソーは、さんざん文章のまとめ方に苦心した末に、次のように決断する。
もっとよいものにしようとむなしい努力をしたすえに、わたしはこれをこのまま発表すべきだと思っている。一般の関心をこの方向にむけることが必要だと考えるからであり、かりにわたしの考えがまちがっているとしても、ほかの人のよい考えを生む機縁となるなら、わたしはまったく時間をむだにしたことになるまい。
素晴らしい。ルソーは自分の主張が正しいとは言っていない。反論が生まれることを歓迎している。なぜなら、その反論によって関心の向かうベクトルが明らかになり、対話が生まれ、新たな創造的な思考に発展するチャンス(機縁)があるからだ。
ルソーは『エミール』という文章によって問題提議をしているのである。自分の主張が正しいと受け止められない可能性があることを認めた上で、反論ウェルカムの姿勢で著作を展開しようとしている。つまり彼の文章は読者が議論や反論をする余地があり、読者に向けて開かれている。
読み進めていくと、この後の第一編では母乳について見解を述べている。農村の女性と都会の女性の母乳を比較する部分があり、さすがに現代ではいかがなものか、と感じた。差別になる。だいたい母乳を扱うことすら問題になり「乳が出ないわたしは母親ではないのですか。チチ親ですか!」など、SNSで炎上しそうだ。
いま川上未映子さんの『きみは赤ちゃん』という出産エッセイを併読しているのだが、母親の苦労を知れば知るほど、こういう安易な発言はできないと感じた。もちろん時代の違いはある。
しかし、時代を超越して反論を促す問題提議になっていることが『エミール』の意義ではないだろうか。
SNSの世界では、読者を過剰に意識するあまり、忖度して「いったい何を主張しているのか、何が言いたいのか」さっぱり分からない文章がある。「Aかもしれませんが、Bもあります。いろいろな考え方がありますよね。おしまい」という結論のエッセイだ。
「私はBだと思います。もちろんAという反論も考えられますが、Cという具体的なケースがあることから、その意見にはデメリットや欠点があります。したがって、私はBであると考えます」という論理的な主張をしなければ、言いたいことが伝わらない。
「Aってあなたの感想ですよね」は議論にすらなっていないし「お前っていつもAって言いがちだよな。分かります」は相手をパターン化することで優位に立とうとするだけの人格否定だ。こうした思考や表現には幼稚さしかない。対話自体がない、何も生まれない。そもそも、お前って言うな。
ところで引用した2か所は、ルソーの『エミール』における序文の1ページにあった数行に過ぎない。彼の教育論とは関係ない部分にも関わらず、3,000文字を超える考察を書いてしまった。教育論に対して書こうとすると、いったいどれぐらいの文章量になるのか。まったく予想がつかない。これが古典的名作の素晴らしさだろう。
なぜ学生時代にルソーの『エミール』を読まなかったのか。いま激しく後悔している。しかし、啐啄同時という言葉があるように、物事には絶妙なタイミングがある。読むべきときにめぐり会った良書かもしれない。
教育DXという言葉が使われる21世紀の現在、たったひとりに個別最適化し、生涯を通じて関わり続けるルソーが理想とした教師の存在は、人工知能によって実現するだろう。したがって、21世紀に『エミール』を読み直すことには大きな意義があるはずだ。
ゆっくり思考を深めながら『エミール』を読み続けたい。
2024.05.18 Bw
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
