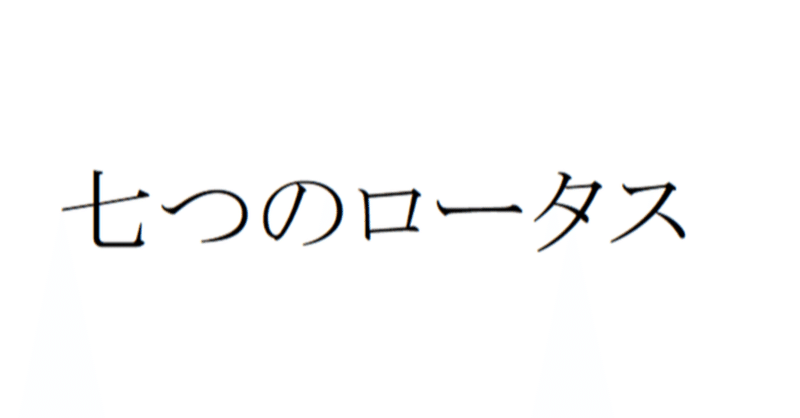
七つのロータス 第55章 スカンダルII
謁見の間の中央に進み出て床に両膝を着き、額が床に触れるほど頭を下げる。
「サイス将軍、あなたに再び指揮杖を預けます」
皇帝の声は、上から降ってくるようだ。
「拝受いたします」
ずいぶん待たせてくれた。皇帝に答えながらも、サイスは苦笑していた。名誉回復を条件に摂政と近衛将軍の排除に協力したのに、一度ティビュブロスから焦らず待てと言われたきり、ここまでなんの音沙汰もなかった。反故にされたかと思い始めていたところだ。それでも待った甲斐はあった。将軍に復帰するのみならず、指揮杖までもう一度手にすることになるとは。笑いを見せるのは不謹慎だと知りつつも、唇が曲がるのを押さえきれない。
帝都のすぐ北の砦に篭もるスカンダルを討てと皇帝が命じる声を受けて、ゆっくり立ち上がる。難しい戦いであるのは確かだが、名誉を回復して余りある武名をあげるにはちょうど良い。侍従がうやうやしく運んできた指揮杖を受け取り、再び皇帝に頭を下げる。重苦しい衣装に身を包んだ娘が、壇の上から瞬きもせずにサイスを見つめている。
床に置かれた大きな粘土板には、グプタとその周辺の地図が刻まれ、小さな粘土の塊が所々に置かれている。家畜の取引に使うのと同じ、様々な形を した小さな粘土のかけら。今は家畜ではなく、軍隊の所在地と数を表している。帝都周辺には近衛軍が定数一万のところ五千、鎮南軍が千、水軍が二千、大河の対岸に征西軍が千。一方スカンダルは、鎮北軍の駐屯地に残っていた千も勢力に加え、一万三千の兵を擁している。他にバグダ守備軍の三千はスカンダルの手勢と見て良いし、状況から考えてプハラ守備軍の生き残りも掌握しているのだろう。サイスはパーバティがスカンダルに与していることは有り得ないと請け負ったが、それも確証はない。パーバティの征北軍が加わってないとしても、反乱軍は合計すれば一万八千から一万九千。もしもバグダとプハラの両都市で徴兵を始めていれば、これが更に増える事になる。オランエは右手に握りこんでいたたくさんのかけらを地図の上に落し、鎮北軍の駐屯地である砦と、グプタの城壁の上に並べた。新兵一万五千を加えれば、手元にある兵力は二万四千。これをどう編成してどうやって戦うか。考えがまとまらず、深い息を吐き出す。動員中の新兵を解散させていなくて良かった。城壁に拠って戦ったとしても九千の兵力では、半ば戦う前に勝負が決まっていたところだ。
視線を地図の上で滑らせる。帝都より南の都市の動向が明らかにならないのも気がかりだ。ジャイヌ討伐の詳細を説明し、改めて新帝への忠誠を促す使者も出した。少なくとも一番近いエンドラからは、そろそろ報せが届いても良さそうなものなのだが。
柱の間隔で幾本分か、あるいは衝立何枚か隔てた場所には、多くの書記が仕事に励んでいる。だけれどもそこには、助けを求められるような者は誰もいない。ティビュブロスやラジも、どこかに行っているらしく姿がない。オランエはもう一度、深い息を吐き出す。
夜が明けてゆく。整列を命じる隊長たちの声が、朝の空気を震わせる。鎮北軍の砦の前で、一万三千の兵士が定められた陣形を取るために列をなして動いている。砦の物見からは、少しばかり離れたグプタの城壁が見える。ほんの半刻もあれば、あの城壁に迫ることができるだろう。昨日は奇襲の予定が狂い、いったん退くことにはなったが、城攻めの用意さえしてあれば帝都の攻略はそれほど難しくはないはずだ。今夜にもグプタの玉座に座ることができる。スカンダルは軽く息を吐き出し物見から降りると、二頭の馬に繋がれた戦車に乗りこんだ。目指すは帝国の都。世界の支配者の座だ。全軍に前進の号令をかけると、夥しい兵士たちがゆっくりと動き出した。
グプタの城門の前ではサイスが指揮杖を手に、兵士たちの整列を見守っていた。再び手にした指揮杖の重みを楽しみ、胸の中に満ち溢れる想いを楽し む。ジャイヌが動員した一万五千を前衛に置き、後衛には近衛軍の歩兵千、騎兵五百、剣や短槍を装備した遊撃兵七百、投石兵二百、戦車五十。更に近衛軍の弓兵五百が城壁の上で待機している。合計一万七千の手勢。予備兵力の少なさと新兵の訓練度が気になるが、兵力で言えば一万三千の敵に充分対抗できる。摂政殿下はずいぶん良い仕事をした。
ほくそえむサイスの背後で城門が開いた。
「サイス殿、つれないですよ。戦が始まろうというのに、声ひとつかけていただけないとは」
降り返るまでもなかった。輝く明灰色の駿馬に跨る、まだ少年と言ってもいいような若い男。まだ肉のつききっていない体も、絶えず浮べている柔和な笑顔も、戦の場にはまるで似つかわしくない。だがこの少年はサッラの防衛戦で目覚しい働きをした。そして馬の扱いにかけては、サイスは足元にも及ばないのだ。
「アルタス殿、まさかとは思うが、助太刀ならご無用です。叛軍とは言え、帝国の兵士を草原の民が討つことは許されません」
「それは残念。ではどこか城壁の上からでも、将軍の戦い振りを見学させていただきましょう」
アルタスは下馬すると、いつもどおりの笑顔で言う。参戦が許されないことは、予想していたのだろう。なんにせよ簡単に引き下がってくれて良かった。
銅鑼の音が空気を轟かせた。
「敵です。アルタス殿、早く城壁の中へ」
サイスは大地の果てに眼をやり、またアルタスに向き直った。
「では失礼します。ご武運を」
再び馬に飛び乗り、サイスに背を向けてアルタスは去った。
「武運があれば、いずれ共に戦うときもあろう」
アルタスを見送りながら、口の中で呟く。サッラの貴公子の戦い振りが見られないのは残念だ。
「確かに残念だ」
もう一度、今度は口に出して呟いてみる。だが今日の所は致し方ない。
馬の背に登ると、兵士たちの頭越しに反軍の群れが見えた。地を真っ黒に覆う蟻の群れとも見える。
「進め!」
サイスの命令を隊長たちがそれぞれの部隊に伝える。
スカンダルは帝都の北に立ちはだかるのが話に聞いた新兵たちだと悟ると、自分の軍を真っ直ぐにぶつけた。帝都周辺の各部隊から選抜された軍は、圧倒的に長槍の歩兵が多く、騎兵や弓兵が少ない。スカンダルには正攻法より他、取る手段が無かったのだ。
それでもスカンダルはいささかもためらわなかった。都を守る主力が帝都で動員されたと聞く新兵なら、歩兵ばかりは敵も同じ事。騎兵も弓兵も一人前に仕立てるには時間がかかるのだ。他の軍から軽部隊だけを借りるにしても、鎮東軍はサッラにおり、鎮北軍がスカンダルの手勢に加わっている以上、さほど多いはずは ない。
横隊の長さを敵の半分ほどに留め、敵よりも厚くする。両翼をあるだけの騎兵と遊撃兵で固めれば、たやすく挟撃される事もあるまい。あとは戦闘に不慣れな敵を、踏み潰すだけだ。
最前列の兵がグプタを守る兵士と接触し、戦いが始まる。スカンダルは戦車の上からそれを眺め、ほくそ笑んだ。
新兵たちが脆すぎる。サイスは無表情のまま、馬上から戦線の様子を見つめていた。整然と向かってくる賊軍の長槍兵を、味方の長槍兵は押さえきれ ず、死傷者を出しながら隊列全体が後退し始めている。隊列の長さを活かして両翼から包囲戦に持ちこもうにも、敵の騎兵や軽歩兵が押さえ込んでいるし、そも そもそのような高度なことをしようにも、適切な指示を出せる隊長が不足している。
動くべき時だ。そう確信すると、サイスは馬の横腹を両足で叩いた。
「予備兵力全体で、敵側面を突く。騎兵と戦車が先行。歩兵は後からついて来い」
指揮杖を振り上げて叫ぶと、自ら先頭に立って右翼へと馬を走らせた。後に従う味方の姿を振り返りもせず進む。長い歩兵の隊列を迂回して敵の左翼を襲う。そうすれば戦況は逆転する筈だった。
思った通りだ。スカンダルは戦車の揺れを心地よく感じた。長槍兵同士が激突する前線はスカンダル側が圧倒している。長槍の扱いに馴れた兵士たち は、徴兵されて間も無い敵を、容赦無く槍の餌食にしてゆく。逃げ腰になればなるだけ、槍の穂先が迫ることはわかっていても、逃げ腰になってしまうのが戦場を経験していない兵士たちだ。敵の戦線は早くも崩れかかっている。
「そら、もう少しだ」
スカンダルは呟く。
後衛の兵士たちに攻城梯子の用意をさせようと降り返った時、スカンダルの目に疾駆する騎兵の一団が映った。思ったより多い。素早く目算したスカンダルは軽くうめいた。大胆にも近衛軍の騎兵を全て投入したものとみえる。厄介ではある。だがこれさえしのげばもう敵には抵抗の手段がない。どれだけの兵力を城壁の内側で待機させてい たとしても、城門を開けばその前面で苦しんでいる歩兵が流れこんで、援軍を出すどころではなくなる筈だ。
「後衛の全軍は左翼へ。敵騎兵の突入を阻止しろ!」
後衛の歩兵は攻城戦のために長槍から剣に持ち替えさせた隊だが、スカンダルは転用をためらわなかった。
「ここがこの戦いの勝負どころだ」
側面攻撃に弱い長槍兵に騎兵が突っ込むか、それを阻止するか。戦いの焦点は絞られてきていた。
馬の首に隠れるように身を低くして、ひたすら疾走する。騎兵の突撃を感づいた敵は、矢と石礫を真っ直ぐに飛ばしてくる。皮紐の投石器から放たれ る石が、うなりをあげてかすめてゆく。サッラの騎兵のように馬上からも弓を射れたらよいのに。サイスは馬の脚を緩めることなく突き進みながら思った。母上も習得できなかったと聞く技術を、使いこなせたら愉快だろう。だが今のところ馬上で揮える武器は騎槍だけだ。サイスはその武器を手に力をこめて握りなおすと、短槍を構えた歩兵の隊列に突っ込んだ。敵の船を引き寄せるための鉤がついた特徴のある槍は、水軍から割いてスカンダルに与えられた兵士たちの装備だ。
「貴様ら、何ゆえ皇帝に楯突くのか?同じ皇軍の兵士を討とうとするのか?」
サイスの問いは両軍の兵士たちの叫び声、あるいは悲鳴の中で虚しくかき消された。サイスの腕が苛立ちとともに、槍を振り下ろした。
周囲で乱戦の度が深まる。後続の騎兵が戦いに加わるにつれ、敵の歩兵が後退して行くが、長槍兵の隊列の側面まではまだ距離がある。隣で味方の騎兵が矢を受けて落馬するのが見えた。
「怯むな!ここを破らねば勝利はないぞ」
味方を叱咤しながら顔を上げる。敵の後衛から更に多くの遊撃兵がやって来るのが見える。首をめぐらせば味方の長槍兵は、既に城壁の近くまで押しこまれて、追 い詰められる寸前になっている。サイスは始めて不安を感じた。自分の名誉、そして母の名誉。それが危険に晒されていた。
サイスたち騎兵の前進が勢いを失って行くさまを見て、スカンダルは玉座が大きく近づくのを見る思いだった。城壁の外の敵を一掃すれば、グプタの 市内に残る兵士は一万に満たない。おそらくは六千から七千といったところだし、グプタの城壁は他の都市と比べても貧弱だ。河港と運河を街の中に取り込んでしまっているという致命的な弱点のせいで、城壁を高くしても意味がないのだ。逆に味方はほとんど無傷に近い。帝都を包囲すれば内輪もめも期待できる。もは や帝位は時間の問題だ。
敵襲を告げる声が、スカンダルの物思いを破った。激しい狼狽が、声の中に感じられる。振り返ると、背後に短槍を持った兵士の一団が近づいていた。鉤つきの槍。水軍だ。スカンダルは目を疑った。帝都グプタは城壁に囲まれてはいても、それは陸地だけのこと。城壁は大河に向かって大きく開け放たれ、河港を形作っている。大河の流域から集まる物産を受け入れるため、都市の防御を犠牲にしているのだ。それゆえ舟を駆る水軍が港を離れれば、グプタはまるで無防備になる。ただでさえ三分の一にあたる千を、プハラ奪回のために割いている水軍をグプタから離すなど、スカンダルは考えてもいなかった。
驚愕から醒めれば、もはや帝都攻略の望みが絶たれたことは明らかだった。密集陣形でなければ戦力にならない長槍兵は、容易に方向を変えられない。ましてや前後からの挟撃に耐えられるものではない。方向転換する間だけでも騎兵や遊撃兵で食いとめられればいいのだが、それらの兵士は全て敵騎兵の突撃を押し留めるのに向かわせてしまった。戦況は一瞬で逆転していた。
状況を認識し驚愕から立ち直るのには時間がかかった。背後から迫る敵と、前面の敵を圧倒する味方を幾度も見比べ、打つ手がないか考える。だが最初に浮んだ考え以外に、破滅を逃れる案はなかった。
「ついてこられる者だけついて来い」
スカンダルは叫ぶと、戦車を戦場とは逆方向へ向けた。自分さえ生きていれば、まだ再起の道はある。そう自分に言い聞かせると、御者に馬を急かせるように命じた。街道を矢のように北へ逃げ返るスカンダルに、従う者は誰も無かった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
