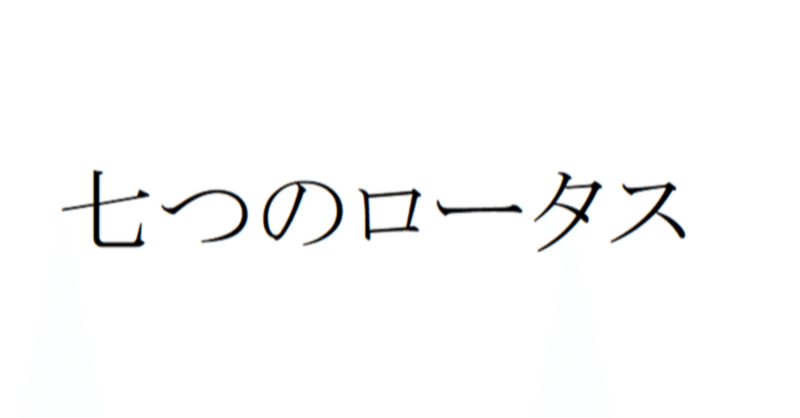
七つのロータス 第49章 ドゥルランダ
無数の蹄の音が轟く。左右からの鬨の声が大気を揺るがす。今、ドゥルランダ率いるウム支族の戦士たちは横一列になって、前を行く農耕民たちを追っていた。遮る物のまるでない平原を逃げる一団は五百人ほど。驢馬に牽かせた荷車がいくらかある以外は、みな徒歩である。対して追う遊牧民は百に満たない。それでも立ち止まって戦おうとする者は一人もない。今日だけで、このような難民の群れを二つ屠ってきた。これで三つ目だ。
騎馬に対して徒歩では逃げようが無い。難民の運命は見つかった瞬間に決している。だが農耕民たちは、足を止めようとはしない。これが弓の練習にはちょうどいい。
「アギ」
ドゥルランダが若い戦士の名を呼ぶと、相手は無言で矢をつがえた。手綱を放し両脚だけで体を馬に繋ぎとめ、なお真っ直ぐに上体を起して胸を張る。その姿勢は惚れ惚れするほど美しい。真剣な眼差しを難民の最後尾を行く男に向け、矢を放つ。農耕民は背に矢を受け前のめりに倒れた。若い戦士の顔に安堵の微笑が浮ぶ。
「よし、次。ジュク」
また名を呼ばれた若者が弓を構える。矢は初老の男の腰に当たった。
「莫迦者!急所を外した」
戦士は大首長の叱責に顔をしかめる。ドゥルランダは更にひとりの戦士の名を叫んだ。
「女を狙うなら、殺すなよ」
矢は若い女のふくらはぎに突き刺さる。女は倒れたはずみに、土の上を二度三度と転がった。
次の射手を指名したドゥルランダの目の前に、先ほど腰を射られて倒れた男が近づいてきた。ドゥルランダは一瞬だけ男に目をくれたが、すぐに弓の的になっている農耕民に目を移した。愛馬の蹄がまだ息のある男の首を踏み砕く感触が伝わってきて、ドゥルランダは薄笑いを浮かべた。
「馬の脚を緩めろ」
ドゥルランダが命ずると、戦士たちは一斉に馬の行く気を押さえ、速度を落した。戦士たちはドゥルランダに合わせて馬を並べ、遂には全く止まってしまった。薄笑いを浮かべたまま、必死で逃げる農耕民を見守る。避難民の一団はゆっくりと遠ざかって行くが、こちらが止まったのを見て気を緩めたのか、長く走りどおしで足が動かなくなったのか、何人かが取り残されつつある。ドゥルランダはまたひとりの戦士を指名した。
「この距離なら届くだろう。仕留めて見せろ」
戦士はゆっくり弓を引き、狙いを定めて息を止めた。矢はもはやほとんど脚を進めることのできなくなっていた老人の頭に突き刺さり、頬を貫いて反対側に頭を覗かせた。
「見事だ」
大首長が馬を進めると、戦士たちも横一線の隊列を保って馬を進める。弓の練習に程良い距離を保っての追跡が再開する。
「欲しければ、急所を外してもいいぞ」
最後尾の老婆に狙いをつけていた戦士に軽口を叩く。真剣な場面なので声をあげて笑う者はいないが、戦士たちの口元が僅かに綻ぶ。放たれた矢は老婆の胸を貫いた。
夕陽も傾ききり、夜が迫っている。日に背を向けた戦士の顔が、陰になって見えないほどだ。生き残った農耕民たちは、逃亡を諦めて荷車を中心にして座りこんでいる。遠巻きにしている戦士たちの輪からドゥルランダが一歩踏み出すと、一番近くにいた女が顔を上げた。既に感情の波は過ぎ去ったのか、目に涙をにじませてはいるが、ほとんど無表情である。近づいて腕を掴み、立ち上がらせる。他の戦士たちも次々と近づいてきて、へたりこんでいる農耕民たちを無理やりに立たせる。
農耕民たちを後手に縛り、家畜のように三つの列に繋ぎ終える頃には、既に草原を照らすのは月明かりだけになっていた。戦士たちは農耕民を繋ぐ縄の端を引きながら、来た道を引き返す。男たちを繋いだ列を引く者が先にたち、次に女たちを繋いだ列を引く者が続く。それぞれに二十騎ほどの護衛がついている。残った者がその後。荷車の驢馬を引く者が最後に続き、年寄りや子どもを繋いだ列は後に残された。役立たずたちを同じように繋いだのは、単に連れて行く者どもを刺激しないため。とどめを刺さずとも、後は山犬か夜の寒さが始末してくれるだろう。
点々と続く屍の列をたどって、仮の宿りのオアシスへ戻る。もともとはこの農耕民たちの暮らしていた場所だ。途中、わざと生かしておいた女が倒れているのを見つけると、馬の背に担ぎ上げて荷物のように運ぶ。
今日もまたドゥルランダにとっての日常が過ぎて行く。
天幕の中で目を覚ます。天幕の継ぎ目が僅かに明るく見える。ドゥルランダは毛織の掛布を跳ねとばした。
皮袋を水甕に沈め、満たした水を飲み干す。天幕の外に出ると、東の空の明るく染まった領域の外側には、未だ星が瞬いている。天幕の杭に繋がれた馬は、地面に無造作に積み上げられた秣を唇の端で玩んでいる。馬の背に敷き布をすることもせず、頭絡や手綱をつける手間も惜しみ、それどころか自らの身に衣をまとう手間さえ惜しんで、ドゥルランダは馬に飛び乗った。
ハラートの戦士たちが眠る天幕の間を、ドゥルランダは矢のように駆けた。オアシスのほとりに設けられた防柵を飛び越え、宿営地を飛び出すと、誰にはばかることも無くひたすら速くひたすら速くと馬を急かす。夜の間に冷え切った空気が肌を刺すが、それもいつしか体の内から湧き出る熱気が退けた。明け方の寒気に晒した肩や腕から湯気が立ち上る。背中や胸を汗の粒が流れ落ちるのを感じる。馬体の躍動と風の流れ。遊牧民としての喜びに満ちた時間。このまま地の果てまで駆け続ける事こそ、ドゥルランダの望みである。
野営地に戻ると、男たちが起きだして食事の仕度を始めていた。移動の途中で狩った野鼠や山犬の肉を火で炙りながら、小さく切り分けたチーズを齧っている。ドゥルランダは肉とチーズを一口ずつ受け取ると、あとは農耕民に作らせたパンで腹を満たすことにした。遊牧民の食い物ではないとパンを口にしない者や、一度試してみたものの口に合わないと言ってもう食べない者も多い。しかしドゥルランダにとっては、食い物の選り好みをするなど、そもそも男のすることではなかった。
飯を食い終わって、日干し煉瓦の城壁を背に腕組をして目を瞑る。このオアシス都市を攻め落としたのはもう三日も前のことな のに、まだ木材の焦げる臭いがしている。もはや人の住む場所としての機能を失った街で、奴隷の身に落されながらも、農耕民たちはしがみつくようにして生きている。この異常な生命への執着もまた、農耕の悪しき影響に数えても良いかも知れん。薄目を開ければオアシスのほとり、かつては人の住む都市の外側だった場所にハラートの天幕が無数に並んでいる。俺はまた一つ、世界をあるべき姿に近づけたのだ。満足感と共に眠りがドゥルランダを覆った。
眠ってしまったか。部下に起されて、目覚めながらそう思った。相手の声はまだ耳に入っていない。ただ起された、という感覚があるだけである。
「いい獲物でも見つかったのか」
ひとつ大きなあくびをして、背を伸ばす。
「使者が来ました。ムラト支族のヴァリィさまからです」
従者に曖昧な返事をして、ドゥルランダは立ち上がる。ハラート全部族は今、行き会う遊牧民は従え、農耕民は滅ぼすべく草原に広く散って西へ向かっている。その中でも最も北側を進んでいる筈のムラト支族から、いったい何をはるばる報せに着たのか。そう思いながら、自分の天幕に使者を連れてくるように命じた。
ドゥルランダは正午近くなって、天幕から姿を見せた。真一文字に結んだ口、正面に据えられたまま見開かれた目に、ウム支族の戦士たちも気圧された。一言も発しない戦士たちに向かい、ドゥルランダが命じたのは全支族あげての出立の用意。全ての家畜、全ての天幕、全ての虜囚を引き連れて、女子どもを置いてきたタラスへと引き揚げる。戦士たちからどよめきと歓声があがる。だがその声はドゥルランダの耳には届いていない。草原の覇者の心は遥か西へと漂っていた。タラスで準備を整えたら、ヴァリィの報せた「帝国」へと向かう。今まで見つけた中で、最大の、それも桁外れに巨大な都。それが七つの都のひとつでしかないという。もしかすると永年探し求めてきた、農耕民の源に行きついたのかも知れぬ。全ての農耕民を滅ぼし、地上から農耕という悪習を一掃する。その夢が手に届くところまで近づいたのかもしれない。
ドゥルランダは命令を終えてからずっと、太陽が赤味を帯びはじめた西を見ていた。身の内側からの突き上げるような思いを堪えて、静かに立ち尽くす。駆け巡る血潮で、頬が熱く感じる。今すぐにたった一人ででも、西に向かって駆け出してゆきたい。
翌朝の出発に間に合わせるために家畜を集めたり、荷物をまとめたりといった大騒ぎも、ドゥルランダの物思いを破ることはなかった。草原の一日はゆっくりと暮れてゆく。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
