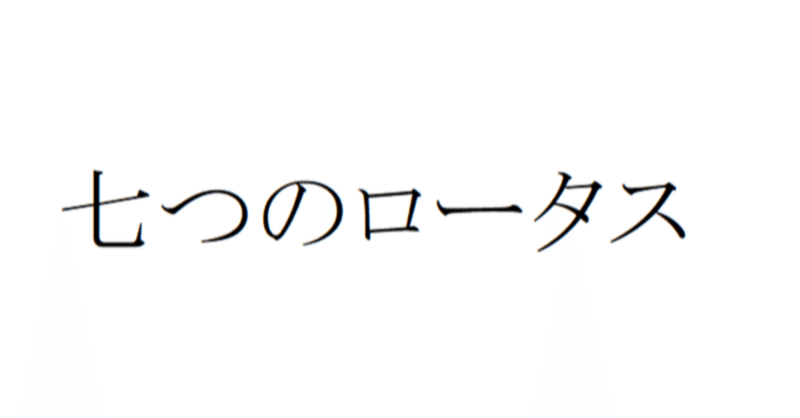
七つのロータス 第50章 スカンダルIII
城壁の上から、水路が張り巡らされた大地を見下ろす。陽に煌く水路と黄金色に輝く麦畑が広がる中を貫くのは、帝国の七つの都市を繋ぐ街道。真昼の空気は澄み、地平線まで霞みも曇りもなくはっきりと見晴らすことができる。街道の伸びゆく先を見遣れば、遥か彼方に帝国の軍旗が揺れている。その下にはようやく姿を現した一団の人影。プハラを解放した軍隊が、いよいよ凱旋するのだ。歓迎の用意はすっかり整っている。神殿に捧げる仔牛も、酒も揃っている。皇宮では宴会の料理が次々とできあがっている頃だろう。竃からは無数のパンが次から次へと吐き出され、酒蔵の甕は残らず運び出されている。床には花弁が敷き詰められ、豊かな香りを放っているだろう。歌や踊りを披露する美姫も楽人も、皇宮の広間に控えている。人々は都城の北門から神殿を経て皇宮へと向かう大路に犇き、近衛兵たちが二列になって帰還した兵士たちの通路を空けている。
オランエは摂政として初めての大仕事を、まずはやり遂げたという実感があった。気が遠くなりそうな眠気に抗いながら、ゆっくりゆっくり近づいて来る兵士たちを眺める。自分が口を出さねばならぬことは、もう何も無いし、式典の最中にひっくり返るわけにもいかない。やはり少し仮眠をとるべきだろう。あの遠く見える軍隊が城門に達するまでには、まだしばしの暇があるのだから。
よし、と思って、狭間胸壁についていた手を突き放し、体ごと振り返った途端、皇帝のお出ましを告げる声が聞こえた。思わず顔をしかめて溜息を吐き出す。これで深夜まで休息を摂ることはできなくなったわけだ。
やがて真珠と他にも十人以上の女官を引き連れて、パーラが姿を現した。城壁の上で等間隔に並ぶ近衛兵が、引き下がって頭を下げる。
「兄さま、いえ摂政殿下、こちらにいらしたのですね。ずいぶんとお久しゅうございます」
にこやかな笑顔が実に疎ましい。
「蓮の花見にご一緒してから、三日しか経ってはおりませんよ」
不快感を周囲の者たち、あるいはパーラ自身に気取られてはならない。それが一番の難事である。
「同じ家に寝起きする兄妹が、三日も顔を合わせないのは、充分に不自然ではなくて?」
思わず舌打ちしそうになるのを、かろうじて押し留める。
「そうかも知れません」
オランエは無感動を装って答える。パーラは話の接ぎ穂を失ったためか、黙って狭間胸壁まで進み、遠く街道の先を見下ろした。
「殿下、わたしの織り上げた軍旗が、先頭をやってきます」
急に華やいだ声をあげたパーラを、オランエは戸惑いながら見た。ついで皇帝の指差す彼方を見遣り、ようやくパーラが皇帝に即位する前に、神殿に篭もって軍旗を織っていたという話を思い出した。兄妹は語るべき言葉もないままに、ただ並んで遥か遠くをやって来る軍勢を眺めた。
せわしない足音が、ぎこちない時を破った。革のサンダルが、焼き煉瓦の城壁を続けざまに叩いている。やがて足音の主が櫓門の上に姿を現した。城壁から更に人の背丈ほど高い門の上へと続く階の上で立ち止まったのは、皇宮の見習い書記の少年である。
「誰に用だね」
居並ぶ近衛兵に誰何されている少年に、オランエは静かな口調で尋ねる。少年は答える前に、一瞬パーラを盗み見た。
「あ、あの、摂政殿下に」
助け舟だ。
「言いなさい。大事な用なのだろう。陛下の前だからとて、気にすることはない」
パーラがどんな顔でこの言葉を聞いたか見たかったが、わざわざ怒らせることもない。
「ティビュブロスさまが、至急お会いして話されたいことがあるそうです。重大で緊急の用件だということで」
オランエはパーラから見えない角度で笑い、すぐに表情を引き締めて向き直った。
「陛下、何やら不測の事態が出来したもようです。至急、事態を把握したいと思いますので、失礼を致します」
パーラの恨みをこめた視線を受けとめてから、オランエは急ぎ足で城壁の通路へと駆け下った。
城門から十分の一ミーリアの道標で、兵士たちは足を止めた。スカンダルだけがただ一騎、そのまま帝都に向け進み続ける。門の前で出迎えるのは、オランエ、ティビュブロス、ゴウイイ、そして後には更に五人の近衛兵が控える。
「丁重なお出迎え、恐れ入ります」
スカンダルは三人の前で下馬すると、丁寧に頭を下げた。
「太守閣下、この度は大変な働き、帝国臣民を代表して御礼を申し上げます」
オランエが進み出て、口上を述べる。
「陛下も皇宮にて、凱旋の将軍を心待ちにしております。兵たちを元の部隊に戻した後、閣下と五百人隊長以上の方々で都を行進していただく手筈になっております」
「お待ちを」
スカンダルの表情が険しくなった。
「全ての兵士たちと栄誉を分かち合えぬのは何故ですかな。凱旋式では将軍と苦楽を伴にした、一兵卒までが栄誉を得るのが通例でありましょう」
この問いに、ティビュブロスが答える。
「通例であれば、凱旋将軍は僅かな手勢を連れて、急ぎ戦勝の報告に帰還するもの。オソリオ征服帝のご親征の際にも、凱旋式に間に合ったのは二千の兵だけでした。一万を越える兵を城内に引き入れた例はございません」
オランエはスカンダルの僅かな表情の変化も見逃すまいと、視線を据えていた。スカンダルの新皇帝への忠誠宣言が届いていないことに気づいたのは、シャタという書記だったという。単に戦いの混乱で忘れ去られ、あるいは使者の身に何かあって報せが届かず、それとも届いた書簡が皇宮で紛失した、などと考えられなくもない。だがオランエの胸中には最悪の予想が居座っていた。いっそ問いただしてみたいという思いが沸き上がってくるが、それは得策ではない。スカンダルが本当に二心を抱いているのであれば、敵に手の内を晒すことになる。
「お話はわかりました。しかし兵たちを納得させねばなりません。しばし説得に戻ります」
スカンダルは再び馬に跨ると、馬首をめぐらし駆け去った。オランエは大きく息を吐き出す。
「あっさり引き下がりましたな」
「やはり杞憂であったろうか」
ゴウイイとティビュブロスが安堵の言葉を口にするが、オランエは胸騒ぎが収まらなかった。最悪の事態に備え、短い時間でできるだけのことをしたのが、無駄に終わればよいのだが…。
誰か勘のいい奴がいたとみえる。スカンダルは心中で毒づいた。本来なら城壁の中で、部隊に決起を促す筈だった。まあよい。こうなった時のことも考えてなかったわけではない。
スカンダルは部隊の元に戻ると、隊列を縦隊から方陣へと組み返させた。
「兵士諸君。我が戦友たち」
スカンダルは兵士たちに状況を説明した。
「プハラを救うため緊張に満ちた日々を送った我々に、帝都でなにもせずにいた者たちが、このような無礼な仕打ちをしようとする。侮辱だ。私はここでこのような扱いを受けようとは、思ってもいなかった」
兵士たちの囁き交わす声が、唸りのように聞こえる。スカンダルは唸りがおさまるのを待った。
「兵士諸君。そもそもあそこにいる連中は、何者だ。皇帝ナープラ、わたしの従兄弟だ。そのナープラを殺したジャイヌによって皇帝に仕立て上げられた小娘と、都合よく死んでくれたジャイヌに代わって、政を思うが侭にしようという男たちではないのか」
兵士たちから大きなどよめきが起こる。隣あう兵士たちが声を交わす中で、とりわけ大きい声で話すものたちがいる。スカンダルの唇が弓の形を成した。一万二千の兵の中にまんべんなく配された、元バグダ守備軍の兵士たち。永年スカンダルの元で働いてきた兵士たちが、何も指示されずとも、スカンダルの言葉を受け入れるよう周りの兵士に働きかけているのだ。
スカンダルは静かに待つ。兵士たちの囀りはますます大きくなる。そして決定的な叫び声が、遂にあがった。
「太守閣下を皇帝にしよう!」
「そうだ!」
すかさず同調する者が出る。賛意を表す者が次々と声をあげる。
たちまち一万五千の兵士たちは、スカンダルを皇帝にの声を連呼し始めた。兵士の中にはグプタに逆らうことを望まぬ者も多いに違いない。だが状況に圧倒され、それらの者は口を閉ざすか周囲と同調してみせているのだろう。兵士たち全体に賛成の声が広がるのを待って、スカンダルは手を広げて静粛を促した。
「戦友諸君。私はそのようなことを願っていたのではなかった。できれば皇帝の座などという重責を背負い込むことなく、いつまでもバグダの太守のままでいたかった。だが、グプタに偽りの皇帝が居座っている今、誰かが道を正さねばならない。諸君が道の正し手に私がふさわしいと言ってくれるのは、身に余る光栄だ」
言葉を切る。静寂。風の音、微かに聞こえる牛馬の息、それだけ。一万五千のうち、言葉を発するものはない。スカンダルは大きく息を吸いこむと、叫んだ。
「諸君らが望むのなら、私は皇帝になろう」
空気が巨大なうねりとなって押し寄せてくるようだった。兵士たちはスカンダルの言葉に、一斉の鬨の声で応えたのだった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
