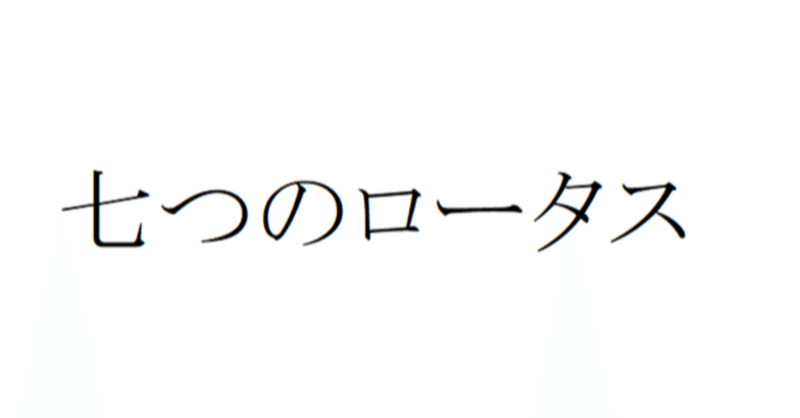
七つのロータス 第51章 オランエIII
オランエはスカンダルが兵士たちを「説得」している様子を、眺めていた。声は聞こえない。ただスカンダルが身振り手振りを交えて、弁舌を振るっている姿が見えるだけだ。やがて兵士たちが一斉に叫んだ声が、伝わってきた。
「何だ?」
ティビュブロスが呟く。スカンダルは軍旗を手に取って高く掲げている。指揮杖を持つ将軍を意味する、黄金色の花弁が一枚混ざった白い蓮の花の軍旗。それはパーラが神殿で織り上げたものだ。
「あ!」
思わず小さな叫び声が漏れる。軍旗には火がつき、充分に燃え上がったところで、地にうち捨てられた。
「近衛将軍、兵士たちを門の中へ」
視線をスカンダルに向けたまま、オランエは呟いた。背後でゴウイイが動き出すのを感じたが、自分自身は身動きもできない。
やがてスカンダルの兵士たちは、方陣の隊形のまま都へと進み始めた。大地の上で弱々しく燃える軍旗の上を、無数のサンダルが踏みにじって行く。兵士たちの槍の穂先が、ぎらりぎらりと光を放つ。
「まさか」
ティビュブロスの呻き声が、オランエの呪縛を解いた。
「先生も、早く」
ティビュブロスを促し、城門へと向かう。走りながら、迫ってくる兵士たちを振り返る。まだ余裕はある。だが…。
「門を閉めろ!早く」
オランエが命じると、まだ少し距離があるうちに城門が閉まり始めた。ティビュブロスをかばいながら走るオランエの目の前で城門が閉ざされる。同時に城壁の上から、太い綱が何本も落ちてきた。オランエは端を輪に結んだ綱に足をかけ、ティビュブロスは綱の先に結び付けられた籠に尻を納めた。最後まで門を守っていた兵士たちも、それぞれ綱にしがみつく。万が一の備えが、役に立ってしまうとは。
何人もの手で一気に宙に持ち上げられた眩暈から立ち直ると、軍勢が地を覆うさまが見て取れた。綱を握る両手に、改めて力が入る。矢の届く距離に入る前に、城壁の上に上がる事ができた。夢中で城壁にしがみついて身を引き揚げながら、オランエは叫ぶ。
「パーラは?いや、陛下は?」
「既に皇宮に下がっておられます」
安堵の息が漏れた。ようやく立ち上がって、城壁の上から見下ろす。反乱の兵士たちは、溢れ返った大河の流れのように城壁に押し寄せてくるところだ。
「つがえ!」
隊長の号令で、近衛弓兵が一斉に矢をつがう。
「殿下、よろしいですね」
尋ねるゴウイイに、オランエは無言で頷く。目は城壁の下、人の洪水から放すことができない。
「狼煙を!」
ゴウイイが叫ぶ。狼煙が上がれば周辺に駐屯する全ての部隊が、帝都に変事ありと馳せ参ずる筈。それまでに城門を破られなければ、危機は逃れられるはずだ。
「放て!」
城壁の上から、一斉に矢が放たれた。帝国の兵が帝国の兵に矢を向ける。帝国の統一以来、始めての内戦。その最初の矢だ。オランエは思わず目を背けた。
見透かされていたのか。スカンダルは閉ざされた城門を、未だ信じきれぬ思いで見上げた。兵士たちは一抱えほどある丸太を持ち出し、門を破る姿勢 を見せているが無駄だろう。城門を破るより早く、近衛・鎮北・鎮南・水軍の各軍に包囲されることになろう。ここは引くべきか……。いや、引くより他に手はあるまい。だが、グプタの連中は帝国にとって恩人である筈の、私の凱旋を拒否したのだ。理はこちらにある。一度引いても、必ず立て直せる。バグダに戻るまでの道には、鎮北軍主力の駐屯する砦もあるが、その大半をプハラ解放の軍、すなわち現在のスカンダルの手勢に取られた鎮北軍は、千にまでその兵力を減らしている筈。いくらか補充があったとしても、蹴散らすことができる。いや、むしろ元鎮北軍の兵を使えば…。帝都内での決起を諦めたスカンダルの頭の中で、新たな計画が次々と組みあがって行く。
城壁の上から、スカンダルの兵士たちが引き揚げて行くのが見えた。引いてゆくところまで、洪水にそっくりだ。オランエの体を疲労感が包んでいる。全く頭が回らない。何も考えられない。オランエは城壁の上に、崩れるように座りこんだ。
「オランエ、大変な事になったが君は休め。皇宮に戻って眠るんだ。反乱軍以外の部隊を掌握するのはゴウイイ将軍に、文官を掌握するのはわたしに任せて」
ティビュブロスが静かに語りかけてくる。まっすぐに目を覗きこむようにして。まだ幼かった頃以来、聞いたことのないような口調だ。
「僕をのけ者にする気ですか」
先生を見上げる。泣き声が漏れる。
「そうではない、そうではない。お前は休まねばならんのだ。この数日、ほとんど眠っていないのだろう?凱旋式が終わるまでと思っていたから言わなかったが、酷い顔色だ。わしらには、いや帝国にはお前が必要なのだ。早く休め、そして早く万全になって戻ってきてくれ」
オランエは声もなく立ちあがり、兵士たちがあわただしく走りまわる中、身を引き摺るようにしてその場から逃れた。確かに体が重い。脚や肩や首の後ろに、重石をつけられているようだ。だけれども横になったといって、眠れるものだろうか。
何百人も入れる広間の床を、皿で覆い尽くそうというかのように料理が並べられている。だけれど、ご馳走を味わう者の姿はどこにもない。何人かの 下男や下女がぼんやりと立ち尽くしているだけである。オランエは広間の中央に立ち、料理を見まわした。何百人分もの料理が、むなしく冷めていく。凱旋将軍を迎える式典の準備に忙殺されたこの数日間の努力は全て無駄になったのだ。
「誰か」
オランエの言葉に数人の召使たちが、進み出た。
「料理がみな無駄になってしまった。酒や蔵に戻せる食べ物はしまって、駄目になってしまうものは、宮殿のみんなで食べるといい。皇宮の外にいる兵隊のところにも、持っていってやるのを忘れるなよ」
召使たちは無言で互いに目配せしあった。この場に並んでいるのは、貴族たちが食す料理ばかり。食べ残しが口に入ることは期待していただろうが、手付かずの料理を食べることになるとは思わなかったので戸惑っているのだろうか。それとも外で何があったかもう知っていて、喜びを表すのを躊躇っているのだろうか。
考える事も面倒になって、広間を横切り中庭に面する回廊へと進む。さっきは重く感じた体が、今は軽い。霞のように頼りないものになってしまったように思える。
回廊に出ると、琵琶の音が聞こえた。いつもどおり美しい庭の上を、小刻みな音が響いてくる。楽を奏でるのではなく、調子を整えている音だ。廊下の先に目を遣る。音の主は柱に背を持たせ、膝に琵琶を置いた女だった。見覚えのある華やかな衣装。オランエの姿をみとめ、女は静かに立ちあがる。軽い衣が水の流れる ような音をたてた。
「摂政殿下、ご機嫌…、麗しくはいらっしゃらないようですね。お顔色が悪うございますわ。それに汗も」
オランエは白蓮をただ見返した。女が何を言っているのかも、良く考えねばわからない。
「熱がおありのようね」
白蓮が顔を近づけるので、化粧の匂いがする。
手布が額に当たる。宙に浮ぶような感覚とともに、視界が暗くなる。
化粧の匂い。息を飲む音。白蓮の顔。驚きに飾られた美しい顔。大きく見開かれた眼。暖かな光。揺れる光。頬に触れる冷たい掌。渦を巻く様々な想念に追いたてられるように目を覚ますと、寝室の中は夕陽の色に満たされていた。
「お目覚め?」
声の方に顔を向けると、寝台の傍らに白蓮が座っていた。
「お水はいかが?それとも何か召しあがられますか」
柔らかな笑みが、女の顔に浮んでいる。言葉も無くその笑顔を見ている間、白蓮も静かにオランエを見つめ返していた。
寝台に半身を起こし、水を飲み、僅かな食べ物を口に運んだ。香草をつけて焼いた子牛の肉、ゆでた豆、煮た玉葱、蜂蜜を練りこんだパン。行われなかった宴の料理を、ほんの一口ずつ飲みこむ。その間中ずっと、白蓮の視線はオランエの顔に注がれている。
「何を見ている」
「今日は仕事ができるかと、考えていますの」
オランエはめんどうになって、白蓮に背を向けて横になった。掛布を肩まで引き上げ、目を瞑る。遊女は何も言わない。身動きするようすも無い。
「琵琶を弾いてくれ。それだって君の仕事だろう」
背を向けたまま言う。やがて静かで緩やかな音色が部屋を満たした。琵琶一丁でもこれほど繊細で豊かな音楽を奏でることができるのだな。眼を閉じたまま聞き入っていると、白蓮の声が琵琶に唱和した。歌でも楽でも踊りでも帝国一と言われる遊女の声は、評判にたがわず美しかった。オランエはその歌をいくらも楽しまないうちに、紫色の眠りの中に引き摺りこまれていった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
