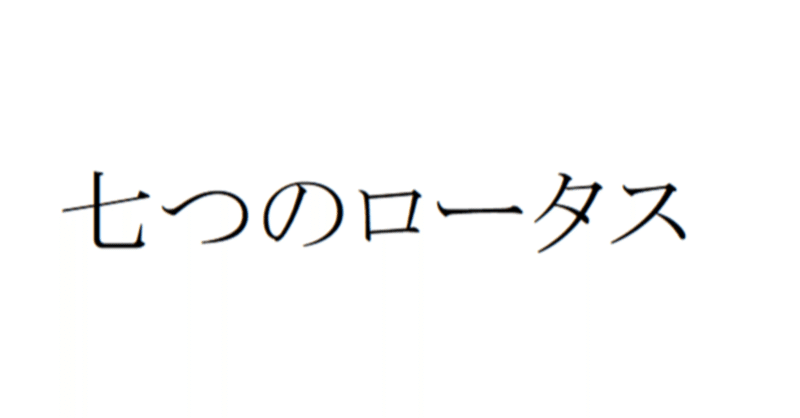
七つのロータス 第59章 ゼン
第1章から
ゼンは決断を下した。エンドラはエンジャメナに従う!
南のウラマの都は自らエンジャメナの前に門を開いた。エンジャメナの軍はウラマの軍を合わせて倍増し、更には自ら望んで軍に加わろうとやって来た男たちも、その配下に加えている。一方、グプタは叛旗を翻したスカンダルに城壁まで攻め込まれて、このままでは落城するかもしれないという。グプタの軍は南下してエンドラを守ることはできない!エンジャメナはグプタに向かっている以上、必然的にエンドラを通る。エンジャメナに城門を開かねば、戦いになるだろう。帝都からの援軍も無しに、人々から慕われているエンジャメナと戦うのは気が進まない。下手をすればエンジャメナの統治を望む住民たちによって、後から背中を刺されることにもなりかねない。
何日も何日も考え続けた難問に答えを出すと、ゼンはゆっくりと周囲を見まわした。エンドラの主だった人々が、太守の決断はいかにと、瞬きもせず見つめている。
グプタの皇宮にある会議の間を小さくしたような部屋は、息苦しさまでよく似ている。天井近くの隙間から入りこむ光だけの薄暗い部屋。その場にいる十人ほどの男たち。この街の太守としてグプタからやってきてからの五年間、なんとかうまくやって来たつもりだ。それでもこの地の有力な書記や地元貴族たちが、自分に従うかどうかは自信がない。
「足止めしてあるグプタからの使者を、牢に移せ」
一人の書記が頷いて、部屋を出ていく。それ以外の者は、なおも体の動かし方を忘れたかのように、ゼンを見つめ続けている。
「反論がある者があれば、今のうちに言ってくれ」
声をあげる者は誰もいなかった。
グプタの皇帝と、突如皇帝を名乗ったエンジャメナのどちらにつくか迷っていた間にも、ゼンは内乱に参加する準備は進めていた。エンドラ守備軍を 全て市城の中に入れ、農民に戻っている退役兵や、まだ兵役についたことのない若者を徴集し、正規兵の代わりに各地の守備につけた。争う両者の間に位置している以上、中立を貫ける筈もなかったからだ。
ゼンは太守の公邸のバルコニーから、広場を埋める三千の兵の前へ進んだ。六千の目が一斉にエンドラの太守を見上げる。
「諸君、聞いてくれ。グプタでは今、皇帝の座を巡って無益な争いが続いている。ナープラ帝が亡くなったのは聞いてのとおりだが、都に居座る連中はこれ以後、帝位を巡る混乱を収拾できずにいる。摂政ジャイヌをナープラ殺しの下手人として捕らえた者たちは、これを葬ったにもかかわらず、ジャイヌが皇帝の位につけた小娘を、未だ皇帝に掲げている。
「ジャイヌは女子どもを帝位につけて権力を欲しいままにしたが、そのジャイヌを討った者たちもジャイヌにとって代わっただけで、帝国全体の事を考えているわけではないことはこのことからも明白だ。自らが影から皇帝を操ろうということだけが望みだ。
「この腐ったグプタの貴族たちに対し、ビーマの太守エンジャメナが蜂起した。エンジャメナは自身が立法帝ナープラ一世の子という正しい血筋であり、またビーマでは善政と冷静な判断力によって、軍民に慕われているのは知っての通りだ。帝国の人々は皆、エンジャメナが帝位に登るのを願っている。彼ならば権力欲にまみれた帝都の貴族たちを排除し、帝国に新たな時代を迎え入れる皇帝になるだろう。兵士たちよ。このエンドラにエンジャメナを、皇帝にふさわしい男を迎え入れよう。そして我々の手でグプタの玉座に導こうではないか」
森が嵐に揺れるような音が兵士たちの間を渡ってゆく。兵士たちは戸惑っているのだろう。今まで何も知らされていなかったところへ、いきなりグプタに兵を向けるというのだから無理もない。
俺は兵士たちに慕われているだろうか。ゼンは躊躇いながら、再び口を開いた。
「戦友たち、聞いてくれ。この土地は平和だったから、君らと戦場で寝食をともにしたのは僅かな機会しかなかったかもしれん。だから君らを戦友と呼ぶのは、おこがましいのかもしれん。だが俺はあえて君らを戦友と呼びたい。ムジャの荘園の一揆や、三年前に草原の民の隊商が乱暴狼藉をはたらいた事件で、俺は確かに君らとともに戦った。君らを戦友として頼もしく思った」
兵士たちは静まり、真剣に耳を傾けてくれているようだ。
「だから友よ、隠さずに言おう。今まで通りグプタに忠誠を誓うか、エンジャメナの軍に門を開け放つのか、これは難しい判断だった。しかしどちらかにはつかねばならない。中立などと言おうものなら、両者から攻撃されるのは明らかだ。
「友よ、いろいろ考え合わせた結果、俺はエンジャメナに合流するのが、エンドラにとって最善だと判断したのだ。どうか信じてくれ。この帝国の危機を乗り越えるため、手を貸してくれ」
躊躇いがちな空気が周囲を包んだ。長い沈黙。身が押しつぶされるような気分が続く。ゼンは視線を落としそうになったが、意志の力でそれだけは踏みとどまる。まだ負けを認めるには早いだろう。
長い沈黙の後で、数人の兵士が槍を掲げて躊躇いがちな賛意を示した。続いてその周囲の兵士たちが、声を上げて槍を高く掲げる。すると兵士たちのあちらこちらから、喚声とともに槍が突き上げられる。兵士たちは指導者の名を連呼し始めた。それはエンジャメナではなく、ゼンの名。エンドラの太守は膝から崩れ落ちそうになりながら、それは耐えた。だけれども両目から涙が溢れるのは、押し留められなかった。
五日の間、ゼンはグプタの軍を迎え撃つ用意を進めていた。勿論、先にエンジャメナと合流してグプタを攻撃できれば、それに越したことはない。し かしエンジャメナ軍の到着より、帝都の軍が先に到来した場合、エンドラは単独で帝国軍の主力を迎え撃たねばならないのだ。また万一、エンジャメナが帝都の攻撃に失敗して退却するようなことになっても、エンドラで敵を食いとめる意義は計り知れない。城壁の前に木の柵を設け障害物にする。街道の部分を除いて堀をめぐらして、更にその上には木材を渡し革を張り泥を被せた。
この準備が裏目に出る可能性は意識せずにはいられない。街の広場で兵士たちに決起を促したこととあわせて、両都市の間を今も自由に行き来する商人たちが、グプタに伝えてしまうだろう。実際に実権を握っているのが誰かはわからないが、グプタで忠誠宣言を苛立ちながら待っているだろう者に、過剰な怒りを与えるかもしれない。
ゼンは城壁の上から作業を眺めている。城壁のすぐ際まで、水を引き入れた耕地が迫っている。その泥の中に足を沈めながら、兵士や奴隷や徴集した農民が忙しく動き回っている。作業の物音や、指示する者の怒声ばかりではなく、時には笑い声も風に乗ってくる。収穫には少しばかり早いけれどただ踏み潰させてしまうよりはと、小麦を刈り取った後の農地で人々は戦いに備えている。午前中の穏やかな陽光がそれを照らしている。ゼンはこの長閑すぎる光景を、目に刻み込まなくてはならないと唐突に思った。間もなく失われてしまうものだ。日差しが暖かさよりも、苦痛な暑さを運んでくる時間が近づいているというのに、エンドラの太守は体に震えが走るのを感じた。
決起から七日目。ゼンはグプタに通じる門の上にいた。朝霧に遮られて何も見えない時間ながら、その巨大な灰色の塊を透かして見える物がないかと、寝床から這い出して城壁に上らずにはいられなかった。
グプタの将軍サイスが、スカンダルの軍を退けたという報せは届いていた。その後でグプタが急いで兵を再編成してくれば、もうそろそろエンドラに到達する頃 だ。逆に損害が大きくて、身動きがとれなくなっているかもしれない。あるいは逃亡したスカンダルを追う方を優先するかもしれない。ここで気を揉んでいても、敵が姿を現さないということも充分あり得る。グプタの内情がわかれば、もう少し落ちついていられるだろうに。
決起を決めてからというもの、 ゼンはゆっくり眠ることができなくなっていた。起きている時に心臓の鼓動が突然に早くなり、息苦しさを感じることも多い。戦いが始まってしまえば、このような苦痛から逃れられるのは、過去の戦いから知っている。とにかく一刻も早く、エンジャメナの本隊と合流したいものだ。ゼンはエンジャメナに出した使者が戻ってくるのを、何日も待ちわびていた。
日が昇ってからは、太守公邸で巻物と格闘していた。内乱が迫っているといっても、おろそかにできない太守の勤めがあるのだ。夜眠れない代わりに、文字を読んでいる時に眠気が襲ってきて、頭が落ちた衝撃で目を覚ますことを幾度も繰り返す。だから使者が戻ってきたと聞いたとき、最初に浮んだのは眠気覚ましになる、という思いだった。エンジャメナからの返事だと気づいて、眠気が吹き飛ぶまでに一呼吸以上の時間がかかった。
急に眠気を振り払った時に特有の、体が冷たいという感覚を引き摺りながら、使者を待たせている部屋に向かった。普段なら公的な使者とは広間で会うところだが、内密な話もあるだろうと、使者は賓客を泊めるための個室に通されていた。
「エンドラの太守閣下、御自らのお出まし、わざわざ申し訳ありません」
ゆっくりと頭を下げる使者に、ゼンは身振りで座るよう促した。
「儀礼は省こう。エンジャメナ殿の軍勢はどこまで進んでいる?」
そしてエンドラにはいつ、グプタにはいつ到着するのだ?ゼンはまくしたててしまいそうな気持ちを必死で押さえる。
「状況が変化してしまいました」
なんだと?ゼンは思わず相手の顔を真っ向から見据えた。心なしか使者を務める若い騎兵は、顔が青褪めて見える。
「まだこちらには報せが届いていないかもしれませんが、草原の民が大挙して帝国の領域内に侵入しております。エンジャメナさまは、軍の針路を変えて蛮夷の撃退に向かわれました。ゼンさまには、現有の兵力でエンドラを防衛していただきたいと」
俺は見殺しか。一瞬、絶望的な考えが頭をよぎった。だがよくよく考えれば、内乱の途中だからといって、蛮族の跳梁を許すわけにはいかない。それでももしもグプタの軍が南下してきたら、見殺しと同じことだ。
ゼンはエンジャメナの使者との短い会見を終え、よろめく足取りで自分の仕事場へ向かった。
「グプタからの使者を牢から出せ。そしてグプタへ使者を!」
もう手遅れかもしれないが、なんとか巧く立ち回らなくては。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
